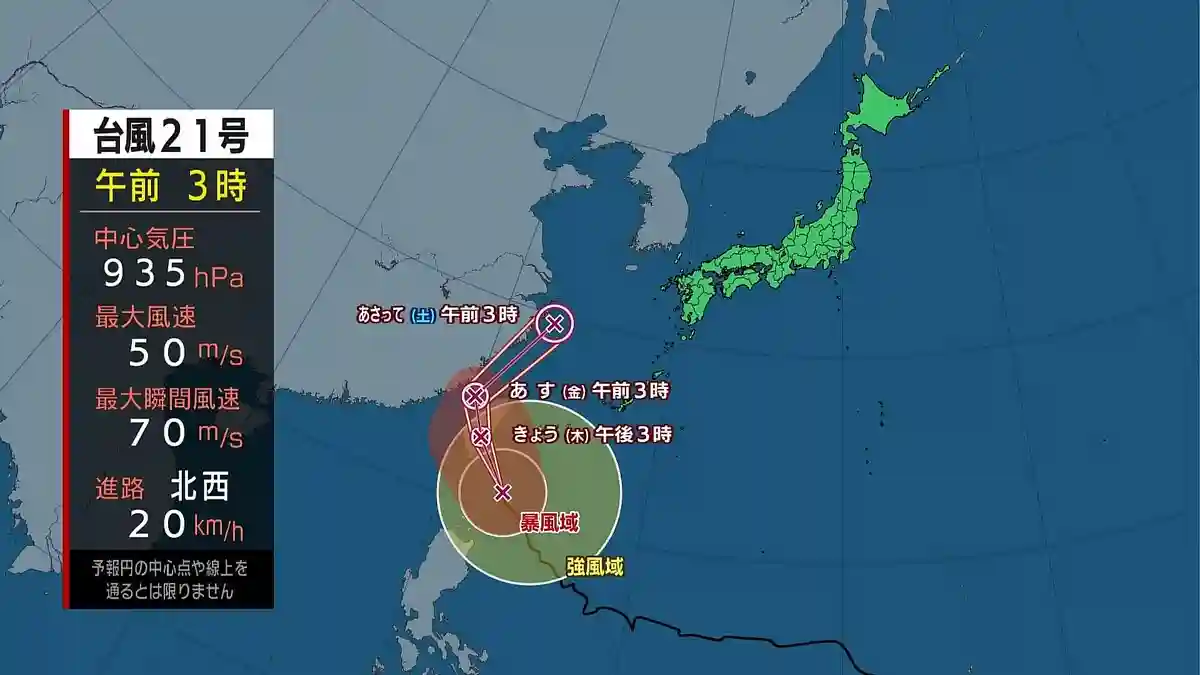日本の鉄道が存続の危機に瀕している。これから総人口や生産年齢人口(15歳〜64歳)が急速に減少すれば、鉄道の利用者数が減るだけでなく、鉄道を支える人材の確保が難しくなる。そうなれば、現存する鉄道の維持が困難になるのは必至だ。 そのため、先日都内では、この危機を回避する技術の講演会が行われた。本稿では、その概要や、紹介された技術を紹介する。 初めてタイトルに入った「省人化」 冒頭で紹介した講演会は、公益財団法人鉄道総合技術研究所(以下、鉄道総研)が主催する「鉄道総研講演会」であり、本年10月18日に有楽町朝日ホールで行われた。鉄道総研は、設立の2年後の1988年から毎年(コロナ禍の2019年を除く)「鉄道総研講演会」を開催しており、今回がその第37回目となる。 今回の講演会のタイトルは「鉄道の持続的発展を目指して—省人化と自動運転—」。ここで言う「省人化」は、鉄道を支える人員を減らすことを指す。「鉄道総研講演会」のタイトルで使われたのは、今回が初めてである。 今回のタイトルは異色だ。過去の「鉄道総研講演会」では、「高速化」「エネルギー効率向上」「未来を創る」「革新的」といったポジティブで前向きな言葉がタイトルに使われていた。いっぽう今回は、「省人化や自動運転を実現しないと、鉄道の持続的発展は難しい」という鉄道関係者たちの危機感をダイレクトに表現したものと言える。 それゆえ筆者は、ある鉄道関係者から今回の講演会の聴講を勧められた。日本の鉄道技術の方向性が大きく変わる転換点となる機会だったからだ。 会場に行くと、多くの聴講者が集まっていた。申し込み人数は470人(閉会時発表)。筆者は会場を見渡し、聴講者の9割以上が50代以上の男性だと感じた。鉄道関係の管理職クラスの人物が集まった印象だ。 日本がパイオニアだった自動運転 鉄道の省人化というと、列車の自動運転を思い浮かべる人が多いだろう。「ゆりかもめ」などの多くの新交通システムのように、乗務員(運転士や車掌)が乗務しない無人運転が多くの鉄道で実現すれば、鉄道現場で働く人を減らせると考えられるからだ。 その点日本は、鉄道をふくむ軌道系交通機関の自動運転においては世界のパイオニアだった。講演会の冒頭で特別講演をした東京大学の古関隆章教授によると、自動運転による無人運転は、1970年の大阪万博の会場内輸送用のモノレールで実施され、1981年に開業した神戸の営業路線「ポートライナー」で世界で初めて実用化された。 ところが現在は、日本は無人運転の実施において出遅れてしまった。今では列車の無人運転を行っている鉄道路線が、海外の先進国や新興国に多数存在する。 たとえばフランスの首都であるパリのメトロ(地下鉄)では、1号線と14号線で無人運転を実施している。いっぽう日本では、無人運転を新交通システムの一部で実施しているものの、地下鉄での実施例はゼロだ。 この背景には、日本の特殊性がある。日本の社会では、鉄道の安全性に対する要求が高く、鉄道が重い社会的責任を担っている。それゆえ、たとえ海外で実績があっても、その考え方が国内ではなじまず、鉄道の無人運転を社会実装するのが難しいのだ。 しかし、近年日本の鉄道では、運転士が乗務しないドライバレス化の必要性が確実に高まっている。それは運転士の確保が難しいだけでなく、その養成に時間を要するからだ。日本で鉄道の運転士になるには、養成施設で8〜9ヶ月間講習を受け、動力車操縦者運転免許試験に合格する必要がある。 このため鉄道総研は、ドライバレス化を実現する技術として、「GOA2.5」による自動運転システムを開発に取り組んできた。「GOA2.5」は、自動運転の国際規格とは異なる日本独自の規格で、「添乗員付き自動運転」とも呼ばれる。列車の先頭部には、運転士の代わりに動力車操縦者運転免許を持たない係員を乗務させる。 「GOA2.5」の大きなメリットは、設備投資が難しい地方路線でも自動運転を実現できる点にある。運転保安装置などの既存の設備をそのまま活かすことができるからだ。 JR九州は、本年3月から香椎線の営業列車に「GOA2.5」を本格導入した。現時点では、複数の鉄道事業者が「GOA2.5」の実証実験をすると発表している。 インフラ点検作業員の人手不足 講演会の一般講演では、鉄道総研の各研究部長から、省人化を実現する技術が紹介された。その内容は車両よりも、電気設備や軌道、構造物といったインフラの話が多かった。鉄道では、線路という長大な設備が大部分を占めており、その維持・管理に多くの人員を割いているので、それは当然のことであろう。 従来のインフラの点検は、人の力に頼る部分が大きかった。専門性の高い技能と知識を持った作業員が定期的に線路を歩いて、目視や手作業で設備の異状を見つけていた。それゆえ、作業員の経験や勘に頼る部分も大きかった。 現在は、このような作業員を確保することが難しくなっている。それは生産年齢人口の減少だけでなく、作業員に求められる技能や知識が高度で、技術継承が難しくなっていることが関係している。 AIを活用したインフラ点検の省人化 このため近年は、インフラ点検の「車上化」が着々と進められている。ここで言う「車上化」とは、インフラ点検を行う装置を車両に搭載することを指す。たとえば本年6月に引退が発表された「ドクターイエロー」は、インフラ点検の「車上化」を実現した車両であり、東海道・山陽新幹線を走りながら線路の各種設備の「健康診断」を行っている。収集されたデータは、深夜に行われる精密検査や補修に生かされている。 現在は、インフラ点検でAI(人工知能)の導入が進められている。AIの発達によって、膨大な数の画像データの解析が可能になったからだ。 鉄道におけるAIの導入は、すでに世界的な潮流になっている。筆者は先月、<じつは危機に瀕している「日本の鉄道」の救世主となるか…世界でトレンドになっている「鉄道業界のAI活用」の現状>と題して、ドイツで開催された「イノトランス(InnoTrans=国際鉄道技術専門見本市)」で「AIモビリティラボ」という展示が初めて設置されたことや、日本の日立製作所がAIを活用した新技術を発表したことを紹介した。 いっぽう鉄道総研も、AIの活用に取り組んでいる。その例としては、車両に取り付けたカメラでレールやまくらぎなどを撮影し、得られた画像から異状を検知するシステムの開発や、異状を検知するセンシング技術の開発、そしてツールの共通化やデータ連携の基盤となる技術(プラットフォーム)の開発などがある。 ただし、これらの技術の完成度を高めるには、技術基準等の安全性や信頼性を担保するための科学的根拠の提供や、AIが学習するための膨大なデータの蓄積が必要になる。技術基準等の整備には国(国土交通省)、データの蓄積には鉄道事業者との連携を要する。 鉄道総研の役割は「接着剤」 その点鉄道総研は、中立的な第三者機関なので、国や鉄道事業者と連携しながら技術の構築を支援できる。また、多くの鉄道事業者を結びつけ、組織の枠を超えた連携を図り、技術やデータベースを共通化して社会で活用できるしくみをつくるうえでも、鉄道総研が果たす役割は大きい。 このため、講演会の最後に行われた「提言」では、鉄道総研が各鉄道事業者をつなげる「接着剤」としての役割を果たし、日本の鉄道全体の発展に貢献したいという意思が示された。 冒頭で述べたように、日本の鉄道は存続の危機に瀕している。今後進む人口減少のスピードを考えると、鉄道の省人化と自動運転の導入を早急に実現する必要がある。 そこで必要になるのが、先ほどの連携だ。鉄道総研が中心になって各鉄道事業者が協力し合って新たな技術革新をもたらし、目前に迫る危機を回避する。それがまさに今、日本の鉄道に求められているのだ。 じつは危機に瀕している「日本の鉄道」の救世主となるか…世界でトレンドになっている「鉄道業界のAI活用」の現状