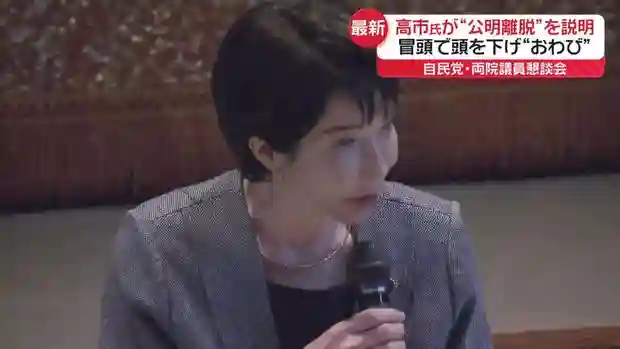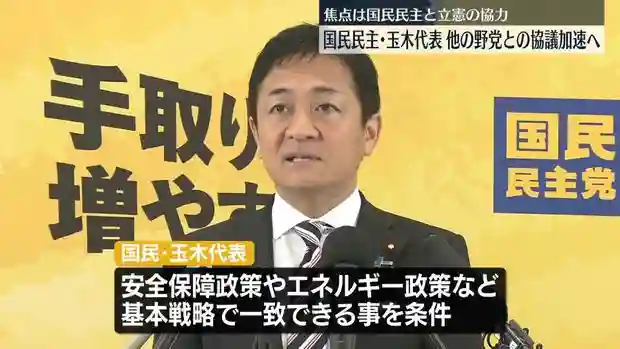10円、20円を握り締め、学校帰りにおやつタイム。とりわけ40代以降の中高年にとって、駄菓子の思い出は深いものがあるだろう。そんな業界に身を置く、名古屋の老舗企業に理不尽ともいえる判決がくだり、衝撃が走った。 甘じょっぱいたれと噛みごたえがクセになる「紋次郎いか」。そのラベルのイラストが著作権を侵害しているとして、小説『木枯らし紋次郎』の著者の遺族が訴えを起こし、被告の駄菓子メーカーが知財高裁で敗訴したのだ。 駄菓子の利益率を考えると、約5630万円という賠償額が与える打撃は想像に難くない…。 半世紀近く、‟共存”してきたようにみえた中、「なぜいま」だったのか…。そして、このイラストと『木枯らし紋次郎』は「本当に似ている」といえるのだろうか。(本文:友利昴) 駄菓子業界に鞭を打つ衝撃の判決!? 糸引き飴(耕生製菓)、いちごミルク(アメハマ製菓)、花串カステラ(鈴木製菓)、梅ジャム(梅の花本舗)、ピースラムネ(土棚製菓)…。 いずれも、製造元の廃業により、ここ数年で姿を消した愛すべき駄菓子たちである。10円、20円と安価で買えることに商品価値があるがゆえの利益率の低さ、それを圧迫する近年の原材料費、包装費、運送費などの高騰、さらに工場や製造設備の老朽化や後継者不足などの問題もあり、今、駄菓子業界は危機に瀕している。 そんな業界に、さらなる追い打ちをかけるかのような事件が起きた。するめを竹串に刺した珍味菓子の定番「紋次郎いか」を製造販売する一十珍海堂が、2023年に著作権侵害で訴えられ、この9月、知財高裁で敗訴、約5630万円の賠償命令を受けたのだ。 訴えたのは、小説『木枯らし紋次郎』の著者で2002年に亡くなった笹沢左保(さほ)氏の未亡人・佐保子氏(「笹沢左保」のペンネームは妻の名から採られたという)と、同氏から著作権管理を受託する企業「スーン」。なお、本裁判係属中に佐保子氏が亡くなったため、その後は息子らが原告を引き継いでいる。 訴えの内容は、「紋次郎いか」のラベルに印刷されていた旅人風のイラスト(図1)が、『木枯らし紋次郎』の主人公・紋次郎にまつわる著作権を侵害するというものだった。 左:「紋次郎いか」ラベル(図1)、右:テレビドラマ版『木枯らし紋次郎』(図2)。いずれも知財高裁令和6年(ネ)10007号判決文別紙 50年間見過ごしてきたのに、なぜ? まず引っ掛かりを覚えるのは、「今さら訴えるの?」という点である。駄菓子の定番「紋次郎いか」は、いつからあったのかが気にならないほど、日本人の生活史に溶け込んでいる商品だ。実際、1972年の発売以来、訴えられる2023年まで実に50年以上の歴史がある。 訴訟までの出来事を追ってみよう。2002年に笹沢氏が亡くなり、2011年に佐保子氏がスーンに著作権管理を委託している。そして2022年。笹沢氏の息子の一人であるA氏が、取引先から1億円近い金額をだまし取る詐欺事件を起こしているのだ。 この件で、A氏は2024年に逮捕されている。事件を報じた当時の新聞や週刊誌報道では、同氏が資金繰りに窮していた様子が書かれ、だまし取った金を借金返済にあてていたと見られていた。この流れの中で提起されたのが本訴訟なのである。 もっとも訴訟の動機については、これ以上は憶測にしかならず、深入りは止めておこう。こうして2023年に提起された訴訟だが、実は同年12月の第一審・東京地裁では遺族側が敗訴している。 東京地裁の判決文によれば、笹沢氏の遺族側は、「紋次郎いか」の旅人イラストは、小説の主人公・紋次郎に関する抽象的な4点のキャラクター設定(①大きな三度笠を目深にかぶり、②長い道中合羽で身を包み、③口に長い竹の楊枝をくわえ、④長脇差を携えた渡世人)についての著作権侵害である、と主張しているようにうかがわれた。 キャラクターの著作権保護を論じるとき、具体的な表現である「キャラクターイラスト」は著作権の保護対象だが、抽象的な「キャラクター設定」はアイデアに過ぎず保護されない、という考え方は、著作権を学ぶ者にとっては基本といっていい。 これをごっちゃにしているかのように見えた遺族側の主張は、いかにも無理筋な「エセ著作権」に映った。実際、判決文でも「原告らは〔…〕著作権が侵害されたという著作物を具体的に特定しないものとして、その主張自体失当というほかなく」と一蹴されている。 逆転勝訴の背景にあった、遺族側の真の主張とは だからこそ、控訴審で遺族側が逆転勝訴という報道に接したときは驚きであった。 判決文を読むと、第一審では曖昧だった遺族の主張の全容が見えてくる。彼らは、小説『木枯らし紋次郎』における紋次郎の「キャラクター設定」を根拠としているわけではなく、佐保の小説を原作とする、テレビドラマ版『木枯らし紋次郎』の映像を主張の主な根拠としていたのだ。 テレビドラマ版『木枯らし紋次郎』は、佐保の小説を原作として、市川崑が監督し、1972年からフジテレビ系で放送されていた。遺族は、その著作権を自らが保有するとしたうえで、「キャラクター設定」ではなく「ドラマに登場する紋次郎の姿」(図2)と旅人イラストを比較して類似すると主張したのだ。これを、控訴審の裁判官が認め、「紋次郎いか」の著作権侵害を認容している。 小説を原作とするドラマなどは「二次的著作物」と呼ばれ、これについては原作者も著作権を有する。例えば『劇場版 鬼滅の刃 無限城編』の権利表記は「©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable」だ。映画製作者の集英社、アニプレックス、ufotableに加え、原作者・吾峠呼世晴の名が著作権者として併記されているのは、その表れである。 それと同じように、ドラマ『木枯らし紋次郎』について笹沢氏の遺族が著作権を保有するということは確かであり、そのドラマの映像は具体的な表現だから、著作権で保護されることも明らかだ。なるほど、遺族側の主張には道理がある。しかし、それでもなお、この判決にはもうひとつの「引っ掛かり」を覚える。 もしこれが著作権侵害なら、次に狙われるのはあの駄菓子…? 仮に「ドラマに登場する紋次郎の姿」に遺族の著作権を認め、これと「紋次郎いか」の旅人イラストを比較したとしても、果たして両者は「類似する」といえるだろうかということだ。 「ドラマに登場する紋次郎の姿」は、俳優(中村敦夫氏)が演じた姿を撮影した実写映像であり、映像に捉えられた表情、身のこなし、撮影構図などは、「紋次郎いか」では全面的に省略されている。 三度笠、道中合羽、口にくわえた楊枝といった衣装・小道具の選択と組み合わせ方は両者に共通するが、しかし「紋次郎いか」の三度笠は、ドラマ版紋次郎と比べてあまりに巨大である(ほとんどキノコの傘状態だ)。合羽も巨大で、それが大きく風にたなびく様子の描写になっている。楊枝も長過ぎて、しかも顔のパーツが省略されていることも相まって、もはや楊枝かどうかも定かではない。 ここまでの省略と誇張、変化が施されていれば、ドラマをもとに描いたイラストだとしても、もはや共通するモチーフを用いた、別物の表現とみるべきではないだろうか。 もし、このレベルでも著作権侵害になるのだとしたら、この事件はもはや一十珍海堂という一企業の問題にとどまらず、ひょっとすると駄菓子業界全体に大きな影響を及ぼしかねない。 知っての通り、駄菓子や駄玩具には‟パロディ”が多い。「ウメトラ兄弟」(すでにいつの間にかウルトラマン感が減じている!)や「うまえもん(うまい棒)」にとっても対岸の火事ではないかもしれないのだ。 報道によれば、一十珍海堂は最高裁への上告を検討しているという。引き続き、事の趨勢(すうせい)を注視すべき事案である。 【友利昴(ともりすばる)】 作家。企業で知財実務に携わる傍ら、著述・講演活動を行う。 ソニーグループ、メルカリなどの多くの企業・業界団体等において知財人材の取材や、講演・講師を手掛けており、企業の知財活動に詳しい。 『江戸・明治のロゴ図鑑』『企業と商標のウマい付き合い方談義』『エセ著作権事件簿』の他、多くの著書がある。1級知的財産管理技能士。