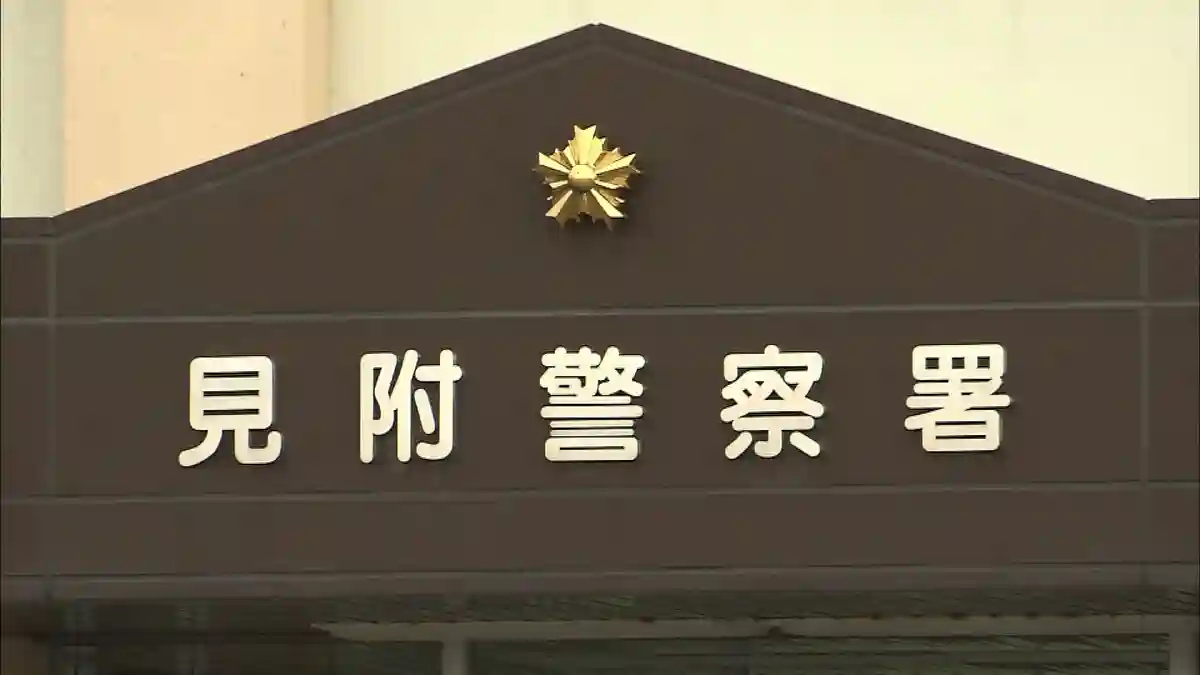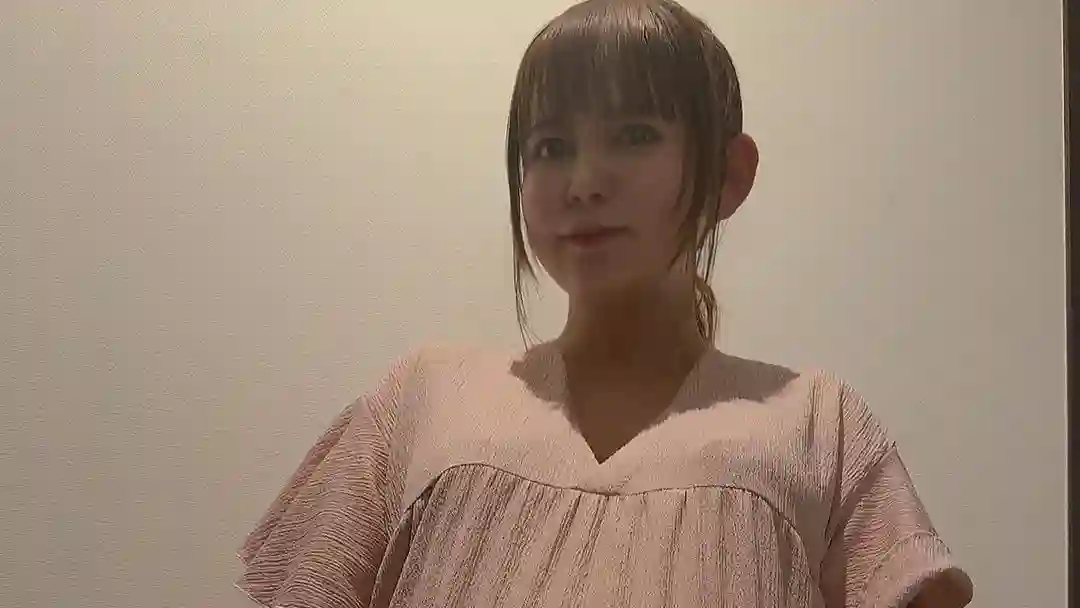幸福になれないけど、人が集まる街 私が暮らしている世田谷区。最寄りの駅に向かうと、昼時は決まってガード下にある、某パスタチェーン店に行列ができている。一人当たりの客単価は、おそらく1000〜1500円。安いわけではないのに、なぜ猛暑の中、並んでまでチェーン店に入ろうとしているのだろう? 東京にいると、こんなふうに息苦しさを感じる場面に遭遇することが少なくない。 都道府県ごとに住民の幸福度や生活満足度、愛着度、定住意欲度などを数値化する「第6回幸福度調査2024」(出典:ブランド総合研究所)によると、東京は40位だという。2023年の調査が28位だったことを鑑みると、わずか1年で急落したことになる。東京は、“幸福になれないけど、人が集まる街”になりつつある。 4年前、東京の暮らしづらさに疑問を覚えた私は、熱海にほど近い神奈川県真鶴町に居を移した。中古のマンションを購入し、生まれてはじめて東京から住民票も移した。現在は、世田谷との二拠点生活をしているが、その快適さは雲泥の差だ。東京を客観的に眺められるからこそ痛感することがある。どうして東京は、こうも疲れるのか——。 疑問を解くヒントを得るため、國學院大學観光まちづくり学部教授の吉見俊哉氏を訪ねた。 『都市のドラマトゥルギー』『東京復興ならず』『敗者としての東京』といった社会学、都市論の著書を持つだけでなく、『東京裏返し』シリーズなど東京を歩きながら考察する教養人の目に、今の東京はどのように映っているか聞きたかったからだ。 「東京の暮らしづらさは、主に3つの要素に起因しているのではないか」 そう吉見氏は切り出した。 「一つ目は、『東京空間』。世界の大都市と比較したとき、東京ほど窮屈な都市はありません。居住空間が狭いのは昔からですが、人口の多さに比べて東京ほど公共的な空間に自由度が乏しい都市はありません。規制が厳しいということです」(吉見氏、以下同) その最大の象徴が車だという。自動車用道路が網の目のように張りめぐらされ、街々が道路で分断され、車の交通が幅を利かせているのが『東京空間』だと指摘する。 「東京は、高度成長期の首都改造の中で『より速い、より高い、より強い』都市を標榜した。そのため、川や運河にふたをするように首都高速を造り、“ゆったりとした東京”の象徴でもあった都電を廃止し、幹線道路を拡幅し、モータリゼーションを推進した」 こうした動きに警鐘を鳴らす人々もいた。1974年に出版された、宇沢弘文の『自動車の社会的費用』は先駆的な例で、1970年代の時点で、自動車が社会にもたらす負の側面を指摘した。それにもかかわらず、東京は道路の拡幅や高速道路建設を続けた。 ニューヨークで起きた変化 「やろうと思えば、今からでも変えられるんです。実際、ニューヨーク市の交通局長を務めたジャネット・サディク=カーンは、ニューヨークの街路空間を“車中心”から“人中心”へと大転換させた。タイムズスクエアやブロードウェイなど都心の象徴的なエリアに広場やベンチを整備し、意図的に車を排除していった」 その結果、道路に賑わいが生まれ、人々がお金を落とす空間へと様変わりしたという。ニューヨーク都心を、「ウォーカブル」(歩きやすく、多様な人が利用できる)な空間へと進化させることに成功した。 吉見氏は、「東京にも、人間のためにたくさん再利用できる道路がある」と断言する。その一つが、今年4月5日に廃止・閉鎖された、銀座の上を通る全長約2kmの東京高速道路KK線だ。開通した1959年当初は都心の混雑回避や、首都高へのアクセス拡張が大きな意義だったが、中央環状線(C2)や他の都市高速網の整備によって交通需要が移行し、KK線の重要性は低下。また、民間所有の無料道路であったため、大規模改修の困難もあり、その役割を終えた。 しかし、4月18日と19日には、「Roof Park Fes & Walk」と題して、KK線の高架道路上を歩行者に開放するイベントが行われた。 ゆくゆくは、歩行者中心の公共的空間へと再生するという。 実際に、私は19日にKK線を歩いてみたが、「銀座の空はこんなにも広かったのか」と感動した。上下左右に広さを感じたのだ。 「KK線の再生は、ニューヨークのハイラインを意識していると言われますが、ハイラインよりはるかに幅が広いのです。とてつもない可能性を持っています」 「そして東京の都心部には、KK線のように、人間のための道に転換できる道路はまだあります。例えば、中央区の江戸橋JCTから台東区の入谷出入口までを結ぶ、延長4.4kmの首都高速1号上野線。同線は、江戸橋JCTが京橋JCT方面としか連絡していないため、他の首都高に比べて交通量が少なく、慢性的な渋滞はほとんどない。それでいて、下には大幹線である昭和通りが走っている。だから高架道は、はっきり言ってもう必要ない(笑)。 この高速道は、緑あふれるパブリックスペースへと変えることができたら、秋葉原から上野までの西側エリアと東側エリアをつなげる豊かな媒介装置へと変貌する可能性を秘めている。『東京空間』は、変えることができるということです」 「東京時間」の息苦しさ 空白を作らなければ、余裕は生まれない。余裕がないから人々は、限られた時間をギチギチに満たそうとする。ここに2つ目の要因である『東京時間』が関係してくる。 「東京の生活は、時間の進み方が限界を超えて速すぎます。車を優先する社会を作ってきたため、どうしても人々はスピードや利便性を重視してしまう。 それで私は、学生たちを連れて街歩きをするときに、“3つの原則”を教えるようにしています。原則1は、広い道と狭い道があったら、必ず狭い道を行きなさい。原則2は、真っすぐな道と曲がった道があったら、必ず曲がった道を行きなさい。原則3は、平らな道と登り下りがある坂道があったら、必ず坂道を行きなさい。人生も、学問も、同じです」 「そうした道を通ると、忙しい日常とは違う東京の風景を経験することができます。目的地に速く着きたいなら、広い、真っすぐな、平らな道を選べばいい。しかし、そうすると途中の経験が消える。つまり、より速い利便性や効率性を求めていくと、 途中のプロセスはどんどん空虚になってしまうのです」 たしかに、東京は便利だ。誰かと会うにしても、会いやすい。何かを買うにしても、買いやすい。目的をすぐに達成できるから、次第に回転率が上がっていく。コストパフォーマンスに次いで、いよいよタイムパフォーマンスなどと叫び始めたのは、その証左だろう。 だが、暮らしを営むということは、そういうことだったのだろうか。私が東京から距離を置いたのは、まるで強制されるような“東京に合わせるしかない暮らし”から抜け出し、自分だけの暮らしを取り戻したかったからかもしれない。半面、東京のメリットも理解しているから、完全には離れられない。その葛藤は今もある。 「『東京時間』は効率がいい。しかし、効率が良いと、人々はますます加速化していく。加速化することによって、プロセスが失われ、経験が失われていく。東京時間は、“何のためにしているのか”という感覚を奪っていくとも言える」 吉見氏は、石川県珠洲市を数度訪れたという。「能登半島地震で大きな被害に遭われたけれど、移住する若い世代が少しずつ増えている。たくましくて、素晴らしい場所です」。そう表情を崩す。 「珠洲には、『海浜あみだ湯』という銭湯があるのですが、被災後もさまざまな人がここを訪れ、 “なじみ”が生まれる場所になっている。そこにたむろしていた1年半ほど前に東京から移住してきた20代の女性が、『珠洲には珠洲の時間があります』と、ものすごくシャープなことを言っていた。時間の流れ方が、東京とはまったく違うと。だからこそ、震災後の珠洲には独自の社会が形成されている」 時間をかけた「なじみ」をつくるために ゆったりした時間があれば、経験が大切にされ、 “なじみ”や“縁”が生まれる。一方、東京生活にそうした時間はあるだろうか。もちろん、行きつけの飲み屋を含め、コミュニティを作る場所はあるだろう。しかし、ソサエティーとして考えたとき、東京はひどく淡白ではないか。 パッとやってきてパッと散るような街。知らない者同士が出会い、すれ違う場所。3つ目の要素、『東京社会』とも呼べる東京ならでは希薄なつながりに、「心を満たされない人は多いのではないか」と吉見氏は語る。 「“なじみ”がなければ、思い入れは生まれない。文化というのは、時間がかかるものなんですね。文化は英語ではCultureと綴りますが、農業を意味する英語Agricultureと同じ語源です。文化は耕作と似ていて、循環的なプロセスがなければ豊かにはならない。文化は大量生産できるものではなく、時間をかけて育んでいくしかない。ところが、過度に集中した東京は、空間的にも、時間的にも、社会的にも良い循環を生み出しづらい」 20世紀を代表する歴史学者ヨハン・ホイジンガは、著書『ホモ・ルーデンス』の中で、遊びが文化の形成に先行し、そこから社会や文化が生まれると論じた。余裕のない空間で、効率性を追い求め、つながりが希薄——そんな街では、遊びも文化も生まれない。 現在、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県の人口は、約3600万人と言われる。日本全体の人口が、約1億2000万人だから、首都圏に約3割の人口が集中していることになる。それだけの人がいるのに、幸せを感じられない人が増えている。その事実と、我々はもっと真摯に向き合わなければいけない。 *** さらに【つづき】「東京は、じつは日本の「リスク」である…東京が「地方から奪い」「巨大化」することの危うさ」では、吉見氏が、東京一極集中の危うさについて解説します。 【つづき】東京は、じつは日本の「リスク」である…東京が「地方から奪い」「巨大化」することの危うさ