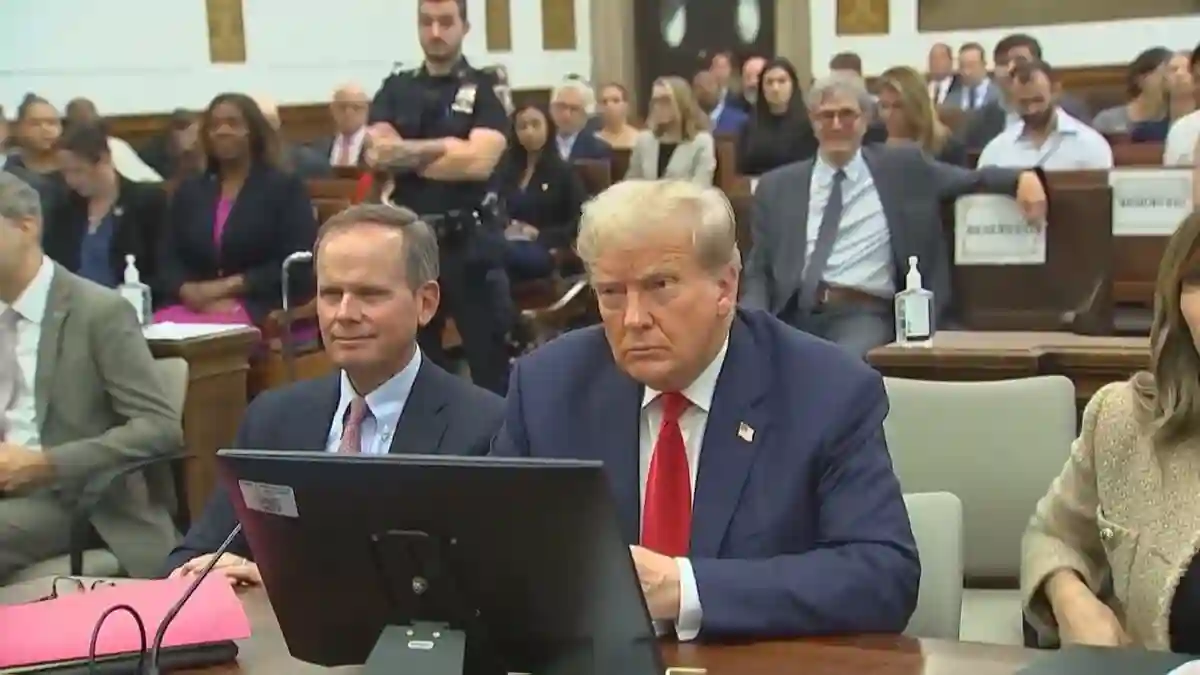日本人にとって得なのはどちらか? マナーの悪い外国人は、たしかに目立つようになった。大坂城の石垣によじ登る、京都市の伏見稲荷への途上にある踏切がごった返すなか、線路に立ち入って写真を撮る、といった外国人観客の行動が報じられるのは、ほんの一例だ。マナー云々では済まない例もある。7月26日に佐賀県伊万里市の住宅で、40歳の女性と70代の母親が、ベトナム国籍の技能実習生にナイフで殺傷されたのは衝撃だった。 【写真】「DON’T TOUCH」外国人観光客による“迷惑行為”を受けて設置された「黒い幕」 今年6月の訪日外国人旅行者数は、日本政府観光局(JNTO)が発表した推計値によれば、前年同月比7.6%増の337万7,800人で、6月としては過去最高を記録。1月から6月までの上半期の総数は、前年同期比で21%増の2,151万8,100人となり、過去最速で2,000万人を超えた。 外国人に頼らなければ社会が回らない また、総務省が8月6日に発表した今年1月1日現在の人口動態調査によれば、外国人の人口も前年比10.65%増の367万7,463人で、過去最多を更新した。 外国人による目に余る行動や、悪質な犯罪が目立つこと。訪日旅行者、居住者とも外国人数が過去の最高値を更新していること。それらはいま起きていることである。このため、「日本人ファースト」という主張が共感を呼ぶのも、理解できないわけではない。 だが、この問題は冷静に眺めるほど、「日本人」「外国人」という紋切り型の言葉でとらえられるものではない。外国人を「外国人」として十把一からげにして排除する方向に進めば、損をするのは外国人よりもむしろ日本人であり、逆に日本人の生活が脅かされかねないことを、理解しておいたほうがいい。 刑法犯とインバウンドは結びつかない 「日本人ファースト」を支持する人たちのあいだでは、外国人が増えると治安が悪化するという主張が多く聞かれた。街を歩く外国人の数が目立って増えたことを、治安への不安に結びつける人も少なくなかった。 たしかに、来日外国人(定着居住者や在日米軍関係者などを除いた外国人で、訪日外国人旅行者とおおむね重なる)による犯罪は、警察庁の「警察白書」(2025年版)をみると、若干の増加傾向にある。2024年の刑法犯の検挙数は、前年の1万40件から1万3,405件に増えた。 ただし、警察庁の説明では、その原因はベトナム人やカンボジア人の窃盗犯が増加したことにあり、外国人旅行者数が増加したから検挙数が増加したとは、単純に結びつけられない。 検挙数のうちベトナム人が占める割合は、24.8%と目立って多い。その多くは換金目的の窃盗で、窃盗団としての組織的な犯罪である疑いが濃厚だ。それを厳重に取り締まる必要があるのはもちろんだが、一般的な来日外国人=訪日外国人旅行者全般、すなわちインバウンドとは関係ない。インバウンドを刑法犯と結びつけて白眼視するのは、お門違いなのである。 また、来日外国人による刑法犯の検挙数は、短期的にはいま記したように増加傾向にあるが、ピーク時の2013年から18年に2万件台から3万件台だったのにくらべると、かなり減少している。しかも、来日外国人の分母は大幅に増えているのに、検挙件数が減っているので、犯罪率は低下している。同じ傾向は外国人居住者についても確認できる。 排除ではなくハードルを上げる とはいえ、冒頭で述べたように、インバウンドにも劣悪なマナーが見られるのは、多くの人が目撃しているとおりである。それでも、インバウンドが現在、思うように経済成長できない日本を支える大事な因子である以上、冷静に対処する必要がある。 現在、日本が好きで、または日本に興味があって訪れる外国人旅行者がいる一方、過度な円安のおかげで「安いから」日本を訪れる旅行者も少なくない。そのことがマナーの低下につながっている面は否定できない。だから、出国税や宿泊税を増額するなどして、訪日の負担を増やす必要があるだろう。 また、日本人と外国人の二重価格をもっと積極的にもうけていい。昨年、姫路城の入場料を外国人だけ日本人の4倍にするという案が検討されたが、賛否両論沸き起こった末、市民以外の入場料だけ1,000円から2,500円に値上げすることで落ち着いた。 しかし、そうして躊躇するから、「外国人が優遇されている」と感じる日本人が減らない。そもそも姫路城のような史跡や文化財は、維持管理に巨額の費用がかかり、国や自治体から補助金も支給されている。つまり、日本の居住者が支払った税金が充てられている。そうである以上、日本に税金を納めていない外国人旅行者の入場料を、日本居住者より高く設定することは理に適っている。 こうして訪日のハードル、続いては、各観光地を訪れるハードルをいまより高くし、外国人を選別することは、オーバートゥリズムの解消にも、一定数の人がいだいている外国人への悪感情を軽減するためにも必要だろう。 同時に、伏見稲荷近く踏切のような、近隣住人の生活に支障をきたす状況を改善し、危険な行為を防ぐために、観光名所の管理者や自治体、鉄道会社などが協力し、人を派遣して観光客を誘導するなどの措置は欠かせない。秩序が失われた状況が報じられ、外国人への不安が煽られることは、ほかならぬ日本人にとってマイナスだからである。 外国人に頼らなければ社会が回らない現実 人口動態調査で外国人の人口が過去最多を更新したと述べたが、同じ調査で日本人の人口は、前年にくらべ90万8,574人減った。16年連続の減少で、減少数も減少幅も、1968年に調査が開始されてから最大だった。それも当然で、厚生労働省による2024年の「人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、昨年の出生数は68万6,061人だった。 2016年にはじめて100万人を下回ったのは、その当時、衝撃のニュースだったが、それからわずか8年で3割も減少し、70万人を割り込んでしまった。国立社会保障・人口問題研究所は、2038年には70万人を下回りかねないと警告していたが、14年も前倒しになっている。 万が一、少子化に歯止めがかかったとしても、毎年70万人前後の出生数にすぎなければ、これからさらに進む高齢社会を支えることなど到底できない。すでにコンビニエンスストアなどの小売業から、飲食や宿泊業、製造業から建設現場まで、日本でも多くの外国人労働者が働いている。日本人の労働力人口が今後、必然的に、しかも急激に減っていく以上、これからは介護の現場をはじめ、いまよりはるかに外国人に頼らないかぎり、日本人は憲法第25条で保障された健康で文化的な最低限度の生活すら、営むのが困難になるだろう。 また、先の参院選では、「日本人ファースト」を掲げる参政党の躍進を受け、海外投資家が日本株への投資に慎重になりそうだと警戒された。日本株は日本人が保有すべきだ、と考える人もいるようだ。しかし、現実には、2024年末時点で、日本株における外国法人等の保有比率は32.4%にも達しており、彼らが手を引けば、事実上、日本経済は崩壊する。 外国人に対しては、人それぞれにさまざまな感情をいだいていると思う。だが、外国人に対して感情論に左右されて排除や制限をいい出せば、今後の日本は社会も経済も機能しなくなる。そのことを肝に銘じて、外国人の良好な受け入れ方、よりよい付き合い方を考えていく道しか、私たちにはないのである。 香原斗志(かはら・とし) 音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』(ともに平凡社新書)。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。 デイリー新潮編集部