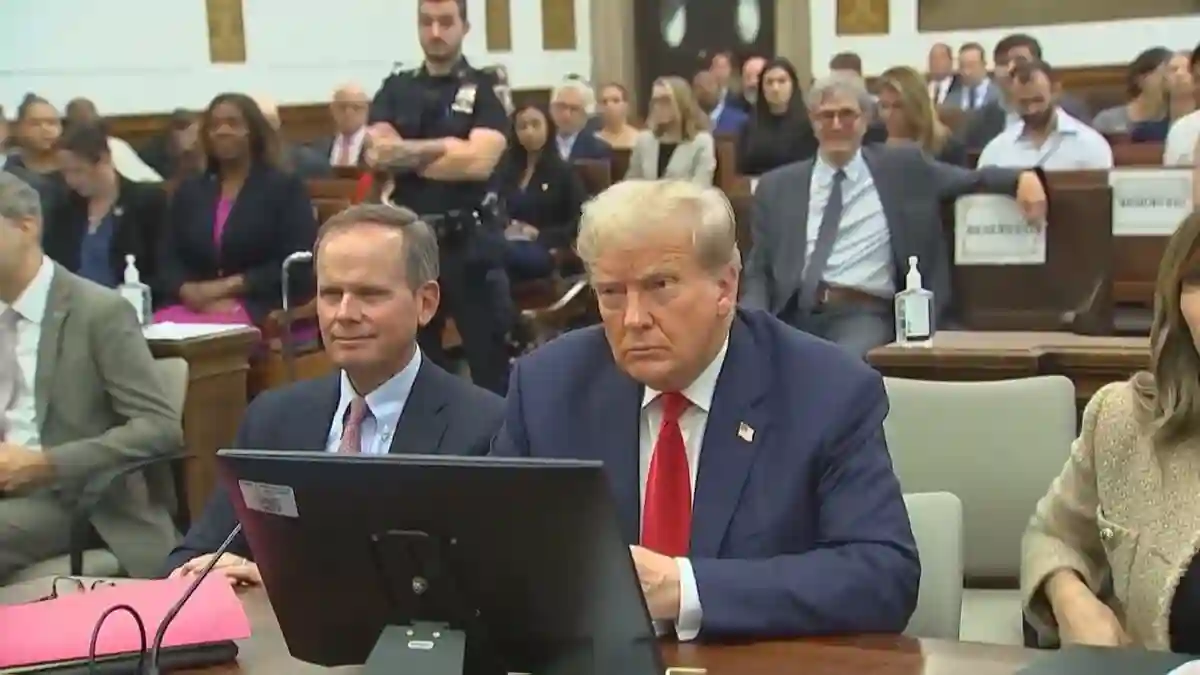東京・千代田区が「不動産協会」に対して行った“異例の要請”が波紋を広げている。その要請とは、投機目的のマンション取引を規制することで、過度な住宅価格の上昇の抑制を求めるというもので、「原則5年間の物件転売の禁止」など、踏み込んだ内容になっている。ただ、要請を受けた側は“寝耳に水だった”と困惑を隠さない。そこで、今回の舞台裏について、不動産協会の専務理事に話を聞くと——。 *** 【写真を見る】2027年に「もう住めなくなる」区は? 東京23区「将来賃料」を試算 今年完成した分譲マンションの7割で居住実態がなかった!? この要請について、不動産協会に取材すると、意外な事実が明らかとなった。 「実は、今回の要請は事前に当協会に対して何の説明もありませんでした。突然のプレスリリースに驚き、千代田区に求めて説明を受けたのが7月24日のことでした」(不動産協会の担当者) 要請が出されてから6日後に、ようやく説明を受けたということになる。 皇居の所在地であり、都内有数の高級住宅街を擁する千代田区 「ただ、その場では十分な説明を受けることができませんでした。改めて確認事項を書面でお知らせし、現在はその回答を待っているところです」(同) 協会が確認を求めているのは、第一にこの要請の「位置付け」にあるという。 「行政機関である千代田区からの要請がどのような法的性格を持っているのかが判然としません。仮に今回の要請が不動産事業者に対する『行政指導』なのであれば、行政手続法に定めるところの『一定の行政目的を実現するため』(行政手続法第2条第6号)が根拠となるはずですが、その『行政目的』が曖昧なのです」(同) つまり、今回の要請の強制性や具体的な目的、その実施方法について明確な説明が得られていないため、手の打ちようがないというのだ。 加えて、実効性の面でも疑問が残るという。 「今回の要請では特に“転売制限”について、不動産業者と購入者との間の契約において措置することが求められていますが、実際にどうやって実効性を持たせるのかという問題があります。例えば法律や条例に基づく規制であれば刑事罰(罰則)や行政罰(過料)による強制力を持たせることができますが、契約上の義務違反については、訴訟などの民事上の手続きに頼らざるを得ません」(同) 具体的には、契約書上で転売に関するペナルティを規定した上で、それが履行されない場合に民事訴訟という流れが想定されるというが、 「それでは強制力を持ち得ません。また、居住の実態を調べるための立入権限もないため、事実の把握が極めて困難となることが想定されます」(同) 協会の吉田理事長は、今回の要請について報道機関に意見を求められた際、「合理的でない」といささか強めのコメントをしたと報道されているが、その背景にはこのような事情が関係していたのだろう。 吉田理事長が報道陣に「要請は合理的でない」と話した理由 ただ一方で、東京23区の不動産価格の“沸騰”が続いているのは事実だ。特に都心3区と呼ばれる千代田区、中央区、港区ではファミリー向けとして一般的な70平米・3LDKのマンション価格が2億円を超える例も珍しくない。 「住みたくても住めない」という都心不動産の現状について、協会はどのように考えているのだろうか。 「都内のマンション価格高騰は、一つは建築費の高騰や開発用地の減少に伴う原価の上昇、もう一つは供給戸数の減少による希少性の高まりに起因するものと考えています」 そう説明するのは、千代田区との折衝にあたっている不動産協会の野村正史・副理事長専務理事だ。 「建設資材の高騰に加え、慢性的な建設技能労働者の減少や働き方改革に伴う労務費の上昇で、建築費が高騰しています。また、マンションに適した開発用地が少なくなってきており、用地費も上がっています。そのように供給戸数が減少している一方で、若年世帯を中心に住宅取得意欲は依然として旺盛ですので、需要が集中するマンションでは希少性が高まり、価格の高騰につながっていると認識しています」(野村専務理事) マンション価格の先行きは「こうした需給の状況や経済情勢に変化がない限り価格が下落することは考えにくく」、当面は高い水準のまま推移すると考えているという。 マンション価格の先行きについて、不動産協会専務理事の見解は では、千代田区の要請の根拠となっている「投機目的のマンション購入増加」については、どのように考えているのだろうか。 「投機目的とみられるマンション購入は、実態としては『ある』と認識しています。ただ、そのような事例は、物件の立地や仕様など物件個別の特性によるもので、分譲マンション市場全体において数多く生じているものではないと考えています」(野村専務理事) その上で専務理事は、憲法の定める「財産権の保障」については、常に頭に置いておく必要があると指摘する。 「マンション価格の高騰は課題の一つだと思いますが、一方で不動産を取得した方が物件を売却する際になるべく高く売りたい、賃貸に出す際になるべく高く貸したいという当然の権利を制限することに繋がらないか。その点は慎重に考える必要があります。本来、財産権を制限するということは、非常に重たいものなのです」(同) 協会としては、引き続き千代田区とコミュニケーションを取りつつ、投機目的のマンション購入に対してどのような手立てが可能なのか、あらためて見極めていく方針だという。 マンション高騰は“投機”なのか、それとも“市場原理の範疇”なのか。守るべきは資産を持たない人の将来か、資産を持つ人の権利か——。千代田区の要請の裏には一言では片づけることのできない、複雑なテーマが横たわっているのである。 投機目的のマンション購入は「ある」と認識しているものの… では、千代田区の要請の根拠となっている「投機目的のマンション購入増加」については、どのように考えているのだろうか。 「投機目的とみられるマンション購入は、実態としては『ある』と認識しています。ただ、そのような事例は、物件の立地や仕様など物件個別の特性によるもので、分譲マンション市場全体において数多く生じているものではないと考えています」(野村専務理事) その上で専務理事は、憲法の定める「財産権の保障」については、常に頭に置いておく必要があると指摘する。 「マンション価格の高騰は課題の一つだと思いますが、一方で不動産を取得した方が物件を売却する際になるべく高く売りたい、賃貸に出す際になるべく高く貸したいという当然の権利を制限することに繋がらないか。その点は慎重に考える必要があります。本来、財産権を制限するということは、非常に重たいものなのです」(同) 協会としては、引き続き千代田区とコミュニケーションを取りつつ、投機目的のマンション購入に対してどのような手立てが可能なのか、あらためて見極めていく方針だという。 マンション高騰は“投機”なのか、それとも“市場原理の範疇”なのか。守るべきは資産を持たない人の将来か、資産を持つ人の権利か——。千代田区の要請の裏には一言では片づけることのできない、複雑なテーマが横たわっているのである。 デイリー新潮編集部