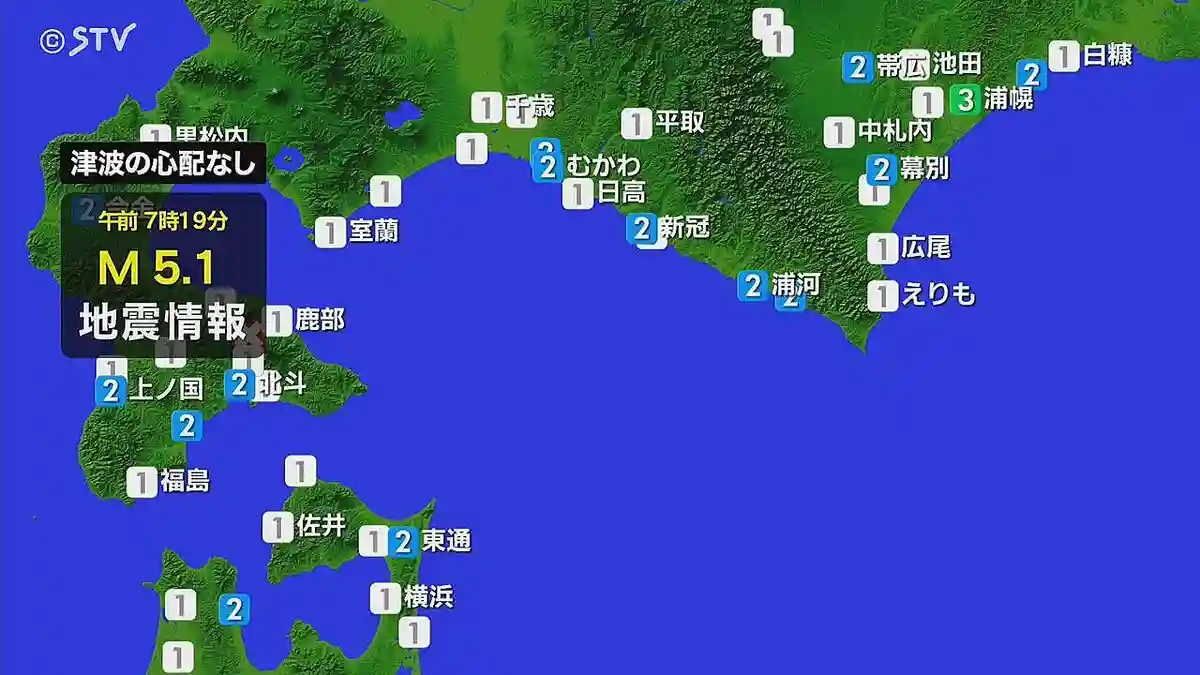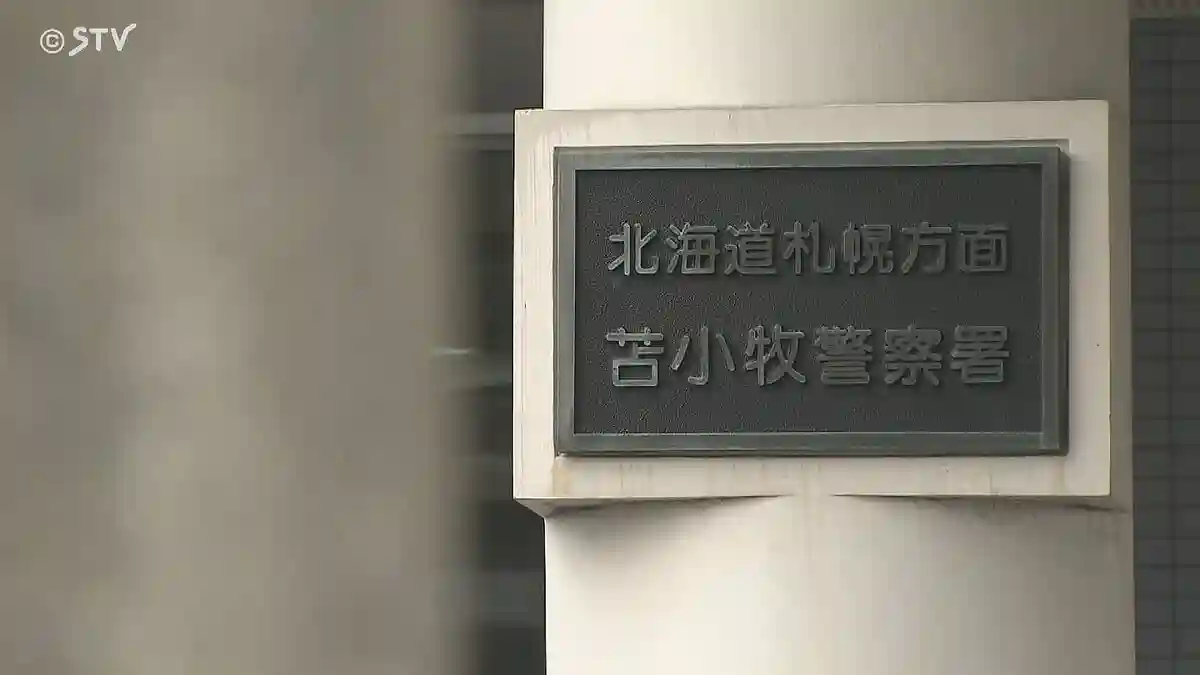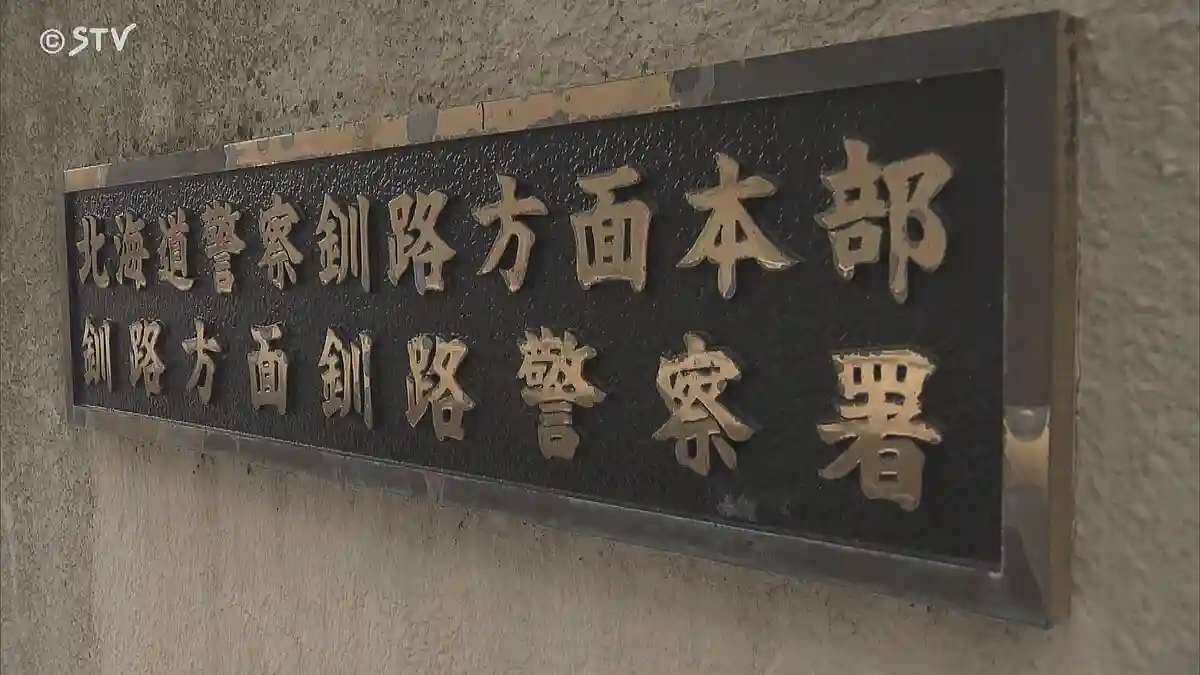1985年夏の甲子園、桑田真澄、清原和博の“KKコンビ”が最上級生となったPL学園は、初戦で東海大山形に大会史上最多の29得点で圧勝。当時「セ・リーグ最下位のヤクルトより強いかも?」の声もあったスーパーチームの本領を発揮した。一方、郷土の代表が歴史的大惨敗を喫した山形県では、県議会で「どうしてこんなに弱いのか」の議論も交わされる政治問題に発展した。【久保田龍雄/ライター】 【見つけられるかな?】1985年夏の甲子園で優勝旗と共に入場行進する清原と桑田の初々しい姿 PL打線は一向に攻撃の手を緩めない 1983年夏から5季連続で甲子園にやってきたPL学園は、大会第7日の8月14日に初登場。2回戦で山形代表の東海大山形と対戦した。 試合結果が政治問題にも発展することも 当時九州の地方紙記者だった筆者は、地元代表チームの同行取材で大阪に来ていた。この日は、初戦を突破した担当チームが勉強を兼ねてPLの試合を観戦するという話を聞き、現地で選手の感想を取材するため、梅田から阪神電車で甲子園に向かった。 すでに試合は始まっていた。街頭のモニターテレビの前を通りかかると、1回表、PLの2番・安本政弘が左翼ラッキーゾーンに先制ソロを放ったシーンが放映されていた。「いきなり本塁打で先制か。さすがはPL」と目を見張ったが、これはほんの序曲に過ぎなかった。 甲子園到着後、一塁側スタンドで観戦していると、PL打線は2回にも連打、また連打で、あっという間に7対0。得点が入るたびに三塁側PL応援席から「パン、パカパン」で始まるファンファーレが鳴り響き、5回終了時点で20対1の大差がついた。この日、PLのファンファーレを20回以上もライブで耳にした筆者は、帰りの電車の中でも「パン、パカパン」の“幻聴”が聞こえてきた記憶がある。 当時小学3年生の渡辺俊介(元ロッテ)も、次の第3試合に登場する国学院栃木の応援で筆者と同じ一塁側スタンドにいたことを、ロッテ時代の取材の際に本人から聞いて知った。生で見る憧れの清原の迫力に圧倒された後のサブマリンエースは「いつか清原さんと対戦してみたい」と夢見たという。 PLの先発・桑田は、6回を3安打6奪三振の1失点に抑えると、お役御免となり、22対1の7回表からライトに回った。ライトスタンドでは、第1試合で岡山南を破った東海大甲府の1年生・久慈照嘉(元阪神、中日)が、他の部員たちとともに兄弟校・東海大山形の応援中だったが、大量リードを奪われた悔しさもあって、ライトにやって来た桑田に野次を飛ばしたという。 地方大会なら5回の時点でコールドゲームになってもおかしくない点差にもかかわらず、終盤に入っても、PL打線は一向に攻撃の手を緩めない。 県勢初の8強入りを達成 7回は6長短打を集中して5点を追加。無死一塁で打席に立ち、「一発を狙った」清原は左飛に倒れたが、「あんなに高々と上がったレフトフライは、山形では見たことがなかった」と左翼手を驚嘆させた。この日は先発9人中6人までが3打点以上を記録する猛攻にあって、5打数2安打1打点2四球とあまり目立たなかった清原は「あの試合はしんどかった。誰がアウトになるのかという感じやったから」と回想している。 さらにPLは8回にも2安打と敵失に乗じてとどめの2得点。この瞬間、春夏の甲子園を通じて史上初の毎回得点が記録され、これまた春夏通じて史上最多の29得点となった。 東海大山形は、エース・藤原安弘が県大会で肘に重度の炎症を起こし、本来なら投げられる状態ではなかったが(試合後に剥離骨折が判明)、エースの責任から打たれても、打たれても歯を食いしばり、5回まで132球、被安打21、四死球4、失点20で投げ切った。だが、エース降板後の6回以降の3イニングもいずれも失点を重ねるという結果に、滝公男監督も「1回ぐらいは0点に抑えられると思ったが……」と絶句した。 27点差を追う9回、東海大山形はPLの3番手・小林克也に4長短打を浴びせて3点を返すと、春に続いて甲子園のマウンドに上がった清原からも2つの押し出し四球で2点をもぎ取ったが、反撃もここまで。この回11人目の打者・高橋勝利が一飛に倒れ、PLが29対7で勝利した。 プロのチームも顔負けの破壊力に、プロで活躍する同校のOBも驚くばかり。西武・金森栄治は「かわいげがないほど強過ぎるね。今年のチームじゃ、オレでもレギュラーになれないんじゃないか」と苦笑し、広島・小早川毅彦も「相手の青春を壊しちゃいましたね」と東海大山形に同情的だった。 一方、山形県では、歴史的大惨敗から約2ヵ月後の同年10月、県議会予算特別委員会で「我々山形県民は大変悔しく、残念な思いをした」「県民の意識高揚にもつながる大事な問題だ」などの声が挙がり、高校野球が政治の場で論じられる異例の事態となった。 山形県勢はこれまで全国で唯一甲子園8強以上がなく、夏の甲子園が1県1代表制になった1978年以降も、2勝8敗と負け越し。うち7度が初戦敗退だった。長年にわたる低迷が、29失点という歴史的惨敗を契機に、「どうして勝てないのか」「全国との差を縮めたい」という県民レベルの活発な議論を呼び、改革への大きな第一歩となる。 こうした流れを受けて、県高野連も強化に本腰を入れるようになり、1997年末に野球強化特別本部が設置されると、秋の県大会上位3校を冬季に雪のない地域で合宿させるなど、本格的な強化事業が推進された。 この間、東海大山形も悪夢の大敗から2年後の1987年夏に甲子園初勝利を含む2勝を挙げ、79年の日大山形以来の県勢の最高成績・ベスト16入りを実現。前出の強化事業を経た2006年夏には日大山形が県勢初の8強入りを達成し、13年夏にも、奥村展征(元巨人、ヤクルト)、中野拓夢(現・阪神)らの活躍で初の4強入りをはたしている。 久保田龍雄(くぼた・たつお) 1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘!激突!東都大学野球』(ビジネス社)。 デイリー新潮編集部