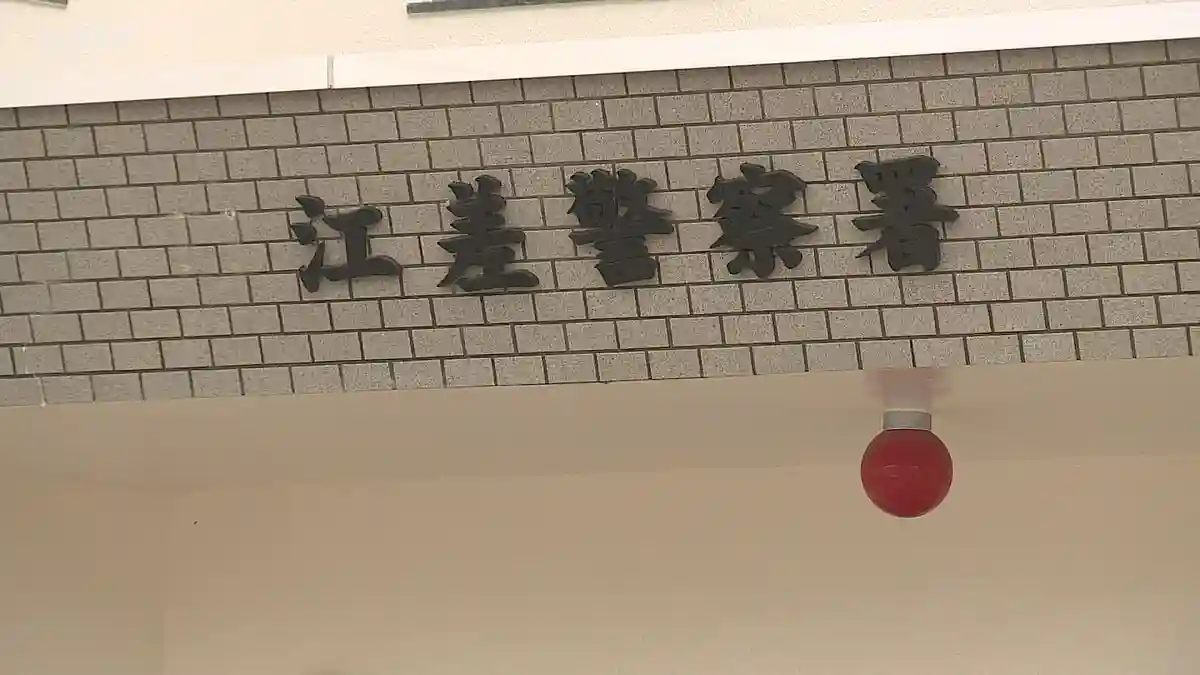「進化は再現不可能な一度限りの現象なのか? それとも同じような環境条件では同じような適応が繰り返し発生するのか?」 進化生物学者の間で20世紀から大論争を繰り広げられてきた命題をめぐるサイエンスミステリーの傑作、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』が発売されました。 本記事では、〈小笠原にたどり着いた「カタマイマイ属」の祖先がもたらした、進化の「特異な結末」〉に引き続き、「進化の繰り返し」について見ていきます。 ※本記事は、千葉聡『 進化という迷宮 隠れた「調律者」を追え 』(講談社現代新書)より抜粋・編集したものです。 未来の創始者 海洋島の陸貝は、たまたま海流に乗ったり、鳥に付着して運ばれるなど、偶発的なプロセスで本土から移り住む。だから祖先がどの系統になるかは、小型だとか変動環境に強いとか、移住に有利な性質も関わるものの、偶然の要素が非常に大きい。本土や大陸に住む様々な系統の中から、オオベソマイマイ族の系統が小笠原に辿り着いたのは、その進化の歴史を含めて偶然の結果だろう。 もしこの系統が辿り着かなかった並行世界があれば、その世界の小笠原では、違う陸貝の姿が進化したかもしれない。その世界での「調律者」がする仕事は、全く別の結末に適応を導くはずだからだ。太平洋の多数の島々で細長い塔形のカタツムリが示した「進化のパーツ」(第八章)は、別のどんな結末が有り得るかを示唆している。 塔形の系統では、ニッチ分化は起きても、それに対応した形の進化は繰り返さない。理由ははっきりしないが、重力や付着基質が形に及ぼす効果が相対的に小さく、他の環境要因や偶然の効果など、多くの要因が適応度に関わるためかもしれない。 殻に及ぼす重力の作用や殻の効率的な背負い方は、細長い塔形の殻と平巻きの殻ではかなり違う。細長い丸太は肩に担ぐほうが運びやすいが、平たい木の切り株なら背負うほうが楽に運べるのと似た理屈である。物に付着したり身を守るのに有利な条件も違っている。 例えば塔形の殻は垂直面の多い樹上では、細長いほど幹に安定に付着できて脱落しにくい代わりに、万一脱落して地面に落ちると、先端部が折れて破損しやすい。このように塔形の殻の場合、暮らし方や機能に関係するトレードオフは、カタマイマイ属のような平巻きの殻とは大きく異なる。同じ問題の最適解が塔形と平巻きでは違うのである。 カタツムリでは、塔形と平巻きの中間的な殻をもつ種は少ない。塔形と平巻きの間を移り変わる進化が起こるケースも非常に少ない。これは両者の自由な移行を妨げる、制約が存在するためだと考えられる。 要因の一つは、適応の谷。重力下では、両者の中間的な形の殻はバランスが相対的に悪く、取り回しにエネルギーを必要とすることが、数理的な解析から推定されている。 もう一つは、発生的制約。セリオン属の成長様式を分析したグールドは、殻の細長さは適応の結果ではなく、殻の成長と巻き方の幾何学的ルール(発生的制約)で説明できると結論した。また、平巻きのカタツムリから背が高めの個体を選抜し、人為選択で塔形を進化させようとしたら、中間的な形で進化が止まり、それ以上背が高くならなかったという実験結果もある。 いずれのプロセスにせよ、塔形と平巻きは、相互の移行が制限されている。 一部の系統で例外はあるものの、平巻きか塔形かという殻の概形には、系統的制約が強く効いているのである。島で進化した子孫がどちらになるかは、その祖先がどちらだったかで、おおむね決まってしまう。特に祖先が塔形だった場合には、そこから平巻きの子孫が進化する可能性は極めて低いので、その多様化の行方はほぼ祖先の時点で決定される。 もし小笠原にたまたま塔形の祖先しか辿り着かなかったなら、太平洋の他の島々と同じく、カタマイマイ属のような同じ適応放散の繰り返しは起きなかっただろう。 実はこの推測を確かめる「進化のパーツ」がある。小笠原にも細長い塔形の祖先に由来する系統がいるからだ。それはオガサワラキセルガイモドキ属という長さ1〜1.5cmの系統で、種や集団により木の位置──樹上、根元などの住み場所と殻の形が分化している。 では、その進化史はどうか?この推定に取り組んだ、和田慎一郎の研究によれば、未記載種も含めて恐らく10種以上に分化し、一部に形態の収斂が見られるものの、やはり明確な繰り返しは、その適応放散には見出せないという。 日本本土や大陸には、この仲間のキセルガイモドキ科がいる。特に中国では非常に多様性が高いが、やはりどれも塔形で、中国から来た学生の研究によれば、明確なニッチ分化も認められない。ただし昆虫など捕食者への適応で、形の収斂は起きているようだ。 殻に備わる機能的なトレードオフが適応地形の峰とその数を決めるなら、『進化という迷宮』第五章で触れたように、多くの環境要因が関わるほど地形は複雑化し、峰の数は増える。また島ごとに適応地形が変わり、島ごとに異なる一期一会の適応進化が起きる可能性が高まる。 この考えが正しければ、平巻きでも直径数mmしかない小型種のカタツムリでは、同じ進化を繰り返さない可能性が高い。小型種では重力に加えて、表面張力や抵抗力が殻の取り回しに強く関与するし、樹木や落葉層の細かな構造も影響するからだ。 では小笠原の平巻き小型種はどうか。オガサワラヤマキサゴ属とエンザガイ属は著しい適応放散を遂げ、カタマイマイ属とほぼ同じ種数に分化したグループである。系統推定の結果、予想通り、複数の島や地域で、同じ形と生活様式が独立に進化したケースは、オガサワラヤマキサゴ属では半数以下の種に限られ、エンザガイ属では一つもなかった。 第十章で登場したオガサワラベッコウ類も同様だ。異なる島で独立によく似た形が進化したのは地上性のタイプに限られる。もっと小さい1〜2mmの微小貝でも、形の違いと住み場所の関係は不明確で、似た進化の繰り返しは見られなかった。 実は殻の大きさにも制約があって、島嶼で小型の系統が大型になることはめったにない。塔形か平巻きかに限らず、たいていの島嶼では、そこで進化したカタツムリの大きさと形は、最初そこに"どんな奴"がやってきたかで、あらかた決まる。 実際、小笠原以外の太平洋と大西洋の一一の群島では、各群島で見られるカタツムリの殻の形態の多様性は、生態やニッチの違いより、分子系統樹から区別された科や属の違い──つまり、どんな系統がそこに移住したかを強く反映している。島で進化した子孫の殻の特徴は、その祖先が大陸で辿った進化の履歴に制約されるのである。 というわけで、海洋島で同じ大進化が繰り返されるかどうかは、祖先次第で決まると言えるだろう。適応放散が何度も似た結末に至るかどうか──小笠原でカタツムリの暮らし方や形の最適解がいつも同じスペシャリストのセットになるかどうかは、殻が塔形か平巻きか、大型か小型か、大型で平巻きなら、殻の変化のしやすさや、それに反映された遺伝的要因に依存する。 つまり、同じ自然選択が作用して、彼らの進化が「調律」されるかどうかは、彼らの祖先が持っていた殻の姿形と性質次第なのだ。従って、祖先にそのような姿形と性質を与えたものこそが、「調律者」の正体であろう。 * さらに〈かつては「70cm以上のトンボ」が存在していたことも…なぜ「巨大な昆虫」は現代に存在しないのか?〉では、巨大生物の進化について見ていきます。 【つづきを読む】かつては「70cm以上のトンボ」が存在していたことも…なぜ「巨大な昆虫」は現代に存在しないのか?