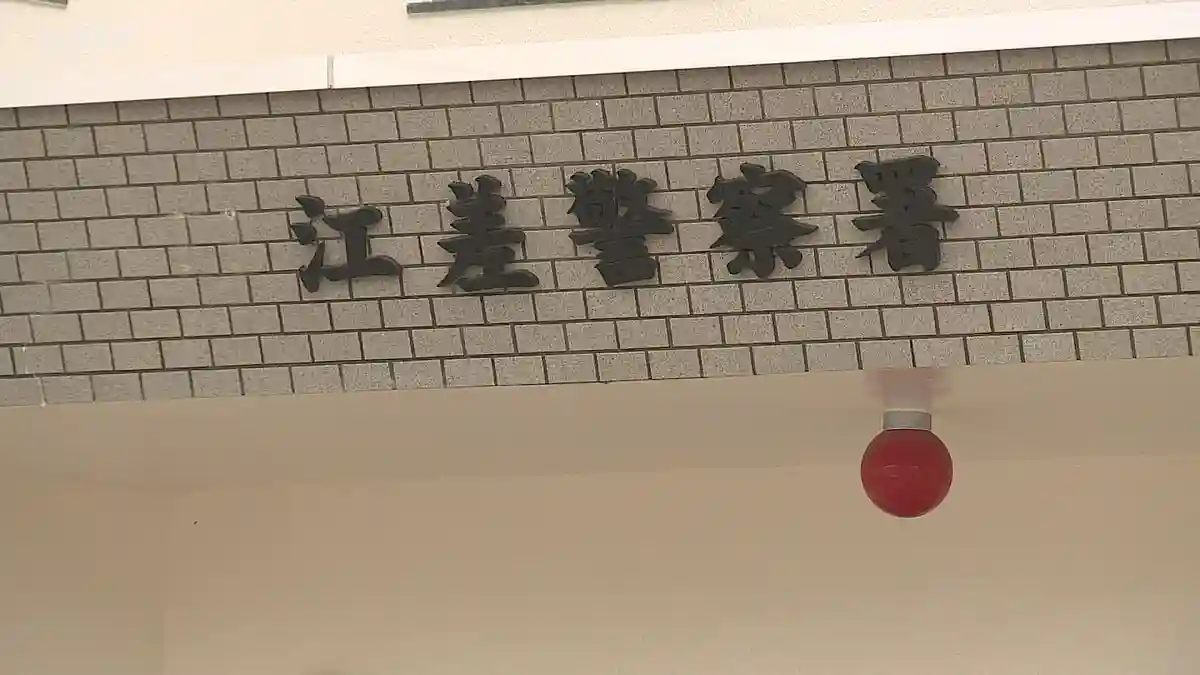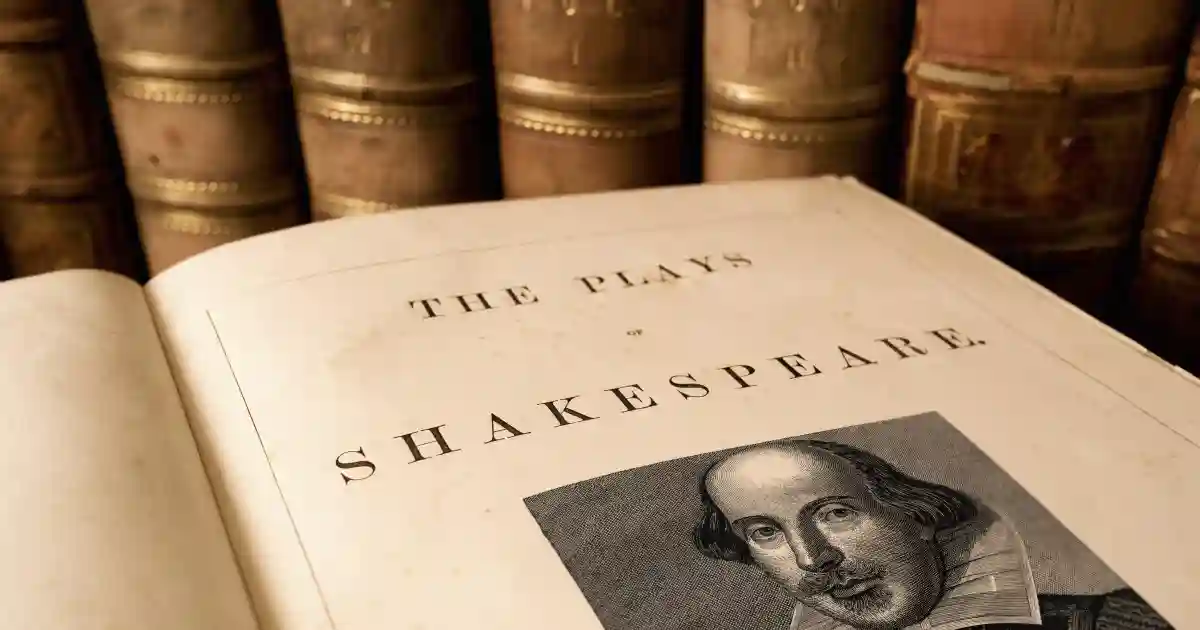
人類は進化の過程で共感力を獲得し、言語を発達させてきた。そのなかで生まれたのが歌やダンス、演劇だった。そうして演劇は人と人とを繋ぐ芸術となっていった。戦争が止まらないこの時代にこそ私たちはもう一度立ち止り、人類の来し方に思いを馳せたい。群像にて連載中の『ことばと演劇』では、劇作家の平田オリザが演劇の起源に迫っている。 ※本記事は群像2025年9月号に掲載中の連載『ことばと演劇』より抜粋したものです。 シェイクスピア劇と近代 シェイクスピア劇は、まさに近代の黎明の時期に書かれた。イングランドがスペイン無敵艦隊を破り、のちに世界に冠たる大英帝国となる、その一歩を踏み出しはじめた時代。初期の「囲い込み」(エンクロージャー)が起こり、農村は崩壊し都市が生まれる。くり返すペストの流行などもあって、決して一足飛びに人々の生活が豊かになった時代ではないが、しかし、それでも人はいい時代に生きた。明日は今日よりましになると信じられた時代。自由は人々を平等にし、豊かにすると希望を抱けた時代。しかし一方で、その精神の揺らぎが始まった時代。 念のため、その核の部分を年表のように表すなら、おおよそ以下のようになる。 一五五八年 エリザベス一世即位。 一五六四年 ウィリアム・シェイクスピア誕生。 一五八○年代後半 シェイクスピアはロンドンに移住し演劇活動を始める。 一五八八年 アルマダの海戦でイングランド海軍がスペイン無敵艦隊を撃破。ナショナリズムが高揚する。 一五九○年代前半 シェイクスピアが執筆活動を開始。多くの歴史劇や初期の喜劇を書く。 一五九二年頃 『リチャード三世』 一五九四年 シェイクスピア、宮内大臣一座に加入。 一五九四年−一五九五年 『ロミオとジュリエット』、『夏の夜の夢』、『リチャード二世』 一五九六年−一五九七年 『ジョン王』、『ヴェニスの商人』、『ヘンリー四世 第一部・第二部』 一五九八年−一五九九年 『ヘンリー五世』 一五九九年 グローブ座開場。シェイクスピアの主要な上演拠点となる。『ジュリアス・シーザー』 一六○○年頃 『お気に召すまま』、『十二夜』 一六○一年 『ハムレット』 一六○三年 エリザベス一世崩御、ジェームズ一世即位。宮内大臣一座は国王一座に改称し新国王の庇護を受ける。シェイクスピアの劇団は、王室の公式な劇団として、さらに権威と地位を高める。 一六○四年頃 『オセロー』 一六○五年頃 『リア王』 一六○六年頃 『マクベス』 一六一一年頃 『テンペスト』(最後の単独執筆戯曲とされる。) 一六一三年 グローブ座焼失、その後シェイクスピアは失意のうちに引退。 一六一六年 ウィリアム・シェイクスピア死去(享年五十三)。 ここでまず注目してもらいたいのは一五八八年、スペイン無敵艦隊を破ったアルマダの海戦と、その十年後に書かれた『ヘンリー五世』の上演だ。 『ヘンリー五世』では、若きヘンリー五世が放蕩王子から一転して偉大な国王へと成長し、フランスとの百年戦争におけるアジャンクールの戦いを勝利に導く姿が描かれている。 『ヘンリー五世』の影響 この作品では若き国王が国民を鼓舞し、団結させ、母国を勝利へと導いていく。特に有名な「聖クリスピンの日の演説」は、数的に劣勢なイングランド兵士たちの士気を高め、彼らに共通の目的と帰属意識を与えた。この演説は身分の隔たりを超えた「兄弟」としての絆を強調し、国家の一員としての誇りを兵士たちに植え付ける。シェイクスピアは、史実を基にしつつも、ドラマティックな要素を加えてヘンリー五世を国民的英雄として再構築した。 この連載を読んでいただいている奇特な読者なら、歴史の強い相似性に思い至るだろう。古代ギリシャにおけるサラミスの海戦の勝利と、その八年後に上演された『ペルシャ人たち』だ。アテナイを中心としたギリシャ連合軍が、ペルシャの大艦隊を打ち破ったのが紀元前四八○年、その勝利を歌った『ペルシャ人たち』をアイスキュロスが書いたのは紀元前四七二年。それまでバラバラだったギリシャ人たちは、『ペルシャ人たち』を観ることによって、ギリシャ人としてのアイデンティティを確立した。 もちろん『ヘンリー五世』は、アルマダの海戦そのものを書いたのではない。しかし、イングランドが数的不利を覆して大勝利を収めたアジャンクールの戦いは、当時のロンドン市民たちに、アルマダの海戦を容易に想起させただろう。 スペイン無敵艦隊を破ったとは言え、まだまだイングランドはひ弱な新興国だった。一五九九年はエリザベス一世の晩年、アイルランドでの反乱などイングランドを取り巻く国際情勢は不安定だった。この時期、『ヘンリー五世』の上演が果たした社会的な影響は小さくなかったはずだ。 演説ということで言えば、アルマダの海戦前のエリザベス一世のものも有名だ。 愛する国民たちよ、(中略)私はあなた方の忠誠心に疑いを抱いているからではなく、また、不信感からでもなく、あなた方の間に秩序と規律を保つために、そして、もし敵が侵攻してきたときに、彼らをすぐに打ち破れるように、この軍営にやって来たことを知っていてほしい。 私自身、いま、こうしてあなた方のもとにやって来た。いま、危険のただ中に、困難のただ中に、共に私の命と血を賭す覚悟である。あなた方と共に、神と共に、私の王国と民のために、その名誉と血を土の中に横たえる覚悟である。 私は弱々しい女の体を持っていることを知っている。しかし私は、国王の心と胃を持っている。そしてスペインや、欧州のいかなる君主も、私の王国の領域を侵害するという傲慢なことを考えるなら、私はそのことを軽蔑する!(後略) 『エリザベス ゴールデン・エイジ』のケイト・ブランシェットほど、本物のエリザベス一世が格好良かったかどうかは定かではないけれど、演劇好きであったとされるこの女王が、当時の劇作家の言葉、俳優の息づかいから雄弁のなんたるかを学んでいたことは間違いないだろう。 残念ながら、この時点では、まだシェイクスピアは戯曲の執筆を開始していない。ただ、この時代は近代英語が形成された時期でもあった。英語による弁論術とエリザベス朝演劇はお互いに影響しあいながら進化したはずだ。シェイクスピアはその発展を正しく受け継ぎ、新しい言語である英語が持つ表現力の豊かさを極大化した。 ちなみに第二次世界大戦中にローレンス・オリヴィエが監督・主演した『ヘンリー五世』の映画版は、戦意高揚を目的としたプロパガンダ的性格が強いことで知られている。英国にとって、この作品がいかに重要な文化遺産であるかが解るだろう。