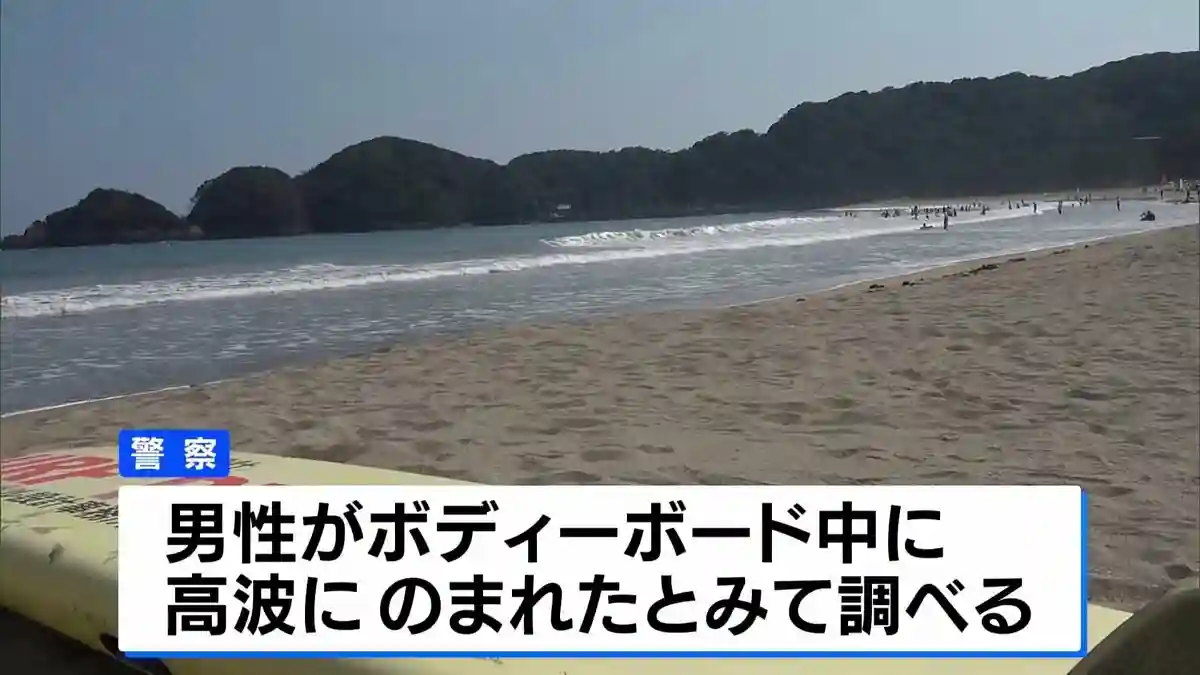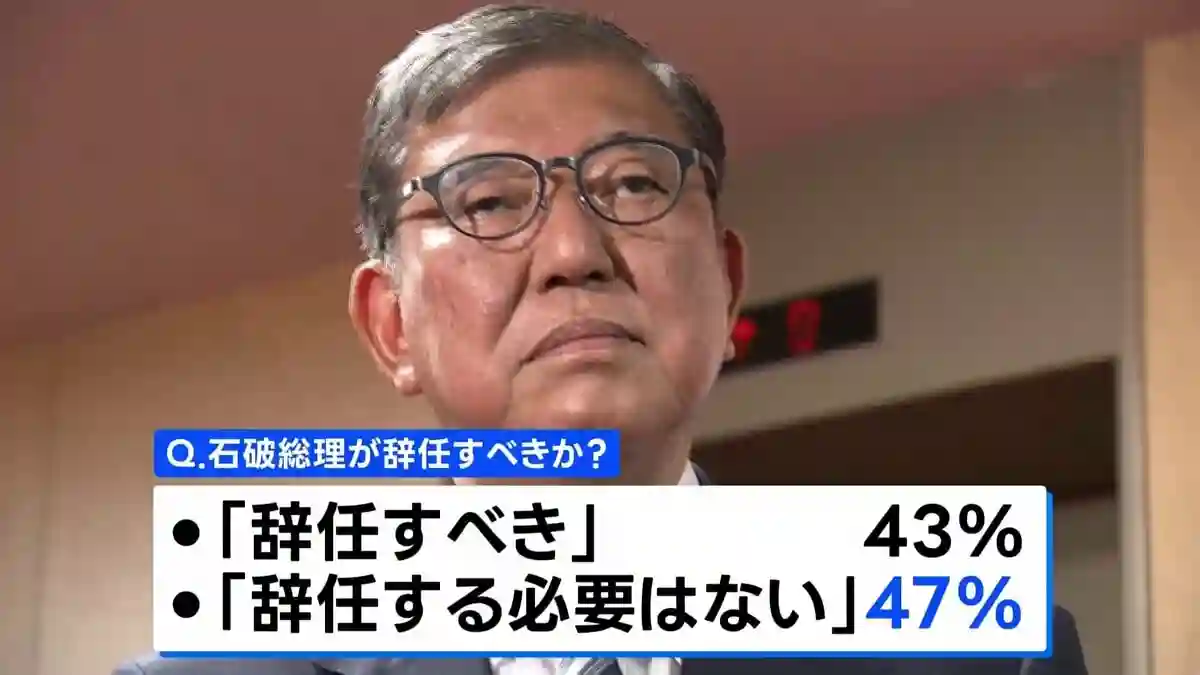13年ぶりの「あ展」 「明治おいしい牛乳」といえば、弧を描いた青いパッケージがパッと思い浮かぶだろうか。静かなド直球を放つあの青いパッケージ。日本を代表するグラフィックデザイナーの佐藤卓がこのパッケージをデザインしている。 【写真】巨大な「あ」に驚いたあとに始まる…「すわる」「こわす」「たべる」動詞で遊ぶ体験の数々 佐藤氏は一貫して、「小学校の低学年から、デザインを授業の中で教育したい」という願いを持っている。その願いからNHK Eテレ『デザインあ』が生まれ、さらに番組を全身で感じる「デザインあ展」へと展開した。 第1回の「あ展」が開催されたのは13年前の2013年。その後4年間にわたり全国を巡回し、会場に入るまでに長蛇の列ができるほどに人気を博し、累計116万人もの動員を記録した。 巨大あ おしゃべりしたり、笑ったり、家族で楽しめる貴重な展覧会で、あの頃「あ展」を楽しんだ子供たちの中にはもう社会人もいるだろう。 その「あ展」が「あ展neo」としてアップデートして帰ってきた。 さあ、展覧会を訪れてみよう。 「しっかりとみる」面白さ 会場は、東京・港区の虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階に位置する「TOKYO NODE GALLERY A/B/C」。最寄りの虎ノ門ヒルズ駅を降りると、その瞬間からもうデザインの力に導かれ始めている。 駅から会場までの道のりは複雑で長い。エレベーターとエスカレーターを乗り継ぎ、心細さを誘う細い廊下をぐるりと巡り、なんとか会場にたどり着いた時には、 「自分たちでなんとか辿り着けた!」 と安堵と同時に小さな達成感を抱く。 なぜ誰にも案内されずに辿り着けたのか? そう、これは私たちの動作をつなげてくれたデザインのおかげ、というわけだ。 ということで、「デザインあ展neo」のテーマは「動詞」。というこの流れもデザインの一部。 会場に入ると巨大な風船でできた「あ」に遭遇して「あっとおどろ」き、そして「あるく」「たべる」「すわる」など今まで無意識にやり過ごしてきた「動詞」をまじまじと意識する。 今まで当たり前のようにスムーズに座っていたのは、座りやすくデザインされた椅子のおかげ。偉そうな気分になるのはそんな気分になるようにデザインされた椅子のおかげ。 かと思えば豆をつまんだり、海苔をごはんにくるんだり、ちぎったり突き刺したり、変幻自在な役割をするお箸はなんともシンプルなデザイン。 身近なあれやこれやが改めて「展示」されることで、日常の中で自分の目がいかに見ているようで見ていないかがわかってくる。そして「しっかりとみる」面白さがフツフツと芽生えてくる。 いろいろな「動詞」を体験 この展覧会の醍醐味は体験。 「むち」「パリ」「ジュワ」など食べた時の感触が記された丸いつみ木を、ハンバーガーや海苔巻きの中にはめ込んで食べ物を想像上で完成させる「オノマトピース」。 天井に逆さに吊るされたゴミ箱にゴミを捨てる(?)「るてす」。 壺をこわす、なんて滅多に出来ないことを思い切り楽しんで、そしてなおす「こわすとなおす」。 いろいろな「動詞」を体験した後に、あたかもゴール地点のように設けられているのが「デッサンあ」。広々としたスペースの真ん中に、これほど複雑な形の椅子があるだろうかと思えるほどの多機能のワークチェアが1脚置かれ、その周りを大勢の来場者がぐるりと囲む。老いも若きも関係なく、誰も彼もが黙って夢中で鉛筆を走らせてデッサンしているのだ。この光景が一つの展示といっていいほどに何よりも印象的で、そして美しい。 「かく」行為が、押し付けではなく自発的になるために流れがデザインされた展覧会。「かく」ために「よくみる」が絶対的になる複雑なデザインの椅子。 これらの後に、映像と音楽の没入体験で、「あ展」のクライマックスに身をゆだねる。改めて、「つくる」という行為は美しい、と感じる。そして、この映像や音楽をじっくり時間をかけて作った人たちにも思いを馳せてみたりする。 デザインの本質 「あ展」で感じるのは、削ぎ落とせるところはとことん削ぎ落とした、一見無機質にも見えるシンプルな展示構成だ。陳列は整然としているし、キャプションの言葉は必要最低限。けれども少しも冷たい感じがしないどころか、だんだんと手間ひまかけて整然と整えた「人の手」が感じられてくる。そしてユーモアも見えてくる。 展覧会の監修者でもある佐藤氏は著書『塑する思考』(新潮社、2017)の中で繰り返し語っている。 「デザインの本質は、物や事をカッコよく飾る付加価値ではありません」(帯より) 「『間に入って繋ぐ』のがデザインの役割です」(176頁) この思いが、展覧会とNHK Eテレの番組を通しての土台になっている。 「私は今、切実に、小学校の義務教育の授業に『デザイン』を取り入れるべきだと思っています。前述してきたように、ありとあらゆる物事と人との間にデザインはなくてはならなず、人の営みの中で何事かに気づき、これからを想像し、先を読みつつ対処するのがデザインであるならば、それは『気づいて思いやる』、つまり『気づかう』ことに他なりません。 デザインは、自ずと道徳にも繋がっており、それは、我々を取り巻く地球環境を人の営みと共に気づかい考えることでもある。 だから一日も早く、小学校低学年からデザインマインドを育む『デザイン』の授業を、世界に先駆けて日本で始めてはどうかと提案したいのです」(219頁) 本気でとことん作品を作り込む 「デザインあ」シリーズは、子供向けに作られたテレビ番組や展覧会であるにも関わらず、キャラクターは一切登場しない。その代わり、デザイナーやアーティスト、ミュージシャンが本気でとことん作品を作り込んでいる。 そこからは、子供一人ひとりを一人前として信頼し、対等に作品を提供している大人の姿が見えてくる。 「はぐくむ」 展覧会の中心に、この動詞を体感できる。 土居彩子(どい・さいこ) 1971年富山県生まれ。多摩美術大学芸術学科卒業。棟方志功記念館「愛染苑」管理人、南砺市立福光美術館学芸員を経て、現在フリーのアートディレクター。 デイリー新潮編集部