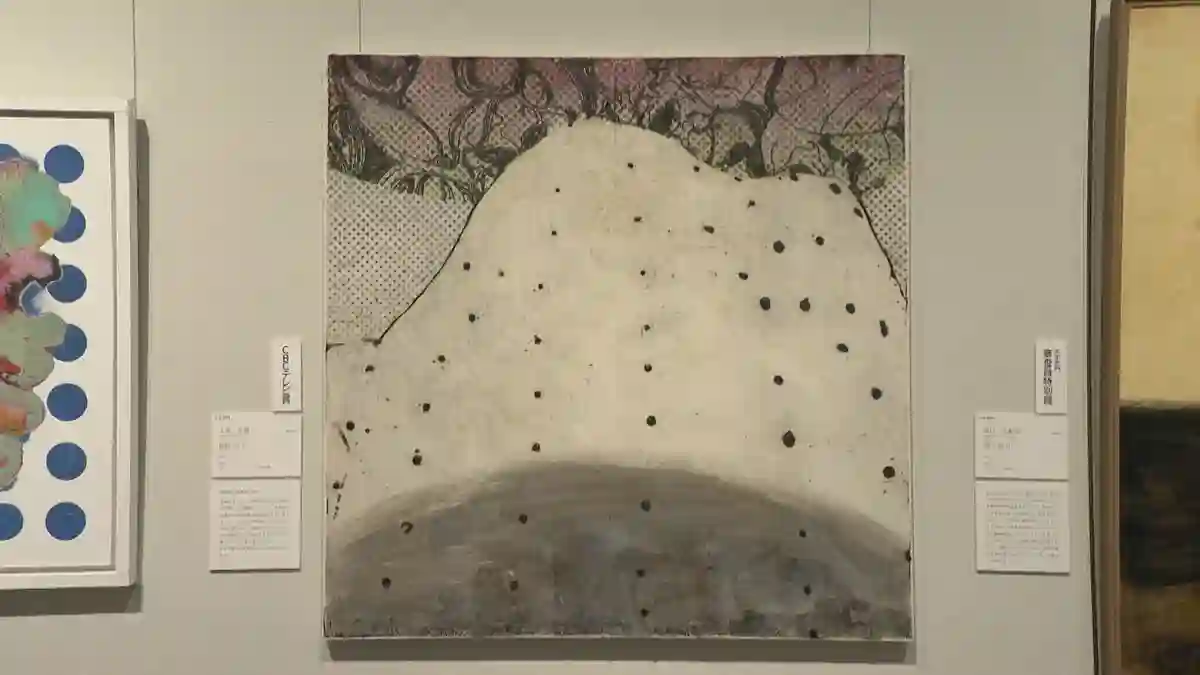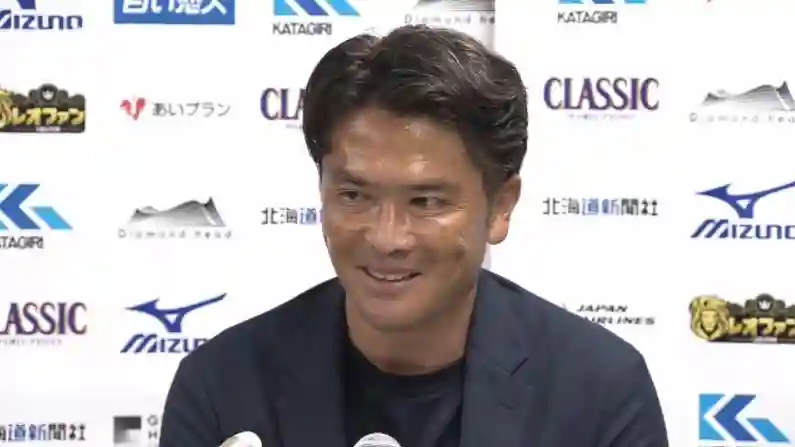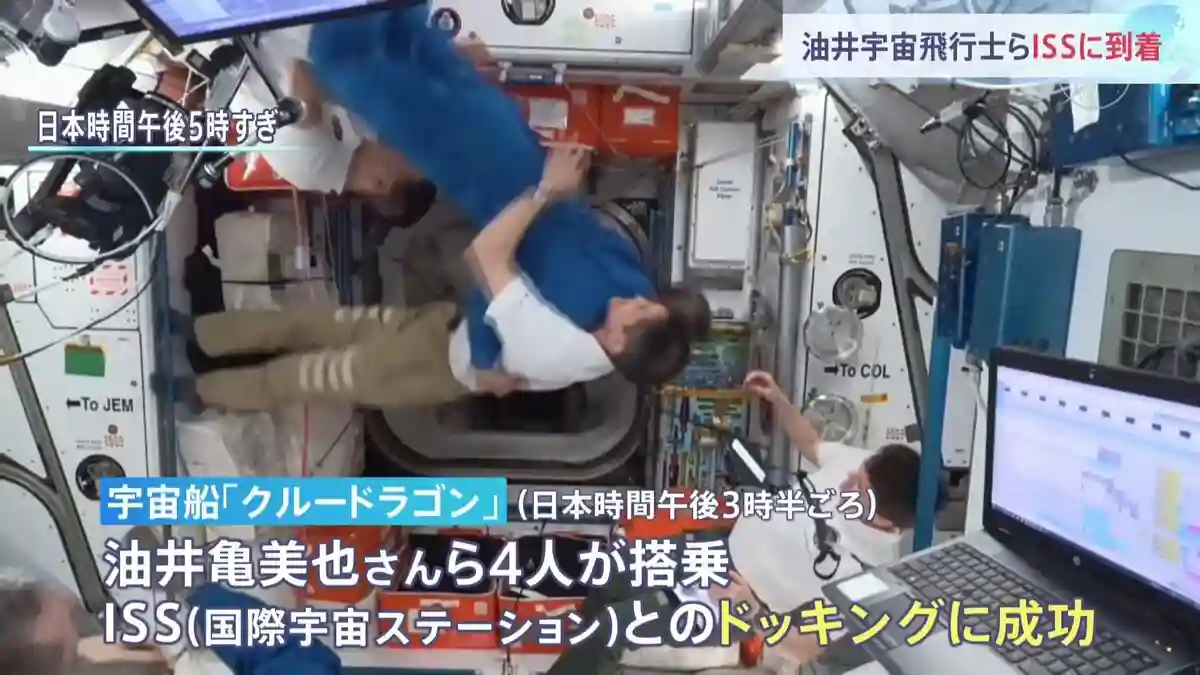ゆいまーる精神に根差した沖縄特有のヤミ金文化も転換期を迎えている 求人誌にもハローワークにも求人が出ないいわゆる「裏稼業」にも、地域ごとに独自の発展を遂げるものがある。列島各地の文化・風俗がそれぞれ異なるように、その土地に根付く人々の生活様式や慣習などに応じてそのあり方が変わるというわけだ。 【写真】ヤミ金業者が使っているスクーター 日本最南端の「沖縄のヤミ金」もそのひとつだ。2000年代初頭、多重債務者への苛烈な追い込みが社会問題化したことを受け、全国のヤミ金業者の多くが淘汰され、不良たちが手がける金融がらみの犯罪のトレンドが振り込め詐欺などの特殊詐欺へと移行した一方で、「沖縄ヤミ金」は地元の不良たちの主要なシノギであり続けた。 そんななか、地元の捜査関係者の間で波紋を呼んだのは、7月に「首謀者」とされる男の逮捕が報じられたグループの存在だった。昔ながらのヤミ金とは一線を画すシノギを行っていたというこのグループ。その実態はどんなものだったのか。 ■沖縄ヤミ金トップの逮捕 「沖縄を拠点とするヤミ金グループのトップを逮捕」。沖縄のメディア各社が一斉にこんな見出しの一報を打ったのは7月24日のことだった。沖縄県警がこの日、海外に逃亡していた「ヤミ金グループ」の幹部とされる37歳の男らを逮捕したと発表したのだ。 地元メディアなどによると、男は県内を中心に違法な高金利で全国600人以上に総額約4億円を貸し付けていた「ヤミ金グループ」のトップ。グループは2024年2月、県警の大規模な摘発を受けてメンバー9人が逮捕されていたが、男ら数人が海外に逃亡し、県警が行方を追っていたという。 「県警がグループトップの『指示役』とみている男は、自身に捜査の手が伸びる前にカンボジアに逃亡していました。ほかのグループ幹部もその男の後に続き、行方をくらませていた。 男らには外務省を通じて旅券返納命令が出ており、県警側が現地当局に情報提供を呼びかけていた中で、『ベトナムで日本人が拘束された』との情報が外務省に入った。これを受け、県警が現地に捜査員を派遣し、今回の逮捕に至ったというわけです」(地元メディア関係者) 事件は、男が率いたとされるグループについて、県警が「匿名・流動型犯罪グループ(通称トクリュウ)」と認定していたことでも注目を集めた。「トクリュウ」は、警察庁が、「半グレ」との俗称でも呼ばれる「準暴力団」に次いで、新たな組織犯罪の類型として定義づけた集団だが、このグループの摘発が、県内では「トクリュウ摘発第1号」になったことで地元でも大きく報じられたのだ。 「すでに大規模な摘発があった際に逮捕された9人の公判を終えていたこともあり、地元では男の逮捕が驚きをもって受け止められました。いっぽう、県警側はグループの存在を把握した当初から危機感をもって捜査を進めていたとみられます。このグループによる債務者への貸付額が巨額だったのと、これまでのヤミ金グループには見られなかったような、ある意味で�洗練�された手口が使われていたからです」(同) ■ヤミ金文化が根付く特殊な風土 沖縄は、47都道府県の中で県民の所得がひときわ低いことで知られる。県が公表した2022年度の1人当たり県民所得は224万9000円で全国最下位。同年度の1人当たり国民所得は327万4000円となっており、沖縄県民所得との間では実に100万円超の開きがある。 こうした経済事情もあってか、生活のために借金を重ねて多重債務に陥る県民が後を絶たず、そうした人たちを食い物にする違法なヤミ金業者がのさばり続けてきたという実態がある。 「もともと沖縄には『模合(もあい)』という独特の風習も根付いています。友人や知人、親族で会費を持ち寄って定期的に会合を開き、集まった会費を参加者のひとりに貸し付けるというシステム。『ゆいまーる』という言葉に象徴される、相互扶助の精神が根付く沖縄独特の慣習ですが、貸金業法の規制に牴触するグレーな部分があるのは否定できない。 そんな事情もあり、ヤミ金が根付きやすい土壌があるのに加え、いわゆる『うーまくー(やんちゃ)』な不良少年たちが、ヤミ金のノウハウを仲間内で伝授しあってきた�伝統�もヤミ金業者がなくならない要因のひとつになっています」(地元関係者) 沖縄ヤミ金構成員愛用の125ccスクーター 沖縄では、中型免許が必要な125CC以上のスクータータイプの中型バイクを目にする機会が多い。沖縄を南北に縦断する国道58号線で車を走らせると、渋滞をすり抜けてバイクを爆走させるヤンキー風の青年たちの姿が目に入ることだろう。 「彼らの多くは、ヤミ金業者です。やんちゃな若い子たちの間で、『ヤミ金』というのは金を稼ぐ手段のひとつとして定着している面があります。彼らが好んで使う半帽型のヘルメットは『ヤールーメッタ—』と呼ばれて人気のアイテムのひとつにもなっている。タイト目のジャージ上下などもヤミ金ルックの定番で、彼らは一種のトレンドリーダーのような存在もあるのです」(同) ■本土式の手法流入に警戒 沖縄のヤミ金の特徴としてあげられるのが、債務者に対する対応だ。 金の貸し付けと回収は基本的に「対面」で行う。債務者への苛烈な追い込みは御法度で、法外な金利をトラブルなく長期間にわたって回収するのがセオリーだとされる。債務者と債権者という立場ながら、関係性を大事にする点は「ゆいまーる」の島らしいともいえるが、閉鎖的な島社会では債務者が逃げることは困難だ。 地元の「うーまくー」の中には、ヤミ金で稼いだ資金を元手に飲食などの事業を始めたりする事例も少なくなく、「なかには裸一貫で始めて、億単位の資産を築いた者もいる」(前出の地元関係者)という。 熾烈な取り立てやSNSでの集客など、本土式のヤミ金運営システムが上陸したことに、地元当局も警戒を強めている 「当局もこうした背景を理解しており、地元に根付く彼らを半ば黙認している面もあります。よほど強引な取り立てをやらない限りは、そこまで業者に追い込みをかけることもない。ただ、今回『トクリュウ』として摘発されたヤミ金グループについては、こうした沖縄独特のヤミ金の�常識�とは外れていたことが捜査関係者にとっては衝撃だった面があるようです。 トップの男が本土式の手法を持ち込んだとされており、取り立ての電話をかけまくる『鬼電』で債務者を追い込んだり、アシがつかないように郵便を介して貸し付けや回収を行うなど、これまでの沖縄ヤミ金にはないやり方をしている。顧客名簿をスプレッドシートで管理し、XなどのSNSを集客のために使うなど、手法はかなりシステム化されている。 県警側が大規模な捜査に乗り出したのは、こうした新たなヤミ金の手法が県内で広がるのを警戒したということも背景にあるようです」(前出のメディア関係者) ゆいまーる精神に根差した沖縄伝統の金融システムは、転換期を迎えている。 文/安藤海南男 写真/photo-ac.com