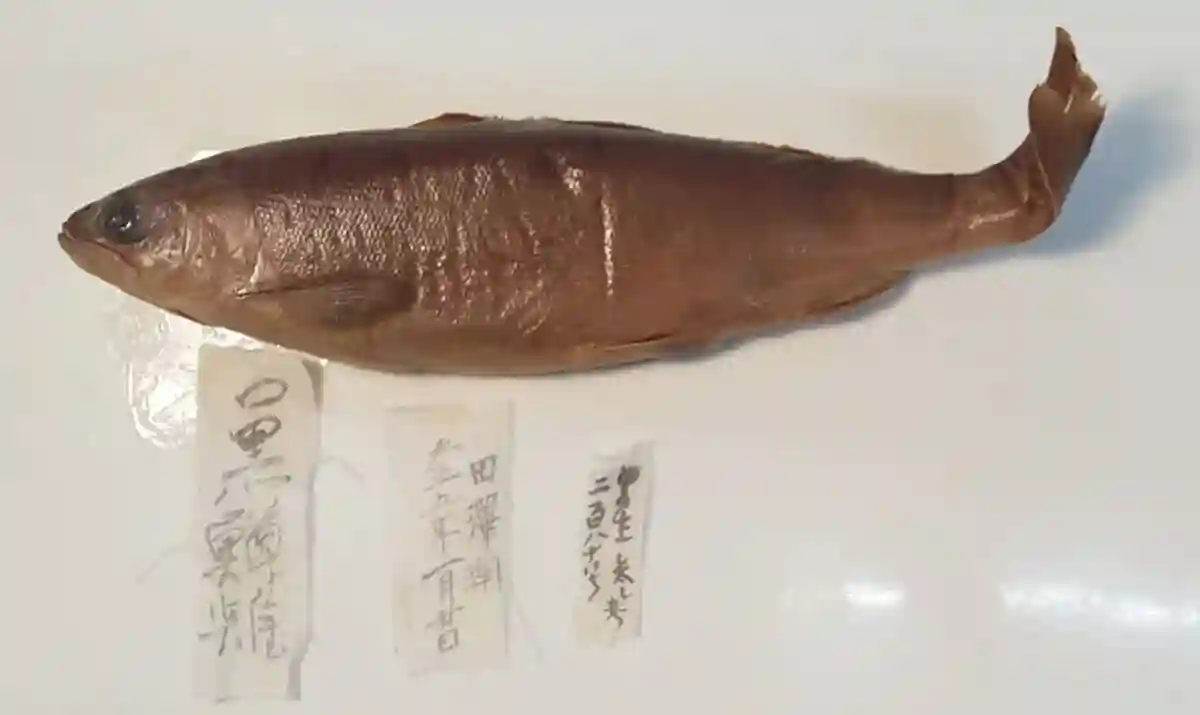国会議員と弁護士は、法律に携わるという共通点がある。2021年に初当選した塩崎彰久衆院議員(元厚生労働政務官)は、大手総合法律事務所のパートナーを務めた弁護士だ。政治家として、デジタルから人工知能(AI)、社会保障、政治改革、企業統治など、非常に幅広い分野で政策立案を手掛けている。 先代の塩崎恭久元官房長官は1990年代後半、金融機関の不良債権処理などに精力的に関与し、「政策新人類」と呼ばれた若手の代表格だった。時を経て、なお「失われた30年」が続く日本。再浮揚の鍵を握る政策マップを、彰久氏に語ってもらった。 (インタビューは2025年6月25日に実施しました) 【政策ニュース.jp×紀尾井町戦略研究所:聞き手=市ノ瀬雅人/政治ジャーナリスト】 *** 【写真を見る】“論文引用”で日本より上位の驚きの国とは 世界13位の衝撃 ——科学技術政策を重視している。 塩崎彰久・自民党副幹事長 (塩崎彰久氏、以下同)政府は2026年度からの5年間をカバーする「第7期科学技術・イノベーション基本計画」を策定する方針だ。私が事務局長を拝命している自民党「科学技術・イノベーション戦略調査会」は、この計画に反映させる内容を議論している。4月に論点整理を公表しており、8月には中間提言をまとめ、政府に提出する予定だ。 議論の内容を端的に言うと、日本の基礎研究力の相対的な低下が著しく、強い危機感が出ている。被引用数が各分野の上位10%に入る論文数で見ると、わが国の順位は、2000年頃は世界第4位だったが、第13位まで落ちてしまった。 ——どのような国々の後塵を拝することになったのか。 科学技術・イノベーション基本計画はこれまで6期、30年間をカバーしてきた。しかし、その間、インド、ドイツ、イタリア、オーストラリア、カナダ、韓国、フランス、スペイン、イランに抜かれた。インドやドイツを除けば、日本よりも人口や予算規模が小さい。明らかな政策の失敗であり、厳しく受け止めるべきだ。 人口減少が進む中、日本が経済発展、競争力、国力を維持し、向上させるためには、科学技術は重要な鍵だ。基礎研究力なくしてイノベーションやビジネスは生まれない。日本は技術で勝るが、ビジネスでは負けると言われることがある。しかし、技術でも負けていることを、謙虚に受け止めることが出発点だ。 資金少なく非効率な研究環境 ——なぜ、日本の科学技術力が相対的に低下したのか。 調査会では、なぜ30年間で基礎研究力が相対的に低下したのかに関し議論を重ねた。4月に公表した論点整理は、計19の原因仮説を立てた。それを大きく分類すると、資金確保、資金活用、人的資源の三つとなる。 まず、資金確保については、民間研究資金がもともと不足している中で、公的研究資金も減少していることなどが課題となる。次に、資金活用における問題点は、若手への配分不足、研究分野の硬直性、国際共著論文の少なさ、研究機器の非効率な利用といったことが挙げられる。最後に、人的資源では、若手研究者の減少、雑務に追われて研究に充てる時間が少なくなるなどの課題がある。中間提言では、これらへの対応策を示したい。 大学改革は「脱護送船団」 ——中間提言のポイントは、どうなりそうか。 大きく三つの柱がある。まず、科学技術と経済安全保障の有機的な連携。一つの科学技術研究の行方が、一国の経済安全保障に直結するようなものが多く出てきている。そのような重要な科学技術には戦略的に投資する必要がある。 次に、世界トップレベルの基礎研究力の回復だ。世界で13位ではいけない。具体的目標を立て、達成に向け、なすべきことを考える。 最後に、改革実現力の抜本強化。一言で言えば、大学改革における護送船団方式をやめ、それぞれの大学の機能分化を進める。トップ10%の論文数をどんどん生み出す大学は必要だが、すべての大学がそうならなくてもいい。例えば、各地域で人材育成に集中する大学も必要だ。大学の特性に合わせ、さらなる機能分化の推進を打ち出したい。 政府には、中間提言を重く受け止めてもらいたい。また、調査会は、提言の提出後は年末にかけ、有識者らからのヒアリングを継続する。政府による計画策定に向けた具体的検討に、提言内容が反映されていくかを確認したい。 「一石三鳥」 ——科学技術の向上を重視する理由は。 政治の世界に入って驚いたのは、悲観的な声がとても多いことだ。人口減少の進行、財政状況、経済力低下などが背景にあるのだろう。多くの国民の皆さんに希望を届けることが、政治の役割だ。 人口減少が進む中、一人ひとりが豊かに、幸せになるため、どの国よりもテクノロジーを積極的に導入する必要がある。科学技術力は日本の成長のための大きな柱だ。 ——テクノロジー活用の具体例を知りたい。 例えば、社会保障分野は従来、負担を上げるか、あるいは給付を下げるかの二者択一で議論されていた。私が昨年に厚生労働大臣政務官として取り組んだのが医療DXだ。 国民皆保険の下における高品質な医療・介護データは、デジタルにつなぐことで、医療の質を上げ、医療・介護にかかるコストを下げ、さらにイノベーションを生み出すという「一石三鳥」のアプローチが可能になると思っている。他分野でも、そうした手法を取ることができる部分を見極め、取り組むことが必要だ。 ドローンで農薬散布 ——他には、どのような分野がありそうか。 米の値段の高騰が課題になっている。農業も科学技術を生かせば生産性を上げる余地が多くあるのではないか。例えば、大型トラクターを導入すれば、これまで大人数でやっていた作業を1人でできる。ドローンを利用すれば、山向こうの畑まで農薬の散布が可能となる。 設備投資によりテクノロジーを使えば、生産性が上がる。ただ、その前提条件として、一定の規模集約化が必要となる。そうした条件を整えるのも政治の役割だ。人口減少が進行し、生産性を上げないと国は縮小してしまう。逆に、人口が減少しても生産性を上げれば、もっと豊かになれる。そこに日本の未来がある。 国会質問2週間後の通達 ——企業の有価証券報告書(有報)について、定時株主総会前の開示の重要性を唱えてきた。 弁護士時代からさまざまな企業のコンプライアンス案件に携わり、企業統治(コーポレートガバナンス)の強化が日本の成長のために必要だと感じていた。例えば、科学技術関連の部分では、R&D(研究開発)投資が少ない一方、内部留保が多いと指摘されている。株主を含むステークホルダーの声を受け止め、ガバナンスがより効いてくれば、日本企業の成長力は上がると思う。 長年の課題でありながら、変わらなかったのが、定時株主総会前の有報の開示だ。多くの企業が、事業報告書より多くの情報を含む有報を、総会の当日、または翌日に開示しているという実態があった。 ——今年、国会質問により、前進を成し遂げた。 今年2月の衆院予算委員会分科会で、加藤勝信金融担当相に対し、本来は総会の2、3週間前に有報を開示し、株主が十分な情報を持った上で質疑できるのが望ましいと指摘した。そして、急な変更が困難なら、せめて総会の1、2日前の開示を企業に促してほしいと求めた。 その2週間後に早速、金融担当大臣名の通達を出してくれた。5〜10社でも対応してくれたらありがたいと思っていたが、日本経済新聞によると、3月期決算企業の55%が総会前開示に応じていた。まさに「山が動いた」と、大きく感動した。 ナッジ理論 ——総会前開示が進み始めたことの意義は。 1、2日前でも総会前に開示すれば、株主は多くの情報を基に総会で質問できる。逆に総会前に開示しないなら、企業の代表者は、その理由の説明を求める質問に備えなければならない。 企業はこれまで、総会前に情報をできるだけ出さないようにして、リスクを回避するといった対応を続けてきたように思う。今後は株主の意見を含め、できるだけ深く対話することで、よりよい経営を目指す形に変わっていくはずだ。それこそが日本の経済成長力の底上げにつながると思う。 ——なぜ、働きかけが成功したのか。 大きな変革をする場合、通常は大きなエネルギーが必要だ。しかし「ナッジ理論」というのがある。端境で小さなきっかけがあると、わずかな変化が起き、それが大きな変革の導入につながるというものだ。有報の総会前開示は、まさにナッジ理論がうまく機能したパターンだ。これまで、総会2週間前の開示を目指す法改正の動きがあった。今回は、1日前ならできなくはないし、できない理由も見つけにくいとして、多くの企業が対応してくれたのだと思う。 政治家は法律を変えられる ——弁護士から国会議員に転じた。 21年、新型コロナウイルス感染症の流行で、小学生だった息子が通学できなくなったり、私自身が仕事に行けなくなったりした。また、海外の報道などを見る中で、政治の判断一つで、われわれの生活は深いところまで影響を受けると痛感した。そうした折、父(塩崎恭久元官房長官)が衆院議員の引退を決め、候補者が公募されることになった。危機管理の専門家としての経験を生かそうと、応募した。 ——実際、政治家の仕事をどう感じるか。 これほどやりがいのある仕事はない。困っている人のさまざまな悩みを解決しようとする点は、弁護士時代と共通する。ただ、政治家は個人の方々に加え、より大きなステークホルダーやその関係者の方々の課題と向き合う機会と責任がある。解決しようとする課題がより大きくなれば、そのためのツールも変わる。例えば、法律は、弁護士によって変えることはできないが、政治家は変えることができる。だからこそ、この仕事に無限の可能性とやりがいを感じている。 政策ニュース.jp(せいさくニュース・ドット・ジェイピー) 政策・政治関連の情報を発信する。 https://www.policynews.jp/ 市ノ瀬雅人(いちのせ・まさと) 大手報道機関にて20年近く国政、外交・国際関係などの取材、執筆、編集を務めた。首相官邸、自民党、旧民主党、国会のほか外務省などの官庁を担当した。 デイリー新潮編集部