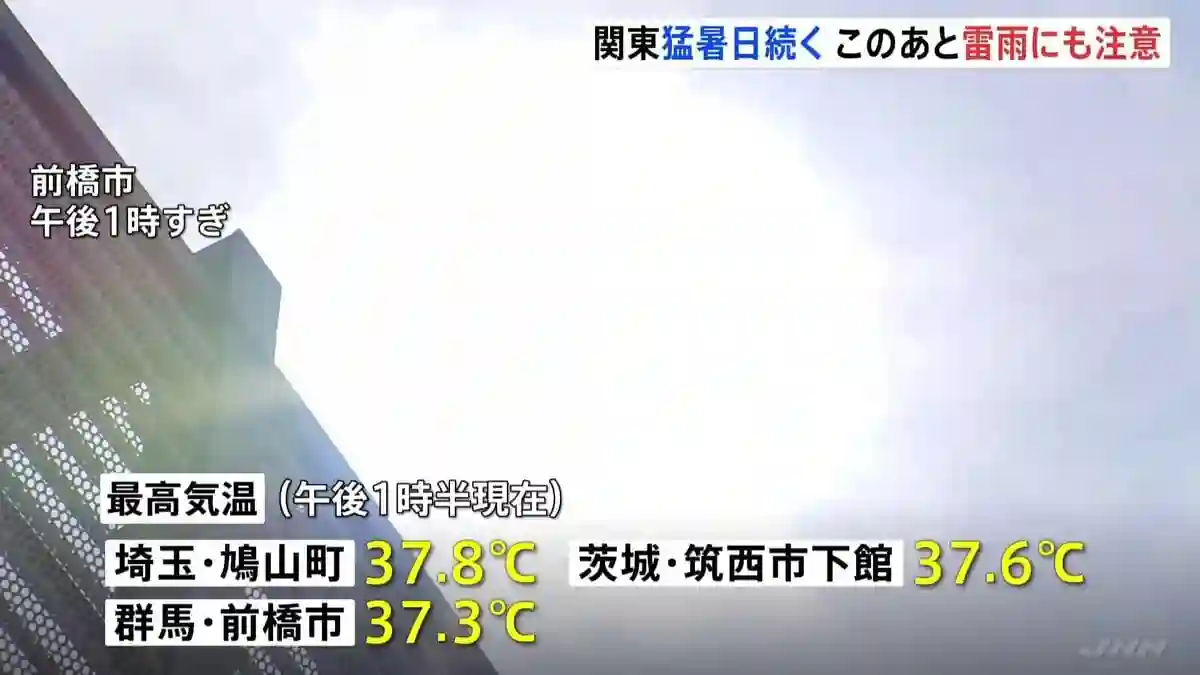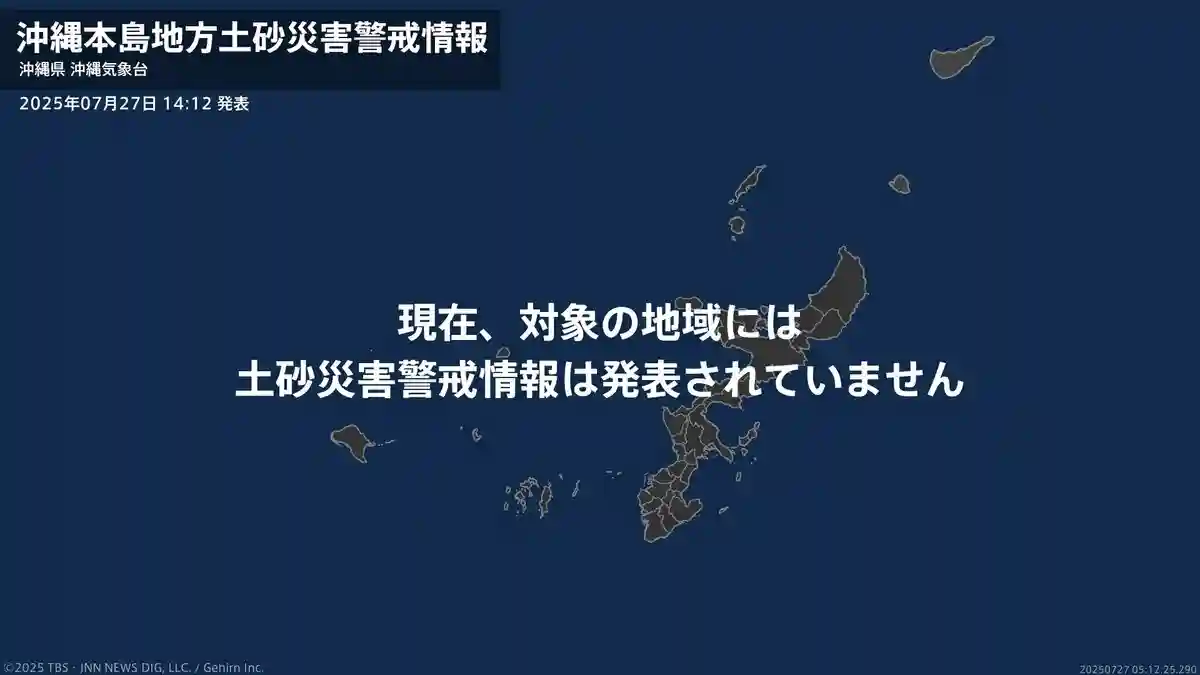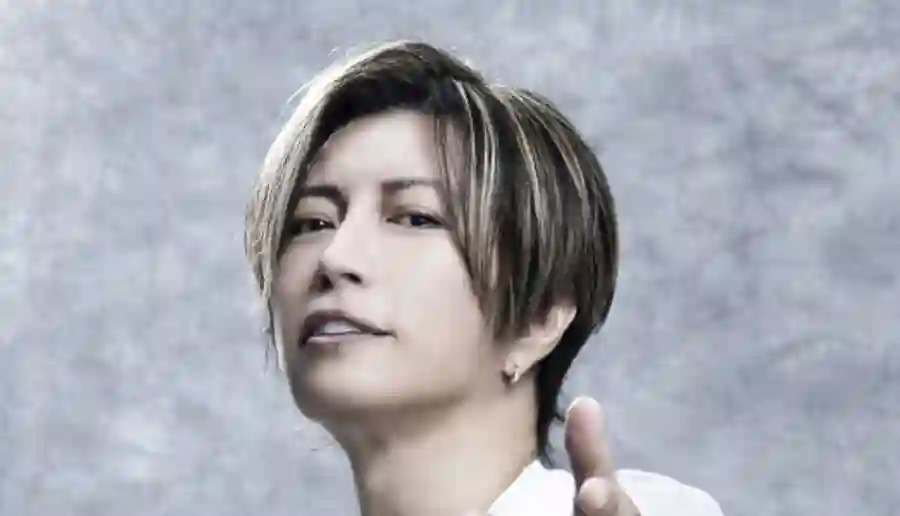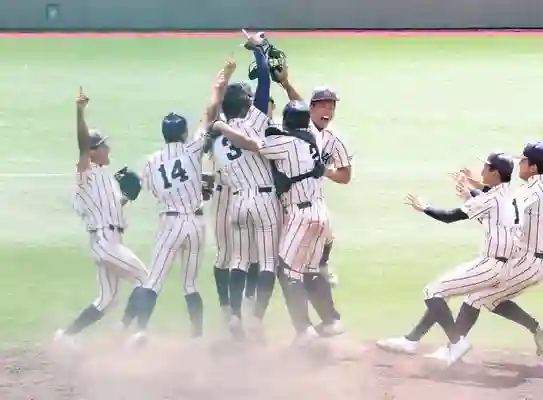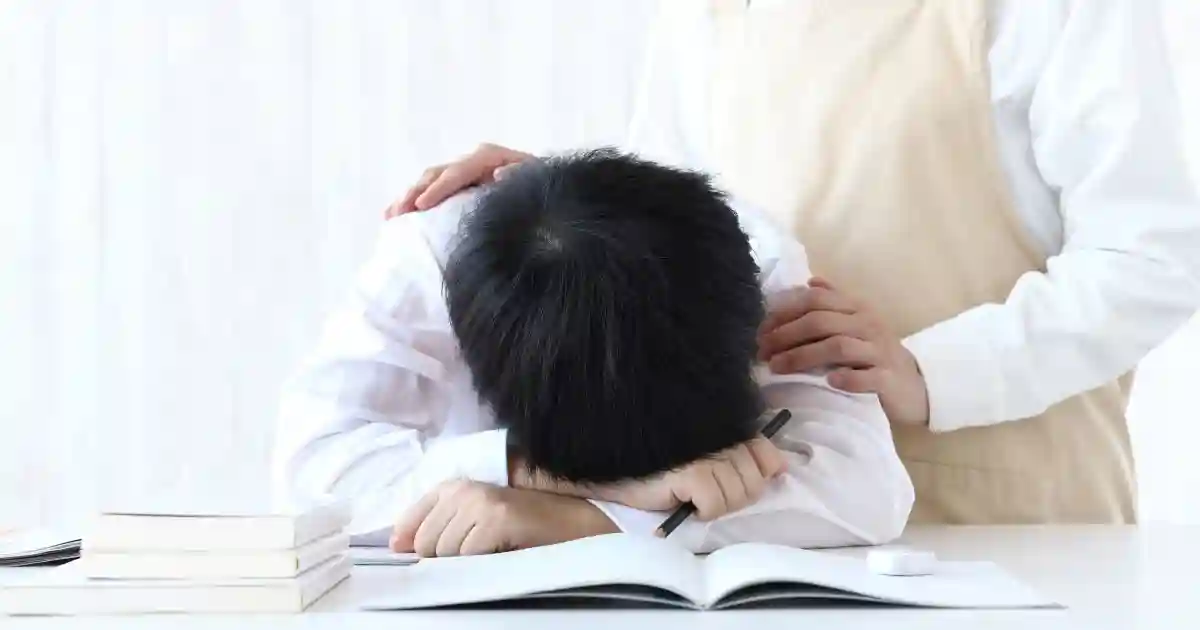
不登校の子どもたちを30年にわたり診続けている小柳憲司医師(長崎県立こども医療福祉センター所長)が、『不登校の子どもを支える』(新興医学出版社)を出版した。2009年に刊行され、15年にわたって読み継がれたロングセラーを大幅に改訂・改題した最新版だ。 不登校の児童生徒数が34万人を突破したと報じられたのは記憶に新しいが、新版が刊行されるまでの間に、不登校をめぐってどのような変化があったのか。その変化のなかで親や教師はどのように子どもたちに関わっていけばよいのか。現役の小学校教諭でコラムニストとしても活躍中の原良平氏が小柳医師に訊く。 どこかにつながっておくことが大切 【原】今年の5月に刊行された『不登校の子どもを支える 家族・教師・医師のための対応ガイド』は本当に参考になる本でした。目次を拝見すると次のようになっています。 〈おもな目次〉 https://shinkoh-igaku.jp/mokuroku/data/934.html 盛りだくさんな内容ですが、まずはこの本で「先生が最も伝えたかったこと」をおうかがいしたいと思います。よろしいでしょうか。 【小柳】最も伝えたかったのは、やはり「子どもと家族を孤立させずに見守り続けよう」ということです。いま不登校で困っていても、どこかにつながっていてほしい。そうすれば、いつかそこから物事は必ず動き始めます。 私が診ている子どものなかには、それこそ何年も何年も、長いこと、ここ(長崎県立こども医療福祉センター)に通っている子どもがいます。長いこと学校に行けなかった子や、ずっと引きこもっていた子もいます。しかし、(ちょっとスパンの長い話になってしまいますが)そういった子どもでも、二十歳過ぎくらいになると、けっこう自ら動き始めるものなのです。その「動き出すとき」まで支援を続けられるようにつながっている、そういう状態にしておくことが肝心です。 とりわけ大切なのが、家族だけで子どもを抱えなくてもよいようにすることです。子どもを支えるのはもちろんですが。教師、医師、あるいはそれ以外の支援者が、家族を上手に支援してほしい。そういう気持ちも込めつつ『不登校の子どもを支える 家族・教師・医師のための対応ガイド』というタイトルにしました。 【原】不登校に関する本がたくさん出版されていますが、この本はとても実用的ですね。 【小柳】『不登校の子どもを支える』は、私自身が日々たずさわっている臨床から得られた知恵、「臨床知」の塊です。実際にあったケースをふまえて、「こういうときには、こんなふうに関わったらいい」というのを、できるだけ実践的に述べるようにしました。 私は研究者ではありませんから、統計であるとか、あるいは「(教育とは/支援とは)こうあるべきだ」とか、「こうしなさい」というような教条的なことは書いていません。なかに書いてあることを実践しても、支援者の過剰な負担にはならず、長く子どもをフォローしていける、そんな本を目指しました。 不登校の子どもを抱える親御さんに、できそうもないことを「頑張ってやりなさい」なんて言っても意味がありませんよね。たとえば「子どもを毎日欠かさず学校に送る」なんてことは到底続けられません。だから私は「できることを、できる範囲でやりましょう」と読者に伝えるつもりで書きましたし、臨床の現場でも、いつも「無理なく続けられることでないと、どんな立派な支援も継続できませんよ」とアドバイスしています。 親御さんが元気でないと、不登校で家にいる子どものほうも元気にはなれないのです。元気さの度合いを私は「こころのエネルギー」という言葉を使って表現していますが、「こころのエネルギー」が低下すると、子どもは意欲が低下し、情緒が乱れ、学校にも行けなくなります。 もちろん、休んでエネルギーを回復させれば、また活動できるようになります。ただし、「こころのエネルギー」は人から人に渡っていくもので、不登校になっている子どもの場合、身近にいる家族からしか分けてもらえません。家族に元気がないと、子どもに元気を分け与えるなんて、できっこないわけです。 だから、私は親御さんに必ず「自分が元気でいることが大切ですよ」とお伝えしていますし、もっと言えば、できるだけ楽しく過ごしてほしいとも言っています。「子どもが不登校なのに自分が楽しむなんて」と罪悪感をもつ方もおられるのですが、何事も楽しめないと長続きしません。 「こころのエネルギー」と不登校の経過 【原】「こころのエネルギー」という概念は、先生の不登校理論の特徴のひとつですが、もうひとつ、不登校の経過を6段階にわける捉え方も興味深いものでした。どのように分けておられるのか、ここでちょっと振り返っておきますと、 (1)前駆期……徐々にこころのエネルギーが低下する不登校の初期 (2)混乱期……こころのエネルギーが最も低下して親子とも混乱する時期 (3)休養期……学校に行けない状況を受け入れ、少し落ち着いた時期 というふうにして学校に行けなくなり、その後、こころのエネルギーが回復してくると、 (4)回復期……少しずつ外に出られるようになる時期 (5)助走期……学校の教室は難しくとも、定期的な外出が可能になる時期 (6)復帰期……学校生活や仕事に本格的に復帰する時期 という経過をたどると書かれています。このように不登校の経過を段階にわけ、各段階に応じた子どもへの関わり方を提案なさっているのも、小柳先生の理論の特徴だと思います。段階わけして考えると、支援においてどのようなメリットがあるのか、教えていただけないでしょうか。 【小柳】段階にわけ、段階ごとの対応を提示することで、様子を見ながら関わり方を試したり、修正したりしやすくなるところがよいのではないかと思います。目の前の子どもが、不登校のどの段階にいるのかよくわからなくても、 「この段階かな」と予測を立てて対応してみる ↓ うまくいきそうなら続ける、ダメそうならちょっと引いて前の段階の対応を試す という感じで、押したり引いたり、試行錯誤しやすくなりますよね。 不登校の子どもを前に「いったいどうしたらよいかわからない」というときもあるでしょうが、そういう場合でも、段階に分かれていれば、状態を予測して何かを試すことができます。そんな対応ができるように、経過を分けて考えているのです。 不登校に限った話ではありませんが、何であれ問題が起こると、誰しもまず「原因を特定して、その原因をどうにかしよう」という発想になりがちです。ところが、原因がわかったところでどうにもならないことが、世の中にはたくさんあります。 ましてや不登校は、いろいろな因子が絡み合って起こっていることであり、原因をひとつやふたつに特定できることなど、ほとんどありません。原因を特定して「治療」しようとしていたら先に進めないのです。 だから、原因を特定することにはこだわらず、「今の状態を見て、それに応じてどう支援するかを考えていく」という関わり方でいい。そのことをわかっていただくために、不登校を6つの段階にわけ、各段階に応じて対応方法を提案しています。 原因探しにこだわりすぎてはいけない 【小柳】念のため補足しておきますが、「原因探しは無駄だ」と言っているわけではありません。子どもの状態や、家族の置かれている状況を理解するために、「なぜこうなったのか」を考えるのは大切なことです。 私はよく「ストーリーを考える」という言い方をしています。原因と思われる複数の因子をつなぎ合わせて、子どもが不登校になったストーリー(あるいは仮説)を考えることで、子どもへの理解が深まります。原因はひとつではなく、いろんな因子が絡み合って今の状態が形成されていますから、原因を探るのではなく、因子の絡み合いをストーリーとして捉えるのです。 しかし、そのとき考えたストーリーが本当に正しいかどうかなんてわかりません。特定のストーリーに固執することが支援の妨げになる場合もあります。その点には注意が必要です。 【原】ありがとうございます。本のなかで先生は、対応方法をいろいろ提案してくださっていますが、インタビュー後半ではその具体的な例についても触れたいと思います。 後編記事『不登校の臨床を30年続ける医師が「無理に何かをさせなくてもよい。一見、無駄に見える時間にこそ意味がある」と保護者に伝える深いワケ』へ続く。 発達障害を抱える子どもたち…「5歳・9歳・13〜14歳」の時期がとくに要注意といえる理由