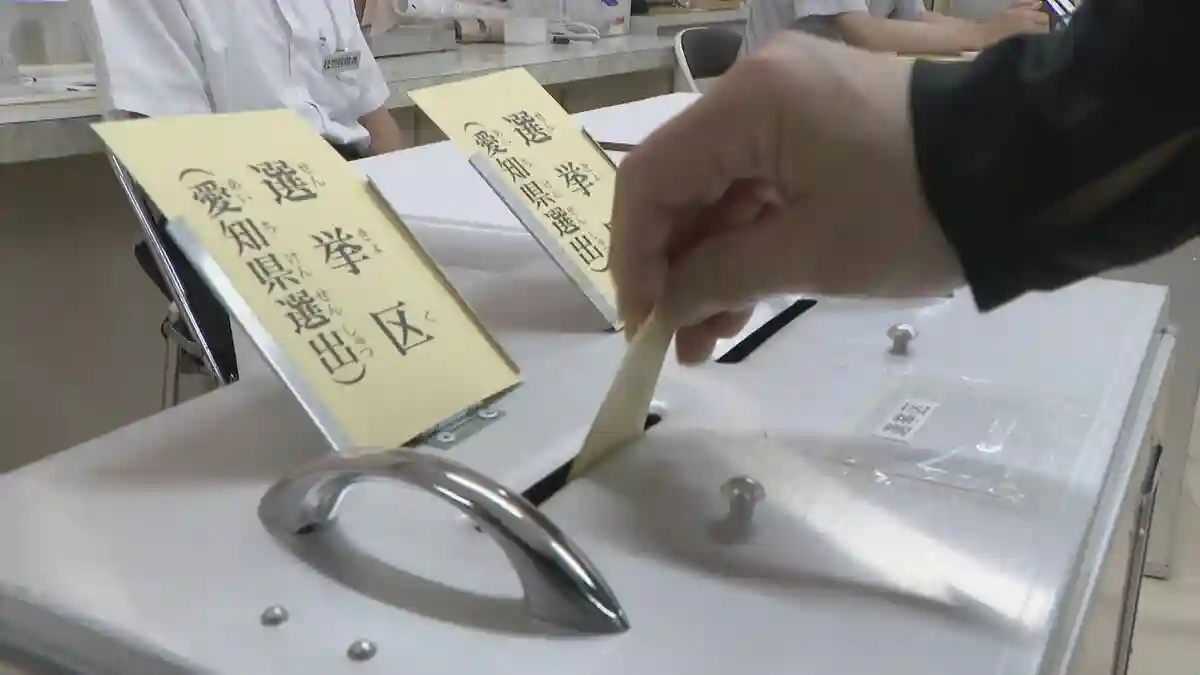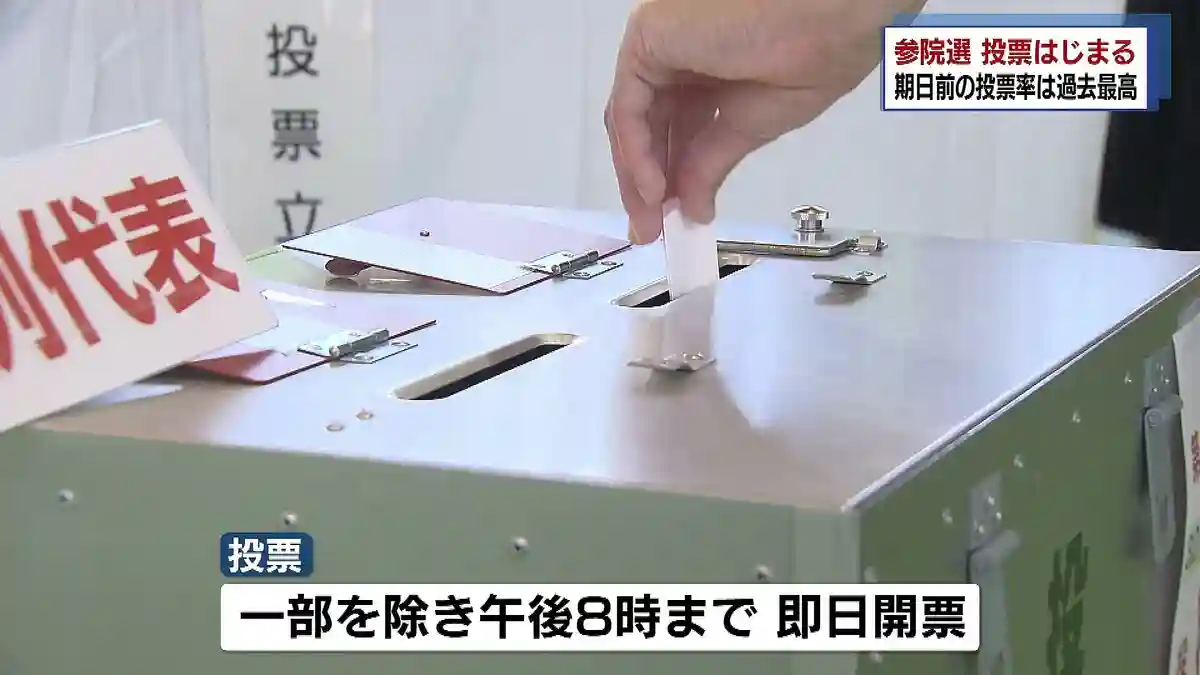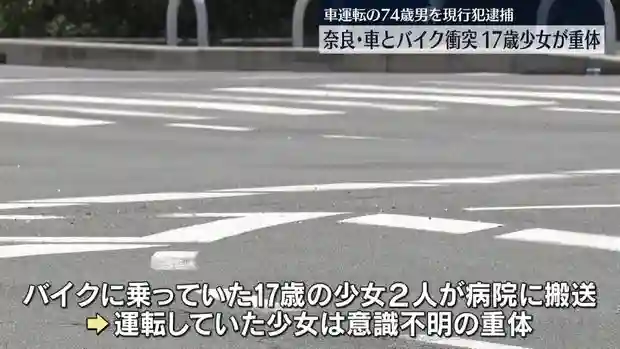東京都江東区にある都立猿江恩賜公園で、セミの幼虫が乱獲される事態が相次いでいると7月13日に産経新聞が報じた。公園に《セミの幼虫を採取しないでください。子供達がセミを楽しみにしています》との張り紙が掲示され、その文言が中国語、韓国語、英語の4か国語で書かれていたことも大きな話題となった。 【写真14枚】 「セミのチリソース炒め」(幼虫使用)他、成虫タコスや親子串揚げなど魅惑のメニューが全5品! 記事中ではこの数年、公園利用者から管理会社に“食用目的の乱獲がされているのでは”といった苦情が寄せられ、セミの羽化が本格化する6月末に約30枚を掲示したと報じられていた。 Xの当該記事は2日間でおよそ450万回閲覧され、1300を超えるリプライがついた。 猿江恩賜公園(江東区)のポスターに「食用」の文字はないが… 《今年セミが鳴かないねって話してたところ》《セミはエビに似た味がするらしい》 セミ取り禁止の看板について取り沙汰されたのは、実は今回が初めてではない。過去には荒川区、杉並区、埼玉県川口市でも“セミの幼虫の採取を禁止する注意書き”の掲示がされており、中には“食用目的での”という文言も入ったものもあった。 これらの自治体での張り紙は、現在いったいどうなっているのだろうか。 「存在がない」「どういう意図か」 まずは、埼玉県川口市。2018年に市内の公園に掲げられた【お願い 食用としてセミの幼虫等の捕獲はやめて下さい 川口市公園課】という看板の現在について尋ねると、 「たしかに2018年6月から市内の青木町公園を含む公園2か所にそういった看板を設置し、報道されたことはあります。そもそも、市民からの“セミの幼虫を大量に捕っている人がいる”という声、研究者から“クマゼミが減った”という情報が寄せられての対応でした。その後、セミのシーズンが終わったタイミングで撤去されています。とくにそれ以上の情報も残されておらず、翌年からは設置もされていないので、その後、目に余るような事態はなかったのではないでしょうか」(川口市公園課管理係) 看板が効力を発揮したのか、1シーズン限りの掲示となったようだ。 つづいて荒川区。2020年8月に、都立尾久の原公園に掲示されたという張り紙の写真が個人のブログ上で公開され、SNSで拡散された。 その看板には、【セミ幼虫捕獲禁止】という日本語とともに、より大きいサイズで書かれた【不要捕蝉的幼虫】という中国語が。【食用を目的としたセミの幼虫等の捕獲はやめてください】という日本語の下にも中国語と英語での表記があり、「尾久の原公園」の署名も見える。だが、公園の管理事務所に張り紙の効果やその後の状況を問い合わせたところ、 「現在、そういった張り紙の掲示はない。その存在も知らない。何を根拠に、どういった意図で連絡をしてきたのか」(尾久の原公園サービスセンターの担当者) と、そもそも掲示があったかも明かされなかった。 「イメージが悪くなる」寄せられたクレーム 一方、杉並区は文言を変えて、現在もポスターを掲示し続けているようだ。 2020年に、『文春オンライン』が区内の妙正寺公園、清水森公園、天沼西公園の3か所にポスターが貼られていた旨を報じている。 【おねがい 区内の公園で食用その他の目的でセミ等を大量捕獲するのはおやめください】 かつて上記のように記されていた文言は現在、 【おねがい 公園内で昆虫などを大量につかまえないでください】 と改められており、ポスターイラストにはセミらしき姿が見えるものの、具体的な“昆虫”の種類や、その目的には言及していない。 ポスターの文言に変化があった背景を、杉並区都市整備部みどり公園課に尋ねた。 「2020年の報道の際、ポスターにあった“食用” “セミ”というワードがクローズアップされる形で、うっかり記事がバズってしまいました。これを受けて“杉並区のイメージが悪くなる”と区民からクレームが殺到。食用と明記していた部分については、子どもの虫取りなどは黙認する形だったからですが、そこを外し、“セミ等”とオブラートに包んでいた部分もさらに“昆虫”と変更。その後、通年で掲示をしております」(担当者) 食文化としてのセミ食は否定すべきではない セミを大量に捕獲することに加え、“食べる”という点がセンセーショナルに映ってしまうようだ。昆虫料理研究家でNPO法人昆虫食普及ネットワーク理事長、NPO法人食用昆虫科学研究会理事の内山昭一氏は、 「今回のニュースがあって、コオロギ給食の事案のように“昆虫食”全般への逆風となることを懸念しています」(内山氏、以下同) と語る。 内山氏によると、セミを食べる食文化はタイや中国に多くあり、東南アジアと文化的に近い沖縄地方にもあるそう。長野にも「イナゴ」「蜂の子」「ざざ虫」の甘露煮といった高級珍味もあり、日本における昆虫食文化は奈良時代にまでさかのぼるといわれている。 “セミは中国や東南アジアの郷土食であり、ふるさとの味として楽しむ行為は否定すべきではない”と内山氏。 「たしかに販売目的で毎夜毎晩、何百匹単位のセミを乱獲し、食材店などで販売しているとすれば、それはよくないことだし制限すべき。ただし、今回の報道への反応は、日本における外国人問題のような政治的な要素もあるのではないか。セミ食などの昆虫食自体をそれらと混同して語るべきではないし、各地の食文化を否定すべきではありません。アリストテレスはセミを美味しいと言い、ファーブルも『昆虫記』のなかで試食している。井伏鱒二は小説『スガレ追ひ』のなかでセミは美味しいと書いている。温暖化など地球環境問題に関連して昆虫食が話題になっており、自然環境教育の一環として身近なセミを食べる行為を否定してほしくない」 ちなみに内山氏がおすすめするセミの調理法は“ナッツのような味わいの幼虫なら燻製、成虫ならサクサクとした歯ごたえが楽しい素揚げ”だそう。ビタミンBが豊富なセミは夏バテにぴったりの旬の食材だといえる。 「小中学生の夏休みの自由研究のテーマとしても人気です。問題になるような乱獲は絶対にしてほしくないが、夏の新鮮なうちに一度、味わってみませんか」 デイリー新潮編集部