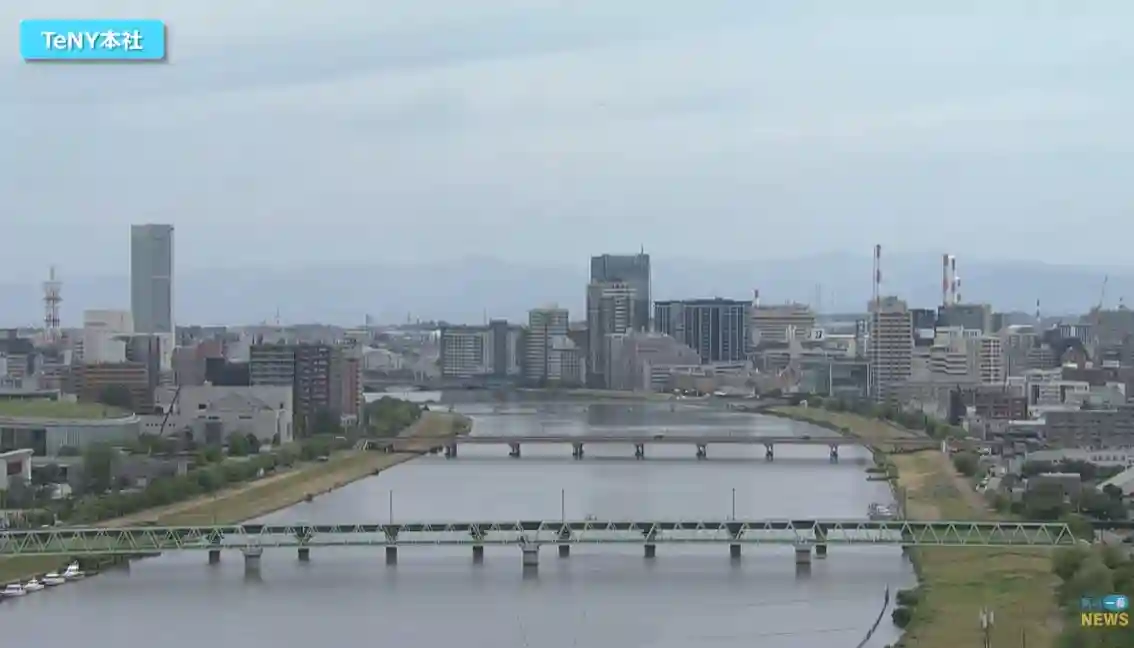あらゆる分野でIT化やAI活用が進み、医師の診察もオンラインで行われる機会が増えた。そのメリットを享受する患者もいるだろうが、やはり「先生」に直に見てほしいと思う人も少なくないだろう。それは診る側も同様で、現役の医師である里見清一氏には、これらの技術の進歩を全面的に肯定することに疑念があるという。 現役医師が投げかけた「テクノロジー信仰の問題点」 テクノロジーを無邪気に受け入れることに落とし穴はないのか——里見氏の新著『患者と目を合わせない医師たち』所収、「オンライン診療に抵抗があるのは『古い』のか」から抜粋・引用してみよう。 *** 「私が看取る」も古いのか 今年の年賀状で、私が救命センター研修医時代にさんざんシゴかれた先生が、一言「働き方改革って、なんなんだ」と嘆いておられた。昭和の研修医は連日泊まり込み勤務だったが、今やそんなのは時代遅れどころか法律違反である。そんなことで指導できるか、また修業になるのか、というオヤジの断末魔の叫びのようだが、この感覚は私にもわかる。 テクノロジーを無邪気に受け入れることに落とし穴はないのか—— (※写真と記事本文は直接関係ありません) 医師向けポータルサイトの掲示板で、ある先生が「当直医に代理の看取り(患者の死亡確認・診断書作成・お見送りなど)をさせるケースがあるが、よくないと思う。私は学会出張などの事情がない限り、自分で看取る」と書き込んだ。私自身も、休日でも夜中でも出て行って自分の患者の臨終に立ち会う。それが当たり前と思っていたが、どうもそうではないらしい。 「身体に触る」診察は、不要なのだろうか (※写真と記事本文は直接関係ありません) これへのレスポンスは「そういうのは古い価値観」「他の医者に考えを押し付けるな」なんて反対論ばかりだった。果ては「そんな前時代的考え方が世の中をダメにする」「それで時間外手当をもらうのなら、病院経営上好ましくない」という指摘もあった。衆目の一致するところ、「働き方改革に逆行する」のである。 触診は無駄か 同僚の外科医が、ウィーン大学病院に短期留学した。彼の話では、患者がどの外科医によって手術を受けるかは順番で決まるそうで、「受け持ち」なんてないらしい。そして、午前中の手術が長引いて午後の手術開始が遅れ、5時までに終わらないとなると、翌日に延期になったり、その日の当直が手術をしたりするという。結果、術者が変わるので、手術のやり方も変更になるそうだ。 誰も書かなかった「医者の本心」と「病院の実態」。若手医師への疑念、「患者様」の無理難題……。ベテラン臨床医が明かす医療の内実 『患者と目を合わせない医師たち』 彼に、「外科医で働くとしたら日本とウィーンとどっちがいいか」と尋ねたら、「ウィーンの方が働きやすいようにも思う」と答えた。では患者として医療を受けるとしたら、と聞くと、「そりゃ日本の方がいいですよ」と即答した。ただ、好むと好まざるとにかかわらず、日本の医療も向こうに近づいていくことだろう。 そういう「先進国」の医療を聞くと、旧世代の私などは感覚的についていけない。パンデミック以降、オンライン診療の利点が強調され、それに難色を示す医師会の先生たちは「抵抗勢力」扱いである。 だが「身体に触る」診察は、不要なのだろうか。 ブラジルで、癌患者に対する身体診察の意義を検討したところ、身体診察を行っても87%で新たな異常は発見されず、診察の結果で治療が変わったのは「わずか3%」だったそうだ。 研究者たちは「身体診察にはあまり意義がなく、リモートでOK」と結論している。 そうなのか? ニューヨークのダニエル・オーフリ先生は「たとえ検査でわかるとしても、身体に触るのは大事である」と主張している。私も賛成だが、患者側からは「もうそんなの不要」なのだろうか。 テクノロジー信仰の問題点 4人の子供を難関の東大理三に合格させた「佐藤ママ」という方が、12歳までの子供にチャットGPTを使わせるべきではなく、「今まで通りアナログで育てて、タブレットなんか全部捨てて欲しい」と主張し、批判された。堀江貴文さんは「こいつバカでしょ笑」とフェイスブックでコメントし、茂木健一郎さんも「ChatGPTに限らずテクノロジーを使わずに受験勉強せよという主張は愚かだと思う」、さらに「スマホもそうだけど、日本の中のある種の教育化石層は、やたらと新しいテクノロジーを嫌がる。だったら永遠に江戸時代の寺子屋教育でもやっていればいいと思う。その間に世界はどんどん進んでいく」と批判した。 これが「受験勉強」に関する話だったら、別にどうでもいい。それこそ「このテクノロジーの時代」、いろんなカンニングの方法も編み出されていて、大学入学への選抜基準をどうするか自体も変わっていくだろう。それに対応してどう受験勉強したら大学に受かるか、なんてことに私は興味がない。問題は、「勉強」は何のためにするのか、そしてその本質に適した方法は何か、である。 車ができて、ウサイン・ボルトといえども普通の乗用車より速くは移動できない。だからみんな歩いたり走ったりしないかというと、そうでもない。ボルトのように、競技としてやっている「プロ」は別としても、一般の人だって全部車だと「身体に悪い」と知っている。身体能力を超える道具があっても、自分の身体能力を維持するためにやはり動くのである。 もし「正解」にアクセスすることが勉強の目的なら、テクノロジーを使うというよりテクノロジーに任せてしまった方が話が早い。だが自分の知的能力を維持向上させるためなら、それでは逆効果である。 効率からこぼれ落ちるもの そのチャットGPTだが、米国や日本の医師国家試験を解かせてみたら、いずれも合格ラインに届いたという。ただ、日本の試験では、患者に対して安楽死を促すような言葉がけの選択肢を選んだりしたそうだ。問題を解かせた研究者は「日本の医療現場の法律やルールを知らなかったりする」のが課題として、今後学習によって克服させるというが、そもそもそのうち日本でも「安楽死に誘導する」のが正解になるかも知れない。そうなったら「学習し直させる」のか。 ここで怖いのは、「安楽死を是とする」考えそれ自体よりも、「是としたらその『正解』をそれ以上考えない」ことだろう。 福田恆存先生は安楽死の法制化に反対し、己の良心の痛みや後ろめたさを感じてこそ医者は人間たりうるのであり、判断を外的メカニズムに委ねてはならないと指摘されている。医療の「本質」の一つは、医療者が人間の「心」を持つことだと私は思っていたが、現在では「効率良く正解に至る」方が重要なのだろうか。 医療も教育も、「効率」と「本質」は別である筈だ。ただ、「本質」はわかりにくく、測れない。目に見える「効率」の方がどうしても優先される。それとも、「効率」なくしては落ちこぼれてしまう世の中では、「本質」もまた変わるというのか。 タブレットから「教わる」べく、画面と睨めっこしている現代の子供が、寺子屋で読み書き算盤や論語の素読を教わっていた昔の子供より高級な教育を受け、高等な人間になっていくとは、私には思えない。みんながAIの示す「正解」を目指し、それでハッピーになる社会は、多分ディストピアである。 里見清一(さとみせいいち) 本名・國頭英夫。1961(昭和36)年鳥取県生まれ。86年東京大学医学部卒業。国立がんセンター中央病院内科などを経て日本赤十字社医療センター内科系統括診療部長。著書に『医学の勝利が国家を滅ぼす』『死にゆく患者と、どう話すか』『「人生百年」という不幸』など。 デイリー新潮編集部