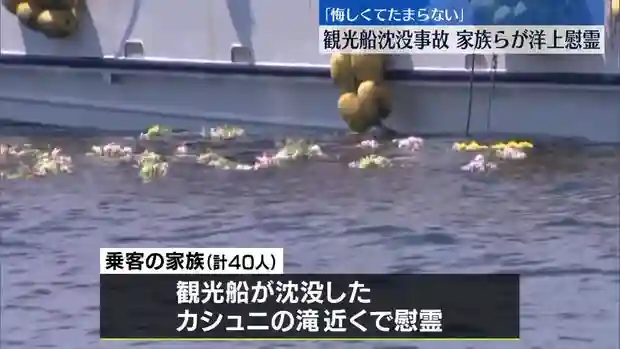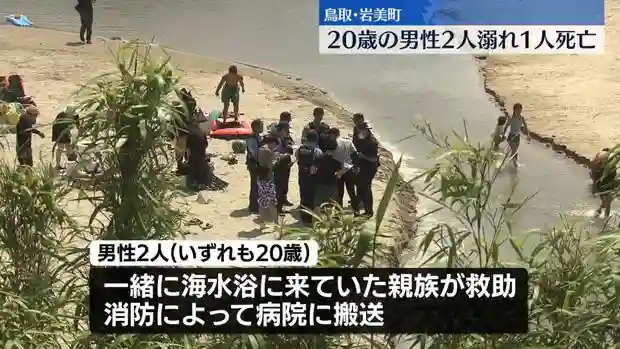動物が好き。自然が大好き。 そんなわが子の姿を見て、「このまま好きなことを仕事にできたら……」と考えたことはありませんか? たとえば、動物に関わる仕事。動物園の飼育員や獣医さんなど、いろいろな選択肢がありますが、なかには“研究する仕事”に興味を持つ子もいるかもしれません。でも、動物学者って実際どんなことをしているのか、想像がつきにくいもの。「研究」といっても、具体的にどんなことをしているのかよくわからない、と思う方も多いのではないでしょうか。 『ざんねんないきもの事典』や動く図鑑「MOVE」シリーズなど、子どもから大人まで幅広い世代に愛される作品を監修してきた動物学者・今泉忠明先生は、お父さんもお兄さんも、そして息子さんも動物学者という、まさに「動物一家」の出身。今泉先生が子どものころどんなふうに動物と出会い、なぜ動物学者になったのかを著書『気がつけば動物学者三代』(講談社)から抜粋して3回に分けて紹介しているシリーズ第2回では、動物学者とは具体的にどんなことをするのか、そして今泉先生が「なぜこの道を選んだのか」について、お伝えします。お子さんの“好き”が未来につながるヒントになるかもしれません。 動物採集の裏側 僕たちが、どのように動物採集をしているのか、ここでくわしくお話ししておきましょう。 みなさんが修学旅行に行くときは、目的地までの行き方や訪れる場所の歴史的背景など、いろいろなことを事前に調べていくと思います。事前の準備が大切なのは、採集旅行でも同じです。なにせ行き先は森の中です。地図で目的地の場所を、きちんと把握しておくことが重要になります。 「国道〇号線を進んで、このあたりで左折だな」 どのようなルートで車を走らせるのかを何度も確認し、頭の中でシミュレーションしておきます。当時は車のナビゲーション・システムなどありませんから、曲がるタイミングをひとつ間違うと、そのまま違う場所から山に入ることになります。事前に決めたルートから外れるので、それだけ危険度が増してしまうのです。 持ち物も事前にそろえます。キャンプ場や山小屋などに泊まることもありましたが、森の中で野営するときは、テントや寝袋、穴を掘るためのスコップ、そして森の中は街灯などありませんから懐中電灯も必須です。もちろん、動物を捕まえる罠も忘れてはいけません。食料品も買いこんでおきます。一日三食×人数分となると、なかなか大量の食料が必要になります。「初日の夜ご飯はカレーにしよう。二日目の朝はパンだ」などと全日程の献立を考え、必要な食材を用意しなければなりません。 これらの大量の荷物を、出発前日までに車に積み込まなければなりません。ほとんど僕ひとりに任されていたので、ぼつぼつ支度して準備に一週間ほどかかりました。 出発の日は、早朝四時ごろには家を出ます。日が出ているうちに現地に到着して、罠を仕掛けるなど生態調査の事前準備をするためです。 僕が車のハンドルを握り、いざ目的地へ! 森の中の野営に適した場所を見つけたら、荷物を降ろし、父や父の助手の人たちは、すぐに罠を仕掛けに行きます。その間、僕はテントを張り、夕食の支度を始めます。飯盒でご飯を炊くこともありましたが、どうしても手間がかかるため、水がたくさんある場所では、ガスバーナーでお湯を沸かし、温めるだけで食べられるタイプのご飯やレトルト食品を使いました。食事が用意できたら、僕も罠を仕掛けに行きますから、手早く食事の準備を終わらせるように心がけていました。 森のトイレは迷いやすい もうひとつ、野営をするときに大切なこと。それはトイレの場所を決めることです。近くにキャンプ場や山小屋などがあれば、そこにあるトイレを借りるのですが、なければ森の中の木陰に穴を掘って、それをトイレにするのです。 テントから離れていて、ほかの人の目につきにくいところに穴を掘ったら、「この穴をトイレにしましょう」と全員で場所を確認しておきます。しかし、森には目印になるような建物もなく、景色も変わり映えしません。たとえ日中でも迷ってしまいます。ただでさえ人の目につきにくい場所を選んでいますし、夜であればなおさら、トイレに行っただけで迷子になってしまうこともあるのです。 トイレに行くとき、人はたいてい急ぎ足で向かいますから、周囲の景色を確認するゆとりもありません。用を足して、「さあ、テントに戻ろう」と振り返って、「あれ?」と来た道がわからなくなることがあるのです。メンバーがトイレから長時間帰ってこないときは、車のクラクションを鳴らしてテントの位置を教えてあげます。するとヘトヘトに疲れた様子で、トイレとはまるで違う方向から現れたりするのです。 森でトイレに行くときは、ときどき後ろを振り返って、帰る際に自分が見るであろう景色を確認したり、木に紙テープを巻き付けて目印にしたりするのがオススメです。 紙テープを用いる理由は、材質が自然に返るものだからです。 さて、夕食を食べ、片づけを済ませたら、横になるかといえば、すぐには寝られません。夜は罠の見回りという大事な仕事があります。ネズミやモグラなどは夜行性ですから罠にかかっている可能性があります。罠を仕掛けた場所には、そばの木などに紙テープを巻いて目印をつけておきます。 罠の確認を終えて長い一日が終わり、ようやくテントで横になれるのは夜の十一時ごろ。みんなが眠りにつき、話し声が止むと、とたんに静寂が訪れます。聞こえてくるのは、虫の鳴き声と風に揺れる木々のざわめき。澄んだ空気を吸いこむと、土と木の香りが身体いっぱいに広がるような気がしました。あたりは電灯ひとつなく真っ暗ですが、「怖い」という気持ちは起きません。晴れている日なら、夜空を見上げると都会では信じられないほどの星がまたたいています。 森の中だからこそ聞ける音、感じられる空気、見える景色。これらも、僕が採集旅行を大好きになった理由のひとつかもしれません。 罠の確認から始まる採集作業 二日目の朝は、五時ごろに起きて朝食を済ませたら、前日に仕掛けた罠をチェックしに行きます。ひとり当たり五十個ほどの罠を仕掛けますから、すべてを確認するだけでひと苦労。小学生のころに使っていた「ビクタートラップ」とは違い、このころは生け捕りにできる「シャーマン・ライブトラップ」という箱型の罠を使っていました。動物がかかっていたら、すぐに罠から外してテントに持ち帰ります。無事に生きていれば写真を撮り、飼育観察用として東京まで持ち帰ります。もし死んでいたら、その場で計測、標本作りを始めます。初めて捕れた珍しい動物であれば、写真を撮ってから標本にします。移動の途中で死んでしまうと、肉が腐ってしまって標本作りが間に合わないことがあるからです。 みんなで標本作りに没頭していると、父がそれまで訪れた採集旅行での経験や、父の専門である分類学のおもしろさ、動物の進化についての話を聞かせてくれることがありました。そんな、ふとしたときに聞ける父の話に引き込まれて、思わず標本作りの手を止めてしまうほど真剣に耳を傾けていました。 採集旅行で行うことは、基本的に決まっています。罠を仕掛ける→動物を捕獲する→標本を作る——この繰り返しです。ある地点で調査し、「ここのネズミは、ある程度、採集できたな」と思ったら、別の場所に移動することもあります。調査記録には、採集地点の場所を地図で記し、そのエリアの標高や、「森」「草原」といった環境の種類も書き込みます。当時はありませんでしたが、今ならば人工衛星からの電波で、自分のいる位置情報を知ることができるGPS(Global Positioning System の略)で簡単に記録できます。 「自分は独立した動物学者になりたい」 こうして短くて三日間ほど、長いときだと一週間ほど宿泊し、作業にひたすら没頭します。使い終わった罠を、きれいに洗うのも僕の仕事です。生け捕り用の罠はとても細かい仕組みなので、バラして洗うのがなかなか大変です。使い古しの歯ブラシでゴシゴシとこすって泥などの汚れを落とし、谷川の水できれいにすすぐのですが、水が冷たくて手がかじかんでしまうほど。調査員が数人いれば二百五十個もの罠を仕掛けますから、それをすべて洗って乾かして組み立てるのは、とても大変な作業でした。 すべての日程を終えると、テントなど自分たちが使ったものを片づけ、トイレのために掘った穴に土をかぶせ、標本や荷物を車に積み込んで家に帰ります。森を汚さないようにすべて持ち帰るので、車の中はゴミだらけです。帰路のドライバーも僕なので、家に着くころにはヘトヘトでした。それでも、小学生のときに山に連れていってもらったときと同じで、「面倒だな」「行きたくないな」と思ったことは一度もありません。 こうして月に一〜二回のペースで採集旅行を重ねるうちに、さまざまな能力が身についてきました。罠を仕掛けて動物を捕まえ、標本にする技術は当たり前ですが、山道を運転できて、テントも張れて、野外で料理ができ……僕がいなければ、調査はスムーズにできないという自信も出てきました。そのころには、幼い日に見た兄の姿と同じで、父の「助手」ともいえる存在になっていたのです。 調査には父の正式な助手も何人かいましたが、僕が息子だからといって特別扱いされることもなく、父は全員に同じように接しました。ただ、子どものころとは違い、僕のほうは、かなりのストレスを感じるようになっていました。思春期を過ぎて、親のそばにいて同じことをやっていると、周囲の人たちが僕をどう見ているのかが気になって仕方ありません。「あいつは親父が教授だから、任される作業も楽でいいよな」なんて思われているかもしれません。このプレッシャーをはね返すには、助手の人たちと同じか、それ以上のレベルの知識や技術を備えていなければならないと思いました。 それと同時に、このころには、自分が作った標本が科学博物館にどんどん収められていくことにも、とてもやりがいを感じていました。 「自分が楽しいことで生物研究の役に立てるのなら、こんなに素晴らしいことはない」 大学時代には、こんなことを考えていました。なかば、父に巻き込まれるようにしてスタートした道でしたが、僕は自分でも気づかないうちに、どんどん動物学者の世界に引き込まれていたのです。それとともに、「自分は独立した動物学者になりたい」という思いも強くなっていったのです。 第3回【『ざんねんな生きもの事典』今泉忠明が語る学生時代、自宅にイリオモテヤマネコが来た日】では、大学卒業前に進路について考えていた今泉先生のもとに突然やってきたイリオモテヤマネコとの暮らしについてお伝えします。そこで起きた、動物学者一家ならではのバトルとは。 【後編】『ざんねんな生きもの事典』今泉忠明が語る学生時代、自宅にイリオモテヤマネコが来た日