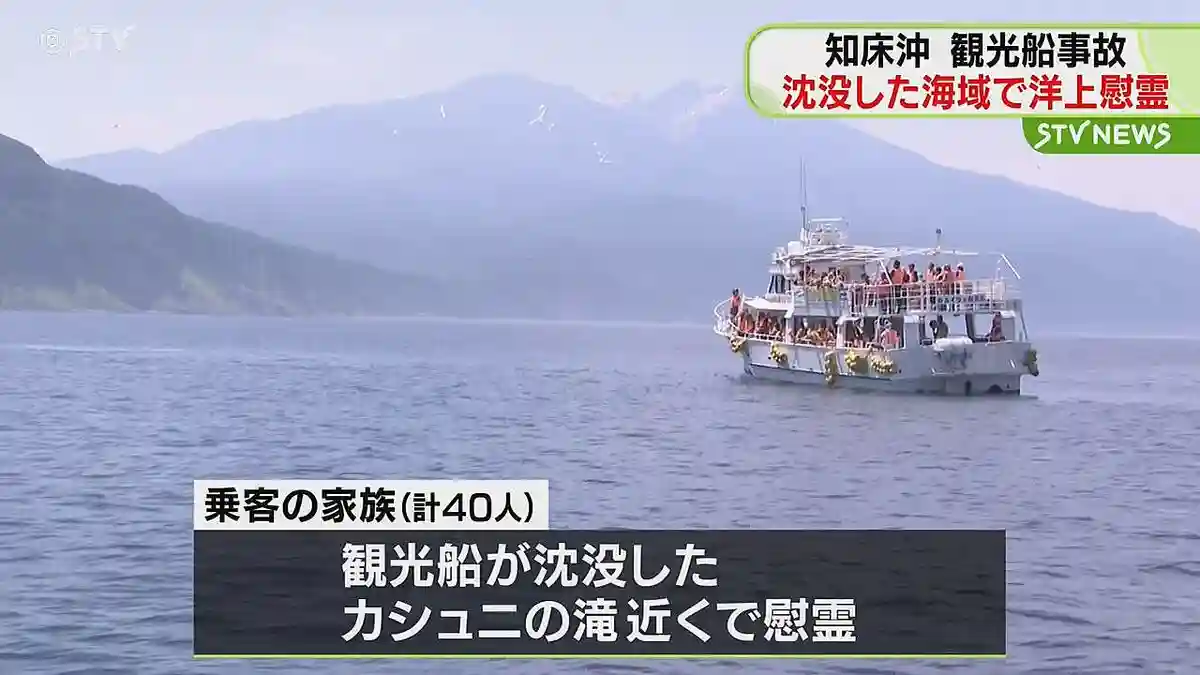「日本人だもの、教養のために一度は落語を聞いておかないとね」と落語を聞きに行ったもののそれっきり、本当に一度きりとなってあれから何十年。なんて人は案外多いのではなかろうか。私もその一人で、日本人なのになぜか落語の良さを理解できなかった「不可解さ」と「落語」をまとめて「時代がね」という紐で縛って置き去ったまま20年以上。 そんなある日、ひょんなことから立川志の輔の落語に出会った。そして驚いた。これが落語なのか? 落語ってこんなに面白いものだったのか! 落語を面白く感じるか、退屈と感じるか、この境目はどこにあるのだろうか? 失礼は百も承知。落語を知らない者の代表として、日本を代表(いや、地球を代表)する落語家の一人、立川志の輔師匠(71)にお話を伺った。 てるてる亭の客席より 撮影:土居彩子 ※許可を得て撮影しています 【写真】志の輔師匠の語る「落語を愛していける人」の素養とは…? 映画にも、舞台にもまさる没入感 「落語を聞くには、自分の持つ集中力とイマジネーションをフル稼働していかなければならない。というか自然にフル稼働するようになっています。というのも何も小道具もなければ、背景も変わらない、照明も変わるわけでも音楽が鳴るわけでもない。ただただAとBが喋っている、その会話をずっと聞いていると、なんとなくその二人がどこにいるのか説明がなくてもわかってきたりします」 そう。舞台には座布団一枚。落語家一人。小道具は使っても扇子と手拭いだけ。なのに、落語に聞き入っていると、暗がりの中で行灯を手にしているようにふっと目の前に景色が浮かんで広がってゆくのだ。いろんな人物に出会ってゆくのだ。 そしてあっという間にその世界に引き込まれ、「教養」という言葉は一瞬で煙となって消え去って、ワク ワク前のめりで没入していくのだ。どんなに凝った舞台装置の中で繰り広げられる演劇でも、四方八方からの音響を駆使した映画でも、ゴーグルを装着して手を泳がせるバーチャルリアリティでも、座布団の上で一人語る志の輔らくごの没入感には敵わない。 舞台の下での立川志の輔は、言葉一つひとつを自分とズレのないように大切に紡いでゆく。そして舞台の上と同じように聞き手を引き込んでくる。 「イマジネーションと集中力、この二つを持ち合わせている人が、たぶん落語を愛していける、落語を人生の友としてそばに置いておける、そんな資格のある人だと思っているんです。そして『落語がこんなに面白かったのか』と感じたということは多分、何人かいるであろう、波長の合う落語家の一人が私であったということ、だと思います。波長が合う、合わないというのは絶対にある。今1,000人の落語家さんがいて、前座修行の開けた人が800人いたとして、800人の落語を聞くなんて考えられないことですから、やっぱり好きな落語家さんといったら4、5人の落語家さんになってくる。その落語家さんはタイプが似てるとか、あるいは全く違っていても、何か自分の集中力とイマジネーションを喚起してくれる話法なんですよね、きっと」 落語は一番弱い芸能 「名人上手だから好き、というわけでもない。僕の落語を聞いても合わない人は合わない。それよりももっと私よりも合う落語家さんがいる。そこが、落語の魅力と厳しさにつながっています。厳しさというのは、落語家になって弟子にさえなれば、ご飯が食べていけるとは限らない。お客さんがつくとは限らない。落語は個人業なんです。大変に難しい〈芸能〉なんですよ」 立川志の輔は「チケットを手に入れるのが一番難しい落語家」と言われるほどに群を抜いて人気が高い。お客の集中力とイマジネーションと、そして相性。深く納得はできるが、まだそれだけでは説明がつかないものがある。強烈な人間力を持ち合わせていて変幻自在に会場との波長を調節できるのだ、と言われたらそれもガッテンできるが、〈芸能〉としみじみと語られるその言葉には、それらとは少し異なる落語家としての矜持が感じられる。 「落語の一番楽な紹介の仕方は、『落語なんて聞いて笑えるところがあったら笑って貰えばいいんですから、気楽に聞いて貰えばいいんです』というのが一番楽な紹介の仕方なんです、本当はね。でも気楽になんか聞けないんですよ、本当は、落語はね。日本の中にある芸能の中で、落語は一番弱い芸能なんです。講談は最後まで叩きながらやり切ることができるし、浪曲もストーリーに乗っかってやり切れる。ところが落語は笑う、ということがメインなので、笑わなかったら次にいけない。笑わなかったら、『あ、笑わないんだ』と演者が『あ』と不安になって、『次大丈夫か? あ、次も笑わないんだ、あ、あ……』となっていく」 笑うから次に行ける 「ゲラゲラ笑う、というよりはお客さんが思わず笑ってしまう、というぐらいに笑い声が出るのは、お客さんの集中力にかかっているんですよ。笑わせるんじゃないんですよ。お客さんが自然に笑うという状況に持っていく材料をしゃべっている。話の中にはお客さんが集中しているかどうかわかるポイントがいくつかあって、それがうまく行っている時と、うまく行っていない時とがある。そしてうちには弟子が8人いるけど、さあどの弟子がここで笑わせられるのか、できないのか、そうすると比較が始まる。それは集中力の前に、何か邪魔になるものがあるんですよ。落ち着かないとか、口調が早い、とか。『あ、もうちょっとゆっくりしゃべればいいのに』と思うと、もうもうダメなんですよ」 ここである。 志の輔らくごの出発地点はここにある。「落語は弱い芸能である」ということ、そして「人は集中力を持続させるのが難しい生き物である」ということの、この大前提から出発しているのが志の輔らくごなのだ。 だから客の集中力を削ぐあらゆるものを取り除く努力を怠らない。客は最初から研ぎ澄まされた集中力とイマジネーションを持ち合わせているわけではない。志の輔に助けられて、自分の中にある微かな集中力とイマジネーションをフルに稼働させてもらっているのだ。 例え大ホールの3階最後列の席から、落語を演じる立川志の輔の後頭部を見つめながら聞いていても、それでもただ自分のためだけに語ってくれているように心に響いてくる。志の輔の落語への愛と、歩んできた人生と、目の前の客への想いからの一体感である。その場限りの形に残らないはずのライブが、鮮明にいつまでも心に残ってゆく。 土居彩子(どい・さいこ) 1971年富山県生まれ。多摩美術大学芸術学科卒業。棟方志功記念館「愛染苑」管理人、南砺市立福光美術館学芸員を経て、現在フリーのアートディレクター。 デイリー新潮編集部