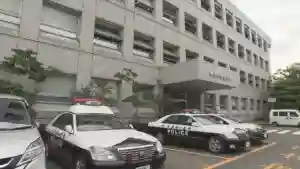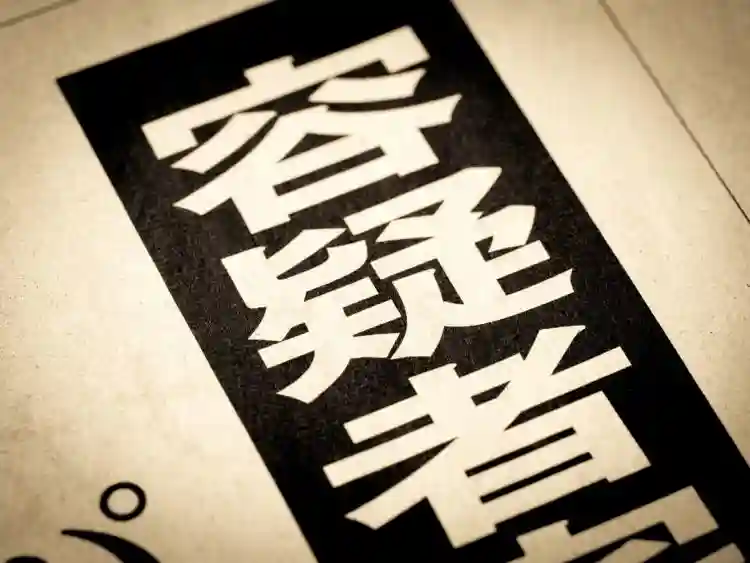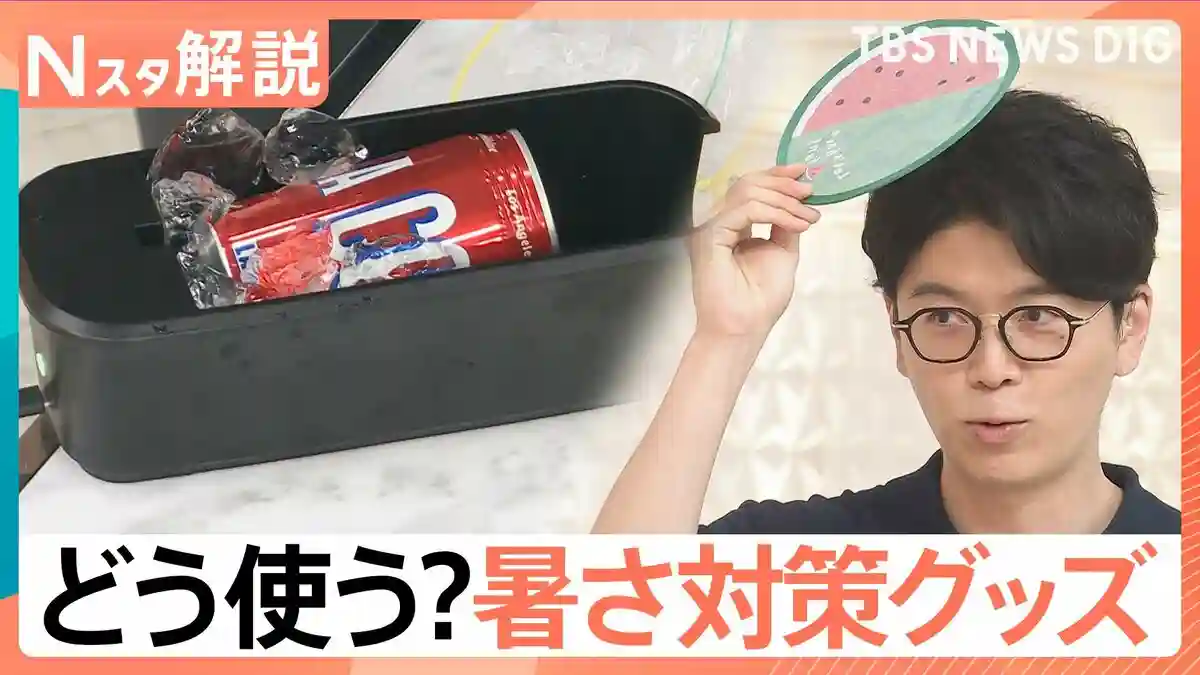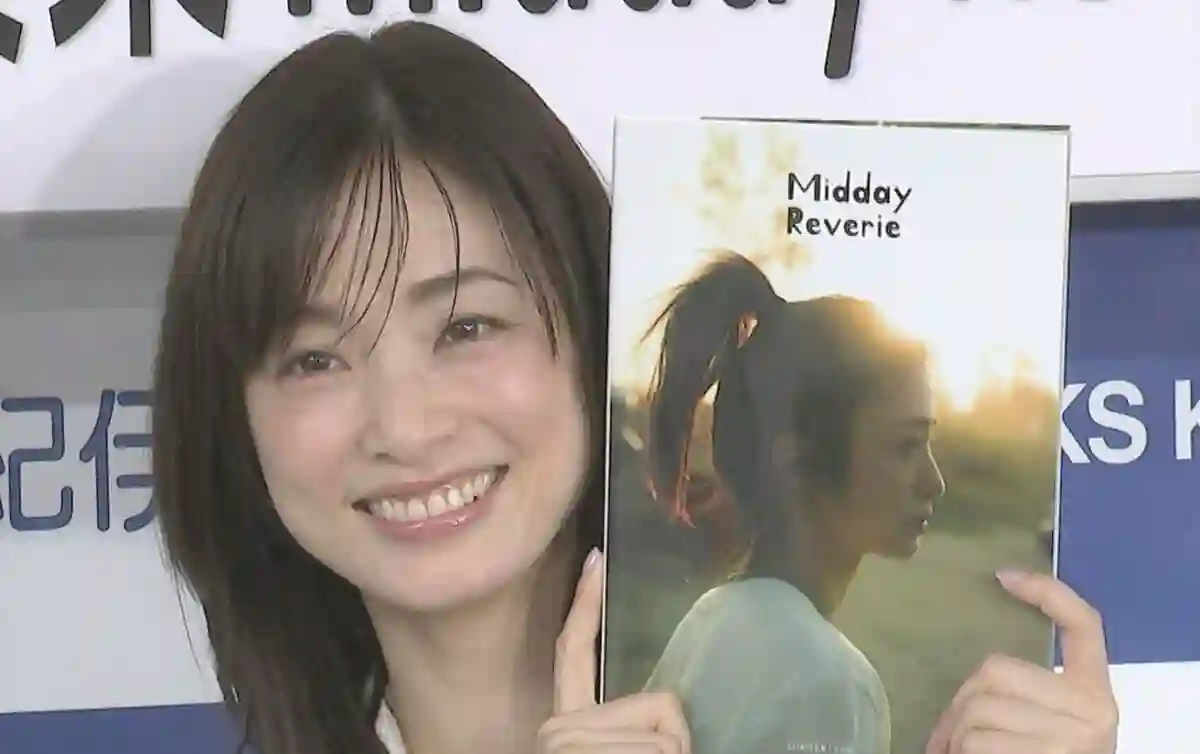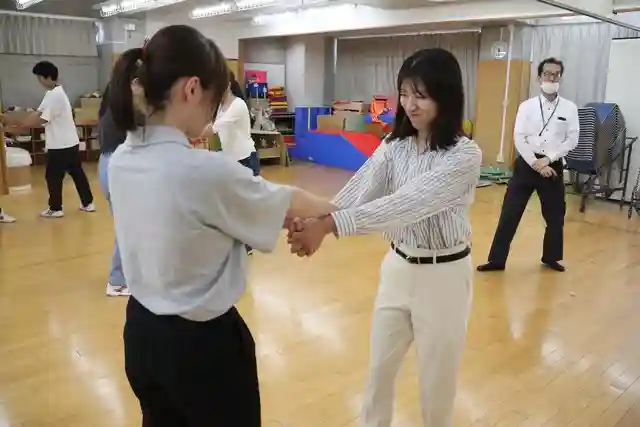『ざんねんないきもの事典』や動く図鑑「MOVE」シリーズなど、子どもから大人まで幅広い世代に愛される作品を監修してきた動物学者・今泉忠明先生。実は今泉先生、子どものころから動物と深くかかわってきました。というのも、お父さんもお兄さんも、そして息子さんまで動物学者という「動物の一家」なのです。 そんな今泉先生が登壇する「FRaU×KANEBO こどもコンテストワークショップ」が2025年8月2日に開催されます。今泉先生の講義のテーマは、「いきものの性別って、オスとメスだけじゃないの?」、「人間の男女はどうして分かれているの?」といった、“いきもののジェンダー”に関するふしぎ。今泉先生が、動物たちのさまざまな「性」のあり方について、クイズを交えながら、楽しくわかりやすく教えてくれます。 イベントを前に、今回は今泉先生の子ども時代や、動物との出会い、そしてどうして動物学者の道に進んだのかを3回に分けてご紹介します。動物好きなお子さんにとっては、将来のヒントになるかもしれません。 第1回では、中学生から大学生時代のエピソードをお届け。外国人研究者との出会いや、運転免許をきっかけに始まった本格的な採集旅行など、今泉先生が自然と動物学の世界に引き込まれていった過程を、著書『気がつけば動物学者三代』(講談社)から抜粋してお伝えします。 野球部で体力づくり 小学校を卒業して杉並区立杉森中学校に進学すると、父や兄といっしょに山に行く機会は、ますます増えました。成長して体力もついたので、二男の僕も、動物採集に必要な人材になってきたのです。 ときには八ヶ岳のような本格的な山に登ることもありました。八ヶ岳は、長野県と山梨県にまたがる山々の総称で、いちばん高い山で約二九〇〇メートルもあります。険しい山道も多く、高尾山とは比べ物にならないほど、登るのに体力がいります。 「もっと体力をつけないと!」 そんな気持ちから、学校では野球部と柔道部に入りました。兄は中学時代から理科部に入って動物のことを調べたりしていましたが、僕は、まだ動物学者への道をそこまでは意識していませんでしたし、野球選手への憧れもあったからです。 ただ、野球はお金がかかるスポーツです。グローブやユニフォームを買うお金がなかったので、グローブはみんなで同じものを使い回します。そのため、練習といってもランニングやキャッチボール、たまにノックをする程度でした。 それに加えて、僕は致命的なことに気がつきました、僕は、あまり野球が得意ではなかったのです! 同じ学年のピッチャー候補だった部員はコントロールが抜群。それに引き換え、僕は走るのも遅いし、投球もイマイチ。野球部の練習がないときは柔道部の練習に参加して体を鍛えましたが、それでもいっこうに野球はうまくなりません。 では柔道はどうかといえば、こちらもやせっぽちで、相手に歯が立たず全然ダメ! それでも、受け身の練習は役に立ったと思います。このおかげで、山で転んでも頭は守るというくせがついたからです。 野球が下手で、柔道は弱い......。そう実感させられた中学時代でしたが、不思議とショックはありませんでした。「野球はダメだけど、泳ぐのは得意だし」と、すぐに気持ちを切り替えられたからです。できないことを考えて落ち込むより、得意なことを挙げていったほうが、よっぽど楽しいと、このころから思っていたのです。 それに、下手だからといって野球が嫌いになったわけではなく、成城高校に進学しても、なんとなく野球部に入部しました。驚いたことに部員が九人しかいなかったので、こんな僕でもレギュラーになれてしまいました。部員は少なかったものの、元プロ野球選手の息子で上手な選手がいたため、甲子園に出場するような強豪校に勝ったこともありました。練習は中学時代とは比較にならないほどハードで、ついていくのがやっとです。毎日、家に帰るのが夜の八時。家に帰ってから、練習用のボールを縫ったり、磨いたりといった手入れもしなければなりません。死にそうなほどくたびれましたが、体力はかなりつきました。 週末には、父との動物採集も変わらず続いていました。ほかにもやりたいことがありながらの部活との両立はきつく、二年生の途中で野球部を退部しました。しかし、ここでの練習で培った体力は、その後の人生におおいに役立つことになります。 スウェーデンから来たコウモリ学者との出会い 「忠明、夏休みにいっしょに富士山に行かないか?」 父にそう誘われたのは高校二年生のときのことです。なんでも、コウモリの研究をしている学者がスウェーデンから来るので、富士山を案内したいということでした。 「スウェーデンのような遠くの国から、わざわざ日本にまでコウモリを調べに来る人がいるのか!」 海外渡航が当たり前という時代ではありませんから、その事実に驚きつつ、父にくっついて人生で初めて富士山を訪れました。 そのスウェーデン人はラルス・ヴァーリンという学者で、僕が初めて接する外国人でした。今は日本にも外国人がたくさんいますが、当時は外国の人、とくに白人に会う機会などほとんどありませんでした。 「なんて背が高くて、足が長いんだろう!」 それがヴァーリンの第一印象です。富士山に向かうため、東京から電車に乗った際の彼の様子は今も忘れられません。日本の列車の狭いボックスシートにヴァーリンの長い足は少々窮屈そうでしたが、それでも、ダラッと足を広げたり、姿勢を崩したりすることなく、静かに座っていました。 「紳士っていうのは、こういう人のことをいうんだなぁ」 そんなふうに感じたものです。 ヴァーリンの目的は、富士山麓の森に生息するコウモリを調べることでした。富士山のふもとから四輪駆動のバスで五合目まで行き、冨士山小御嶽神社の山小屋で一泊しました。あいにく台風の直撃で暴風雨に見舞われ、せっかく富士山まで行ったというのに、ほとんどコウモリの調査はできませんでした。あきらめきれなかったようで、ヴァーリンは薄暗くなったというのに、ゴウゴウと吹き荒れる嵐の中、森へと入っていきました。一時間ほどすると、ずぶ濡れで帰ってきましたが、どうしてもコウモリを見たかったのだそうです。 そんな期待外れの調査でしたが、帰り道にうれしい出来事がありました。富士五湖のひとつ、河口湖にあった、町の資料館に立ち寄ったところ、ヴァーリンが展示物の中に奇妙なヒナコウモリの標本を発見したのです。ヒナコウモリは、ロシアのウスリーや中国東部、日本だと福岡県や、埼玉県の秩父などに生息するとされるコウモリです。 ヴァーリンは耳が細長いなどの特徴から、たんなるヒナコウモリではないと見抜いたのです。 「こんなヒナコウモリは見たことがない!ぜひスウェーデンに持ち帰って研究に役立てたいのですが」 ヴァーリンは資料館に交渉し、この標本を持って帰ることに成功しました。そして彼の帰国後、日本で見つかった新種のコウモリとして論文が発表されたのです。 和名:トウヨウヒナコウモリ 学名:Vespertilio orientalis Wallin, 1969 発見したヴァーリンの名前と発表した年が、学名の後にあります。この学名の読み方を父が教えてくれました。僕は、世界の学者が驚くような貴重な動物が、まだ日本にいることに強い衝撃を受けました。ヴァーリンとは、その後、会う機会はありませんでしたが、このときの出来事は、僕の胸に鮮明に焼き付いています。 これを発端として、僕は今日に至るまで、数え切れないほど調査のために富士山を訪れています。当時は、まさか自分がその後、足しげく富士山に通うことになるなんて想像もしていませんでしたが、ヴァーリンとの出会いは、僕が動物学者になるという運命の導きだったのかもしれません。 ミッション: すぐに運転免許を取ること! 高校卒業を控えた僕は、東京水産大学(現在の東京海洋大学)を受験することにしました。海や海洋生物の研究に特化した国立大学で、海が好きで泳ぎが得意だったという理由もありますが、小学生のときにクストーの映画で観た海の光景が忘れられなかったからでした。 しかし......受験勉強が間に合わず、あえなく不合格でした。一年間の浪人生活を送り、翌年、無事に合格を果たし、水産学部の増殖科で資源学を専攻しました。資源学とは、「この海には何匹ぐらい伊勢エビがいるのか」などの統計をとる学問です。海に潜り、網をかけて海洋生物を捕ることも多く、子どものころから培ってきた泳ぎの技術がおおいに役に立ちました。 ただ、海や海洋生物について勉強するようになったからといって、父との動物採集の楽しさを忘れたわけではありませんでした。むしろ、すでに新潟県にある長岡市立科学博物館の研究者として働き始めていた兄の代わりに、父はこれまで以上に、僕を積極的に山に連れていくようになりました。 「忠明、車の運転免許を取ってくれ」 父にそう頼まれたのは、大学三年生のときでした。当時は、今のように一家に一台、車を所有できる時代ではなく、自家用車はまだ高嶺の花です。当然、僕の家にもありませんでした。 「うちには車もないのに、父さんは、なぜ僕に運転免許を取らせたいんだろう.........」 そう不思議に思いながらも、「海に行くときに運転できれば便利になるし」という気持ちもあり、自動車教習所に通い始めました。すると、弟が中古車を買ってきました。古びていましたが、荷物がたくさん積めるワンボックスタイプです。弟は牛乳配達をして貯めたお金で、父に車を買ってあげたそうです。これには頭が下がりました。 免許取得で広がった採集の世界 ほどなく運転免許の検定試験に合格し、念願の免許が交付されました。それからわずか一週間後のことです——。 「免許を交付されたってことは、もうどこでも走れるから大丈夫だよな。車で採集旅行に行くぞ!」 父は突然、言い出しました。そうです、僕に運転免許を取れと言ったのは、動物採集に車で行くためだったのです。 父は運転免許を持っていないので、運転するのはもちろん、免許を取り立てほやほやの僕しかいません。教習所で運転技術はひととおり習ってはいますが、カーブの多い山道を走る自信などまったくありません。「大丈夫なんだろうか」と冷や汗を流しながら、僕はワンボックスカーのハンドルを握りました。危険極まりなく、今考えるとゾッとします。 父と父の助手の人たち三人を乗せて向かった先は、新潟県の妙高高原です。ニイガタヤチネズミ(当時の呼び名)が、アメリカ人の研究者マルコム・アンダーソンによって初めて捕獲された赤倉(新潟県妙高市)が近いので、この場所が選ばれました。この山の中にテントを張って野営し、ネズミやモグラなどの動物の採集を開始しました。本格的な野営は初めてだったので、小学校の遠足のときのようにわくわくした気分になったことを覚えています。 僕はてっきり妙高高原に何泊かして調査をするのかと思っていたのですが、父は車の移動が快適だったのか、目指すニイガタヤチネズミがたったひと晩で捕まえられたからなのか、「この際、どうせなら.........」と欲が出たようです。 「ずっと南だろうけど美ヶ原高原にも行きたい。移動しよう」 父の言うとおり、黒姫山と長野市を挟んで長野県中部にある美ヶ原高原へ行き、そこでも一泊し、さらに父のリクエストにしたがって、西の乗鞍岳、最後には富士山まで車を走らせ、富士山二合目のブナの原生林の中でテントを張って一泊しました。 結局、父の思いつくまま、延べ六日間かけてあちこちへと訪れた大採集旅行になりましたが、大きな収穫がありました。最後に訪れた富士山二合目の森は「低山帯と亜高山帯の分かれ目にある落葉樹と針葉樹が入り混じった混交林」で、生物調査にとても適した場所だとわかったので、その後も動物採集のために東京からここに通うようになったのです。 なによりも、この採集旅行は、森林の中で寝泊まりし、動物を探すことのおもしろさを僕に教えてくれました。運転免許の取得をきっかけに、僕の行動範囲はぐっと広がり、同時に父と採集旅行にいく機会も格段に増えていったのです。 第2回【『ざんねんないきもの事典』今泉忠明、“親の助手”から動物学者になると決意するまで】では、動物学者とは具体的にどんなことをするのか、そして今泉先生が「なぜこの動物学者になろうと思ったのか」についてお伝えします。 【中編】『ざんねんないきもの事典』今泉忠明、”親の助手”から動物学者になると決意するまで