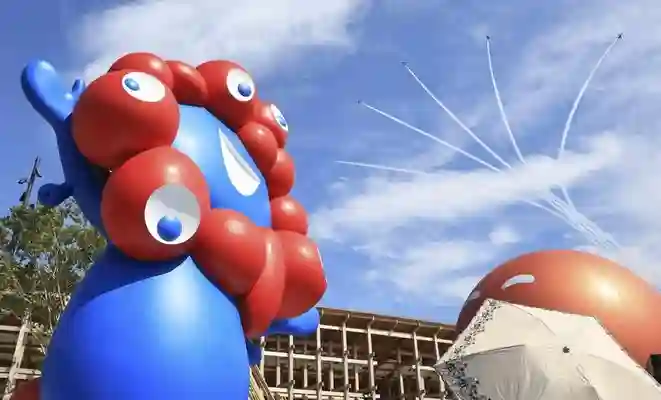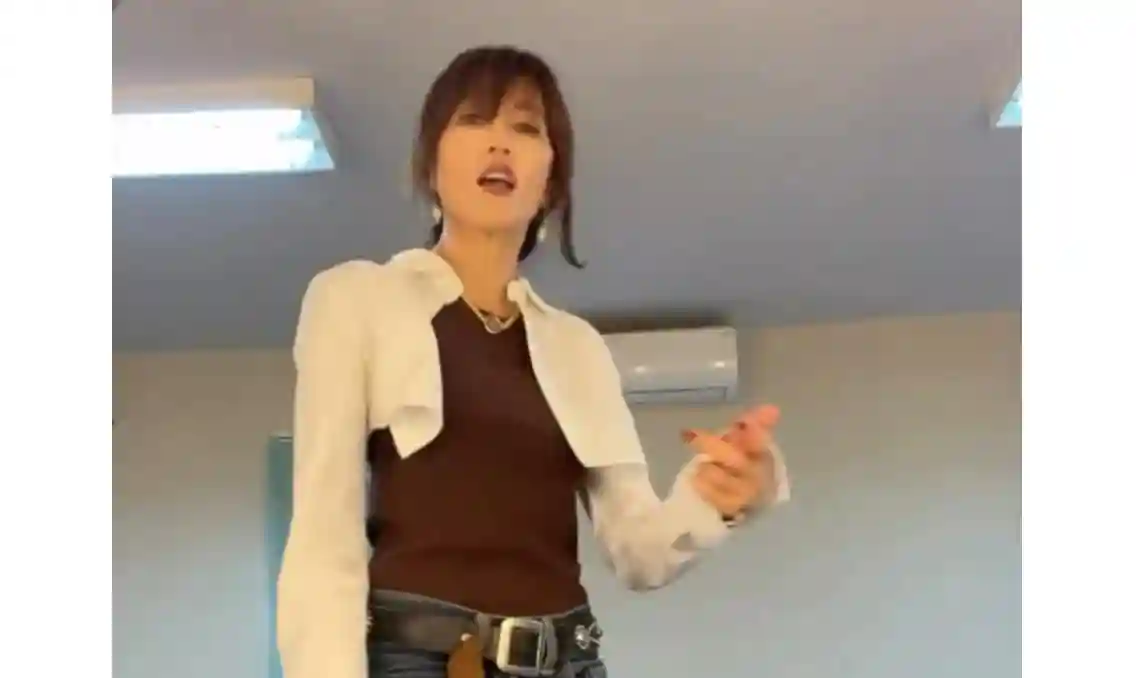米中間のハイテク覇権争いが、新たな「冷戦」段階に突入しています。半導体とレアアース(希土類元素)を軸に、トランプ米政権(2025年)の強硬な通商策と中国の報復がエスカレートし、貿易・技術を巡る摩擦は激化の一途をたどっています。 2025年4月には米国が対中関税率を累計145%という前例のない水準に引き上げ、中国は対抗措置としてレアアースの輸出規制に踏み切りました。さらに米中双方は、迂回輸出を封じ込めるため、ベトナムやインドなど第三国にも高関税を課す構えを見せ、貿易摩擦の火種は周辺国にも飛び火しています。 そこで今回は、この「新冷戦」の最新ロードマップを整理するとともに、グローバル企業が生き残りを図るために講じつつあるサプライチェーン再編やリスク分散策について考察し、激変する国際ビジネス環境の行方を探ります。 145%関税時代の到来 ── エスカレートする報復合戦 2025年4月初旬、米国のドナルド・トランプ大統領は対中強硬策を一段とエスカレートさせました。前述したように145%関税という前代未聞の数字には、米中間の貿易不均衡是正を掲げた「相互関税」分としての125%と、中国からの違法薬物(フェンタニル)流入を理由とする追加関税20%が含まれています。従来から段階的に積み上げられてきた対中関税がついに三桁台に乗り、これは米中貿易に壊滅的打撃を与えかねない水準だと受け止められました。 この極端な関税措置は、いわば「移行期間の痛み」を伴う荒療治でした。トランプ大統領自身、「移行に伴うコストや問題は発生するだろうが、最終的には素晴らしい結果になる」と自信を示し、高関税が一時的な混乱を招く可能性を認めつつも、長期的な米国産業振興に資するとの楽観姿勢を崩しませんでした。しかし、市場は敏感に反応し、米株式市場は関税引き上げ発表直後に貿易戦争激化リスクを警戒して急落する場面も見られました。米政権内でも「90日間の関税上乗せ停止(対中以外)措置」など柔軟策が示唆され、各国との交渉次第で税率調整もあり得るとしましたが、対中に関しては強硬な姿勢を崩さず、7月以降にはさらなる上乗せも辞さない構えが示されています。 こうした米国の動きに対し、中国もただ手をこまねいてはいません。トランプ政権の発表から間を置かず、中国政府はレアアース輸出の規制強化という切り札を切りました。2025年4月4日、中国商務部と税関総署はサマリウム、ジスプロシウム、テルビウムなど7元素とその関連製品を対象に、輸出管理措置を即日施行すると発表したのです。対象品目には各元素の金属・合金、酸化物や化合物まで含まれ、輸出には当局への許可申請が必須となりました。中国側は「国家の安全と利益の維持、核・ミサイル拡散防止など国際義務の履行」を名目に掲げていますが、タイミング的に見て明らかに米国への報復カードといえます。実際、中国商務部は4月3日の談話で米国の相互関税方針に「断固反対」であると表明し、自国の権益を守るため対抗措置を取ると予告していました。レアアースはハイテク機器の製造に不可欠な戦略物資であり、中国は世界生産の大半を握ります。その供給を絞ることは、米国や同盟国のハイテク産業に打撃を与える強力な圧力手段です。 半導体とレアアースの「新冷戦」 こうした事態は「半導体とレアアースの新冷戦」とも呼ぶべき様相を呈してきました。米国は半導体分野で中国に痛打を与えるべく、先端半導体の輸出規制や関連技術の封じ込めに動いています。例えば2022年以降、米商務省は対中ハイエンド半導体や製造装置の輸出を厳しく制限し、さらに人工知能(AI)やスーパーコンピューティング関連の先端チップも事実上輸出禁止にする措置を次々と発動しました。中国企業にとって心臓部ともいえる半導体供給網を断つ戦略です。一方の中国は、米国が弱みを抱えるレアアース供給を梗塞することで応戦し、相手のハイテク製造能力に打撃を与えようとしています。 興味深いのは、こうした睨み合いのなかで物々交換のような駆け引きも行われたことです。2025年7月3日、米中は部分的な歩み寄りを見せ、貿易摩擦緩和に向けた枠組み合意を取りまとめました。その一環として米国側は、中国向けの半導体設計ソフトウェア(EDAソフト)輸出規制を緩和し、一部の輸出ライセンス要件を撤回する措置をとったのです。ドイツ企業シーメンスによれば、「中国向けEDAツールの輸出について、旧世代バージョンに限りライセンス申請は不要になった」と米商務省から通知があったといいます。この規制緩和は、実は中国のレアアース供給制限に対する米国の対抗策の一環でした。同時に両国は合意事項として、「中国が約束通りレアアース輸出許可の迅速化など供給を確保すれば、米国も中国へのエタン(化学製品原料)や半導体設計ソフト、航空機エンジン部品などの輸出を認める」というバーター取引的な内容で折り合ったのです。まさにレアアース vs. 半導体ソフトの交換条件で一時的な緊張緩和が図られた形と言えます。米商務省は2025年5月時点ではEDAソフト大手各社(シーメンス、ケイデンス、シノプシスなど)に対し中国顧客への販売停止を求める書簡を出していたもの、7月には方針転換しライセンス要件撤回を通知しまし。これによりシーメンスなどは中国顧客へのソフト提供を全面再開しています。 こうした米中間の応酬劇は、高度技術分野での相互依存がいかに戦略的リスクとなり得るかを浮き彫りにしました。半導体製造にはEDAソフトや精密装置が不可欠で、それらを握る米国に対し、中国はレアアースという材料面の支配力で対抗する——ハイテク産業の川上から川下までを巻き込んだパワーゲームが展開されているのです。 「新冷戦」とは単なる比喩ではなく、21世紀の経済安全保障を巡る現実の綱引きを表す言葉として定着しつつあります。 関税包囲網と“迂回”阻止 ── ベトナム・インドに飛び火する相互関税 米国の通商戦略は中国との直接対決にとどまらず、第三国を巻き込んだ関税包囲網の様相を呈してきました。トランプ政権は「相互関税(reciprocal tariff)」と称し、各国の対米貿易障壁の度合いに応じて米国の関税率を引き上げる方針を打ち出しました。その結果、中国以外の諸国にも一律10%(当初)というベース関税が課され、特に対米輸出で黒字を出している国々には高めの追加関税率が設定されたのです。例えば、インドからの輸入品には26%の関税が課されることになりました。トランプ大統領は「インドは米国製品に平均52%もの関税障壁を課しており、我々を正しく扱っていない」と批判し、この26%という数字はインド側の高関税への対抗だと説明しています。 実際、インドは長年「関税王」と揶揄されるほど保護主義的な関税政策を取ってきた経緯があり、米通商代表部(USTR)の報告書でも名指しで問題視されていました。米国にとってインドは中国に次ぐ巨大市場であり、戦略的パートナーシップも重視されていますが、こうした高関税措置の対象からは逃れられなかったのです。 さらに注目すべきは、ベトナムなどサプライチェーン移転先として脚光を浴びる国々に対する米国の姿勢です。中国から生産拠点を移す先として多くの企業がベトナムを選んだ結果、米越間の貿易額は急増し、米国にとって対ベトナム貿易赤字が拡大していました。これを懸念したトランプ政権は、当初ベトナムからの輸入品に46%という非常に高い関税率を課す意向を示し、各方面を驚かせました。事実上、中国からの“迂回輸出”拠点と見なして牽制した格好です。この発表はベトナムにも衝撃を与えましたが、同時に交渉の余地も示唆されました。米通商当局者の一部には「中国から移転する生産を促すため、東南アジア諸国への関税は中国より低く設定すべきだ」との声もあり、ベトナム側との交渉が水面下で進められました。 その結果、2025年7月2日に米越両国は貿易協定で合意に至ります。トランプ大統領が発表したその内容は、ベトナム産品に対する米国の輸入関税を20%に抑える一方、ベトナム経由の迂回輸出品には40%の高関税を科すというものでした。具体的には、中国など第三国で作られた部品を組み立てただけの製品や、最終工程だけベトナムで行ったような付加価値の低い輸出品が「迂回」と見なされ、40%もの懲罰的関税の対象となります。一方で、ベトナムは米国からの輸入品にかけていた関税を全て撤廃することにも同意しました。米国製品を無関税で受け入れる代わりに、自国製品には20%の関税を受け入れるというディールです。トランプ大統領は「要するにベトナムが米国に市場を開放するということだ」と述べ、ベトナム共産党の最高指導者グエン・フー・チョン書記長との電話協議で合意に漕ぎ着けたと強調しまし。ベトナム側も声明で「二国間の貿易上の課題解決に向け協力していく」と応じています。 この米越合意は、一見するとベトナムに厳しい条件(20%関税)は押し付けていますが、当初懸念された46%より大幅に低い水準に収まりました。米国としては、あまりに高い関税でベトナムからの輸出を潰してしまうと、中国からの生産移転誘導という戦略目標に反するため、苦渋の妥協を図った形と言えます。 実際、発表された条件では「中国など他国由来の部品を使った製品」に限定して40%を課すとし、純粋なベトナム産品には20%にとどめています。この線引きにより、たとえば衣料・家具といったベトナム独自の製造品(米国の大手アパレル企業ナイキや家具企業などが調達している製品)は20%で済み、市場への影響が限定されるとの見方も出ました。発表を受け、米国株式市場ではナイキやルルレモンといった関連銘柄が上昇したほどです。 「中国製品の抜け道」を塞ぐための関税包囲網 こうして米国は、中国だけでなくインドやベトナム、カンボジアといった国々にも高関税適用を拡大することで、グローバルな関税包囲網を築きつつあります。インドの場合は前述の26%ですが、実はインド政府は当初米国との関係改善のため一部関税引き下げを検討する姿勢も見せていました。しかし米国側は容赦なく「相互関税」の対象に含め、譲歩を迫った格好です。もっともインドとは2025年2月にモディ首相とトランプ大統領の首脳会談で包括的な二国間貿易協定交渉を開始しており、今後の協議で関税率引き下げの交渉が本格化するとみられます。日本や欧州連合(EU)といった同盟国も一律10%のベース関税の例外ではなく、たとえば日本からの輸入品には24%の関税が検討されたとの報道もあります。ただ、これら友好国とは経済連携協定の締結や米国側の柔軟な運用によって高関税の適用が回避・軽減される可能性が高く、実際に日米や米欧間で早期の協議が進んでいる模様です。 米国がここまで網を広げる背景には、「中国製品の抜け道を塞ぐ」という明確な意図があります。米政府高官は「中国が第三国経由で米市場に製品を送り込むのを事実上制限する戦略的意図がある」と指摘しており、迂回ルートとなり得る国々に予防線を張った形です。たとえばベトナムは輸入の約40%を中国から調達しており、米国は「中国がベトナムを迂回拠点に利用している」と非難していました。今回の米越合意ではベトナム側も原産地証明の厳格化など迂回輸出取り締まりを強化する方針を示しており、中国製品のすり抜け封じ込めに協力することになります。インドに対しても同様に、もし中国企業がインド経由で対米輸出を図るようなケースがあれば、米国は高関税措置や是正要求を行う可能性があります。 こうした動きは一歩間違えればグローバル供給網の分断を深刻化させかねません。サプライチェーンの「中国離れ」が進む中、その受け皿となる国々にも新たな関税リスクが生じているからです。企業にとっては、生産拠点を中国から移せば安全という単純な話ではなく、移転先の国が米国と良好な通商関係にあるか(あるいは交渉力を発揮できるか)まで考慮しなければならなくなりました。まさに貿易摩擦がグローバルに連鎖し、多国間の駆け引きが複雑に絡み合う時代となっているのです。 脱・中国依存のリアル ──アップルに見る分散の最前線 高関税と輸出規制が飛び交う中、グローバル企業はサプライチェーンの再編を加速させています。とりわけ顕著なのが、これまで中国に大きく依存してきた製造・調達体制の見直し、すなわち「脱・中国依存」の動きです。その最前線にいるのが米アップル社でしょう。アップルはiPhoneをはじめ主要製品の製造を長年中国に委ね、中国の広大な生産エコシステムの恩恵を享受してきました。しかし米中摩擦の激化や新型コロナ禍での中国ロックダウンによる工場停止などを経て、アップルは危機感を募らせます。そしてついに生産分散先の拡大に本腰を入れ始めました。 象徴的な出来事が報じられたのは2025年4月、トランプ政権の125%対中関税(145%関税の一部)が現実味を帯びたときです。アップルは極秘裏に計画を進め、中国以外の拠点、特にインドでのiPhone生産を約20%増強し、その追加生産分を空路で米国に緊急輸送するという離れ業を成し遂げました。インド南部タミル・ナドゥ州のフォックスコン(鴻海)工場では、通常は休日である日曜日にも操業を拡大し、従業員を増員してフル生産を行ったといいます。こうして確保したiPhoneを、チャーター貨物機で次々とインドから米国へ空輸しました。その総量は600トン(約150万台)にも達し、アップルがいかに必死に「関税の壁」を乗り越えようとしたかが窺えます。インド政府も協力的で、チェンナイ空港では通常30時間かかる通関手続きを6時間に短縮する「グリーン回廊」をアップル向けに特別に設け、出荷を迅速化しました。まさに会社と政府を挙げた作戦で、トランプ関税の発動前にできるだけ多くのiPhone在庫を米国内に積み増そうとしたのです。 数年前までインド生産分はごく一部に過ぎず、主に現地市場向けだったことを考えると、劇的なシフトです。アップルはインドでの製造をさらに拡大する構えで、フォックスコン以外にも台湾のペガトロンやインド企業タタとの連携で工場増設を進めています。同時に、AirPodsなど一部の製品組立をベトナムに移す動きも報じられており、「中国+α」の多極生産体制が現実のものとなりつつあります。もっとも、アップル幹部は「サプライチェーンの地域分散・リスク分散という長期トレンドは今後も変わらない」と述べつつも、完全な「脱中国(デカップリング)」は非現実的であり依然相互依存は残るとも指摘しています。実際問題、インドやベトナムでは電力や水道などインフラ信頼性が中国に劣り、熟練した労働力や部品供給網も整っていないため、一朝一夕に中国の代替とはいきません。アップルの事例は、リスクヘッジのための多拠点化を示す一方で、新興国への移管には課題も多いことを教えています。 日系企業の脱・中国依存 さらに、消費財やエレクトロニクス分野でも「中国から東南アジアへ」のシフトが加速しています。日本のゲーム業界を例に取ると、任天堂は大ヒット中の家庭用ゲーム機「Nintendo Switch」を中国とベトナムの工場で生産していましたが、米国の相互関税発表を受け、2025年6月発売予定の次世代機「Switch 2」の販売戦略を急遽見直す事態となりました。トランプ政権の発表によれば、ベトナム製品には46%、カンボジア製品には49%もの高関税が課される可能性があったからです。任天堂は米国におけるSwitch 2の予約開始日(4月9日予定)を無期限延期し、「新たな関税政策の影響を評価するため」と説明しました。発売日は変えないものの、価格引き上げも視野に入れて戦略を練り直す必要に迫られたのです。 任天堂の対応策は、アップル同様に在庫の先行確保と生産振り替えでした。各種報道によれば、Switch 2の生産の大部分はなお中国に依存していますが、任天堂は「ベトナムでの全製造能力を米国向けに集中させ、猶予期間の3カ月で可能な限り製品を出荷する」方針を立てたといいます。ちょうど米越間での関税協議が合意(猶予期間中の7月上旬)されるまでは、ベトナム生産分を総動員して米国に送り込み、高関税発動による品不足や価格高騰を抑えようとしたわけです。加えて任天堂はグローバル規模でSwitch 2の在庫を積み増しし、その一部は既に米国内倉庫に到着していることも明らかにしました。こうした先手の備えにより、発売直後の米国市場に十分な供給を行うことを目指しているのです。 ただ任天堂にとっても頭の痛い問題は、中国での生産そのものを直ちに他国へ完全移管するのが難しい点です。ゲーム機の複雑な部品供給網や生産ノウハウは中国に長年蓄積されており、ベトナムだけでは需要の全てをまかなえないのが現状です。実際、Switch 2の米国価格は449.99ドルに設定されていますが、仮に145%もの関税が中国製品に課されたままだとすれば、大幅な値上げか利益圧迫は避けられません。米ゲーム産業団体ESAも「ゲーム業界に現実的かつ有害な影響が出る」とトランプ関税に反対する声明を出しており、任天堂のみならずソニー(PlayStation)やマイクロソフト(Xbox)といった業界全体が対応を迫られたのです。ソニーは欧州や日本市場でPlayStation 5の値上げに踏み切りましたが、その理由を「インフレと為替変動」としつつも、専門家の間では米国関税の影響を先回りして反映した可能性も指摘されています。 このように、日本企業もグローバルなサプライチェーン再編の荒波の中にいるのです。エレクトロニクス以外でも、自動車業界では電気自動車(EV)用バッテリーの調達で中国依存を減らすため、国内生産や米国現地生産を拡充する動きがあります。トヨタやホンダは米国の政策(インフレ抑制法によるEV補助金要件など)に対応して、北米での電池工場建設計画を進めています。電機大手では、パナソニックが家電生産の一部を東南アジアから日本に回帰するケースや、半導体不足に備えて在庫を積み増すケースも報じられています。2020年には日本政府がサプライチェーン対策費用を補助する制度を創設し、中国から東南アジア等への生産移転を支援しました。これを活用して実際にベトナムやタイに新工場を開設した中堅企業も数多くあります。こうした公的支援もあり、日系企業は「中国リスク」を直視した長期戦略を模索しています。 以上の事例から浮かび上がるのは、コスト最優先でグローバル生産ネットワークを構築してきた時代から、リスク分散と柔軟性を重視する時代への転換です。企業は地政学リスクや貿易障壁の変化を念頭に置き、生産拠点や調達先を多元化しつつ、需要地への素早い供給ルートを確保しようと奔走しています。それは決して容易な課題ではありませんが、米中摩擦という構造的リスクに対峙する上で避けて通れない経営戦略となっています。 ビジネスへの示唆 ── フレンドショアリング、在庫戦略、規制モニタリングの3本柱 激化する米中摩擦と新冷戦下において、ビジネスパーソンや企業経営者が学ぶべき教訓は何でしょうか。最後に、今後の企業戦略の柱となるべきポイントを3つ挙げます。 <フレンドショアリング(友好国への拠点シフト)> これからのサプライチェーン構築キーワードは「フレンドショアリング」です。フレンドショアリングとは、信頼できる同盟国や友好国に限定して供給網を組み立てることを指します。すなわち、政治的に不安定な国や対立関係にある国への過度な依存を避け、価値観を共有する国々との間で生産・貿易を完結させる考え方です。米国が提唱し始めたこの概念は、コロナ禍での物流停滞やウクライナ戦争でのエネルギー・食料危機を経て、一層現実味を帯びています。例えば、半導体やレアアースといった戦略物資について、米欧や日米豪印といった枠組みで協調しサプライチェーンを強靭化する動きが見られます。企業レベルでも、自社の主要市場や技術パートナーが属する国・地域に生産を近接させる「ニアショアリング」と組み合わせ、政治的リスクを最小化する立地戦略が求められます。もっとも、中国市場のように無視できない存在との取引をどう維持するか、各企業は板挟みになる場面もあるでしょう。フレンドショアリングを進めつつも、地域ブロック間の緊張が激化しすぎないよう外交的なバランス感覚も重要です。グローバル企業は、地政学リスクの高まりを前提に、拠点配置の再最適化を継続的に検討していく必要があります。 <在庫戦略の見直し(「Just in Case」への転換)> かつては効率最優先の「ジャスト・イン・タイム(JIT)」生産で在庫を絞り込むことが合理的とされました。しかし昨今のパンデミックや貿易戦争で露呈したのは、過度なリーン体制の脆弱さです。今、製造業を中心に戦略的な在庫積み増し、いわゆる「ジャスト・イン・ケース(JIC)」への転換が進みつつあります。半導体不足に苦しんだ自動車メーカー各社は教訓を活かし、重要部品について従来より長めの在庫を保有する方針を打ち出しました。実際、2022〜2023年にかけて日米企業の在庫水準は上昇傾向にあり、「多少のコスト増や保管リスクを抱えてでも安定供給を重視する」姿勢が強まっています。在庫を単なる非生産的コストではなくリスク緩衝材と位置づけ、適正在庫量を再定義する動きです。例えば、電子部品メーカーは特に不足しがちなチップや原材料を数ヶ月分先行確保し、需給逼迫時に顧客への納入を止めないよう備蓄を増やしています。また前述のアップルや任天堂のように、地政学イベントが見えた段階で一気に製品を前倒し出荷して在庫を積む機動的な在庫運用も求められます。これには需給予測の高度化や物流体制の強化も不可欠です。リスクシナリオを複数描き、「このパーツが〇〇から入らなくなったら在庫で△ヶ月耐える」「需要急増時にすぐ放出できるよう倉庫網を分散配置する」といった綿密な計画が競争力の鍵となります。過剰在庫と欠品リスクのトレードオフを最適化することこそ、現代のサプライチェーンマネジメントの重要テーマと言えるでしょう。 規制モニタリングと柔軟なコンプライアンス <規制モニタリングと柔軟なコンプライアンス> 最後に、企業は各国政府の政策動向をこれまで以上に注視し、迅速に対応する体制を整えねばなりません。関税率ひとつとっても、政権交代や外交交渉で目まぐるしく変更されます。輸出入規制や制裁リストも然りで、今日のパートナーが明日には禁輸対象になる可能性すらあります。したがって、「規制モニタリング」は経営戦略の一部として位置づけるべきです。具体的には、各国の政府発表や通商交渉の進展を常時ウォッチし、自社ビジネスへの影響を分析する専門チーム(経済安全保障担当など)を設置する企業が増えています。また業界団体を通じてロビー活動を行い、自社が不利益を被る政策に対して情報提供や意見表明を行うことも重要です。アップルは米政権に対し自社製品(スマホなど)への関税適用除外を強く働きかけ、一部電子機器を一時的に免除リストに入れることに成功しました。このように、企業側の声が政策に反映される余地を探りつつ、最悪の事態にも備える両面作戦が必要です。コンプライアンスの面では、各国の輸出管理法や制裁リストに抵触しないようサプライヤーや顧客を精査し、場合によっては取引先の変更や製品設計の見直しを迅速に行う柔軟性が問われます。特に軍民両用技術やデュアルユース部品を扱う企業は、自社製品がどの国に最終使用されるか、細心の注意を払う必要があります。中国が導入した「反外国制裁法」により、米国の対中制裁に協力した企業が中国国内で罰せられるリスクも出ています。まさに板挟みの中での舵取りですが、国際ルールを順守しつつ事業継続を図るために、常時最新情報をアップデートし迅速に経営判断する仕組みを社内に作ることが欠かせません。 以上の三本柱(フレンドショアリング、在庫戦略、規制モニタリング)は、激動の国際ビジネス環境に挑む企業のサバイバル戦略といえます。米中ハイテク冷戦は長期化が避けられず、関税や輸出規制の応酬は今後も形を変え続くでしょう。加えて地球規模で予測不能なリスク(パンデミック、戦争、自然災害など)も潜在しています。こうした状況下で成長を持続させるには、安定性と機動性を兼ね備えた経営が求められます。グローバル化の恩恵を享受しつつも、その脆弱性に目をつむらず、変化に強い企業体質への転換を図ること——それこそが新冷戦時代を生き抜くサバイバルの極意ではないでしょうか。 米中摩擦の最新動向を教訓に、今まさに企業は次なる一手を講じるときです。大国の論理がぶつかる現在の国際情勢を注視しながら、自社のサプライチェーン・ビジネスモデルをアップデートし続ける企業だけが、激流の時代に勝ち残っていくことになるでしょう。 【参考資料】 bloomberg.co.jp https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-07-03/SYSS0NT1UM0W00 jetro.go.jp bloomberg.co.jp jetro.go.jp diamond.jp reuters.com gadget.phileweb.com ideasforgood.jp tdb.co.jp 【マンガ】ジョブズが「iPhone」を発表した日にアップル株を「100万円」買っていたら、今いくらになっていた?