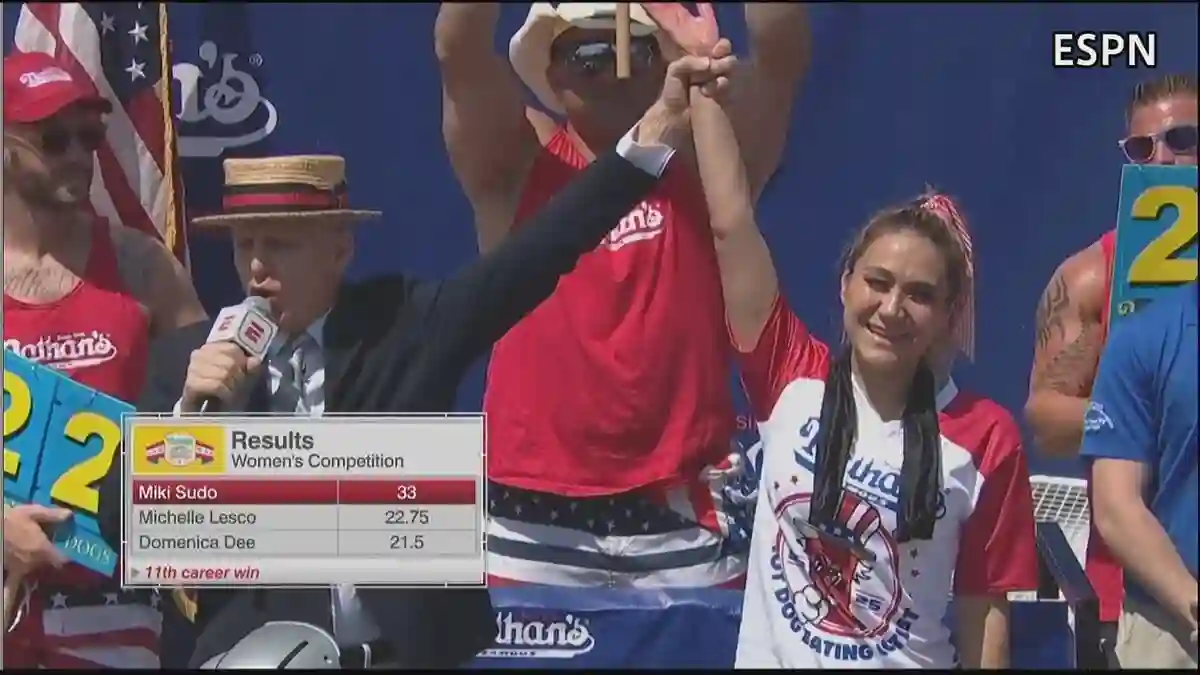立花孝志氏、石丸伸二氏、斎藤元彦氏……熱狂的な支持と多くの反発を同時に集める新時代の政治家たちを、政治の表と裏を知り尽くした2人はどう見るのか。佐藤優氏と舛添要一氏が語り合った新刊『21世紀の独裁』(祥伝社新書)から一部抜粋・再構成して紹介する。 【写真】厳しい表情の佐藤優氏と舛添要一氏 “第二官僚群”が必要だ(佐藤) 佐藤優:立花孝志さん、石丸伸二さん、斎藤元彦さん──彼らにとって今後の局面は、それぞれジェットコースターのように目まぐるしく動いていくでしょう。ただいずれにせよ、三者に共通する課題は「継続性」だと思います。急に騒がれたあと、静かになって終わるのか。それとも何らかの継続性を保てるのか。 たとえば、石丸さんが新党で何かをやっていこうとするなら、安芸高田市長時代のように議会と喧嘩してもいいですし、大多数の役人と喧嘩するのもいい。しかし、自身の手足となってくれる“第二官僚群”と呼ぶべき存在を作らなければ、思い描く政策を継続して実行することは不可能です。 官僚も人間です。そして裁量権を持っています。そこには一定の閾値、すなわち意思決定における基準点・分岐点があります。平たく言うなら、「この役人はどこでやる気を出し、能力を発揮して動くのか」。それを見きわめ、掴んでおかなければならない。舛添さんは「有権者のさまざまなディマンドに応えるには、官僚機構を動かす必要に迫られるケースがある」と言われましたが、そのためにも政治家は官僚個々人の閾値を把握し、それらが集合体になった場合にどうなるかを現実的に想定しておかなければいけないのです。 ただし、実際に省庁のなかに入ってみなければ、官僚の属性を見きわめることはできません。たとえば都庁には、ゴールドのブレスレットを身につけ、思わず「どこの筋の方(任侠団体構成員のこと)ですか?」と聞きたくなるような強面の浜渦武生副知事がいて、長く君臨していました。有象無象が巣食う都庁は、まるで伏魔殿です。伏魔殿の文法は、外から来た人にはわかりません。 ここからはシミュレーションです。石丸さんが都知事になり、そんな伏魔殿に足を踏み入れたとしましょう。その時に必要なのは、江戸幕府で諜報活動に従事した“御庭番”のような腹心を、中堅の部長・課長クラスから選抜して五人くらい置くことです。前述した第二官僚群ですね。そして密かに、都庁官僚たちの公私にわたる動向──異性関係からカネ遣いまでを仔細に調べさせる。彼ら御庭番は「ご注進、ご注進」と、調査結果を知事に耳打ちします。そうすれば、伏魔殿の景色も違って見えてくるはずです。 石丸さんは、SNS社会というバーチャル上の共同体で頭角を現してきました。しかし政治活動のコアな部分においては、数は少なくてもリアルな人間が欠かせないということです。すなわち継続性を保つうえでも、バーチャルとリアルのハイブリッド性をいかに作るかが重要なのです。 斎藤さんの話に戻ると、メディアは徒党を組んで“おねだり”や“パワハラ”疑惑を報道し、彼を叩きました。視察先の地元企業で産品を欲しがった。職員に暴言を吐いたり付箋を投げつけたりした。信用金庫への補助金を増額し、キックバックさせた。それを告発した元局長が亡くなった……。はじめは尾ひれがつく程度だったのが、背びれもついて、そのうち鵺やキメラのような怪物扱いになりました。「ここまでひどい悪人が、この世にいるのか」と思わせるに十分なバッシングの嵐です。 私は、私自身が連座した形で逮捕された鈴木宗男事件(二〇〇二年)を思い起こしました。この時、ワイドショーも新聞も週刊誌も、鈴木さんを悪徳政治家、私をその腰巾着として悪しざまに報じました。勤務先の外務省はおろか、自宅にまで記者が押しかけてきたものです。私が何を言っても、誰も聞いてくれません。私は「本当に生きていていいのだろうか」というところまで追い詰められました。その地獄のような経験から、どうしても心情的に斎藤さん、つまり叩かれる側に立つ自分がいます。 舛添さんも、同じように乱暴なメディアの嵐に潰された経験がおありですが、この点はどう思われますか。 都知事時代のバッシングの真相(舛添) 舛添要一:そうですね。私は斎藤さんを擁護する意図はありませんが、彼がボロクソに書かれているのを見て、率直なところ「俺の時も同じだったなぁ」と思いました。やれ「別荘へ行くのに公用車を使った」だの、「公費で美術品や本を購入した」だの、それは凄まじかった。既存のメディア、いわゆるオールド・メディアの残虐性を、身をもって味わいました。街を歩けば「ああ、舛添の大泥棒が歩いている」と指を差される。まるで魔女狩りです。家族がかわいそうでした。 そして「政治資金という公費を私的に流用する舛添はセコくてけしからん」などと罵られましたが、蓋を開ければ、検察が調べた結果、経理上のミスが五年間で一五〇万円でした。裏金議員にかぎらず、巨額の使途不明金が疑われても議員を続けている政治家もいるのに、世の中は不公平です。 あの当時、今のようにSNSがあれば反論できたのに、と思うこともあります。定例の知事記者会見では何時間もの“吊し上げ”が続き、私には反論の余地が与えられませんでした。いっぽう、斎藤さんは言わばSNSの力で再選され、復活しています。 私は都知事を辞職してからというもの、オールド・メディアには見向きもされず、まだ過渡期にあったSNSでネット上に細々と原稿を書き、なんとか糊口を凌いできました。そのうち、次第に、私に同情的なメディアの人も現れて、著書の刊行を勧めてくれるようになりました。おかげで、あれから九年が過ぎた今、こうして佐藤さんと対談できるわけですが(笑)。 それはそれとして、メディアを味方につけることは大切です。私が厚生労働大臣を務めていた二〇〇七年、いわゆる薬害肝炎事件に対処しました。フィブリノゲンという血液製剤を投与された人たちがC型肝炎を発症し、国や製薬会社を相手取って訴訟を起こした事件です。この時、私はメディアを厚労省側の仲間に引き入れたのです。 私は省内に調査チームを立ち上げるとともに、被害を訴える人たちに面会しました。大臣としては異例のことです。そして年内に解決できるよう、被害者を救済するべく動きました。しかし、そこに財務省と法務省の官僚が立ちはだかります。財務官僚は「国で補償金を出せるわけがないでしょう」と言うし、法務官僚は「国の沽券にかかわるから、裁判に負けるわけにいかない」。私は霞が関の官僚と対立することになってしまいました。 ところが、ここで私に援護射撃をして、味方になってくれたのがメディアです。舛添大臣は被害者に会って話を聞き、がんばっているのに、霞が関の役人はなぜ反対するのか──と。やがて、被害者救済の世論が形成されていきました。 その後、裁判所から調停案が提示されました。当時の首相は福田康夫さんです。私は事件発覚当初、福田さんに「総理、ここは腹を据えてください。私は被害者全員に会いますから」と言い、最終的には「総理の決断で、被害者を一律に救済すると発表してください。私はあとで出ていきます」と進言しました。二〇〇七年一二月二三日、福田さんは議員立法による一律救済を発表します。私がこの日付をよく覚えているのは、上皇陛下の誕生日(当時の天皇誕生日)だったからです。その日は総理も私も、午後から行なわれる皇居宮殿での祝賀行事に参列しなければなりません。そのため、皇居へ向かう前に決める必要があったわけです。最後は「今、決めなければ、内閣が潰れますよ」という感じでした。 ※佐藤優・舛添要一/共著『21世紀の独裁』(祥伝社新書)から一部抜粋・再構成 【プロフィール】 佐藤 優(さとう・まさる) 作家、元外務省主任分析官。1960年生まれ、同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。在ロシア日本国大使館書記官、国際情報局主任分析官などを経て作家活動に入る。著書に『国家の罠』(毎日出版文化賞特別賞)、『自壊する帝国』(新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞)など。 舛添要一(ますぞえ・よういち) 国際政治学者、元東京都知事。1948年生まれ、東京大学法学部政治学科卒業後、同大学法学部助手。パリ、ジュネーブ、ミュンヘンで外交史を研究。東京大学教養学部助教授を経て政界へ。厚生労働大臣、東京都知事を歴任。著書に『ヒトラーの正体』、『ムッソリーニの正体』、『現代史を知れば世界がわかる』など。