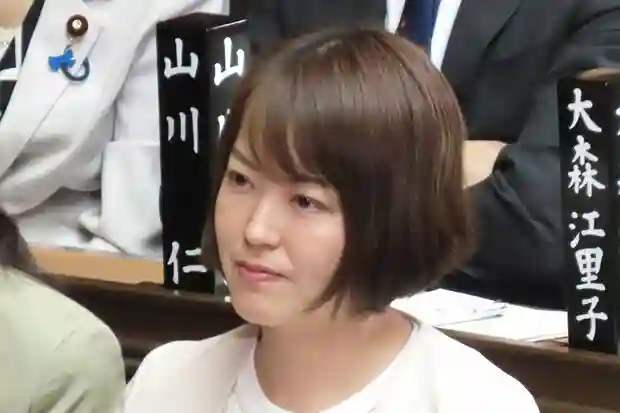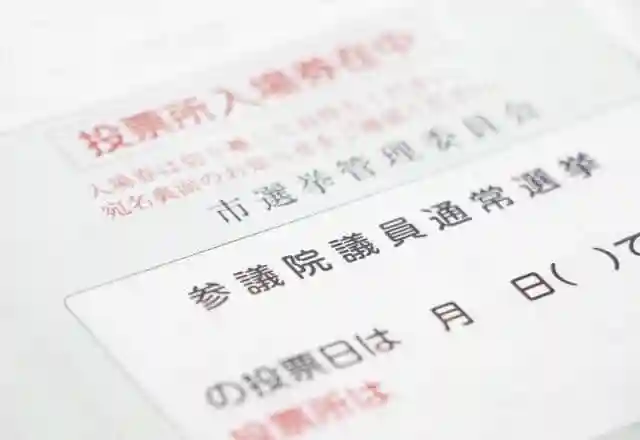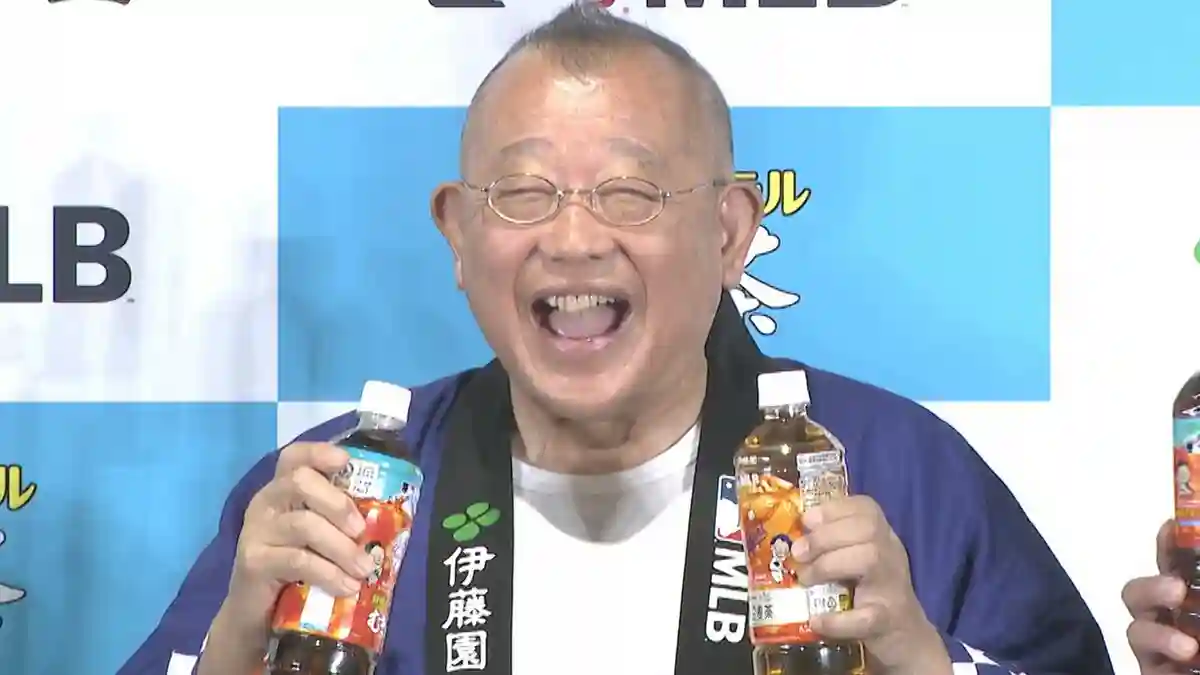病気が見つかって不安で仕方がない時、人はなんとか安心材料を探そうとするものだ。 【写真を見る】独断で判断した患者の結末 医師が「衝撃だった」と語ったワケ 特に担当医には、「絶対大丈夫」と言ってもらいたいのが人間心理というものだろう。 だが当然のこととして、病に「絶対」はない。誠実であろうとするほど、リスクも説明せざるを得ない。 「安心したい」患者と向き合う時、実際のところ医師は何を考えているのか? 長年、臨床の現場に立ってきた医師、里見清一氏は新著『患者と目を合わせない医師たち』で、患者への説明の難しさを吐露している。同書をもとに医師の本音を見てみよう(以下、同書より抜粋・再構成したものです)。 誠実であろうとするほど、リスクも説明せざるを得ない。「安心したい」患者と向き合う時、実際のところ医師は何を考えているのか? (※写真と記事本文は直接関係ありません) *** 独断で薬をやめてしまう患者 私と同じ病院で働く技師さんが、20代で癌になった。幸い、分子標的薬剤という、その癌の特徴に合わせた経口薬で病状は改善し、患者は普通の生活に戻れた。だがしばらくして脳転移が発見された。この分子標的薬剤はいずれ効果がなくなって癌は再発するが、それにしてもちょっと時期が早いなと思った。治療を続けたが病状は進行し、患者は亡くなった。亡くなる数週間前、患者から、「先生、ごめんなさい。調子が良くなった時に安心して、治ったと思い、処方された薬をやめてしまっていたんです」と告白された。 これは非常な衝撃だった。認知症の高齢者ではなく、若い、しかも医療従事者である患者がそんな判断をするとは、思いもよらなかった。私は、患者を診察して処方する度に、「今はいいが、きちんと飲まないと病気は出てくるよ」と一々念を押すべきだったのか。だがそうすると、「飲んでいてもいずれ必ず病気は再発し、あなたはこれで死ぬのだ」とも言わないと、「本当のこと」を伝えたことにはならない。 誰も書かなかった「医者の本心」と「病院の実態」。若手医師への疑念、「患者様」の無理難題……。ベテラン臨床医が明かす医療の内実 『患者と目を合わせない医師たち』 フジテレビ制作の平成版「白い巨塔」(2003年)第1回で、内科の里見医師(江口洋介)が、女性患者に早期膵癌を発見した。別の病気の経過中、所見に疑問を持ち、苦労して診断したのである。その途中では、不確かなことは言えないと、里見は患者に「しっかり調べましょう」としか説明しなかった。何度も検査され、時間もかかり、患者とその夫は不安に駆られていた。 「安全」を損ねない範囲でできるだけ患者に「安心」してもらう。そんなことが可能なのかどうか、悩みは尽きない (※写真と記事本文は直接関係ありません) やっと診断がつき、手術で切除可能と判断され、里見は友人である外科医の財前(唐沢寿明)に診察を依頼した。財前は患者と夫にあっさり「癌です」と告知し、「私が手術するから大丈夫」と保証した。患者と家族は手術に同意した。転移の可能性も皆無ではないのに、なぜ「手術で治る」と断言したのだ、無責任だと詰め寄る里見に対し、財前は「治らないかも知れないなんて言ってる医者に、自分の命を預ける患者がいるのか」と言い放つ。「患者には、絶対に大丈夫と言ってやるべきで、現にこの患者も、それによって手術を受ける勇気を持てたのだ」と。 財前の態度は、医者は患者を「正しい道」に誘導してやるべし、とする昔ながらのパターナリズム(温情的父権主義)で、現在のインフォームド・コンセントの原則からは大きく外れる。その是非はひとまず措くとして、これを題材に、私は看護大学で私のゼミをとった学生たちに質問した。これからどうすべきか? 具体的には、早期といえども膵癌では、一定の割合で再発し患者は死亡する。仮にその確率を20%としよう。現在では再発予防のための術後抗癌剤治療もある程度の効果が見込めるが、当時はなかった。つまり、再発のリスクを知っていてもいなくても、どのみち予防策はない。ここで財前は(あるいは里見は)、術前もしくは術後に、そのリスクを患者に伝えるべきか? 伝えれば、この患者と家族は、常に癌の再発に怯えることになる。何か身体に不具合があったら、すわ癌が出たかと気が気でないだろう。だが、再発してしまっても、一応の「心の準備」はできている。一方で、伝えなければ、80%の確率で患者と家族は「安心」したままハッピーでいられる。ただ再発したら仰天して「話が違う」と、財前や里見を呪い、嘆き悲しむだろう。どちらが正しいと断定は難しく、学生たちの見解も分かれたが、読者の多くは「知らない方がいい」とお考えではなかろうか。むろん現在では、ネットその他から、「知ってしまう」場合も多かろうが。 「安心」か「安全」か 結局、患者に「安心」させていいのだろうか。 先に落とし所を書くと、自分で気をつけなければいけないこと(きちんと薬を飲むなど)がある場合にはリスクを説明し、油断しないようにさせる、だが「起こったらどうしようもなく、それを防げない」場合は安心させる、ということになろうが、話はそう単純ではない。「ごく小さいリスク」の場合はどうか。1%の危険を「仕方がない」と割り切って恬淡としていられる人は少ない。財前が指摘するように、人は「絶対大丈夫」と言ってもらいたいのである。 だが現在の医療は、むしろ里見的に「誠実」であるために、そんな希望には添えない。病院で大きな検査を受けた方は経験されていると思うが、必ず同意書にサインをさせられ、それはいいが説明文書にはありとあらゆる「ヤバい事態」の可能性がこれでもかとばかりに書かれている。私の知る弁護士先生は「あんなの、全部言い訳でしょ?」とおっしゃっていた。 もう一つ付け加えれば、「たぶん大丈夫」だが「念のため」に検査しておく、ということを我々はよくやるし、患者も「安心のため」にそれを望む。だが、コストは別にしても、検査に伴う合併症によりかえって「安全」を損ねるリスクもある。それはCTでの被曝のように、その場ではわからないことも含まれる。 かつて小池都知事が「安全と安心は違う」と言ったのは、その意図はともかく、事実として正しい。しかし行政官は人々の「安全」を守るのが仕事であって、「安心」させるために無駄なコストをかけたり、ましてや「安全」を損ねたりすべきではない。では医者はどうなのか。ハーバード大学の調査によると、進行癌患者の多くは、自分の病態を楽観的に誤解して、「治る」と考えているそうだ。そして、そう誤解している患者の方が、医療者との関係は良いという。「安全」を損ねない範囲でできるだけ患者に「安心」してもらう。そんなことが可能なのかどうか、悩みは尽きない。 デイリー新潮編集部