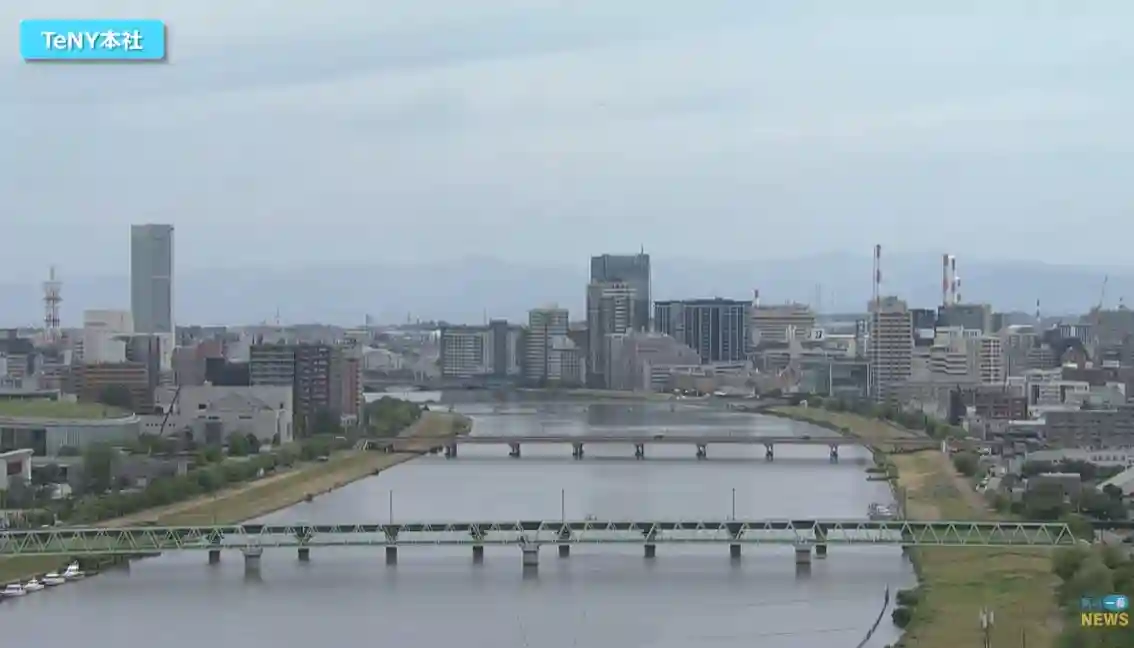来たる6月19日… 名著『基準値のからくり』の待望の続編 『世界は基準値でできている 未知のリスクにどう向き合うか』 が刊行されます!! 今回は発売を記念して、前作にあたる 『基準値のからくり』の一部を抜粋してお届けします! *本記事は、『基準値のからくり』(ブルーバックス、2014年刊行)を再構成・再編集してお送りします。 なぜ「お酒は20歳から」に決まったのか? 基準値が定められたプロセスには、じつに意外なもの、興味深いものが多く、その根拠を知ると、驚かされることがしばしばである。たとえば日本では、20歳未満の飲酒は未成年者飲酒禁止法で禁じられているが、なぜ「20歳」という数字に決まったか、みなさんはご存じだろうか。 国税庁のウェブサイトなどには、20歳未満の飲酒は脳の機能を低下させる、臓器に障害を起こしやすい、性ホルモンに異常を起こしやすい、アルコール依存症になりやすい、といった理由が挙げられている。しかしこの説明では、なぜ18歳でも19歳でも21歳でもなく20歳なのか、という疑問は解消されない。なぜ20歳なのだろうか? その理由は、1947年の青少年禁酒法案に関する参議院会議録に見ることができる。飲酒禁止を25歳未満にまで引き上げるべきだという発案に対し、当時の政府委員はこう答弁している。 「年齢満二十歳以上の者は民法上も完全な能力者であり、公法上は選挙権を有し、国政に参与いたしておる者でありまして……」 つまり、20歳になれば自己責任がとれるなど、法律の面で自立する「成年」となるから、というわけである。すると、新たな疑問が湧いてくる。なぜ成年は20歳と定められたのだろう? その根拠は、1876年(明治9年)の太政官布告にまでさかのぼる。当時、欧米諸国が21〜25歳程度を成年年齢と定めていたのに対し、それらの国の文明・制度に学んでいた日本は、より若い年齢を成年とした。 その理由が面白い。欧米人と比べ、日本人が「精神的に成熟している」ことと、「平均寿命が短い」ことから、20歳が成年年齢として採用されたのである。 飲酒禁止が20歳未満となったのは、この数字が脈々と使われているからであった。しかし、いまの日本人が欧米人よりも精神的に成熟しているといわれれば首をかしげたくなるし、日本が世界に名だたる長寿国であることを考えれば、なんとも奇妙な気分になる。 基準値によくある四つの特徴 基準値には、食品、環境、事故など分野は違えども、共通に見られる四つの特徴がある。本編に入る前に、飲酒禁止における「20歳」という基準値を例にとり、それらを見てみよう。 基準値の特徴1:従来型の科学だけでは決められない 読者のみなさんは、基準値とはきわめて科学的な方法で客観的に定められたもの、と思われているかもしれない。飲酒できる年齢(成年)を20歳と定めたこの例は、そうではない特殊なケースなのだろうとも思われたかもしれない。 たしかに基準値には、疫学データや動物実験、あるいは工学的実験などの科学的な知見や手法にもとづいて定められたものがたくさんある。 しかし、そうした基準値にも、じつは主観的な推定と仮定の要素がきわめて大きく関与している。いわゆる従来型の科学だけでは、基準値を決めることはできないのだ。 これは、基準値が必ずしもゼロリスクを保証するものではなく、ある程度の大きさのリスクを受け入れている場合が多いためである。 むしろ、万人にとってリスクがゼロであることを約束するような基準値はほとんどないといっていい。基準値を決めるには、どの程度の大きさのリスクを受け入れるかを定めなければいけないのである。 このような予測・評価・判断をともなう科学を、従来型の科学とは区別して「レギュラトリーサイエンス」と呼ぶ。「レギュラトリー」は日本語では「規制」といった意味にとられがちだが、ここには「調整」というニュアンスも含む。 レギュラトリーサイエンスは従来型の科学で得られたデータや知見と、政治や行政による規制・調整・政策判断などとの間にある大きなギャップを埋める「橋渡し」の役割をする科学といえよう。 基準値の特徴2:数字を使いまわしてしまう 「成年は20歳」と定めたときに欧米諸国の成年年齢を参考にしたように、関連する基準値や、他国の基準値をベースにして基準値を定める場合は多い。 その際、もとの基準値がどのように算定されたかを十分に考慮せず、なんとなく数字を使いまわしてしまうということがよくある。 米国の疫学者であり衛生工学者のウィリアム・セジウィック氏(1855〜1921)の言葉に、このようなものがある。 「基準というものは、考えるという行為を遠ざけさせてしまう格好の道具である」 基準値はいったん定められると、あたかもある種の「権威」のようになり、その根拠を深く考えることなく使ってしまいがちである、という戒めである。 ある基準値を使いまわして決められた基準値は、ときに十分な安全を確保しているとはいいがたかったり、まったく理屈に合っていなかったりする。当初の目的とはかけ離れた、ちぐはぐなものになってしまうのである。 基準値の特徴3:一度決まるとなかなか変更されない この特徴は日本特有のものかもしれない。飲酒できる年齢を25歳まで引き上げようという青少年禁酒法案が廃案になったように、基準値の多くは、一度決まるとなかなか変更されない。基準値を厳しくする場合もそうだが、基準値を緩くする(緩和する)場合はなおさらである。 米国では、大気中の主要な汚染物質の環境基準値は5年ごとに見直すことが義務づけられているために、科学の進展に応じてこれまで何度も改定されてきた。ところが日本では、科学的判断を加えて定期的に改定するという手続きそのものが、あまり制度化されていない。これは、基準値の成り立ちや意味づけが国民に広く知られていないことにも一因があるだろう。 基準値の特徴4:法的な意味はさまざまである じつは基準値には、その性格によって「規制値」「指針値」「目標値」など、さまざまな呼称がある。本書では基本的に、それらをひっくるめて「基準値」と呼んでいるが、これは少々乱暴な言い方である。 たとえば飲酒の20歳や、水道水の水質基準値のように、すべて守られることが法律によって前提となっている基準値もあれば、環境基準値のように、超過しても罰則がない基準値もある。 法的拘束力のない基準値には、目標値としての基準値、努力義務としての基準値があり、法的拘束力がある基準値にも、罰則がない基準値もあれば、罰則がある基準値もある。 さまざまな基準値の法的な意味も各章で紹介しているので、数字だけでなく、その運用方法も意識しながら読んでいただきたい。 基準値と「受け入れられないリスク」の関係 「受け入れられないリスク」とはどのように決められてきたのだろうか。 基準値の特徴1(従来型の科学だけでは決められない)の通り、「受け入れられないリスク」は時代や社会、文化的慣習のなかで育まれるものであり、自然現象を物理学で解き明かすようには決められない。 米国や英国では、1970〜1980年代頃から「受け入れられないリスク」についての研究や社会調査・議論が熱心になされてきた。 たとえば米国では、食品中の発がん性物質がどの程度までなら安全と見なすかについて論争が巻き起こり、何度も裁判が繰り返されるうちに、一つの化学物質について発がんリスクとして受け入れられるレベルは、生涯でがんが生じる割合が「1万人に1人」から「100万人に1人」くらいという範囲に落ちついた。 このとき裁判所は国に対して、労働者が受け入れられるリスクの基準も定めるよう要請した。また、英国では、1983年に英国学士院が、個人および管理者にとって一般的に受け入れられないリスクの大きさを調査した報告書を提出した。この調査結果は放射線被曝についての基準値を定める際にも参考にされた。 これらに対し、残念ながら日本では、ベンゼンの大気環境基準値制定の際に多少話題になった程度で、「受け入れられないリスクの水準はどれくらいか」という議論はほとんどなされていない。 日本が軽視する不安 基準値設定に関する委員会においては、有識者が提案した受け入れられないリスクをもとに決められることもないわけではないが、たいていの場合、海外で使われている数字をそのまま輸入している。まさに特徴2(数字を使いまわしてしまう)の通りである。 しかも多くの場合、特徴3(一度決まるとなかなか変更されない)が発動し、長い間、その数字が使われつづけてしまう。そこで重要になってくるのが、基準値の運用である。 私たちはつい基準値の数字にばかり注意が向いてしまうが、厳しい数字でも運用がきわめて緩い場合と、緩い数字でも運用が厳格な場合とでは、どちらが規制として厳しいだろうか。つまり、特徴4(法的な意味はさまざまである)をよく認識する必要があるのだ。 心理学者ながらノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏は著書『ファスト&スロー』の中で、こう述べている。 「合理的であれ、不合理であれ、不安は苦痛をもたらし活力を失わせる。だから政策立案者は、市民を現実の危険から守るだけでなく、不安からも守るべく努力しなければならない」 安全管理においては、専門的な知見と、市民の感情の両方を組み合わせることが重要である。 「受け入れられないリスク」についての議論が不十分なまま、専門的知見に支えられた基準値以下だから安全だ、と説明するだけでは市民の感情・直観を満足させることはできない。 いまの日本には「安全と安心は違う」という考え方が広がっていて、科学技術政策や事業に「安全・安心」と銘打つことが一種のトレンドと化している感があるが、安全にはそもそも社会的・文化的・心理的要素が含まれることをないがしろにしてはいけない。 基準値と私たちがめざす社会の関係 基準値とは私たちが社会で安心して暮らしていくためのセーフティネットの無数の束である。 しかし、それは厳しければ厳しいほどよいという単純なものではない。私たちが求めている社会は、単にリスクが小さいだけの社会ではないはずだ。文化的で豊かな暮らしを支えてくれる社会、そこに生きていることに幸せや誇りを感じられる社会、子や孫など次の世代まで継承したいと思える社会のはずである。 1990年代末の遺伝子組み換え作物論争に関する英国政府の報告書には、こうある。 「この論争は安全性に関するものなどではない。どのような世界に生きたいかという、はるかに大きな問題に関するものだ」 安全やリスクをどのように管理すべきか、という問いは、つきつめれば、どのような環境や暮らしを求めているのか、という価値観の問題になる。さまざまな価値観をどのように、どこまで安全管理に反映させるのか。 私たちはどのような世界をめざしているのか。そのような問いを私たちに突きつけたのが、第一原発の事故だったのではないだろうか。基準値設定において前提となる「受け入れられないリスク」には、本来そこまでの考えが求められるはずだ。 これから紹介していく、さまざまな基準値の根拠や算定プロセスを見ていきながら、私たちがめざす社会とはどのようなものなのか、いま一度、想像してみてほしい。 【第二回記事】なんと「消費期限切れ」でも「日本人」は食べている…知らなきゃ損する食品基準の裏側!