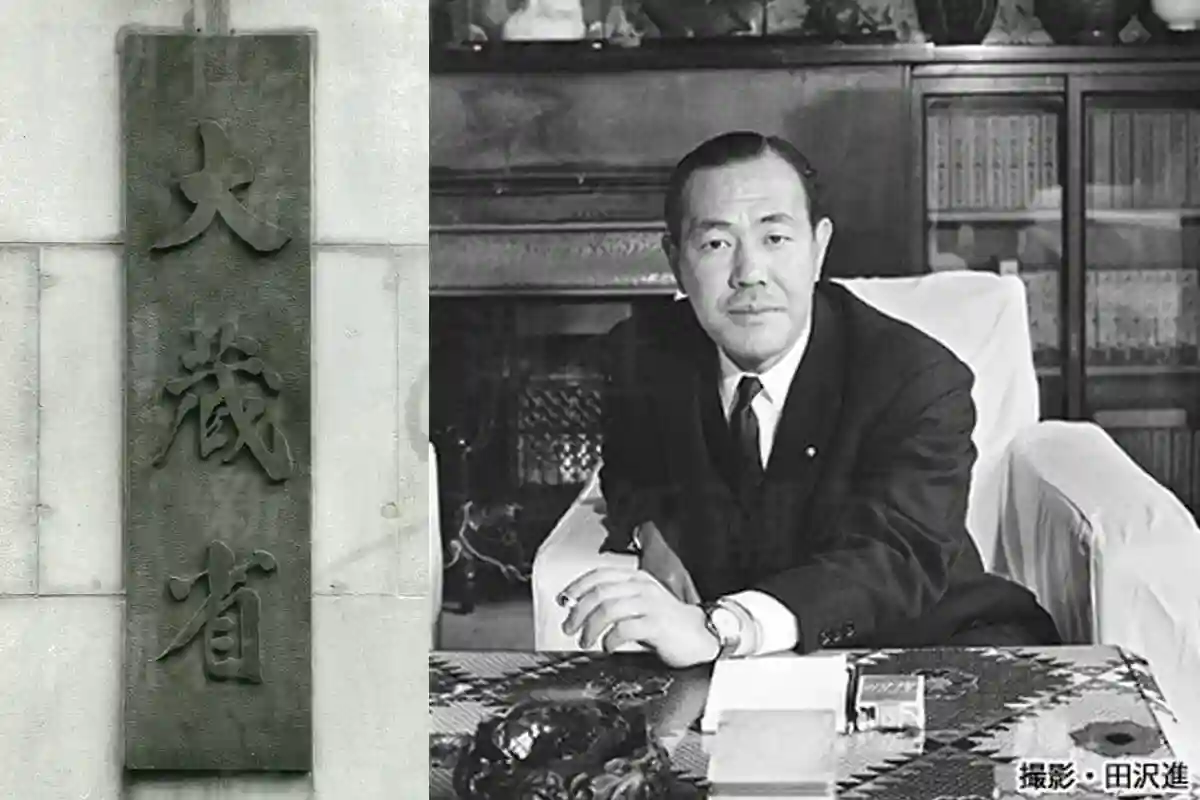19世紀、石炭産業と金属精錬産業から、それまでにない、鮮烈な色彩の絵具が次々に誕生した。そして金属加工産業の発展は、それを詰める金属製のチューブをもたらした。若い画家たちは、それを持ちだして戸外で製作をし、移ろう光、水、空気を輝く色彩で描き、絵画の世界に印象派革命をもたらした。 印象派は蒸気機関車や駅など産業革命を題材にしたことでも知られているが、じつは印象派自体が産業革命の申し子であった。これは産業史と美術史の綾なす物語である。 絵具の値段はなぜ下がったのか 蒸気機関の轟音が鳴り響き、街路を黒い煤が覆った十九世紀。石炭の炎は鉄道と工場だけでなく、画家のパレットにも火を灯した。 セーヌ河畔でクロード・モネが夜明けの光を追いかけたとき、彼の手元にあったのは伝統的な天然素材の絵具ではなく、化学工業と金属精錬業が産んだ虹色の粉を詰めた、錫製のチューブだった。 十八世紀末、イギリスの石炭採掘量は年間1億トンに満たず、燃料や暖房を賄う程度だった。だが1900年には11億トンを突破し、製鉄所や蒸気船では昼夜を問わず石炭がくべられるようになった。 その炉の下に溜まる黒いコールタールは長らく厄介者だったが、化学者たちは、やがてこれを宝の山へと変えてしまう。すなわち蒸留し、抽出した成分を加熱し、化学反応を施すと、それまで見たこともないような、鮮烈な色素が次から次へと姿を現した。 1856年、まだ18歳のウィリアム・パーキンは石炭タールから合成染料「モーブ」を生み出す。薄くグレーがかかった紫色は、モネが晩年の睡蓮の連作で多用することになる。 1868年、ドイツの名門化学メーカーBASFは、石炭タール由来のアントラセンから、深紅のアリザリンを合成した。これは、それまで使われていた天然素材である茜の顔料を時代遅れにしてしまった。 黒い液体から取り出された虹色の粉は、次々に瓶詰めされ、画材商の棚を埋め尽くした。一つも絵が売れない貧しい画家でも、鮮やかな赤紫や群青を手に入れられるようになった。大量に工業生産されるようにつれ、絵具の値段はかつての天然素材に比べて10分の1やそれ以下になった。 石炭化学産業だけでなく、金属精錬産業からも、色彩革命がもたらされた。鉛とクロムを結びつけたクロムイエローは眩しい太陽をキャンバスに呼び込んだ。ザクセン鉱山で採掘されたコバルトは、コバルトブルーとなり、天然顔料であったラピスラズリの独占状態を破壊してしまった。 亜鉛精錬所の煙から分離されたカドミウムは、カドミウムイエローに姿を変え、のちにゴッホの「ひまわり」を黄金色に染めた。銅とヒ素の副産物はエメラルドグリーンとなり、ドガの踊り子の衣裳に冷たい光を投げかけることとなった。 戸外でも絵が描けるようになった しかしこの宝の粉も、絵具が乾いて固まってしまえば使えなくなってしまう。ターナーが使っていた油絵具は、豚の膀胱袋かガラス瓶入りで、開封すればすぐ皮膜を張った。このため、長時間にわたって戸外に出かけ、絵画を製作するには不便であった。戸外では写生かスケッチ程度に留め、あとで記憶を頼りに屋内のアトリエで本格的な絵画制作をするのが普通だった。 しかし1841年、アメリカ人画家ジョン・ゴフ・ランドは折り畳み式錫チューブを発明する(下図)。 薄いブリキ板を丸めてはんだで封じ、ねじ蓋を付けたチューブは、絞るたびに潰れて、絵具は全く外気に触れることがない。蒸気圧延機で量産された薄板、錫はんだ、旋盤で削られる真鍮キャップ--当時の金属加工産業はすでに成熟しており、ランドのアイデアをただちに商品化し、量産まですることができた。 若い画家たちは戸外に出て製作するようになった。銀色のチューブをポケットに忍ばせたモネは1870年、ノルマンディーの浜辺で「トルーヴィルの浜辺」を描く。ウルトラマリンの波、クロムイエローの砂、ビリジャンを帯びた潮風がキャンバスを埋めた。彼は続く連作でセルリアンブルーやカドミウムイエローを重ね、雪景色「ラヴァクール」では白銀の中にカドミウムの残光を灯す。 名高い「睡蓮」の連作ではコバルトバイオレットとビリジャンが水面に浮かぶ光となった。速い筆触を可能にしたのは、つねにベストの状態で絵具を提供するチューブだった。ルノワールは「チューブがなければモネもシスレーも存在しなかった」と語ったと伝えられている。 金属チューブが、まったく実用的な動機ではなく、肖像画家ランドの創意で発明されたというのは驚きだ。だがやがて、それはおおいに実用的な目的に転用されることになる。米国の歯科医ワシントン・シェフィールドはチューブに歯磨き粉を詰めた。1896年にはコルゲート社が帯状ペーストを発売した。医薬軟膏や化粧クリームもチューブ入りとなり、20世紀半ばには年10億本を超える金属チューブが世界を巡った。印象派革命を起こしたチューブは、人々の暮らしも一変させたのである。 ただしチューブは完成した絵の永遠を保証するものではない。クロムイエローは数十年で褐変し、エメラルドグリーンは硫化して暗緑に沈んでしまう。それでも画家にとって大切なのは制作の瞬間の鮮度だった。チューブは「描く前」の絵具の酸化を防ぎ、石炭産業と金属精錬産業が生んだ顔料によって「描く最中」の色の範囲を飛躍的に広げた。工場からキャンバスへ向かう色の奔流は、印象派が放つ眩しさの源泉だった。 「隣接可能性」があったから 蒸気機関と石炭の煙は灰色の時代を連想させるが、その灰の中から掘り出された虹色は、今日も美術館で輝く。産業革命が生んだ石炭炉の熱、無数の化学反応塔と配管、そして折り畳みチューブのねじ蓋を介して、光はかつてない自由を手にした。石炭の黒い炎が色彩の革命を育んだ証は、モネの《印象・日の出》が今なお放つ眩いオレンジと藍に刻まれ続けている。 それ以前の時代、画家にとって絵具づくりは重労働だった。鉱石を乳鉢ですり潰し、亜麻仁油と練り合わせ、膀胱に詰めて口を縛る。気温や湿度で硬さが変わり、再利用も難しい。フェルメールが青を節約し、ミケランジェロが青を買えずに下絵を残した逸話は、色を支配した経済の冷たさを物語る。化学顔料とチューブの登場は、絵具についての不安を過去のものとして、芸術家たちに時間と場所の自由を与えた。 新顔料は光学的にも昔ながらの天然顔料より優れていた。合成されたウルトラマリンは室内の弱い光でも沈まず、ビリジャンは銅緑より澄んでいた。印象派の絵から黒が消え、影が青や紫で描かれるようになったのも、この顔料革命なくしてはなかったことだろう。 ランドが特許を取る前年に、ロンドンではガラスのシリンダー入りの絵具が試験販売されたが、重く割れやすかったため、普及には至らなかった。ランドが発明した錫のチューブは軽く、現場で使い切る分だけ出せるので、モネのルーアン大聖堂の連作のように、刻々変わる光を追う制作法も可能にした。 モネは同じ大聖堂を、同じアングルから、天気の違いや朝昼晩の光の違いで描き分け、大気の動きを積層するように絵具を置いていった。そこでは、チューブのキャップを開ける音が何度も響いたはずだ。 最後に少しだけ、イノベーション研究者としてのコメントをしよう。テクノロジーの変化が生活様式を一変させることはよくあるが、本件は、生活様式ではなく芸術様式を一変させたところが新鮮で面白い。 またランドのアイデアが実現したのは金属加工産業が成熟していたからだが、このように周辺技術が一通り整った状態になっていることは「隣接可能性」と呼ばれている。 この隣接可能性があったので、ランドが絵画用に発明しなくても、錫のチューブ自体は誰かが何かの目的で発明したとことは想像に難くない。 浜岡原発ツアーに行ってみた研究者の記…田沼意次は稼働停止の「理由」をどう見るだろうか