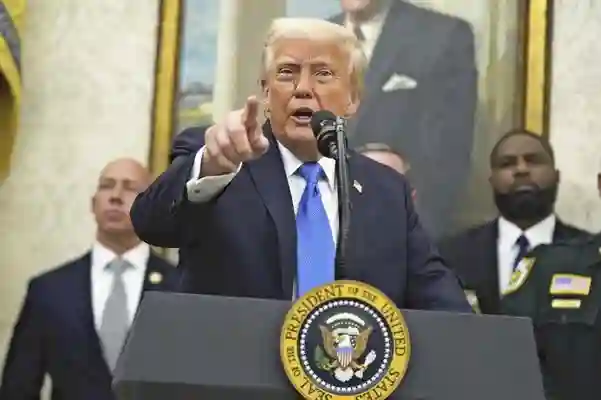効果は単なる「フェンス距離」だけに留まらない? 5月11日に『今年も打てない!中日の“極貧打線” 球団関係者が嘆く「監督交代」だけでは解消できない「根深い問題」』というタイトルで、中日の得点力不足の原因について紹介した。5月18日の巨人戦は4発のホームランを放ち勝利したほか、22日のDeNA戦は、伏兵・田中幹也の勝ち越し弾で競り勝つなど、最近は少し上向きつつあった。しかし、23日には、大卒2年目のDeNA・石田裕太郎にわずか1安打で完封勝利を許すなど、開幕から40試合以上が経過しても、得点力不足は解消できていない。【西尾典文/野球ライター】 *** 【写真を見る】中日ファンの「大御所芸能人」と2ショットにおさまるブライト健太選手 そんな中日の長打力、得点力アップの切り札としてファンからの期待が大きいのが、来シーズンから本拠地であるバンテリンドームナゴヤに設置されるホームランウイング(仮称)だ。 期待されならが今季ホームラン0で打率も冴えない石川昂弥選手 左中間と右中間の部分を狭めて、新たに座席を設置し、ホームからフェンスまでの距離は6メートルも縮まると言われている。また、フェンスの高さは、現在の4.8メートルから3.6メートルに下げられ、これまでその高さに阻まれていた打球がホームランになるケースも増えることは間違いない。 中日の球団関係者も、ホームランウイングの効果についてこう話す。 「左中間と右中間の広さはもちろんですが、フェンスの高さが下がることは大きいと思いますね。これまでも他の球場であれば、ホームランという当たりが高いフェンスに阻まれたということは多かったです。それによって『バッターがバンテリンドームでホームランは狙えない』という気持ちになり、どうしても打撃が小さくなってしまっていた部分もあったように見えました。これをきっかけに本来。“飛ばす力”はありながら、くすぶっている石川昂弥、ブライト健太、鵜飼航丞らにチャンスが増えるはずで、彼らの意識も変わることは期待できると思います」 少年野球などでも、選手の力に合わせたフェンスを設置してやるだけで、それを越えようという意識が働き、長打力向上に繋がることがあるという。プロ野球だけに、そこまで単純なことではないかもしれないが、これまでフェンス直撃にとどまっていた打球がオーバーフェンスするケースが増えれば、打者の意識が変わることは十分に期待できる。 ソフトバンク、ロッテは本拠地の改修でホームラン量産 このように本拠地を狭くする施策はこれが初めてではない。2015年にはソフトバンクの本拠地であるヤフオクドーム(現・PayPayドーム)が「ホームランテラス」、2019年にはロットの本拠地であるZOZOマリンスタジアムが「ホームランラグーン」という名称で、同様の施策を行っている。 果たして、その影響はどの程度あったのだろうか。ホームランテラス、ホームランラグーン設置の前後3年のソフトバンク、ロッテの打撃成績を並べてみると以下のようになっている。 <ソフトバンク> 2012年:打率.252 70本塁打 452得点 2013年:打率.274 125本塁打 660得点 2014年:打率.280 95本塁打 607得点 ・ホームランテラス設置後 2015年:打率.267 141本塁打 651得点 2016年:打率.261 114本塁打 637得点 2017年:打率.259 164本塁打 638得点 <ロッテ> 2016年:打率.256 80本塁打 583得点 2017年:打率.233 95本塁打 479得点 2018年:打率.247 78本塁打 534得点 ・ホームランラグーン設置後> 2019年:打率.249 158本塁打 642得点 2020年:打率.235 90本塁打 461得点(※コロナ禍で23試合減少) 2021年:打率.239 126本塁打 584得点 こうして見るとソフトバンク、ロッテとも本拠地を狭くしたことでたしかにホームランが増えている。 とりわけ、2019年のロッテが顕著で、前年の倍以上のホームラン数となっている。ここまで劇的ではなくても、中日打線のホームラン数増加は十分に期待して良いのではないだろうか。 とはいえ、新戦力の補強は必須か ただ、細かく見ていくと、本拠地が狭くなった以外の要素が大きいこともよく分かる。2019年のロッテは、前年まで日本ハムでプレーしていたレアードが加入し、チームトップとなる32本塁打を記録した。これに加えて、新外国人のマーティンも14本塁打を放った。 ソフトバンクも2017年にロッテからデスパイネが移籍し、いきなり35本塁打を放つ活躍を見せた。狭くなった本拠地の利点を最大化させる補強を実行することで、さらなる得点力のアップに成功したといえるだろう。 中日の長打力不足が課題と言われているのは、決してここ数年のことだけではない。それにもかかわらず、それを解消できないのは有効な補強ができていないからだ。 近年では、巨人から中田翔を獲得したが、高額年俸(推定年俸3億円)に見合うだけの働きを見せることは全くできていない。守り勝つイメージの強かった落合博満監督時代も、ウッズや和田一浩、ブランコといった長距離砲を獲得していなければ、黄金期は築くことはできなかったかもしれない。 ホームランウイングの設置は、大きな前進かもしれないが、それだけで勝てるほど簡単な話ではないはずだ。過去のソフトバンク、ロッテの事例を見ても、これを機に補強戦略を今一度、見直すことは必要不可欠と言えそうだ。 西尾典文(にしお・のりふみ) 野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所(PABBlab)」主任研究員。 デイリー新潮編集部