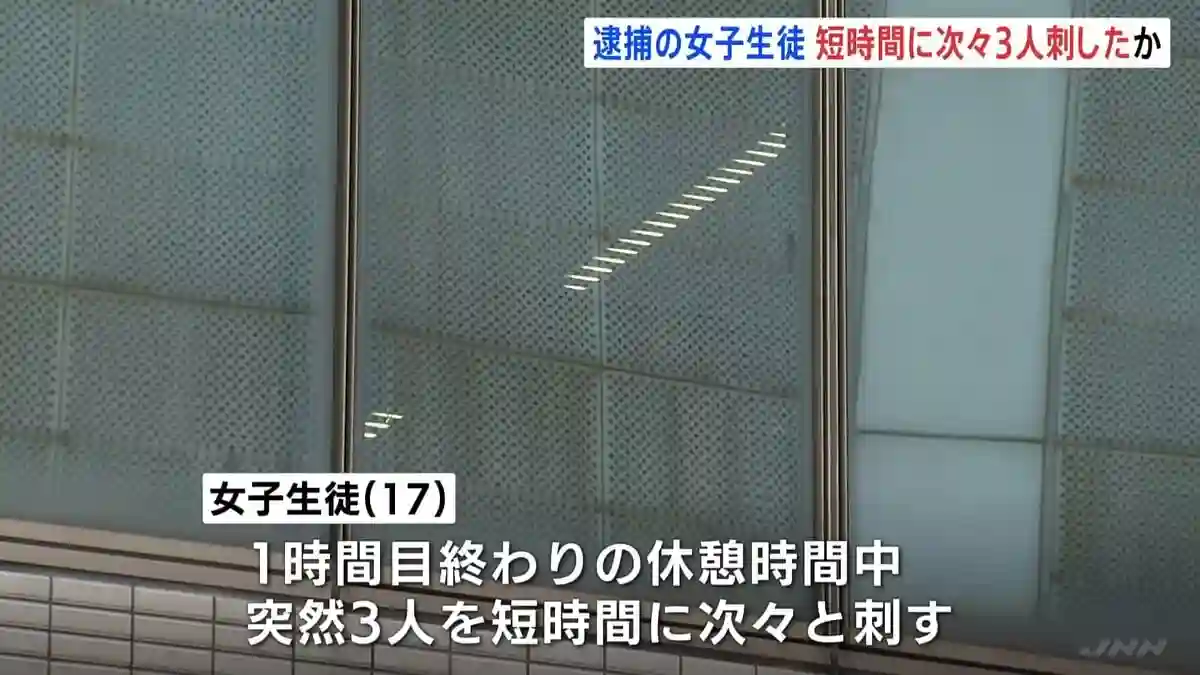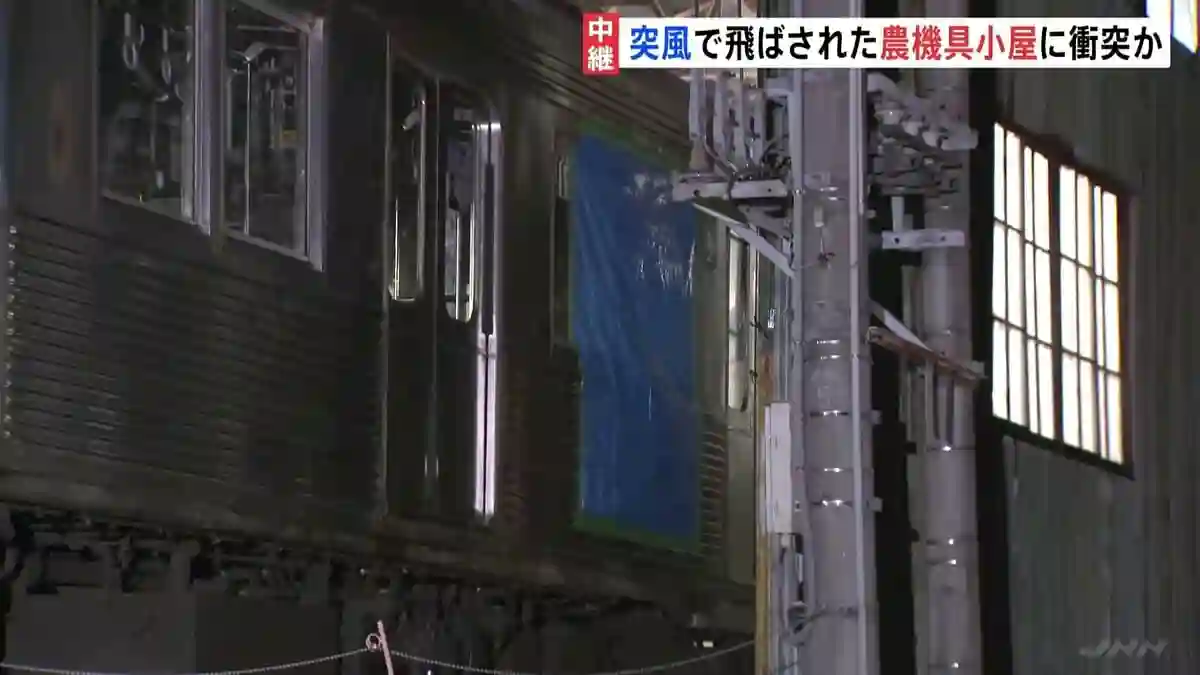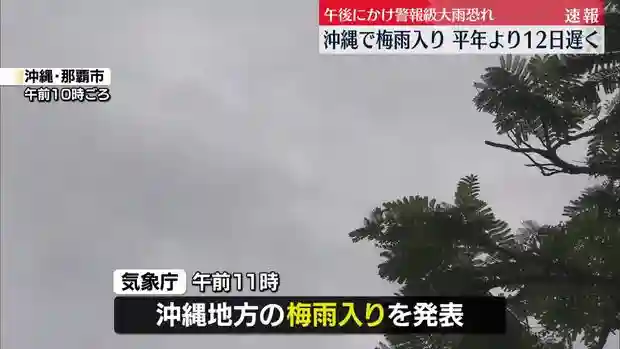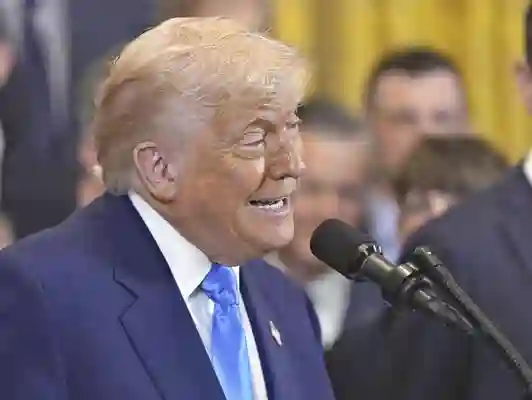日本人は移動しなくなったのか? なぜ「移動格差」が生まれているのか? 注目の新刊『移動と階級』著者で国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師の伊藤将人氏が『移動と階級』に関連するテーマ・論点を掘り下げていく。 全国で深刻化する水道インフラの老朽化 昨今、水道インフラの老朽化に伴う問題が後を絶たない。1月に起きた埼玉県八潮市の道路陥没事故をはじめ、2月には大阪府堺市で、4月5月にも京都市中心部や大阪府城東区での水道管破裂と道路冠水など連日、報道されている。 背景にあるのは、上下水道の老朽化という深刻な問題である。水は、水道管を移動して各所に運ばれていくが、この水道管は総延長74万km、地球18周分の長さに達する。途方もない距離の水道管を設置し、これまで維持し続けてきたことが驚きであり、管理にあたってきた方々には感謝しかない。しかし今、人口減少や少子高齢化による人手不足、地方自治体で厳しさを増す財政状況を背景に、維持管理のリスクが高まっているというわけである。 加えて言うと、水道事業は、基本的に各市町村の独立採算制のため、地域間の格差が大きい。つまり、「水の移動」をめぐり、私たちは住む場所によって格差が生じているのである。 なお、こうした問題は水道に留まらない。車や電車の移動を支える橋やトンネルをはじめ、高度経済成長期以降に整備されたさまざまなインフラが老朽化に伴う危機に直面している。私たちの暮らしを成立させるさまざまな「移動」を支える社会システムが、いま危機に瀕しているのだ。 市民が自ら水道料金の値上げを選択した事例も 人やモノ、情報、水、電気などのモビリティを支えるインフラをめぐるリスクが高まる中で、求められるのは「危機と向き合い、民主的に移動のあり方を決定していく」ことである。 インフラの維持管理は、どうしても多額の費用がかかる。そうした費用の多くは税金によって賄われているが、市民の理解がない状態で費用を上げることは難しい。無理やりあげた場合には、インフラは維持できるかもしれないが、市民との信頼関係は壊れてしまうだろう。インフラを維持できても、移動をめぐる公正さ(モビリティ・ジャスティス)という観点で問題がある場合、中長期的には持続可能とは言えないのである。 そこで私たちが学ぶべきなのが、岩手県矢巾町(やはばちょう)の事例だ。矢場町は、2008年から現在まで「矢巾町水道サポーター」という住民参加型の取り組みを行っている。公共の財産である水道を守るために、住民と事業者、行政が連携して一緒に学び、考え、水道のあり方を決定していくことが目的だ。 定期的に開催されるワークショップでは、水道水について学んだり、実際に浄水場を見学したりといった取り組みを行っている。このように、日々の「水の移動」を支える社会システムと制度を自分の目で見て、危機の構造を知ることで、当事者意識を高めてもらっている。 さらに、2016年には、「将来世代」の視点を取り入れたワークショップを行った。今後、水道が老朽化していくとどんな問題が起こるのか、更新サイクルはどの程度が適切なのか、費用はどのぐらいかかるのか。 実態について正しく知ったうえで議論を行った結果、町は専門家の意見も踏まえ、ワークショップで一つの班が提案した「70年サイクルで水道管を更新するために、料金を6%引き上げる」という案に沿った計画を決定、計画通り値上げに踏み切ったのである。つまり、市民が自ら水道料金の値上げを選択したのだ。 未来人の視点から移動とインフラを考える 移動とインフラをめぐる諸課題は、往々にして「目の前の課題をどうするか」に関心が集まりやすい。しかし、人口が減少し少子高齢化が深刻化するなかでは、いま以上にインフラを維持管理する人手は少なくなる。デジタル・テクノロジーやAIなどの新技術の活用と発展にも期待したいが、それだけですべてが解決することはない。新たなテクノロジーや技術を導入するためにも、結局はお金がかかり、相応の税金が充てられることに変わりはない。 こうした中でモビリティ・ジャスティスなインフラを実現していくために求められるのが、「将来世代」、つまりは未来人の視点である。現在の民主主義システムでは、「私たちが我慢すれば、将来を生きる子ども世代や孫世代、これから生まれてくる世代も豊かに暮らせる」という発想の政策は好まれず、「すぐに自分の利益になる」政策が推し進められやすい。しかし、今を生きる自分たちさえよければそれでいいでは、世代間の分断がますます深まり、将来に負担を先送りするだけで根本的な解決にはならないだろう。 「未来人の視点を取り入れて考えることなんてできるの?」と、思うかもしれない。しかし近年、フューチャー・デザインと呼ばれる研究領域の成果や矢巾町の実践から、丁寧に趣旨を説明し、正しい情報を共有し、話しやすい議論の環境を設けるなどすれば、多くの人が未来人の視点を取り入れて考えられることが明らかになっている。 本記事でテーマとしたのは水道、つまり水の移動であったが、ここでの議論は他の移動をめぐるインフラにも当てはまる。交通による人の移動、電線を通じた電気の移動、電波を通した情報の移動、ガス管を通ってのガスの移動などなど。 こうした移動の未来は、悲観的に映るかもしれない。しかし、どこかで聞いた言葉だが、諦めたらそこで試合終了である『モビリティーズ——移動の社会学』などで知られる社会学者のジョン・アーリが言うように、「未来世界は曖昧模糊としているかもしれないが、参入し、問いただし、希望を抱いて作り変えなければならない(Urry,2016=2019:242」のである。移動は社会的で、政治的な、“私たち”の問題だという意識を多くの人が持つことが、課題解決の第一歩になるだろう。 【文献】 ジョン・アーリ著, 吉原直樹・高橋雅也・大塚彩美訳(2019)『〈未来像〉の未来——未来の予測と創造の社会学』作品社. 新刊『移動と階級』では、意外と知らない「移動」をめぐる格差や不平等について、独自調査や人文社会科学の研究蓄積から実態に迫っている。 【つづきを読む】この世界には「移動できる人」と「移動できない人」に大きな格差があるという「深刻な現実」