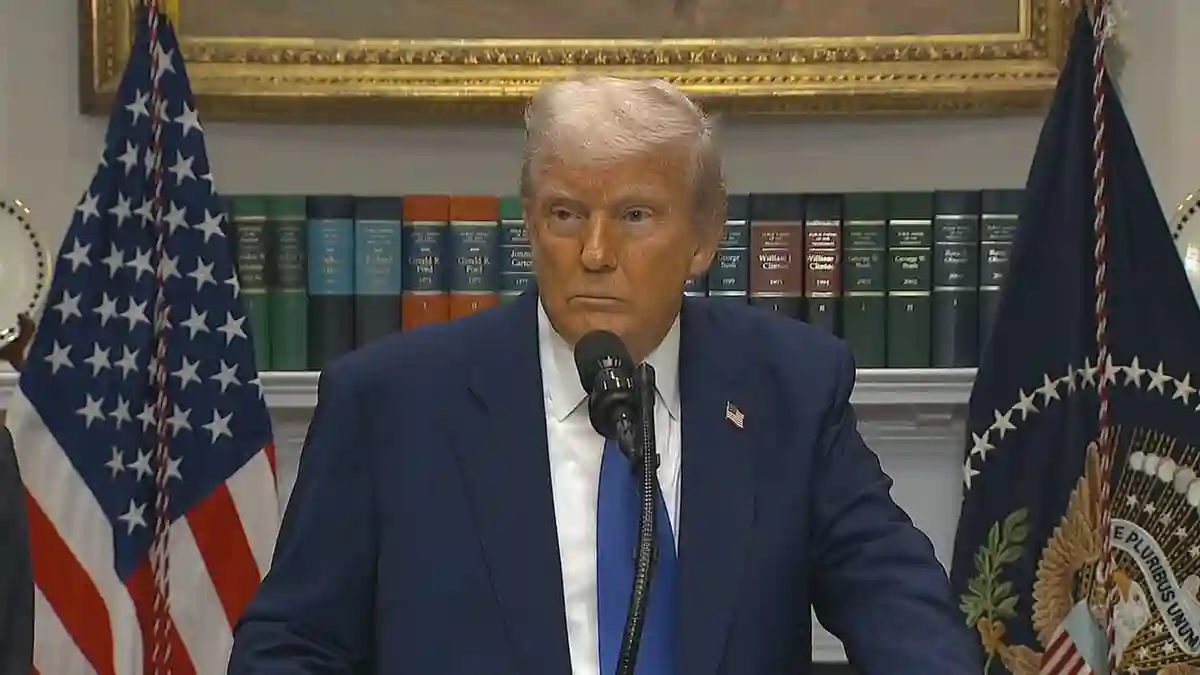フジテレビが「楽しくなければテレビじゃない」からの脱却を宣言した。 同局は1980年代、これをスローガンにしてヒット番組を連発。視聴率争いのトップに躍り出た。一方、90年代には日本テレビが巻き返し、トップの座を奪い返す。折りしも、バブル景気からその崩壊へという時期でもあり、テレビ界もまた、熱気につつまれ、かつ、混乱もきたしていたわけだ。 ちょうどその頃、筆者はテレビ誌の連載などを抱え、テレビ局に出入りすることも多かった。そこで見聞きしたことを思い出しながら、当時のテレビについて語ってみようというのが、この記事の趣旨である。 壮絶だった90年代テレビの現場 まずは93年の早春、日テレのスタジオで見た風景の記憶だ。『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』の取材で訪れたのだが、その現場に司会者の逸見政孝もいた。ただ、彼は手術による休養から復帰したばかりで、体調もよくなさそうだった。若い男性スタッフから「逸見さん、横になっていてください」と労わられ、さして寝心地がよいとも思えないソファーに横たわっていたのを覚えている。 ふと、野戦病院みたいだな、とも感じたが、実際、彼の状態は深刻だった。十二指腸潰瘍と公表されたものの、本当の病名は胃がんで、すでに完治の見込みはないことが妻には告げられていた。その年の9月、彼は「がん告白会見」を行って、再入院。13時間にも及ぶ大手術を受けたが、クリスマスに48歳で亡くなった。 ソファーに横たわる逸見を見た数週間後には、ソファーに横たわるプロデューサーにインタビューもした。ビートたけしと逸見の冠番組でもあった『平成教育委員会』(フジテレビ系)の取材で、相手は越真一、場所は制作会社のイーストだ。 日曜日を指定されたことからかなり多忙なことがうかがえたが、会ってみると明らかに疲れている様子で「すみません。横にならせてください」と懇願された。取材自体は無事に終えたものの、彼はそこからひと月するかしないかで自ら32年の生涯を閉じてしまった。 この番組で売れた辰巳琢郎はのちに、 「ある種『おばけ番組』でしたから、それなりに負荷がかかったんじゃないかな」(クイズジャパン) と振り返っている。 また、同じくこの番組の常連だった天本英世は、逸見を追悼する特番に出演した際、越真一の死にも触れ、 「これで二人目ですよ。『仕事が趣味』と言うのはおかしいです。やっぱり体調が悪ければ、断らなきゃダメなんですよ」 と「日本人の働きすぎ」に怒りをあらわにした。 天本の当たり役は『仮面ライダー』(NET系)で演じた死神博士。それだけにこの発言には鬼気迫るものがあったし「24時間タタカエマスカ」という栄養ドリンクCMのキャッチコピーが象徴する時代への痛烈な皮肉にも感じられた。 また、この年の6月には収録中の死亡事故という悲劇も起きている。『ウッチャンナンチャンのやるならやらねば』(フジテレビ系)でのこと。ゲームコーナーにゲスト出演していた香港のロックバンド・BEYONDのリーダー黄家駒(ウォン・カークイ)がセットから転落して頭を打ち、数日後に死亡した。 これが原因でこの番組は終了したが、そのプロデューサーだった佐藤義和にも、このひと月くらい前にインタビューしている。番組が絶好調だったからか、トークの随所に驕りめいたものが感じられ、印象はよくなかった。事故のニュースを知ったときには、そういうところが危機管理のゆるみにもつながったのではと感じたものだ。 土屋敏男、テリー伊藤…名物Pの意外な素顔 なお、日本進出を目指していたBEYONDの夢はこの事故で頓挫したが、じつは多くの日本人の耳に馴染んだ音楽を残している。前年に始まっていた『進め!電波少年』(日本テレビ系)のオープニングテーマとして、彼らの『The Wall〜長城〜』のイントロが使われ、リーダーの死後も長年親しまれたのだ。 この番組は『進ぬ!電波少年』と改名したり『雷波少年』という姉妹番組を生んだりしながら、約10年にわたって続く人気シリーズとなる。そのあいだ、アポなしロケの松村邦洋やヒッチハイクの猿岩石、懸賞生活のなすびらが売れっ子となり、指令を出すプロデューサーの土屋敏男までもが有名人と化した。その土屋にもインタビューしていて、93年か94年のこと、ただし『電波』ではなく『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』についての取材だった。 業界内ではその剛腕ぶりが知られ始めていて、まだ20代だった筆者は緊張気味に臨んだが、意外なほど気さくで穏やかな対応をされたことが印象的だ。青島幸男や萩本欽一といった先達へのリスペクトを語り『ガキ使い』でダウンタウンに漫才ではなくフリートークをやらせた理由などを明かしてくれた。もちろん「テレビは怒られるようなことをしてこそ面白い」という挑発的な持論もぶってはいたが、それとは裏腹に、極めて真面目な人だと感じた。 その印象と重なる出来事がある。同じ頃『浅草橋ヤング用品店(のちの『ASAYAN』)』(テレビ東京系)の取材でテリー伊藤に会ったときのことだ。こちらは土屋以上にその剛腕ぶりがすでに評判になっていた人。この番組でも江頭2:50に水中無呼吸対決をさせたり、坂本一生と工藤兄弟に本気のケンカをさせたりといった過激な演出を行っていたが、取材対応は丁寧で腰も低かった。 「師弟」コンビの共通点 なお、制作会社(IVSテレビ)出身のテリーと日テレの土屋は『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』を主導した「師弟」コンビでもある。両者に共通するのは、とにかくふざけることに使命感のようなものを持って取り組んでいたこと。そのあたりについて、土屋は2022年のネットインタビュー(マイナビニュース)でこんなことを言っている。 「伊藤さんがそういう大ゲンカを局のプロデューサーとしているのを、目の当たりにしてましたからね。(略)作り手のこだわり、ある種の狂気って言うんですかね。それは欽ちゃんでも見てきたので、狂気のない作り手の番組なんて面白くないって思い込んでるから、自分の中にも狂気みたいなものをむき出しにしようと、自覚的にやっていたと思います」 思えばそれが、当時のバラエティー番組では至高の原理だった。フジが標榜した「楽しくなければテレビじゃない」はライバル局も刺激して、そういうバラエティー番組のあり方を生み出していたわけだ。 ふざけることへの使命感はこの時期、バラエティー番組を作る会社のテレビマンなら当然持っているべきものだったのだろう。それはフジの局アナからフリーになった逸見政孝にも沁みついていたものであり、彼はさらに「24時間ハタラケマスカ」という当時のもうひとつの原理にも忠実だった。それゆえ、その最期は時代への殉死のようにも映る。 24時間テレビが「V字回復」した理由 ところで、逸見がヒットさせた番組のひとつに『夜も一生けんめい。』(日本テレビ系)がある。ありていにいえば、有名人によるカラオケ番組だが、これが日テレの看板番組に影響を与えることとなった。1978年から今も続く『24時間テレビ 愛は地球を救う』だ。 この『24時間テレビ』が低迷期を迎えた際に、その打開を期待されたのが『夜も一生けんめい。』をはじめ、多くの人気番組を手がけていた小杉善信だった。 92年、彼は『24時間テレビ』に歌とマラソンという要素をとりいれる。有名人たちに思い出の曲を99曲歌わせ、100曲目を番組中に作らせて、最後はそれを合唱した。谷村新司・加山雄三コンビによる『サライ』だ。 それと並行して、間寛平に「24時間チャリティーマラソン」を走らせた。この二大企画がウケ、視聴率はV字回復。当時、筆者が連載をふたつ持っていたテレビ誌で、小杉もプロデューサーの裏話的なコラムを連載していたため、ひとつの番組を生き返らせていく手腕に瞠目させられたものだ。 ちなみに、小杉はその8年前「おもしろまじめ」と題した局のキャンペーンCMを作っている。バラエティー系の徳光和夫と報道系の小林完吾というふたりの局アナを使い、面白さと真面目さの両方を味わえる日テレ、というイメージをアピールした。フジの「楽しくなければ〜」に対抗したともいえるし、この方向性が『24時間テレビ』のリニューアルにも活かされたわけだ。 また、前出の死亡事故のような惨事をフジが何度も起こしているのに対し、日テレはそれほどでもない。あるいは「おもしろまじめ」というバランスのとり方が、危機管理の上手さにもつながったのだろうか。 結果的に運がよかっただけかもしれないが、運も実力のうちだ。どちらの局も同じくらいリスキーな番組作りをしていたにもかかわらず、フジは長年の方針を撤回するところまで追い込まれていて、明暗を分けたかたちだ。 ただ、テレビ界の現状について、土屋は前出のネットインタビューでこんな発言もしている。 「こう言ったらちょっとかわいそうかもしれないけど、根性がなくなったというのもあるかもしれない。これは日本全体の問題だと思うんだけど(略)全部上に相談してOKしたものだけをやろうとする。そうすると『これはやめとけ』って話になるわけで、これをテレビ局がどんどんやっちゃうと、新しいものが生まれなくなってきますよね」 フジに限らず、テレビ自体がそろそろ賞味期限切れなのか。はたまた、娯楽の王様と呼ばれた意地を見せ、再び新鮮さを取り戻すのか。いずれにせよ、大きな曲がり角にさしかかっていることは間違いない。 ・・・・・・ 【もっと読む】小柳ルミ子、橋本環奈に今田美桜…「たくましく、天性の明るさがある」福岡女優と朝ドラとの「不思議な縁」 「スタジオで嫌われているMC」を緊急調査!2位宮根誠司、3位マツコ・デラックス…不名誉の1位となった「超人気者の名前」