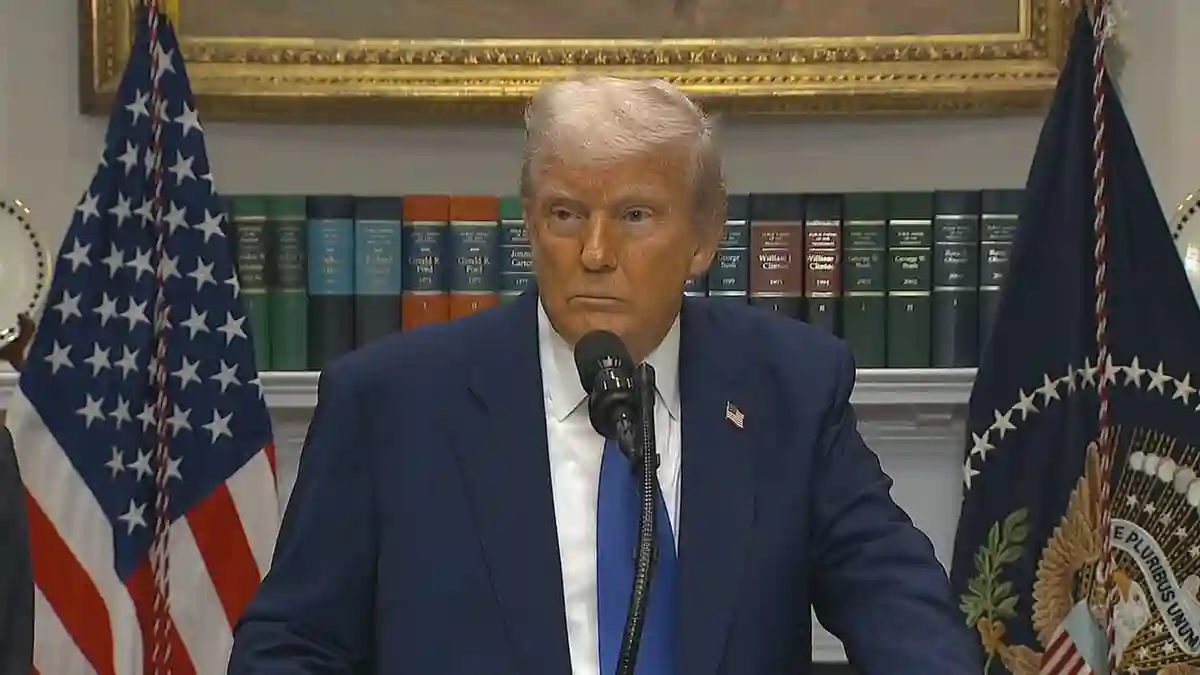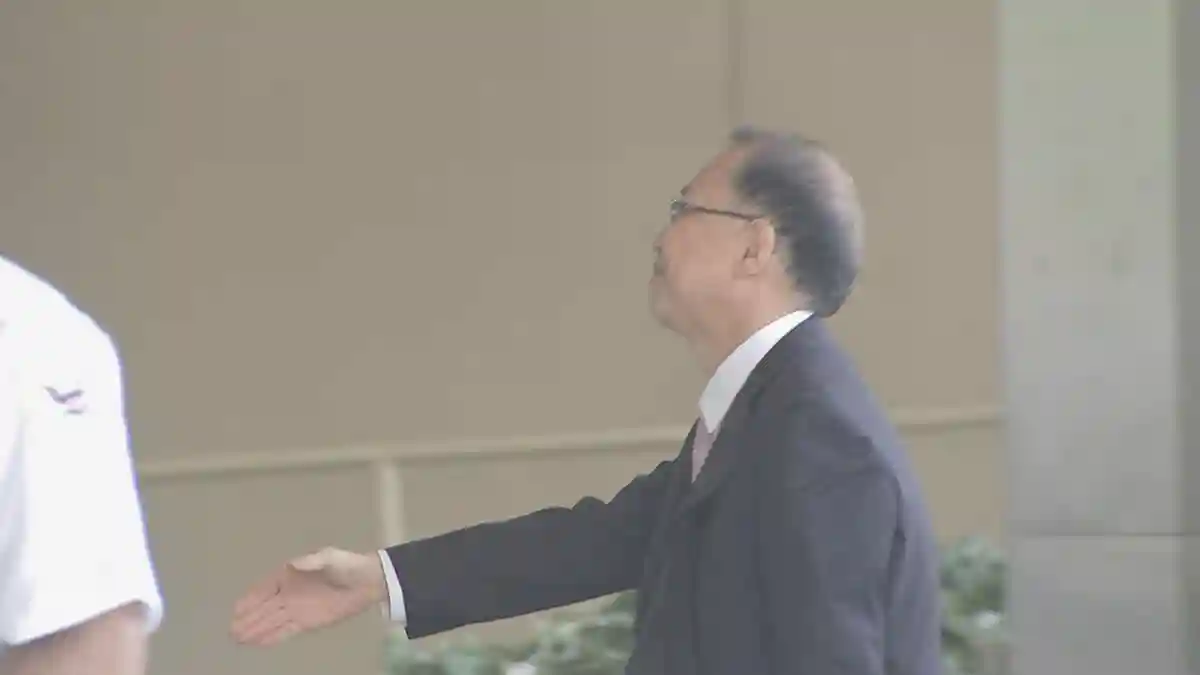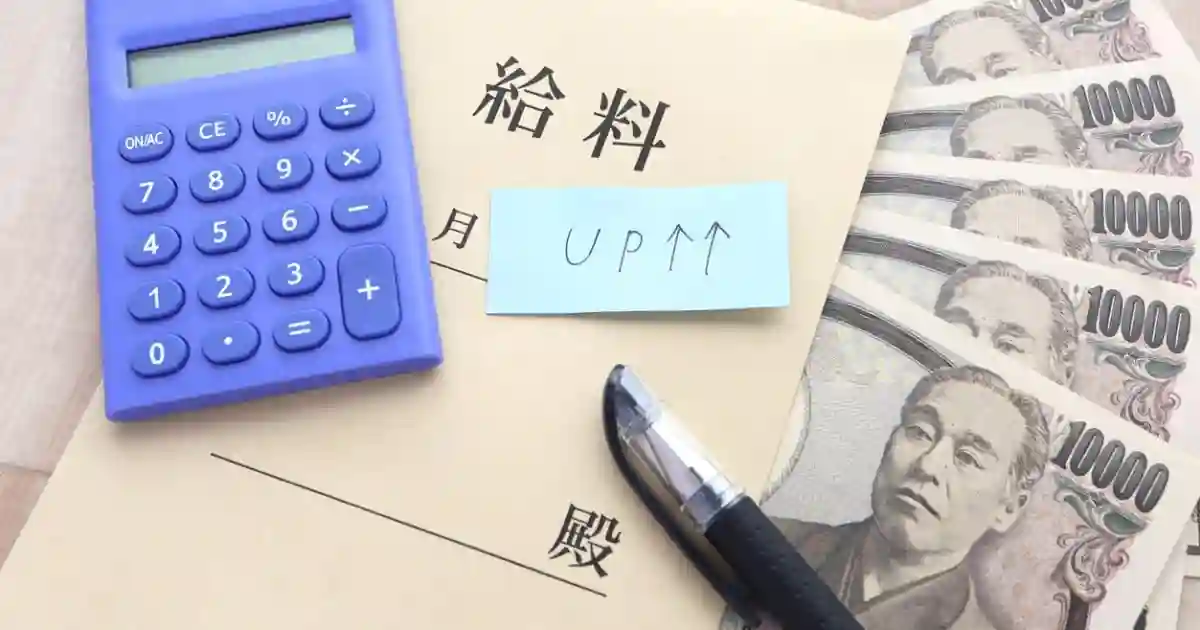
この国にはとにかく人が足りない!個人と企業はどう生きるか?人口減少経済は一体どこへ向かうのか? なぜ給料は上がり始めたのか、人手不足の最先端をゆく地方の実態、人件費高騰がインフレを引き起こす、「失われた30年」からの大転換、高齢者も女性もみんな働く時代に…… ベストセラー『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』では、豊富なデータと取材から激変する日本経済の「大変化」と「未来」を読み解く——。 経済の局面が変わっていけば企業や労働者の行動は変化する。人口減少局面に入った日本経済においてこれから何が起こるのか。企業や労働者は与えられた市場環境のもとでどのように行動を変化させるのか。改めてこれから市場メカニズムが引き起こすであろう経済の構造変化について予想していこう。 予想1 人手不足はますます深刻に 近年、人口動態の変化と歩調を合わせて労働市場の環境は明らかに変わってきている。その変化の根本にあるのは人手不足の深刻化である。労働市場の構造が需要不足から供給制約へと変化している背景には、人口の高齢化が影響していると考えることができる。 今後を展望したとき、高齢化による供給能力の制約はますます深刻化していくだろう。これまでの日本の労働市場では女性の労働参加が急速に拡大してきた。しかし、他国と比較しても既に遜色のない水準まで高まっている女性の就業率を前提にすれば、さらなる上昇余地は限られてくる。女性の就業率上昇の動きに天井が見え始めてきた現代において、期待がかかるのは高齢者の労働参加である。高齢者の労働参加の余地はまだまだ残っている。しかし、高齢者といってもたとえば70代半ばを超える高齢者が現役世代の労働者と同じように働けるかというとそれは難しい。歳を重ねる中で、健康面からも就労が難しくなっていくことは避けられない現実として立ちはだかる。 一方、消費の構造も高齢化によって変化していくとみられる。高齢人口の増加によって医療・介護需要は長期的に増加を続けており、これに引っ張られる形で日本経済全体の需要も高い水準を維持している。今後、人口減少に伴って多くの財やサービスの需要は減少圧力が強まるだろう。しかし、その一方で高齢者の中でも比較的年齢層が高い人が増え続けることで、労働集約的なサービスへの需要は高止まりするとみられる。サービスに関しては貿易を通じて海外の労働力を活用することができない。先進国の人口が軒並み減少し、中国経済が成熟に向かうなかで、安価な労働力を活用する余地はますます限られてくることになる。労働に対する需要は財やサービスの需要の派生需要であることから、今後も堅調に推移すると予想することができる。 一口に人手不足といっても、その言葉の使い方にはいくつかの用法がある。つまり、賃金を上げても上げても労働市場全体として人が採れない状態になっているという意味での人手不足と、あくまで自社がこれまで提示していた賃金では人が採れなくなってきたという意味での人手不足は、同じ言葉であったとしても大きく異なる。このような観点でいえば、現状の日本の労働市場で生じている人手不足とはあくまで後者の側面が強い。 足元の人手不足は景気循環による一時的なものではなく、そこには人口減少と高齢化に伴う構造的な変化がある。日本経済の今後を展望すれば、人手不足が恒常化していくことによって、日本経済の構造はがらりとその姿を変えていくだろう。 予想2 賃金はさらに上昇へ 人手不足という言葉は裏をかえせば、企業側の言い値の給与や労働時間で働いてくれる労働者がいなくなってしまったということを意味している。そう考えれば、人手不足の労働市場で人手を確保するためには、企業はこれまでと同じ労働時間であれば給与の水準を引き上げなければならない。あるいは同じ給与水準であれば労働時間を縮減しなければならない。人手を確保するためには、賃金水準を継続的に引き上げるよりほかに方法はなくなるだろう。 現時点において、すべての経営者がこうした労働市場の環境変化に対応できているかと言えば、そうではない。たとえば、パーソル総合研究所が2022年に行った「賃金に関する調査」では、企業の経営層530人に賃上げに対する考え方を聞いている(図表3-2)。 この調査では、賃上げに対する考え方として「会社の成長なくして賃上げは難しい」と「賃上げなくして会社の成長は難しい」のどちらの考え方が自身の考えに近いかを聞いているが、前者に近いと答えた経営者が63.0%と多く、後者に近いと答えた人は6.4%しかいなかった。同調査は、賃金に関する企業経営者のスタンスを浮かび上がらせている。賃金水準の最終的な決定権を持つのは経営者であるが、企業経営者の多くは労働者の生産性向上が実現しなければ賃金は上げられないと考えている(なお、本調査では成長したら実際に賃上げするかは聞いていない)。 しかし、これからの労働市場においては、このような旧来の経営の考え方は許されなくなる。将来の日本の労働市場では、人口減少が本格化していくなかで、自社の利益水準にかかわらず賃金水準を先行的に引き上げて従業員を確保するように、労働市場が企業に強い圧力をかける。そこに気づいた先見性のある企業は、自社の発展のため、先行者利益を確保するために我先にと賃金を引き上げ、優秀な人手を囲い込もうとするだろう。 実際に、日本の労働市場をみると、そのような動きは少しずつ顕在化してきている。賃上げをしないと人材獲得競争に競り負けるという危機感が同業他社の経営層に波及していけば、企業間で賃上げ競争が起き、労働市場全体としての賃金上昇の動きはますます広がっていくことになる。 そうなれば、これからの日本経済においては、多くの人が予想する以上に賃金が力強くかつ自律的に上がっていく局面を経験することになるはずだ。日本の人口動態を前提とすれば、将来にわたって労働市場の需給はタイトな状況を続ける可能性が高い。そうなれば、労働力はますます希少なものとなり、賃金は名実ともに上昇に向かうだろう。 【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ここへきて日本経済に起きていた「大変化」の正体