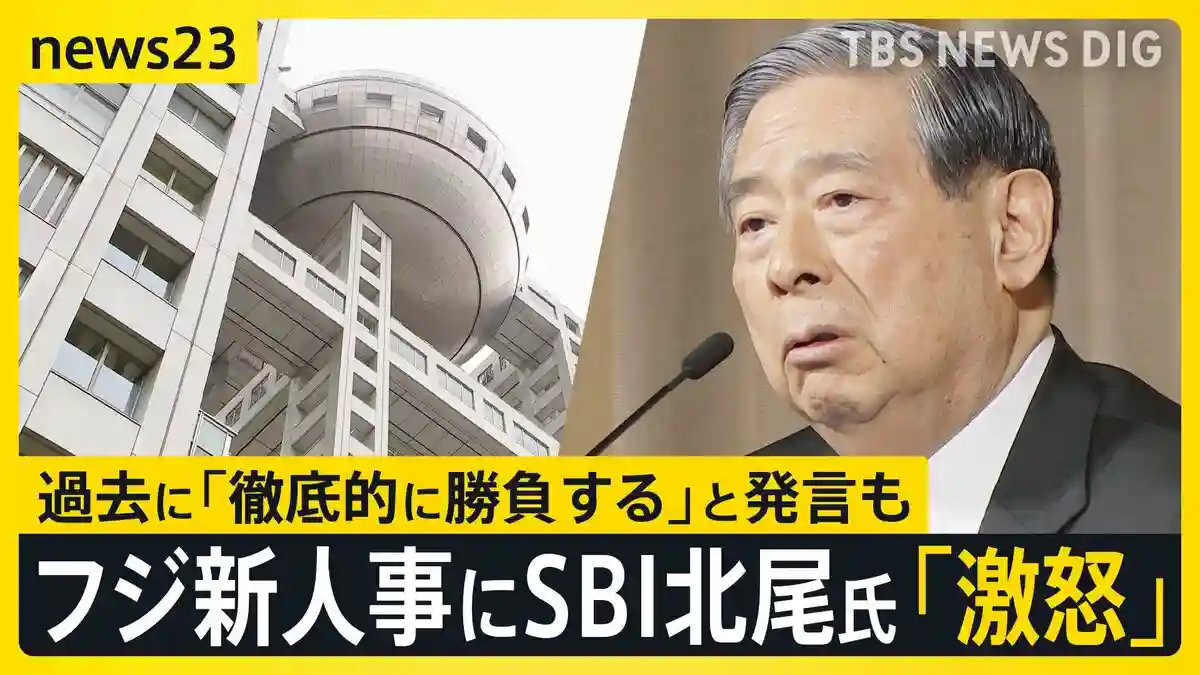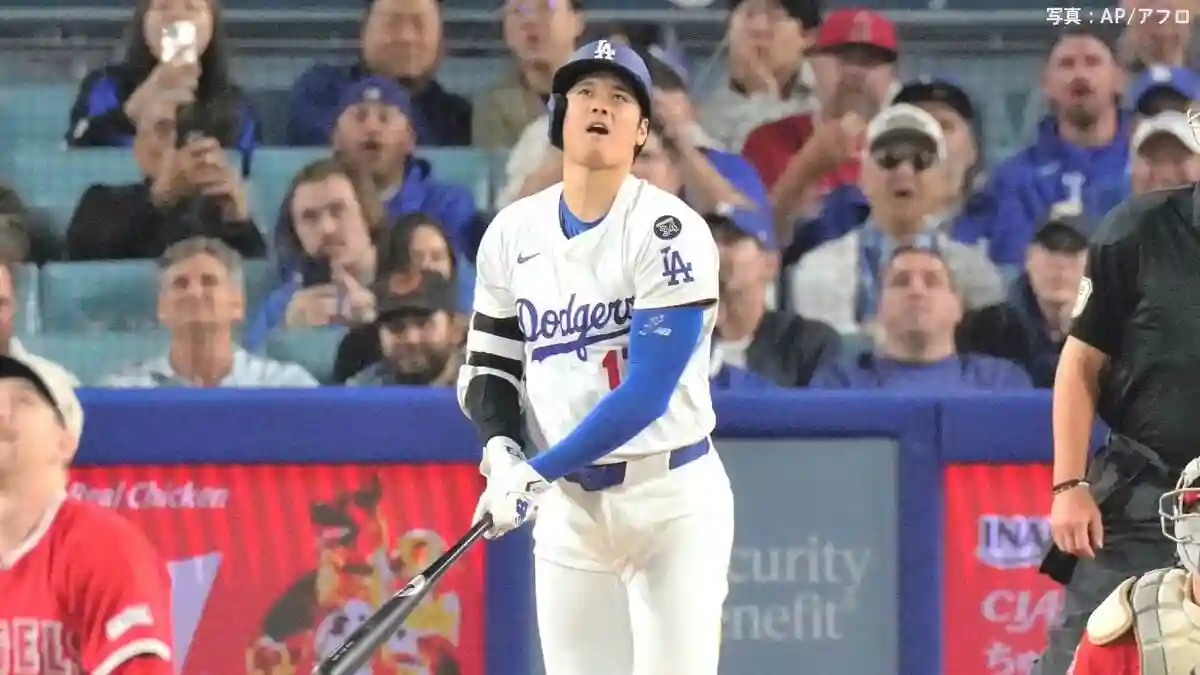2025年は男子普通選挙法が成立、公布されてから100年となり、日本の選挙の歴史が一世紀を超える節目の年だ。また12年に一度めぐってくる、東京都議会議員選挙と参議院議員選挙が重なる年でもある今夏、2024年都知事選で注目を集めた石丸伸二氏と安野貴博氏がそれぞれ政治団体を設立し、選挙戦に挑むという。ライターの小川裕夫氏が、石丸氏と安野氏の対照的な政治スタイルについてレポートする。 【写真】安野・清水両候補による合同街頭演説会 * * * 2024年の都知事選で、広島県安芸高田市の前市長だった石丸伸二氏は既存政党の支援なしに約165万8000票を得票した。落選はしたものの、事前の予想を覆す大健闘に世間を驚かせた。その後は時の人となり、テレビの政治番組などに引っ張りだこになる。 そして石丸氏は地域政党「再生の道」を旗揚げし、2025年6月13日に投開票される東京都議会議員選挙と夏に投開票される参議院議員選挙に候補者を擁立することを発表した。ただし、石丸氏本人はどちらの選挙にも立候補はしないという。 石丸氏ほど目立つことはなかったが、都知事選で約15万4000票を得票した安野貴博氏も5月9日に新党「チームみらい」の設立を発表。同党は参議院選で10人以上の候補者擁立を目指すとし、安野氏本人も出馬する予定であることも明かされた。 グループLINEで街頭演説の情報共有を提案 安野氏はAIエンジニアとして豊かな経験を有し、街頭演説ではテクノロジーが人々の暮らしを便利にしてきたと力説していた。石丸氏のように政治経験があるわけではなく、選挙戦も初経験。そのため選挙戦は洗練されているとは言い難い状態で、支援者も決して多いとは言えなかった。そんな状態で奮闘した安野氏に、各業界関係者は注目した。 特に、安野氏に注目した一人がヤフー株式会社代表取締役社長から東京都副知事に転身した宮坂学氏だった。かつて都庁では主な連絡手段としてFAXを使用していたが、宮坂氏が都庁のIT化やデジタル化に取り組み、業務のDX化を大幅に推進した。 さらに、東京都と都内の市町村のデジタル化やDX化を深化させるべく、一般財団法人GovTech東京を立ち上げて理事長に就任。都知事選後に、宮坂氏は安野氏を同団体のアドバイザーに招聘している。 小池都政下で副知事を務めている宮坂氏が都知事選で敵対した候補者にアドバイザーに抜擢する。「戦いが終わればノーサイド」ということなのだろうが、選挙で競った相手に対してのわだかまりは簡単には消えないだろう。 しかし、安野氏は選挙を候補者同士の戦いとは捉えていないフシがある。それは2024年の都知事選での安野氏の行動からも窺える。 2024都知事選は史上最多の56名が立候補した。56名もの候補者が各地で街頭演説を実施すれば、どこかで必ずバッティングしてしまう。その際、陣営間で「うちが先に場所を確保していた」「こちらは昨日から準備していた」という諍いが起きる。 特に有楽町駅前や銀座4丁目、新宿駅前、渋谷駅前といった人が多く集まる場所は街頭演説の場として人気が高い、土日週末ともなれば、人気の場所が取り合いになることは誰の目にも明らかだった。 そうしたトラブルを未然に防ぐべく、安野氏は候補者56名に対してグループLINEで街頭演説の情報を共有することを提案した。しかし、街頭演説の場所や時間は選挙戦の支持拡大において重要度の高い機密情報でもある。候補者がどこを回るのか、どれぐらい時間をかけるのかといった情報を、そう簡単に他陣営へ漏らすことできない。そのため、安野氏の提案に応じたのは清水国明候補の一人だけだった。 安野氏の提案は不発に終わったが、そこから清水候補との関係性が深まり柴又駅前での合同街頭演説会が実現する。筆者は清水・安野両候補が選挙カーを並べる光景を間近で取材したが、それは選挙の演説というよりも互いの健闘を称え合うエール交換のような光景だと感じた。 SNSで広がった勇ましいイメージ 選挙であっても対立を意図しない安野氏に対して、石丸氏は安芸高田市長時代から一貫して対立構造を明確化して支持を拡大してきた。市長時代の議会答弁は、切り抜き編集されたバージョンも含めてYouTubeなどの動画サイトに多数アップされている。それらを視聴すると、石丸氏が勇ましく答弁していたり、既得権益を打破するかのような立ち振る舞いを目にできる。 また、新聞・テレビという、いわゆるオールドメディアを敵対視し、反撃する姿も喝采を浴びた。選挙特番では社会学者の古市憲寿氏や乃木坂46元メンバーの山崎怜奈氏とのやりとりも話題になった。そのやりとりからは石丸構文という新語も生まれたが、そうした現象が起きるのも石丸氏の絶大な人気を裏付けるものと言っていい。 筆者は都知事選の告示前後で、石丸氏の街頭演説に5回以上、足を運んだ。熱狂的な雰囲気を感じつつも、事前から聞いていたような「これまでの政治家とは一線を画している」とまでは思えなかった。 それでも何かが伝わっていたのだろう、凄まじい勢いで石丸氏への支持が拡大していった。市長時代から主にSNSを通じて広がったイメージに魅力を感じている支持者は多かったようだ。街頭演説に集まった人たちに話を聞いてみると、「歯に衣着せぬ物言いが、これまでの政治家とは違う」と口にし、「だから、何かを変えてくれるかもしれない」と期待している人が多かった。もっとも、街頭演説では攻撃的な言動をしているとは感じず、具体的な内容にも乏しいものだったのだが。 石丸氏への支持は選挙の熱に煽られた盛り上がりに終わらなかった。都知事選後も高い人気は衰えることがなく、その人気を後ろ盾にして2025年1月、新党「再生の道」の立ち上げを発表し、都議選に挑むことも表明。さらに、続けて参議院選にも候補者を擁立すると明らかにした。 明確に異なる政治スタイル 石丸氏と安野氏はどちらも都知事選で全国区の知名度を誇る存在になり、その後は都政にも国政にも影響を及ぼしている。 2人は既存政党ではなく、自ら政党を立ち上げて今の硬直化した政治を動かそうとしている。石丸氏の再生の道、安野氏のチームみらいは、今のところ政党助成法における要件を満たしていないので厳密には政治団体という位置付けになる。 そのため、活動の原資は支持者からの献金(寄付)に頼らざるを得ない。独自の団体を立ち上げて、徒手空拳で既存政党に挑む姿勢も2人の共通点でもある。既存政党のように潤沢な資金がない点も、判官贔屓を好む一部の有権者を鷲掴みにしている。 しかし、ここまで述べてきたように両者の政治スタイルは明確に異なる。どちらの政治スタイルが優れていて、どちらが劣っているのかという話ではない。それを判断し、どちらを支持するのかを決めるのは、あくまで有権者だ。その最初の審判は7月に投開票が想定される参議院選挙で下されることになるだろうが、そこで下された審判だけで石丸・安野両氏の評価が定まるわけではない。 長い目で見た時、有権者はどちらの政治スタイルを選ぶのか? それとも、対立も協調もよく見通せない従来のような政治スタイルが続くのか? 今夏の参院選は政治スタイルの新旧が問われることにもなるだろう。