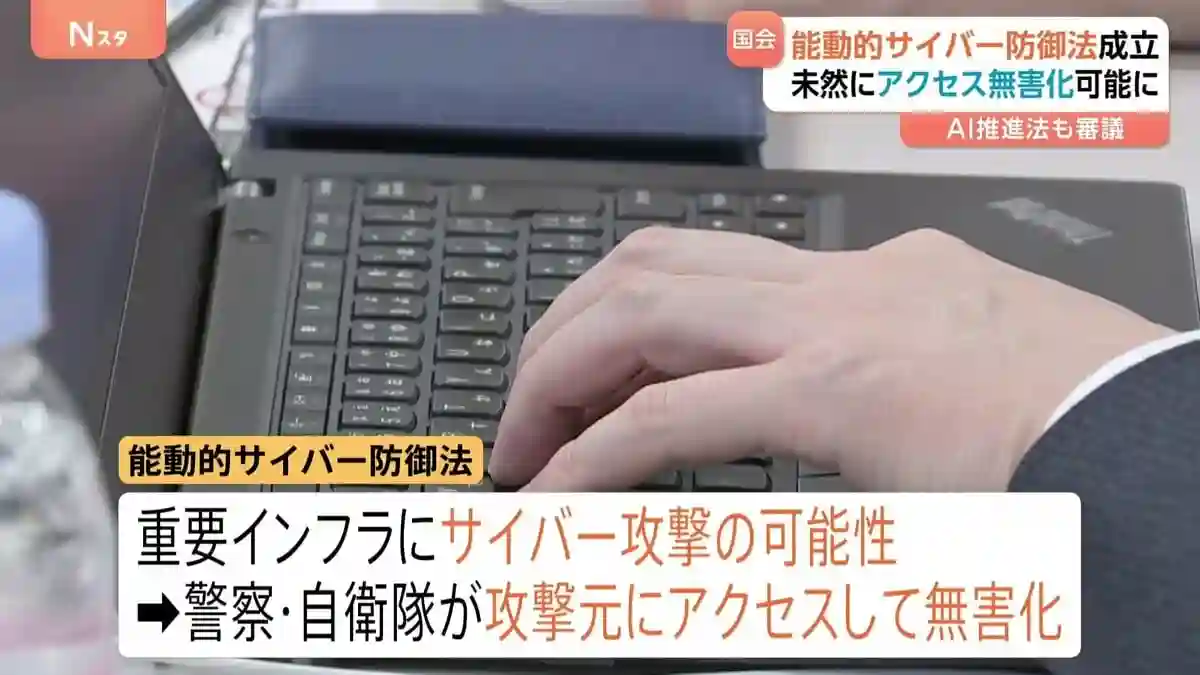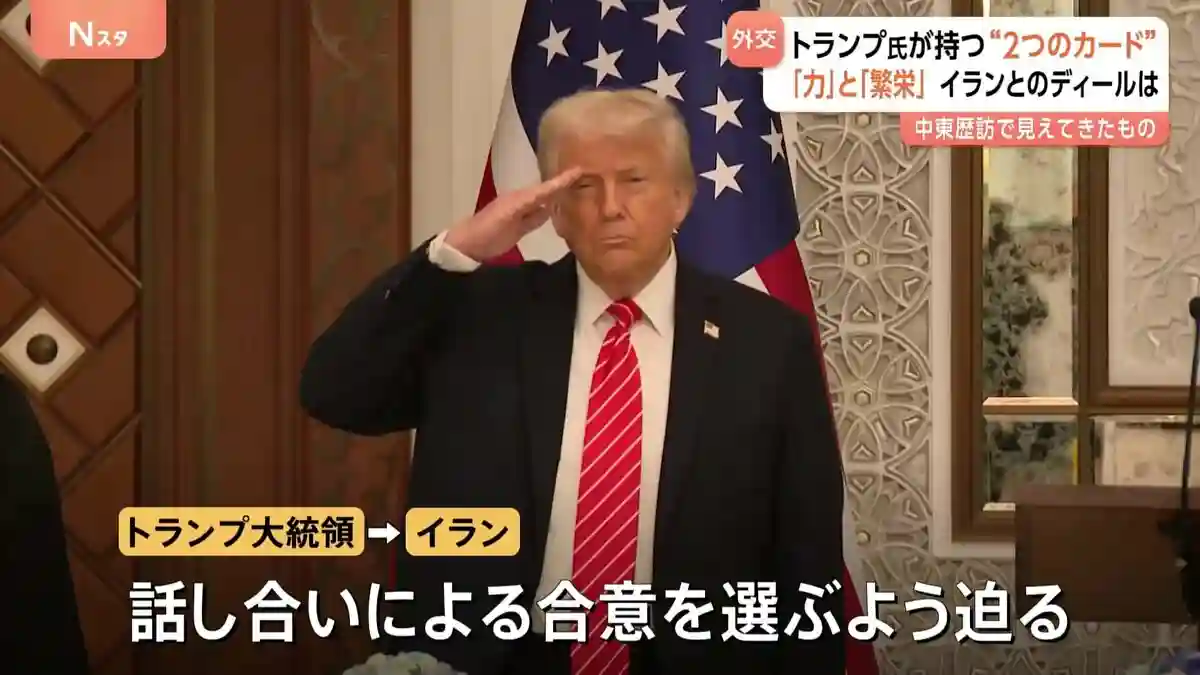5年に1度行われる年金制度改革。16日に閣議決定された「年金制度改革関連法案」は、これまで自民党内部で反対の声が根強く、当初予定していた時期から大幅に遅れて国会に提出されます。老後を支える年金は、今回の法案が成立するとどう変わるのでしょうか。 ■法案の柱「106万円の壁」撤廃へ 今回の制度改革の柱の一つは、パートやアルバイトなどで働く短時間労働者が厚生年金に入りやすくして、これらの人が将来受けとる年金額を増やすことです。 現在、学生以外のパートやアルバイトなどの人たちが厚生年金に加入するには、 ・従業員数51人以上の企業で、 ・週20時間以上働き、 ・賃金が月8万8000円以上(年収がおよそ106万円以上) という条件をすべて満たす必要があります。 今回の制度改革が行われれば、これらのうち、企業規模と年収の条件を将来的に撤廃し、多くの短時間労働者が厚生年金に入りやすくなります。まず収入の条件、いわゆる「106万円の壁」については、最低賃金の上昇もあり、2026年をめどに撤廃される見込みです。また、企業規模については2027年10月からは従業員36人以上の企業…などと段階的に対象を広げ、10年後の2035年10月には、常時5人以上の従業員を雇っている企業などはすべて対象になります。厚生労働省によりますと、収入と企業規模の条件撤廃により、将来的にあわせて180万人が新たに厚生年金に加入する見込みだということです。 ■パートの働き控え対策も そもそもアルバイトやパートの人などは、加入する年金の種類が国民年金なので、将来受けとる年金額が低いのが課題です。社員と同じく厚生年金に加入すれば、年金額が増えるほか、国民年金の場合は毎月の年金保険料を全額自分で負担するのに対して、厚生年金では年金保険料の半額を企業側が負担してくれます。 一方で、たとえば会社員の夫の扶養家族であるパート主婦の場合、年金保険料を納めなくて良い立場(第3号被保険者といいます)ですが、厚生年金に加入することになれば年金保険料を納めることになります。保険料を納めることで手取りが減るのを避けるため、現在、パートの主婦は月給が8万8000円(年収約106万円)の「壁」を超えないよう働く時間を調整する実態があります。 今回の改正には、この「働き控え」を防ぐため、保険料の負担を軽くする特別措置も盛り込まれました。年金保険料は労働者と企業が半額ずつ負担していますが、3年間に限り、労働者の負担分を減らす仕組みが設けられました。企業は、たとえば8万8000円の労働者の場合、保険料の負担割合を労働者25%企業75%に変更できるなどというものです。これに伴う企業への負担も考慮して、半額以上の負担をした企業には補助金も出るということです。 ■断念した基礎年金の底上げ 今回の年金改革法案のもう一つの柱だったのが、国民全員が受けとる基礎年金の底上げです。日本の年金制度では、保険料を納める現役世代の負担を抑えるため、高齢者らに支給する年金額の伸びを、物価や賃金の伸び率に比べて低く抑える仕組み(マクロ経済スライド)が導入されています。この年金額を抑える仕組みのために、基礎年金の額が低い期間が長く続くことが大きな課題でした。去年公表された、5年に1度行われる年金の健康診断ともいわれる「年金財政検証」では、現在50代前半から30代の人が将来受けとる基礎年金額が低くなる見込みであることが改めてわかりました。会社員であれば、基礎年金のほかに、給与に連動した厚生年金が「上乗せ」されますが、就職氷河期世代で企業に就職できず、フリーターや自営業の場合、受けとるのは基礎年金だけなので、老後の生活が苦しくなるとみられ、基礎年金の底上げが今回の制度改革の重要な柱の一つでした。 具体的な基礎年金の底上げの方法としては、会社員と企業が納めた厚生年金の保険料の「積立金」の一部を活用する案がありました。具体的には、会社員だった高齢者が受ける厚生年金を今後約10年間(2036年度まで)減らすとともに、国の税金も現行制度より多く投入(多い年で年間約2兆円増)し、それらを今の50代前半から30代ぐらいの人たち(会社員、フリーター含め全員)が老後に受けとる基礎年金の底上げに使うというもの。すると、この世代の年金額は、制度を変えない場合に比べ3割増えるとの試算が出されました。しかし、この案について自民党内では会社員などからの反発を予想し、「理解してもらえない」などと反対する声が強まりました。結局、「基礎年金の底上げ案」については今回の法案から削除されましたが、野党からは就職氷河期世代への対策が欠けた法案になっているなどと批判の声があがっています。なお、元会社員らが受けとる厚生年金の伸びを物価や賃金の伸びよりも低く抑える仕組みを2030年までは続けることが法案に盛り込まれました。 ■“年金減額”気にせず働ける高齢者を増やす 厚生年金を受けとっている60歳以上の人が、働いて現役世代と同程度の収入がある場合、厚生年金の金額を少なくする「在職老齢年金制度」という仕組みがあります。現状では、65歳以上の場合、ひと月に受けとる賃金と厚生年金の合計が基準額=(今年度は50万円)を上回ると受けとる年金額が減らされますが、今回の法案では、来年度からこの基準額を62万円に引き上げるとしました。引き上げにより高齢者の働き控えが抑制でき、厚労省によりますと、新たに20万人の高齢者が年金を全額受給できるようになるということです。 ■高所得者が納める保険料は増える 会社員や公務員が加入する厚生年金の保険料は給与の18.3%(本人と企業が半額ずつ負担)と決められていますが、保険料を決めるための給与は、「標準報酬月額」という32の等級にわけられています。たとえば、月収が13万8000円〜14万6000円の人たちの標準報酬月額は「14万2000円(等級8)」、月収が25万〜27万円の人たちの標準報酬月額は「26万円(等級17)」となっていて、この標準報酬月額に18.3%をかけた額が年金保険料となります。 現在は、この等級の上限が「65万円」であることから、月収が63万5000円以上であれば、それ以上いくら月収が高くても保険料は「65万円」に18.3%をかけた額で一定になります。つまり、高所得者であるほど納める保険料が賃金と連動しないことから、今回の制度改革では、この標準報酬月額の上限を「75万円」まで引き上げるとしました。引き上げは2029年9月まで3段階にわけて行われます。これにより高所得者は納める保険料が増えますが、将来受けとる年金額も増えます。 ■今後の課題も明記 今回、法案の条文とば別の「付則」には今後の課題として、 ●保険料の納付期間を現在の「40年」から「45年」に延長することを検討すること ●会社員の配偶者で保険料負担のない「第3号被保険者」のあり方の議論に資するよう調査を検討などが明記されました。 ■法案提出してもまだ道は遠い…? 社会や経済の変化に応じ5年ごとにアップデートされる年金制度。今年は夏の参議院選挙への影響もあり、自民党内部では国会への提出に慎重な声もあった中、16日、ついに法案が閣議決定され、今後国会で審議されます。基礎年金の底上げという大きな柱が削除された法案は、野党から「あんこのないあんぱん」とも批判されていて、法案成立の見通しは不透明です。