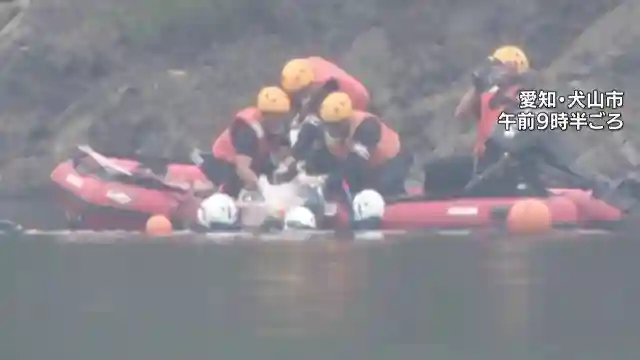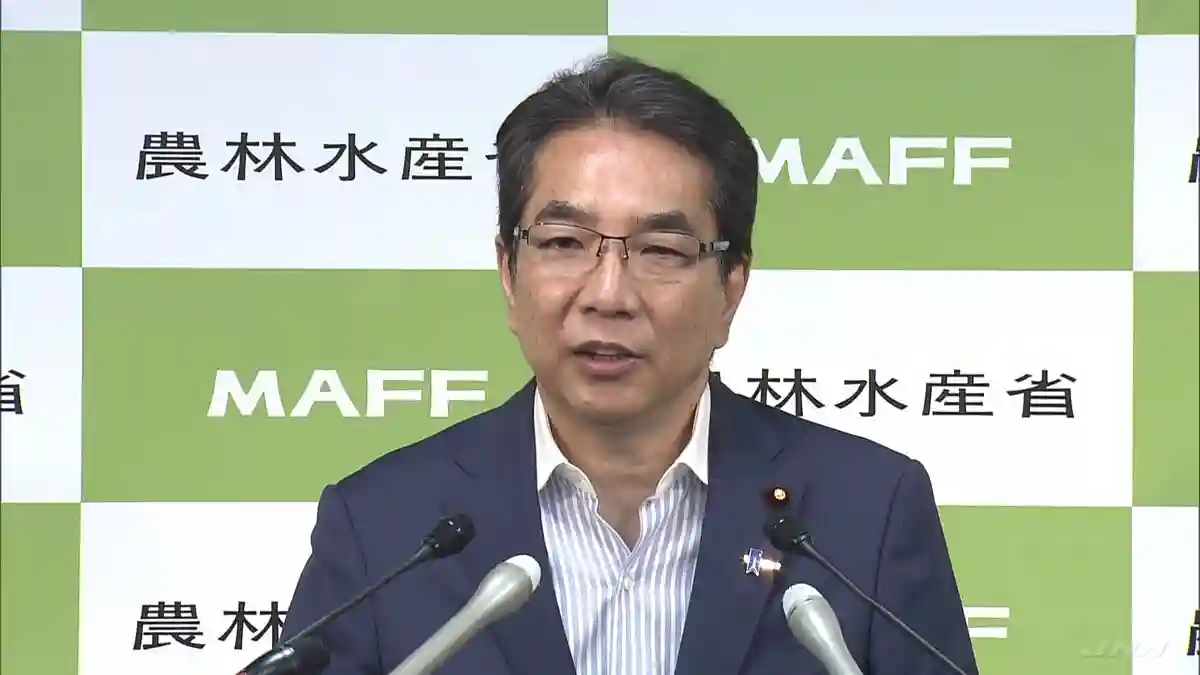トヨタが決めた「戦うべき場所」 5月中旬にヤマ場を終えた3月決算の東証上場企業の決算発表。今後の日本経済を占う材料として、とりわけ重要なのは、まさに我が国の基幹産業であり、トランプの関税措置の影響を直接に受けることになった自動車産業、その中心に位置するトヨタ自動車の決算説明だろう。前編記事にひきつづき、トヨタ自動車の決算のポイントを詳述する。 まずは図1のスライドをご覧いただきたい。 トヨタ自動車は少し前に、ROE20%を目標に掲げた。それはPBR1倍の達成を求める東証要請なども受けながら、テスラなどに比べはるかに低いPER評価である自社の現状など鑑み、重要なステークホルダーである(とやっと近年認識されたのだろう)株主に対して、改めて自社の存在意義を再定義した目標だったのだと思うが、それをどう達成するか、を示した概念図になる。 ここで重要なのは、この概念図が示すものが、テスラやBYDなど新興の米中のEVメーカーとの競争戦略でもあるからだ。そこにはトヨタが設定した「自らが戦うべき場所」が示されている。 トヨタは誰もが知る、世界最大の新車販売台数を誇るメーカーである。2025年3月期の連結販売台数は936万台。ちなみに内訳としては括った数字にはなるが、日本で199万台、北米で270万台、欧州で117万台、アジアで184万台、その他地域で166万台を売っている。自動車メーカーのランキングを考える時、どうしても我々はこうした新車販売台数で優劣をつけたがるものだし、テスラやBYDが強い存在感を示し、日本メーカーの出遅れが懸念されるEVの販売台数が、成長の谷間には陥っていたとしても、いずれ内燃機関を動力とする既存車のシェアを侵食していく未来が想定されるなかで、トヨタのこれ以上の成長にも疑念が生じている(だから低PERに甘んじている)。 しかし、この概念図が示すもの、また実績が示すものは、トヨタは新車販売を変わらずコアの1つとしてはいるものの、例えばメンテナンスや中古車販売、安全と安心、そして変わらない価値(リセール可能な価値)の源泉となる部品補給などVC(バリューチェーン)ビジネスをもう一つの柱として意識し、成果を挙げている現実に他ならない。 BYDやテスラに対する「勝ち筋」 図2は更に分かりやすい営業利益の分解になる。 このスライドに書かれているが、積み重ねられたトヨタ車の1.5億台の保有台数、それ自体が価値の源泉として意識されたとき、BYDやテスラに対する「勝ち筋」が見えてくる、と思うのは筆者だけではないだろう。 また、電池を動力源とするために、その劣化を宿命とするEVに対し、もちろん機械的摩耗などの劣化はあるとしても、内燃機関はメンテナンスや部品供給が適切であれば、その寿命は相対的に長いと考えられるだろう。安心や安全につながる耐用年数の長さ、それこそが日本車が、なかんずくトヨタ車が世界市場で20世紀後半から21世紀前半に覇を唱えた理由ではなかったろうか。 実際、トヨタ車が中古車市場において高い評価を受けているのはカーユーザーであればなかば常識のような話でもある。BYDやテスラについては、それはまさにこれから試される話であり、かつ繰り返しになるが、この土俵においては内燃機関がなお捨てたものではないと感じるのは筆者だけではないだろう。現実は理想を凌駕する、少なくとも一足飛びには世界は「ありうべき世界」に変わりはしない。 また、売り切って終わりではなく端末として、常に最新の機能への置き換えが可能になり、AIの発達や通信の時間差がゼロになるこれから予想される世界にあっては、これまでと全く違うビジネスが展開されると予想されるモビリティの世界だが、そうした進歩にも目を配りながら、まずは地に足を着けた世界でも新車販売というだけではないビジネスを既にトヨタは構想し、着々と実現しつつある。 さらに読む:日産やフジテレビの凋落を予言!10年前に予想した「10年後に大きくなる会社」の答え合わせをしてわかった「衝撃の結果」と「今後の10年間」 【さらに読む】日産やフジテレビの凋落を予言!10年前に予想した「10年後に大きくなる会社」の答え合わせをしてわかった「衝撃の結果」と「今後の10年間」