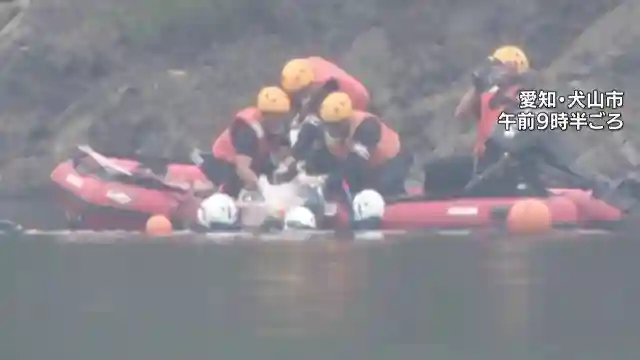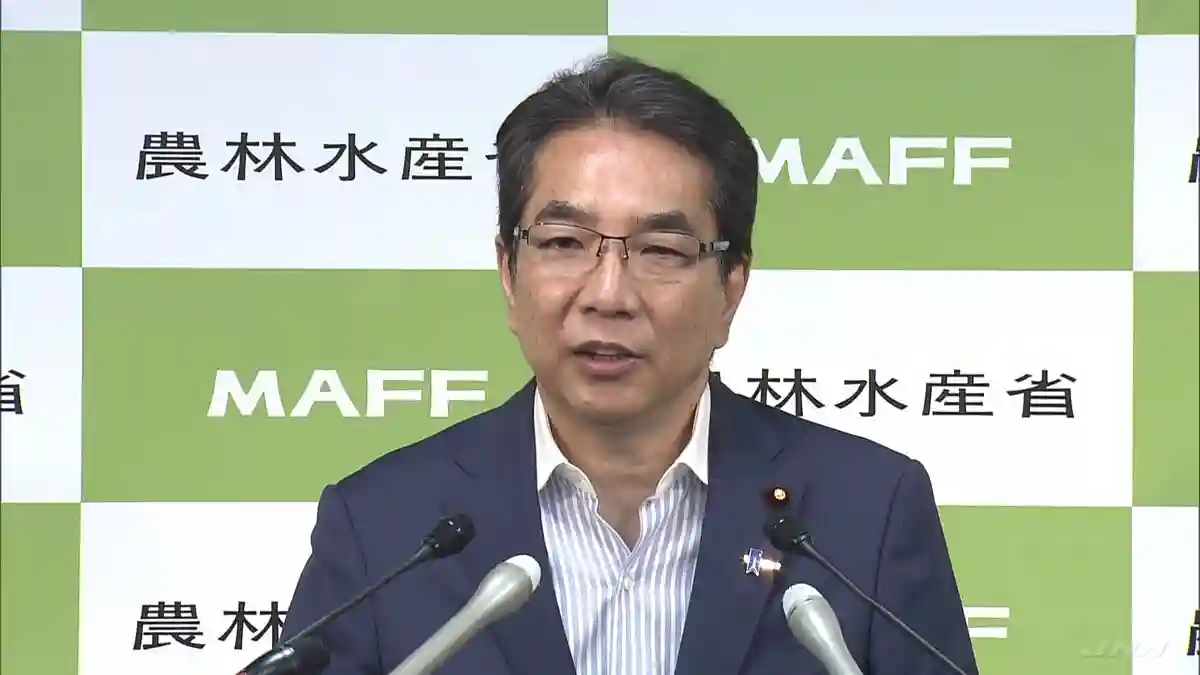世界史の教科書を開けば必ず目にする「秦の始皇帝」。中国を初めて統一し、国家単位での貨幣や計量単位を制定したことで知られる彼は、強烈なリーダーシップで強大な帝国を築き上げた。 【写真を見る】「始皇帝の長男」を自害に追いやった“偽造された遺書”に書かれていたこと しかし、絶対的な権力を手にした彼は、どの息子を跡取りにするか、生前に臣下に伝えなかった。そして、それが彼の死後に政権の混乱を招き、秦の滅亡という悲劇につながった。 中国史家で関西学院大学名誉教授の阪倉篤秀氏がこのほど上梓した新刊『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』(新潮選書)では、始皇帝が最後まで皇太子を選ばなかった理由は、その厳格な統治スタイルに原因があると見る。以下、同書から一部を再編集して紹介する。 始皇帝 (出典:「ColBase」https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-12121?locale=jaを加工して作成) *** 偽造された遺書 皇帝称号を創始した秦の始皇帝は、即位して11年後の紀元前210年に、5回目の巡幸(じゅんこう)の途上、平原津で病を得て、沙丘でその生を終えた。その折に長子の扶蘇(ふそ)にあてた書状を残したというが、それは同行していた丞相(じょうしょう)の李斯(りし)と宦官の趙高(ちょうこう)によって秘匿され、咸陽(かんよう)に帰還してから、死亡の公表とともに、偽造された遺書が黄河湾曲部(河套〈かとう〉)の上郡(じょうぐん)に駐留していた扶蘇に届けられた。 「朕は天下を巡幸し、名山の諸神に祈祷して延命を望んだ。扶蘇は将軍蒙恬(もうてん)とともに数十万の軍を率いて辺境に駐屯し、これで十年余りになりながら、成果なく、兵士は消耗し、少しの功績もないのに、逆に幾度も書面で直言して、私を誹謗し、帰京して太子となれないことを日夜怨んでいる」 秦系図(関係者を含む) (画像は『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』より) 「扶蘇は人の子として不孝である。よって剣をやるから自害せよ。将軍蒙恬は扶蘇とともに辺境にいながら彼を正すことなく、扶蘇のたくらみに気づくべきであるのに、人臣として不忠である。よって自死するよう命じる」 長子扶蘇の自害 扶蘇は、二十数人いたという皇子のなかでの長子であるだけでなく、人柄もよく、また剛毅で武勇との評判があり、後継者にふさわしい人材であると思われていた。だが、父親の厳罰主義的政治手法に苦言を呈したことから、都を追われて、当時は咸陽北部の辺境で蒙恬とともに長城防衛に従事していた。 秦の領域図 (画像は『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』より) この書を受けとって自害を覚悟した扶蘇に、蒙恬は「陛下はまだ太子を立てていない。願い、願い、さらに願い出てみて、それから死を選んでも遅くはない」と諫めたが、扶蘇は聞かずに自害し、蒙恬は自害を拒否して投獄され、その後に死亡した。 後継者の未選定はなぜか? この時、始皇帝は50歳、扶蘇は生年が分からないもののおそらく30歳は越えていただろうから、蒙恬の言葉どおりに後継者に選ばれていて不思議はなかったが、それもなく死を迎えたということになる。 それよりも皇帝称号を創始した時に、「朕、始皇帝たり、後世は計数をもってし、二世・三世より万世に至るまで、これを無窮に伝えん」と豪語した始皇帝が、当時としては長寿といえる還暦をまぢかに控えた年齢に達しながら、扶蘇でなくても皇子のなかから後継者を選んでいてもよいはずである。それがそうならなかったのには、それなりの理由があるといえる。 【「二代目で傾き、三代目が潰す」を回避するための鉄則とは?】中華の絶対権力者であると同時に、一人の親でもある皇帝にとって、皇太子の選定は王朝存亡を賭けた最重要課題であった。強烈な個性を押し通した先代と比較されて苦しむ二代目、甘やかされる三代目など、皇位継承に見られる構造的な困難を乗り越える秘訣を、秦の始皇帝から清の康熙帝まで歴代14人の事例から明らかにする 『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』 秦はもとはといえば、周王朝の支配下の西端にある秦を封地とする小国で、紀元前8世紀の後半に、周が首都を鎬京(こうけい)から洛邑(らくゆう)(=洛陽〈らくよう〉)に移したのを機に、諸侯の地位を与えられて周王朝の正規の構成国に認知されて、雍(よう)に拠点を移した。 「奇貨、おくべし」 紀元前5世紀末に東方に位置する晋が3分割されて弱体化すると、東方への領土拡大をはかり、第25代の孝公(こうこう)の時代に、法家(ほうか)の思想家商鞅(しょうおう)の国家経営理論を取り入れて強国への道を歩み始め、次の恵文王(けいぶんおう)で王の称号を得ることで、戦国七雄の一員として、他の六国から警戒されるまでになった。 そして秦における最初の長城造営を手掛け、強国化を推進した第28代の昭襄王(しょうじょうおう)の孫にあたる子楚(しそ)が、東北に位置する隣国の趙に人質に出された。ここから始皇帝の物語が始まることになる。 戦国時代は戦国七雄をはじめとして、形式上は周の封建制度のもとにある王国がしのぎを削った時代で、各国は安全保障の意味を込めて相互に人質を交換する風習があった。子楚もその一人であるが、当時、趙には各地で手広く商業活動をしていた呂不韋(りょふい)がおり、「奇貨(きか)、おくべし」の言葉通りに子楚を支え、彼の秦王位継承を後方支援して確実なものとし、また求めに応じて愛妾である趙氏(ちょうし)を譲った。 まさにパトロンと呼べるが、求められたとはいえ愛妾まで譲るのはいささか行き過ぎであったかもしれない。この趙氏がほどなくして男児を生むと、この子は秦王室の姓である“えい”に、名を政(せい)、すなわち“えい政”とされた。いわずもがなではあるが、後の始皇帝である。 王室のスキャンダル 父の孝文王(こうぶんおう)なきあと、子楚は妻子とともに帰国、王位を継承して荘襄王(そうじょうおう)となり、当時10歳であったえい政は、王の後継者の位置を得る。ここまでは順調な人生の滑り出しといってよい。 ところが、である。おそらく父の願いを受けてであろうが、呂不韋も彼らの帰国に同行しており、王を補佐する宰相の地位を与えられていたことから、どこにでも、そして現在の我々の周りにもいる、口さがない連中の格好の噂話の種になる。秦の出身者でもなく、商業で得た財を活用して宰相に上りつめた呂不韋へのひがみ、いや、「へんねし」というべきものがあった。 「へんねし」とは京都弁で、他人にただ嫉妬の感情を持つだけでなく、その人物に不都合や不幸が訪れることを願い、表面的にはおくびにも出さずに陰でこそこそ噂話したりして機会の到来を待つことをいう。ことは王室のスキャンダルとくれば、人々の耳目を引くこと請け合いである。「王子の実の父は、子楚ではない」、さらに進んで「実の父は呂不韋のようだ」、肯定するにも否定するにも証拠はないとなると、おおっぴらではなくともじわじわと噂は広がり、ついにはえい政の耳に入らないわけがない。 多感な時期を迎えている少年にとって、不愉快で重い課題であったし、苦しみ悩むことも多くあったであろうが、彼は一つの結論を得ることでそれを乗り切った。すなわち、できる限り過去は問わない。すべては自分から始まり、今を生き、未来に向かうだけのこと。 封建制度は受け継がない 在位3年で子楚が亡くなると、彼は父の跡を継ぎ王位に即いて秦王政(しんおうせい)と呼ばれるようになるが、問題は残っていた。まだ13歳であったこともあり、父を助けて宰相の地位にあった呂不韋はそのまま残し、仲父(ちゅうふ)と敬称して留め置き政治執行を委ねざるをえなかったし、その一方で生母趙氏の寵愛を受ける宦官の“ろうあい”が増長する事態に直面した。 隠忍自重すること10年近くして、ろうあいにクーデター計画があることが発覚したのを好機と捉えた秦王政はこれを未然に防ぎ、重ねて連座の形で呂不韋をも排斥して、服毒自殺に追い込んで、ようやくにして親政、すなわち自らで政権を執行する立場を得ることになった。 孝公以来の法家主義的国家経営をより推進するため、法家の流れをくむ李斯を政策立案・遂行者に抜擢し、宦官趙高とともに身辺を固めた秦王政は、中央統制体制を固めて内政を充実するとともに、活発な外征を敢行した。紀元前230年に隣国の韓を皮切りに、趙・魏、そして南方の楚・北方の燕、そして韓への外征から9年後に東方の斉を滅亡させて、戦国時代の混乱を収束し、中国統一をなしとげるに至ったのである。 この時、臣下に、遠隔地である楚・燕・斉については、周の封建制度に倣い諸子を分封(ぶんぽう)するよう提言する者がいたが、秦王政はこれを即座に却下した。ここに、過去にこだわらないという、あの自分の出生に関する噂話を払拭しようとした姿が重なってみえる。 直接支配へのこだわり 周の封建制度は、創立者の武王(ぶおう)が旧商王朝の領域の支配を弟に委ねたのを最初の例とし、幼少で即位した第2代の成王(せいおう)を補佐した叔父の周公旦(しゅうこうたん)が、東方・南方に拡大する領域の支配を同族血縁者や功臣に委ねたことに始まった。 この地方分権制度であってこそ、広域支配は成立し、周王朝の安定をもたらしたことはよく知られる。戦国時代になると、各国は中央統制力の強い領域支配に傾注することで国力を増強してきたが、これはあくまで限られた範囲内のことでしかない。 それがいま周と同等の領域を確保したとなると、遠方に限るとはいえ周の封建制度の復活を構想しても、それほど奇異なことではないともいえる。それを秦王政は拒否し、あくまでも秦の国内支配で成果をあげていた領域支配を全域にわたり貫徹する意志を曲げなかった。ここに、中央政府による直接支配へのこだわりと、何事にせよダブルスタンダードは認めず、一度立てた方針は徹底して行うという、秦王政の姿勢が確認できる。これは始皇帝となってからも引き継がれることはいうまでもない。 *** このような始皇帝の直接支配へのこだわりが、同族血縁者への権力移譲を妨げ、皇太子の選定という帝国継承における最重要の課題を先延ばしにすることにつながった、と阪倉篤秀氏は指摘する。 現代社会においても、そのリーダーシップが強過ぎるために、なかなか後継者を選べないワンマン経営者がいる。後継者を選ぶ難しさ、権力継承の厄介さは、始皇帝の生きた時代と本質的には変わらないのかもしれない。 ※本記事は、阪倉篤秀『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』(新潮選書)の一部を再編集して作成。 デイリー新潮編集部