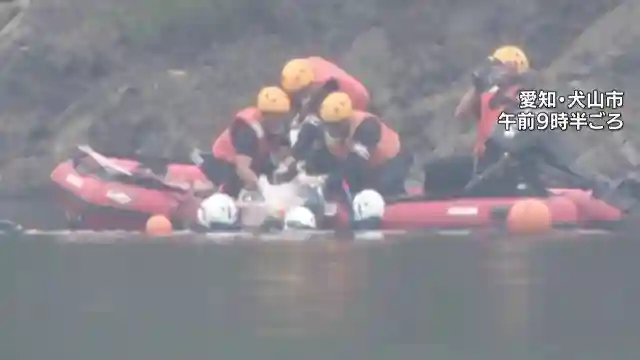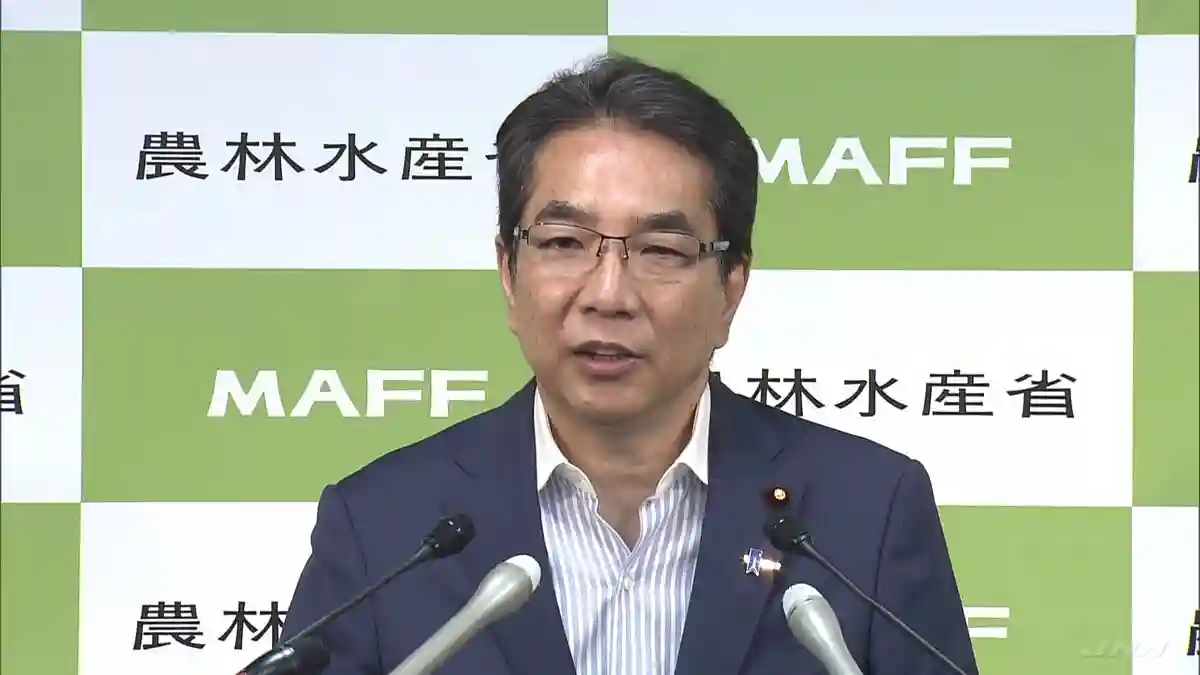絶対的な権力者、始皇帝。彼が築き上げた秦帝国は、中国史上初の統一王朝として燦然(さんぜん)と中国史に輝いている。しかし、その栄光はたった2代で途絶える。なぜだろうか? 【写真を見る】「始皇帝の長男」を自害に追いやった“偽造された遺書”に書かれていたこと 始皇帝の犯した失敗の一つが、生前に後継ぎを決めなかったことである。始皇帝が永遠の生を求めて、後継者指名を先送りにした結果、彼の死後に愚鈍な末子が二世皇帝となってしまったのだ。 では、もう一つの失敗とは何だろうか。中国史家で関西学院大学名誉教授の阪倉篤秀氏は、新刊『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』(新潮選書)の中で、宦官への対応に問題があったことを指摘している。以下、同書から一部を再編集して紹介する。 始皇帝 (出典:Public domain) *** 「天に二日なく、地に二君なし」 始皇帝の自己顕示はその行動にも現れ、強い長生願望のもと不老不死の薬を求めた。生への執着でありそれほど特異なことではないが、彼の場合は権力独占への執着であり、それが後継指名を遅らせることにつながったといえる。「天に二日なく、地に二君なし」で、太陽は一つしかないように、地上に君主たるものは一人で十分で、それに近い存在さえ否定される。自分が生きておれば後継者など必要ないのである。 いくら長生を願い、そのための努力を続けたとはいえ、人の死を知らなかったはずもない。しかし彼には自負があった。不愉快な噂話に心折れ悲観に沈むことがあっても不思議ではない状態で、「過去は問わない。すべては自分から始まり、今を生き、未来に向かうだけのこと」と、過去を切り捨て、苦難を乗り越え、これまでになかった地平を切り開いてきた。 始皇帝陵兵馬俑坑 そんな自分だから、人並みな寿命とは無縁で、死は遠い先のこと、なにより今を生きることに強く傾斜することで、彼なりの心の平安を得ていた。だからこそ、自身の死が前提となる後継者の指名は、先送りにされた。 秘匿された絶対権力者の死 とはいえ、彼にも死がやってくる日がきた。それが全国の各地を巡り、一般民衆のみならず、自己の命令を受けて職務を遂行する地方の官僚たちにも、目にしたこともないその命令者の偉大さと尊厳を見せつけるという、自己顕示を象徴する巡幸のさなかに起こったことは、いささか皮肉なことといえる。 秦系図(関係者を含む) (画像は『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』より) だが、側近として仕え、始皇帝の権威を笠に着て自己の権力を遂行してきた李斯(りし)や趙高(ちょうこう)にとっては、自身の保身を含めて王朝の存続を図らねばならない一大事を迎えたことになる。彼らには、始皇帝の厳格な支配が民衆のみならず、官僚たちにも重荷となり、反発が起こってもおかしくない状況にあるという認識があった。だからこそ、まずはその死を秘匿し、生きているかのように装って巡幸を続け、咸陽(かんよう)に帰り着いた。 この段階で、ようやく始皇帝の死亡を公表して驪山陵(りざんりょう)に埋葬し、その意向に従うという体裁を整えて遺書を偽造し、末子である胡亥(こがい)を後継皇帝として即位させた。始皇帝の死から2カ月後のことになる。この2カ月は、始皇帝の死を契機に起こりかねない反発の動きを未然に防ぐために費やされたと考えられる。 【「二代目で傾き、三代目が潰す」を回避するための鉄則とは?】中華の絶対権力者であると同時に、一人の親でもある皇帝にとって、皇太子の選定は王朝存亡を賭けた最重要課題であった。強烈な個性を押し通した先代と比較されて苦しむ二代目、甘やかされる三代目など、皇位継承に見られる構造的な困難を乗り越える秘訣を、秦の始皇帝から清の康熙帝まで歴代14人の事例から明らかにする 『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』 始皇帝の失態 即位した胡亥は二世皇帝と呼ばれるが、兄弟を幽閉、自殺の強要、そして処刑と様々な手を使い、さらに始皇帝時代の旧臣をも排除し、政権の安定を図った。ただこれは趙高が主導したもので、自身の権力を擁護し強化するためであった。 そしてなにより胡亥は趙高の期待に違わず愚鈍であった。趙高が鹿を馬と言いくるめる話も有名だが、彼の「すでに天下に君臨している自分としては、耳や目の好むところ、心や気分の楽しむものを究めて、我が人生を終えてもいいのではないか」との発言は、自らが皇帝であるという自覚がないことはいうにおよばず、積極的に手に入れた地位ではないにせよ、責任ある立場の人間の言葉なのかと耳を疑いたくなるほどである。 この趙高主導の動きを阻止しようとした李斯は、趙高によって逆に追い込まれ、拷問のあとに処刑されて果てる。学問を修め、その力をもって始皇帝に仕えて地位を得た李斯と、父の咎(とが)から少年時代に去勢刑にあって宮中に入るという逆境にありながらも、法律学を修めて上昇の機会をうかがい、はたせるかな始皇帝の認めるところとなった趙高とでは、権力抗争においてはおよそ勝負にならなかったのである。 宦官の主導するこのような王朝が存続するはずもない。そもそも宦官とは裏の存在である。商周以降すでに、大家を構える一族では、主人の血統の乱れを避けるため、去勢された人間を家事の男手として抱える風習があり、それが王朝に持ち込まれると、宦官という名称で呼ばれて宮中で使役された。 あくまでも宮中奥向き(後宮〈こうきゅう〉)での雑務の男手を確保するためで、裏の存在であることに変わりはない。それなのに趙高は表舞台に姿を現し、あろうことか権力の中枢に自らを位置づけるまでになった。文楽における人形使いの黒子が、堂々とその黒衣を脱ぎ捨てたようなものである。 誤った宦官への対応 宦官の特性は、主君への絶対的忠誠にある。だからこそ絶対的権力者を目指す始皇帝にとって、宦官の趙高はそれなりに利用価値があった。だが自身の死後に、趙高のような人物が残ればどのような事態が生じるか、予測できないわけはない。とするならば趙高への対応は、後継指名を遅らせたことと並ぶ、自身の死を遠ざけ続けた始皇帝の失態ということになる。 始皇帝の死によって上からの強い圧力がなくなると、それまでの規律は一気に失われる。内の趙高の専横に加えて、外では各地で動乱の兆しが現れ、陳勝(ちんしょう)・呉広(ごこう)の乱を皮切りにして秦末の大乱となる。次なる時代に向けて各地で抗争が広がるなか、まずは項羽(こうう)が、そして後進勢力として台頭した劉邦(りゅうほう)が覇権を握ることになる。 そして秦はといえば、劉邦の関中(かんちゅう)突入を受けて危機に陥った趙高は、胡亥を位から引きずり下ろして自害に追い込み、あらたに始皇帝の孫にあたる子嬰(しえい)を擁立したが、その子嬰の裏切りにあって、彼および一族は皆殺しの刑となった。こののちに子嬰は劉邦に投降し、秦王朝の時代は幕を閉じた。子嬰は皇帝とは認められないから、胡亥の退位によって皇帝称号はたった2代で消滅したということになる。 ※本記事は、阪倉篤秀著『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』(新潮選書)の一部を再編集して作成したものです。 デイリー新潮編集部