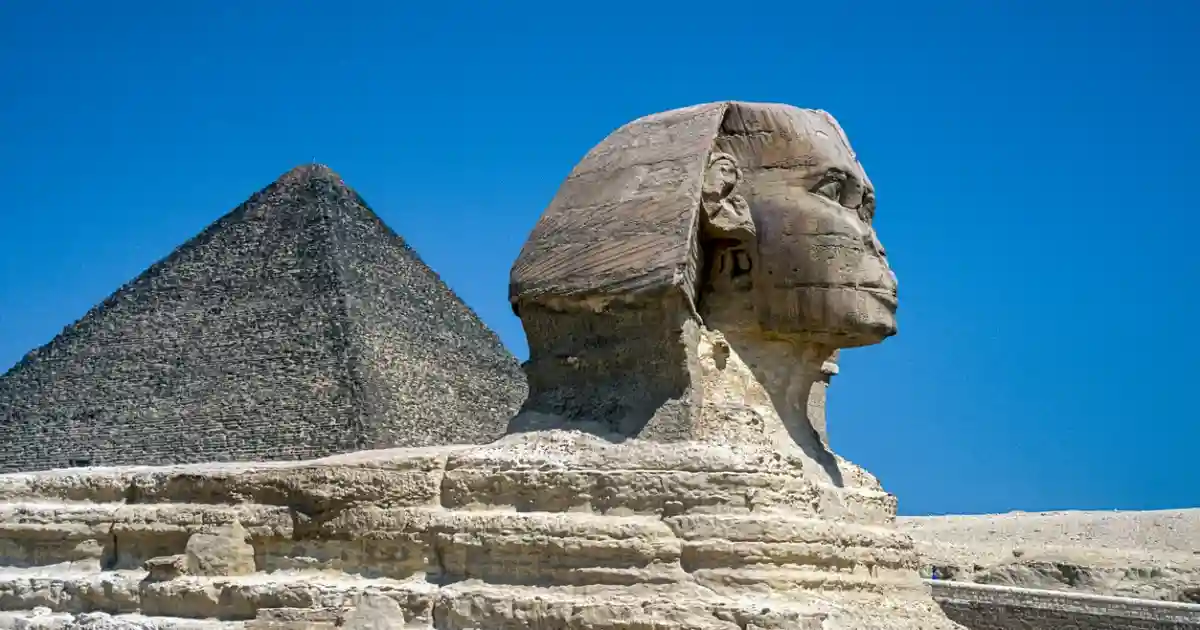
遠い地域の文化がなぜ似ているのか、これは文化人類学における一つの究極的な謎である。百年以上にわたり、文化人類学者たちは諸地域の文化を記述し、それらの間にある構造的なパターンを見出してきた。筆者は、よく似た文化が生まれるのは、人間が社会を作る限りにおいていつでも成り立つ、「文化を生む仕組み」があるからだと考えている。本連載では、数理モデルのシミュレーションによって、人間文化に普遍的な構造を生む仕組みを探求する普遍人類学の試みを紹介する。 贈与によって変化する格差の度合い バレンタインデーにチョコを貰えばホワイトデーにお返しをする。結婚式のご祝儀や葬式の香典には返礼品を贈る。このような贈与とそれへのお返しは、対等な社会的つながりを強めるのに役立っている。 一方で、飲みの席などでいつも奢ってくれる人は敬意を集める。お返しを伴わない贈与は与え手の名声を高めるのである。 これまで6回にわたり紹介してきたが、こうしたやりとりは人間社会に一般的に存在する。文化人類学では、特に貨幣経済が普及していない社会において、こうした贈与が大規模かつ儀式的に行われる「競覇的な贈与」(利子をつけてお返しができないと、周りからの評価が下がるような贈与)によって、名声の覇権争いが起きることが知られている。 この「競覇的な贈与」を数理モデルでシミュレーションした結果、贈与の頻度とお返しをするときに求められる利子率というパラメータによって、社会内での富と名声の格差の程度が変わることが明らかになった。 すなわち、 〇贈与の頻度が少なく、お返しの利子率も小さいと、格差は生まれない。 〇贈与が頻繁かつ大きな利率を伴ってに行われるにつれて、まず富の格差が生まれる。 ○贈与の頻度や利率が増大すると、続いて名声(身分)の格差が発生する。 〇そしてさらに贈与が盛んになると、名声の格差はただ一人を除いて縮小して、名声が絶大な一人とその他の人々に分かれる。 のである。 本記事では、これらの格差の程度と変化の視点から、社会構造をいくつかのタイプに分類する。そして、贈与に駆動されて社会構造が変化するという新しい歴史観を提示する。 社会構造の4分類と特徴 人類学や考古学では、社会構造の分類としていくつかのタイプが提案されている。エルマン・サービスの『未開の社会形態』(1979年)によれば、社会構造の典型的なタイプとして以下の4つがある。 一つ目はバンドである。バンドは主に血縁関係に基づいて組織され、富も身分の格差はほぼ存在しない。 二つ目は部族である(*)。部族は血縁関係にない多くの人を統合する社会組織であり、擬似的な親族関係(例えば「太陽の子孫」という信念のもとに統合される集団)や社会結社(例えば戦士集団とその家族)のようなアイデンティティによってまとまっている。部族には富の格差は見られるが、身分の格差はわずかである。 三つ目は首長制社会である。富の格差は部族よりも著しく、首長、エリート、一般民衆という身分の階層が存在する。 四つ目は国家である。国家は法と官僚機構により組織される。 また、その後の研究で、首長制社会と国家の間に、王国というタイプを加えることが提案されている。首長制社会における、首長、エリート、民衆という階層と同様に、王国にも王族、エリート、一般民衆という身分の階層が存在する。しかし、首長制社会においては首長は他のエリートよりわずかに優位であるのに対し、王族は他のエリートよりも圧倒的に優位であり、王族は首長の場合よりも長い世代にわたってその地位が安定している。 *ただし、「部族(tribe)」という語は、植民地主義的文脈で非西洋社会を一括して分類する際に多用された経緯から、現代では使用を避ける傾向がある。この記事では、あくまでエルマン・サービスによる分類を紹介する目的でこの語を限定的に用いる。 *もちろん、すべての社会がこれらの分類のどれかに必ず帰されるわけではなく、あくまで典型的な社会のタイプを場合分けしたものである。しかし、この枠組みは示唆に富んでいる。例えば富の格差はあるけれど身分の格差は存在しない例(部族)は頻繁に見られるが、富の格差がなくて身分の格差だけが存在する例は稀であることを教えてくれる。 これまでに、社会構造の違いは人口規模や社会の豊かさ、そして戦争の頻度などと関係づけて議論されてきた。しかし、どのような仕組みで社会がこれらの間を移り変わるのかは知られていなかった。 贈与の程度によって社会構造が変化する 競覇的な贈与の数理モデルにおいては、贈与が頻繁に交換され、かつ利子率が高くなるにつれて、(1)富と名声の格差がない状態から、(2)富の格差だけがある状態、(3)富と名声の格差がある状態、(4)富の格差は著しいが名声の格差が抑えられた状態の間を移り変わることがわかった。 (図1)贈与によって駆動される社会変化。モデル上で生まれたバンド、部族、首長制社会、王国について富(黒)と名声(赤)の格差の程度(ジニ係数)を計算した。 実は、このモデルで明らかになった社会の四つの状態は先ほどの4つの社会構造(バンド、部族、首長制社会、王国)の分類に対応している(図1)。 ポイントは、贈与が頻繁に交換され、かつ利子率が高くなるにつれて、富の格差は単調に増大しているが、身分の格差は首長制社会で最大になり、王国ではその格差が抑えられていることである。 ここで前提知識として、前回までの記事で解説した「分布」という概念について簡単に補足する。分布とは、数量の値と頻度の関係(例えば年収がいくらの人が全体の何%であるかという関係)を示すものであり、それを図示したものが分布の形状である。分布の形状として代表的なものは「指数分布」と「べき分布」である。 これらは異なるメカニズムで生まれ、格差の程度によって異なる。指数分布とはランダムなやりとりの結果として生まれるもので、格差はあったとしても小さい。一方、べき分布とは「富める者ほどますます富む」仕組みによって生まれるもので、平均的な人の何倍も豊かな人がいる、格差が大きな状況に対応する。 まず、贈与が稀である場合には、富と名声は指数分布に従う。つまり、贈与がまれにしか起こらずお返しのために必要な利率も小さい状態は富や身分の格差がない「バンド」に対応する。 贈与の頻度やお返しの利率を大きくしていくと、まず富の分布がべき分布に変わる。ここでは富の格差はあるが名声(身分)の格差は存在しない。これは「部族」に対応する。 贈与がさらに頻繁かつ大規模になると、名声の格差もべき分布になる。これは社会が階層的に組織されることを意味しており、「首長制社会」に対応する。 最後に、贈与が極めて頻繁にかつ利率も大きくなると、名声の分布は一人を除いて指数分布に戻る。これは抜群に栄えている王様により、他の人々の活動が抑制されて、王族の地位が安定している状態、すなわち「王国」に対応する。 以上のことから、競覇的な贈与の数理モデルにおいて、社会が贈与に駆動されて、異なるタイプの社会構造の間を移り変わることがわかった。このことは、贈与という個人レベルのやり取りと集団レベルの社会構造の間に、深い関係があることを示している。 さらに、実際の社会についてのデータベースを用いて、「贈与の規模や頻度」と「富や身分の格差の程度」の関係を調べると、その結果はモデルと整合的であった。つまり、人類史のデータは確かに贈与が盛んになるにつれて、まず富の格差が生まれ、そのあとで身分の格差が生まれることを示していたのである。 数理解析から示唆される、人類史の新しいシナリオ ここから次のような「贈与に駆動された社会変化」という人類史のシナリオを提示したい。 そもそも、安定的に贈与を行うためには長期間保管できる装飾品や食料が必要である。しかし、そうした交換のための財がない社会も人類史上には多く存在した。 それでも、贈与が引き起こす社会変化とそっくりの社会変化をひき起こすものが人類史上に普遍的に見られる。それは「結婚」である。 文化人類学者のレヴィ=ストロースは、結婚によってパートナーたちの親族の間に、義理の親族の関係が生まれることに注目した。パプア・ニューギニア近くのトロブリアンド諸島の社会では、収穫したタロイモのほとんどを姉妹や姪とその夫たちに贈るという習慣がある。これは自分の姉妹や姪が生活上受けている恩への返礼としての贈与である。また、他の地域では逆に男性が自分の妻の両親に定期的に贈り物をする場合もある(レヴィ=ストロース『親族の基本構造』2000年)。 つまり、結婚によって、あたかも一方が他方の親族集団に贈与をしたかのように、返礼の義務が発生しているというわけだ。この意味で、結婚は贈与と同じような社会変化を引き起こすのである(*)。 ここで、結婚によってつながりを得る回数はおおよそ、自分が持つ兄弟姉妹の人数と等しいので、人生の中でさほど高頻度で起こるものではない。今のモデルを踏まえると、「結婚」という頻度が小さい「贈与」しか存在しない場合、生まれる社会構造は「バンド」である。 (*古くは結婚を「女の交換」と言うことがあったが、現在ではこのような表現はしない。結婚を贈与のようなものとみなすということは、「人間をモノのように贈与する」という意味ではなく、あくまで「結婚後に義理の親族間に生じる社会関係が、贈与のやりとりの後に生じるものに似ている」という意味である。) その後、農耕が行われたり、狩猟によって毛皮を得るようになったり、あるいはヒスイや黒曜石のような希少品が得られるようになったりして、長期間の保管や長距離の輸送ができるような富が広まると、贈与のやりとりは増える。頻繁になった贈与は格差をもたらし、それによって社会構造は部族や首長制社会、そして王国へと変わっていく。 実際、多くの古代文明において、権力者の墓には希少品が副葬されるのが常である。今までは、権力者が富を誇示するために希少品を集めたと考えられてきた。 一方、ここで提案しているのはそうした希少品の流通が贈与の相互作用を加速させ、権力者を産んだのだという歴史観だ。言い換えると、単に余剰生産物によって非労働者を養えるようになるから分業が進んだというのではなく、余剰生産物によって促される贈与の相互作用こそが、権力者と労働者の分業=格差を生むメカニズムなのだと考える歴史観である。 一つ注意が必要なのは、こうした社会変化は必ずしも一方向的とは限らなく、優劣を決めるものではないということだ。一般的な傾向として、人口密度が増えたり社会が経済的に豊かになったりすれば、贈与の相互作用は頻繁かつ大規模になり、社会の階層化をもたらすと考えられる。 しかし、人類史上において、人口密度が下がるような変化(気候変動や疫病、あるいは移住にともなう環境変化など)は多く存在する。その意味で、バンドや部族は「遅れている」わけでは決してないし、彼らの社会組織がいずれ首長制社会や王国になる必然性もない。 ここで主張しているのは、社会構造が贈与の頻度と返礼の利率というパラメータに依存しているということだ。人類史の変化をこれらのパラメータの変化とみなせば、それが増大しているときも減少しているときも、長期にわたって一定であるときもあり、そのパラメータの変化に応じて社会構造も変化するということだ。 普遍人類学ではこのように、文化人類学の観察事実と数理モデルの解析結果を組み合わせて、人類史上の社会変化を説明するシナリオを提案している。 その取り組みにおいてはまず、人間社会に一般的に観察される対人関係を数理モデルで表現し、シミュレーションを通じて、さまざまなパラメータのもとで何が起きるかを調べる。そして、異なる社会構造がいかなる仕組みで、どのようなパラメータのもとで生まれるかを明らかにすることで、人類史を説明するためのシナリオが得られるのである。 もちろん、今の結果だけからただちに実際の歴史の変化が贈与に必ず駆動されている、と主張することはできない。他のメカニズムによって社会構造の変化のシナリオを提案することも可能だということには注意が必要である。人類史を説明する理論を得るために我々がなすべきことは、そうしたシナリオの候補をたくさん提案して、データを元にどれが現実によく当てはまっているかを比較することで、最も確からしいシナリオに迫ることである。 今回筆者が紹介したのはあくまで可能なシナリオの一つである。他のシナリオの候補を検討すること、そして更なる検証によって理論を洗練していくことは今後の普遍人類学の課題である。 【もっと読む】人類が普遍的に行う「贈与」が「富と名声の格差」をうむ…その衝撃のシミュレーション









