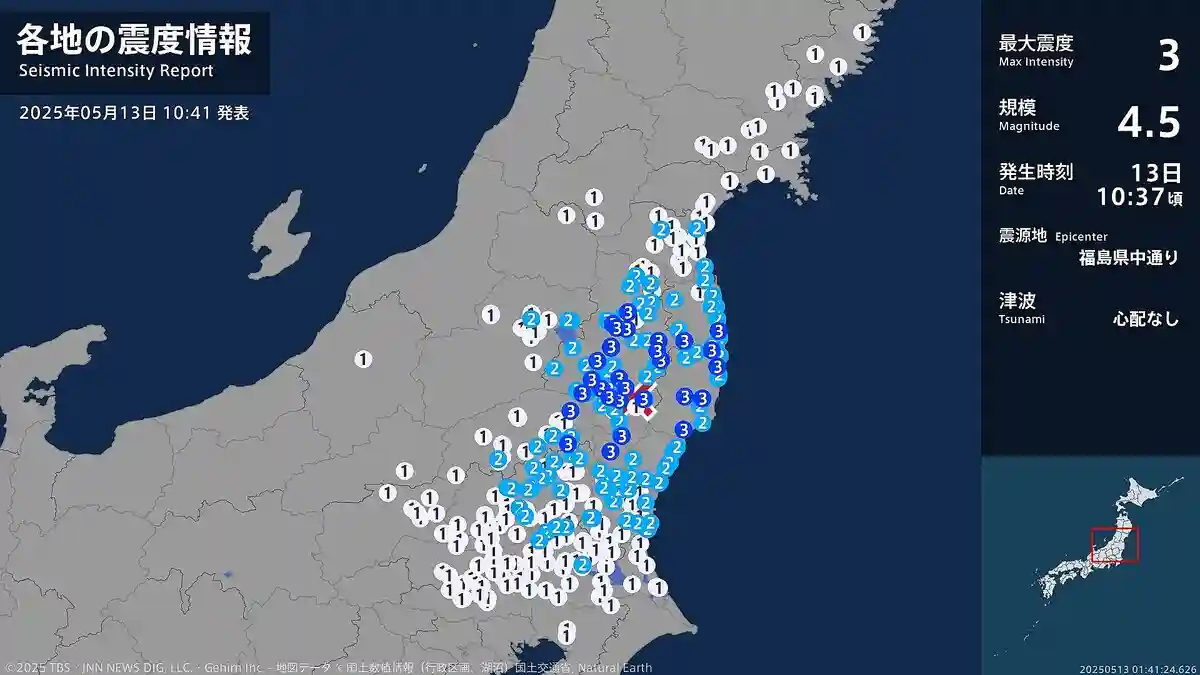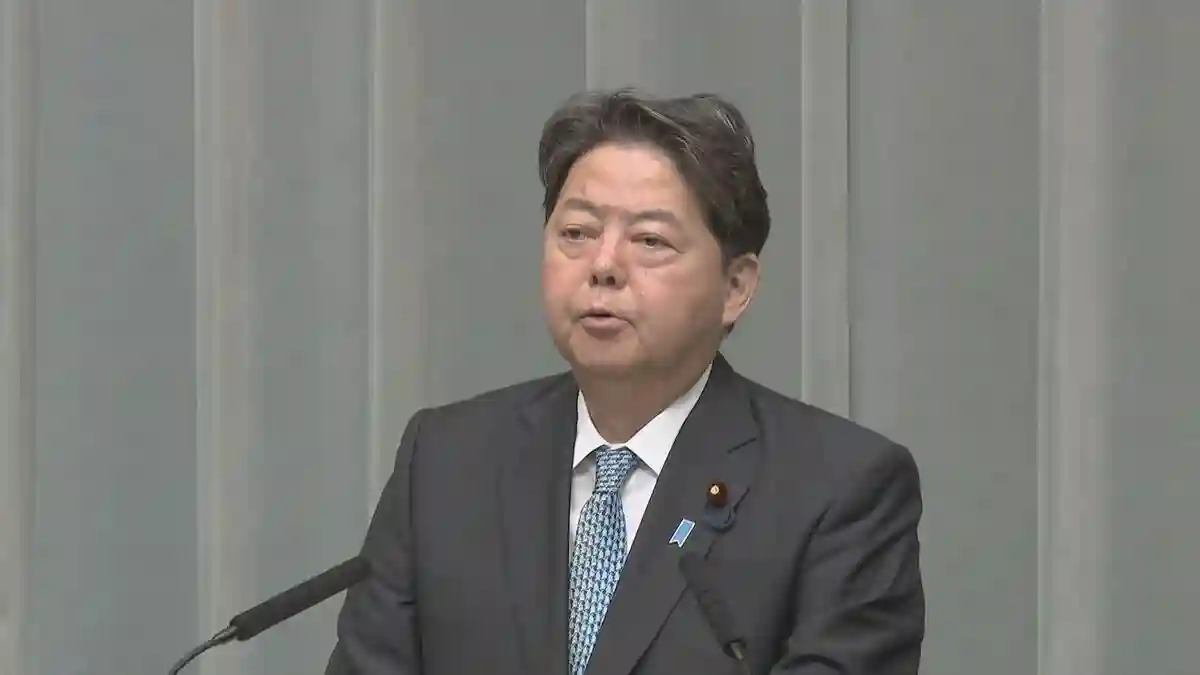個人投資家への株主還元を強化する企業に注目したい。東京証券取引所(東証)は、株式投資の最低金額を10万円程度まで引き下げるよう、全上場企業に要請した。背景には、新NISA(少額投資非課税制度)の普及による個人の投資熱の高まりと、それでもなお高いとされる日本株の投資ハードルの存在がある。 2024年に新NISAが始まって以降、証券口座数は3割以上増加した。新たな投資家層の流入も目立つが、人気の投資先は日本株ではなく、海外株や指数連動型の投信が中心だ。背景のひとつには、海外株の方が「お手頃感覚で買える」ことも大きい。たとえば米国株は1株から購入可能なのに対し、日本株は基本100株単位で売買される。東証プライム市場の最低投資金額の中央値は約20万円と、米国の約10倍も敷居が高い状況だ。 こうしたギャップを埋めるための有力な手段が「株式分割」だ。たとえば100株を10分割した場合、株数は1,000株に増えるが、1株あたりの株価は10分の1へ下がる。資産価値は変わらずとも、必要となる最低投資金額が下がれば投資家への間口は広がる。 代表的な成功例がNTT〈9432〉だ。2023年7月に1株を25株に分割した同社株の株主数は、2025年3月期末で約268万人と分割前の約3倍へ拡大した。とりわけ40代未満の若年層の増加が目立つことが目を引く。 東証の狙い通りに多くの上場企業の投資金額が下がれば、これまで日本株を敬遠していた投資家層を呼び戻すきっかけになるかもしれない。肝心なのはその後だ。新たな株主の期待に応えられる魅力を持つことが、株価の明暗を分けるポイントとなるだろう。個人投資家に寄り添える企業には多くの注目が集まりそうだ。 セブン&アイ(3382) ■株価(5月9日時点終値)2244円 2030年度までに総額2兆円という巨額の自社株買いを計画しており、第一弾として2025年4月から2026年2月にかけて6000億円規模の自己株取得を実施する。取得株数は発行済株式総数の15.4%に相当する大規模なものだ。株主還元の原資として、北米コンビニ事業を手掛ける完全子会社の米セブン—イレブン・インクを2026年後半までに米国で新規株式公開(IPO)する計画も明らかにしている。 株主優待制度も充実している。グループ内で使える2000円分以上の商品券を交付する。3年以上の株式保有者にはさらに500円分を上乗せする長期保有者向け特典もある。同社が株主還元の強化に躍起になっている背景には、カナダの同業アリマンタシォン・クシュタールからの買収提案への対抗という側面がある。 国内外のコンビニ事業はインフレの影響を受けて低調だが、2026年2月期は構造改革効果により業績の回復トレンドへ向かうと予想される。新CEOにスティーブン・ヘイズ・デイカス氏を起用し、経営体制も刷新した。株主還元と成長投資の両立を図り、自社単独路線を鮮明にする戦略だ。 味の素(2802) ■株価(5月9日時点終値)3238円 2026年3月期の連結純利益は前期比71%増の1200億円となり、3年ぶりに過去最高益を更新する見込みだ。生成AI向け半導体の電子材料が牽引役となるほか、主力の調味料・食品事業も堅調に推移している。好調な業績を背景に株主還元策も強化している。発行済み株式総数(自社株を除く)の5.03%にあたる5000万株を上限(最大1000億円)とする自社株買いを実施し、取得株式はすべて消却する方針だ。4月に実施した株式分割を考慮すると実質8円の増配も発表している。 会社側は「引き続き積極的、機動的に株主還元を実施していく」と述べている。2021年度に「ファン株主コミュニケーションタスクフォース」を立ち上げるなど、個人投資家との関係強化にも注力している。工場見学や新製品発表会など年15回のイベントを実施し、一時は減少していた個人株主の比率は回復傾向にある。 2024年11月には株主優待の拡充も発表し、個人投資家との長期的な関係構築を目指してきた。業績向上、株主還元、信頼構築という三位一体の戦略は、NISA時代における模範的な取り組みといえそうだ。 ドトール・日レス(3087) ■株価(5月9日時点終値)2707円 キャッシュリッチ企業の同社も株主還元策を一段と強化している。発行済み株式総数(自己株式除く)の約8%に相当する、最大50億円の自社株買いを実施すると発表した。配当も2025年2月期に前期比10円増の50円とし、従来計画より2円積み増している。さらに株数に応じて株主優待カード(100株以上の保有者には1,000円分)も贈呈される。 業績面では前期連結決算で純利益が過去最高を記録。2026年2月期の連結営業利益は106億円(前期比10.4%増)、年間配当は54円の見通しを示した。経営陣による株価向上への意欲も明確だ。長らく1.0倍近辺で推移してきたPBR(株価純資産倍率)を1.5倍へ、ROE(自己資本利益率)を6%から8%へ、PER(株価収益率)を15倍から23倍へと具体的な目標を掲げている。 主力のドトールコーヒーショップはコロナ禍後の環境変化を乗り越えつつある。コーヒー豆の国際相場高騰には東南アジアなどの新興産地開拓で対応を進めている。潤沢な現預金約350億円を積極活用し、新規出店やM&Aなどの成長投資にも振り向ける方針だ。 TOTO(5332) ■株価(5月9日時点終値)3786円 2026年3月期は、売上高が前期比4%増の7535億円、純利益は2.5倍の310億円を見込む。不動産市況の低迷を受けて懸案事項となっていた中国事業については、衛生陶器の製造2拠点を閉鎖し、リフォーム中心の戦略へ切り替える方針だ。株価は中国事業の悪化懸念から弱含んでいたが、抜本的な構造改革を発表したことで払拭が期待される。 一方、米国では差別化できるウォシュレット(温水洗浄便座)を拡販することで、前年比14%増収・営業13%増益の計画を打ち出している。米トランプ政権との関税交渉の行方は気がかりだが、決算説明資料では「米国の関税政策影響は発表日時点での発動分を計画に織り込み」としている。 株主還元策では、連結配当性向目標を40%以上に設定し、2025年5月から12月にかけて発行済株式総数の4.7%に相当する800万株・200億円を上限とする自己株取得を実施する。また、株主優待では100株以上保有の株主に対し、同社製品のほか「お米2キロ」など豊富な選択肢を設けている点は嬉しい。 JR東海(9022) ■株価(5月9日時点終値)3048円 2025年3月期決算と同時に発表された最大1000億円の自社株買いは、同社にとって初めての試みであり、発行済み株式の4.57%にあたる4500万株を上限に取得する意向を示している。2025年3月期はインバウンド(訪日外国人)の急増が追い風となり、運輸収入が前期比7%増の1兆4325億円と、6年ぶりに過去最高を更新した。 2026年3月期も人件費などのコスト増を見込むが、連結営業収益は前期比2%増の1兆8650億円と高い利益水準を維持する。長期的には国内人口の減少という課題が待ち受けるが、東海道新幹線では距離に応じた単一料金ではなく、サービスに見合った多様な価格設定を導入する方針を示すなど手札は豊富だ。 これまでリニア建設費に備えて内部留保を重視してきた同社だが、株主還元策の大幅強化に踏み切った背景には、1.0倍を大きく下回るPBR(株価純資産倍率)の低評価を改善させたい意図がある。リニア新幹線に関する工期延長や工事費見直しなどのリスクには留意すべきだが、キャッシュフロー創出力、健全な財務体質、電鉄株の株主優待などからみて株価指標の割安感は大きい。 株式分割や還元強化などの取り組みが、“NISA世代”と呼ばれる新たな投資家層の「最初の一歩」を後押しする時代が来ている。次のステージでは、個人投資家との距離を縮め、長く付き合える企業が主役となるかもしれない。 【マンガ】約20年前にマイクロソフト株を「100万円」買っていたら今いくら?