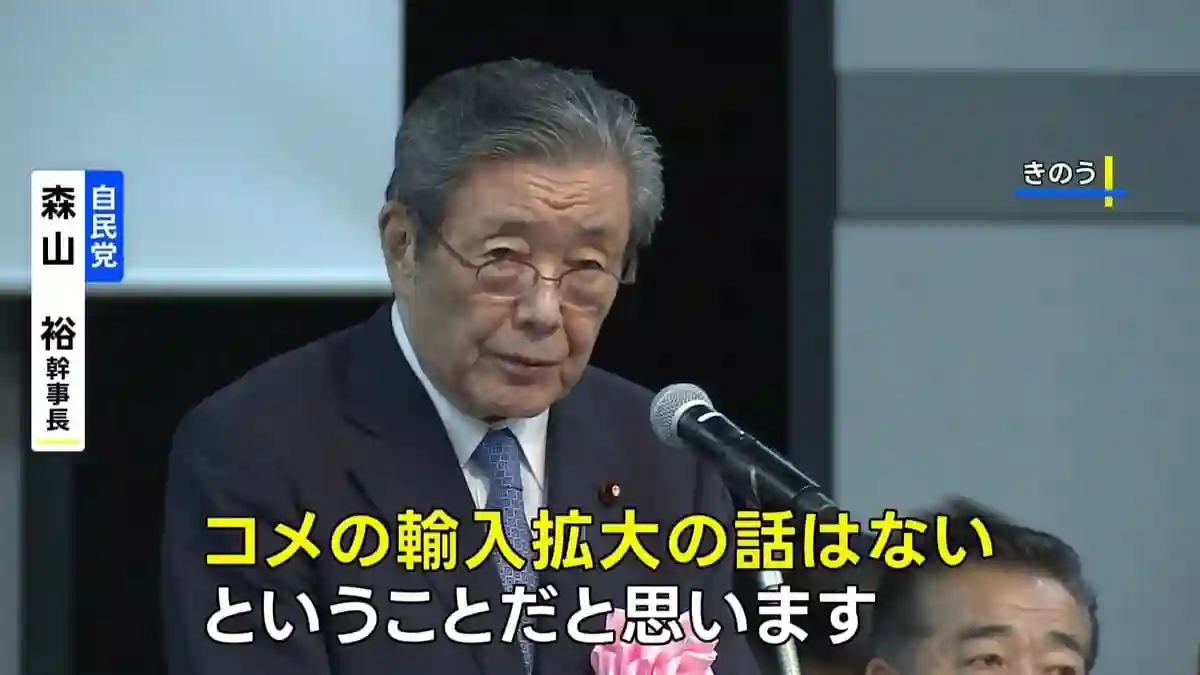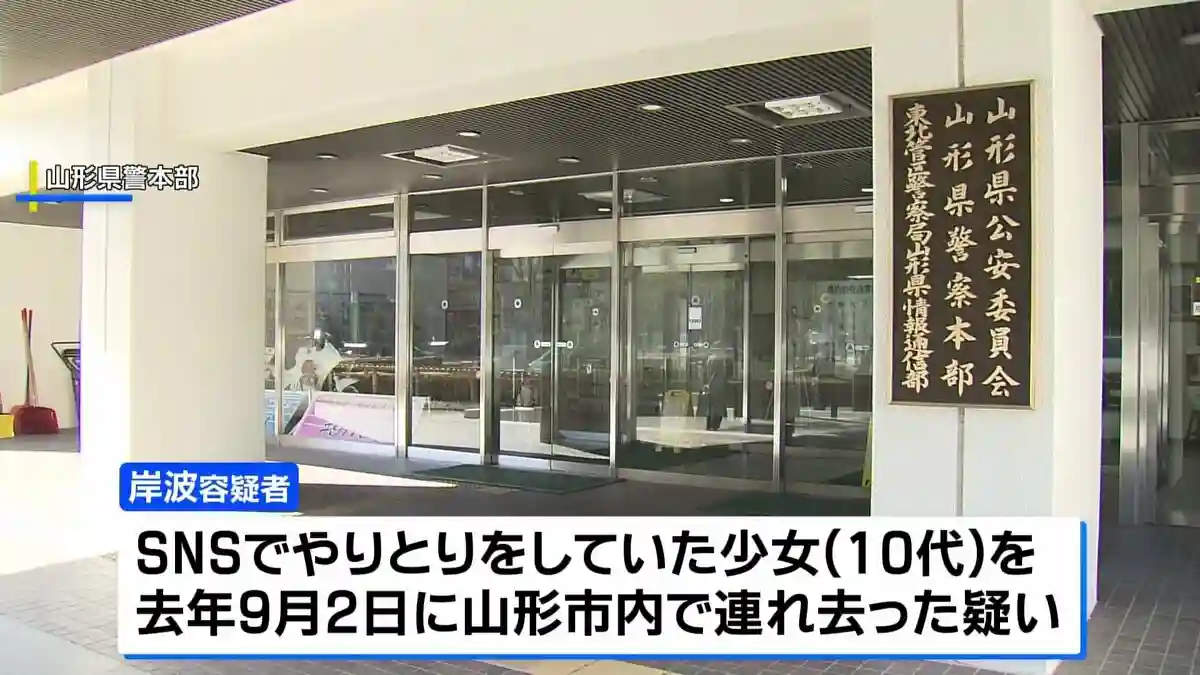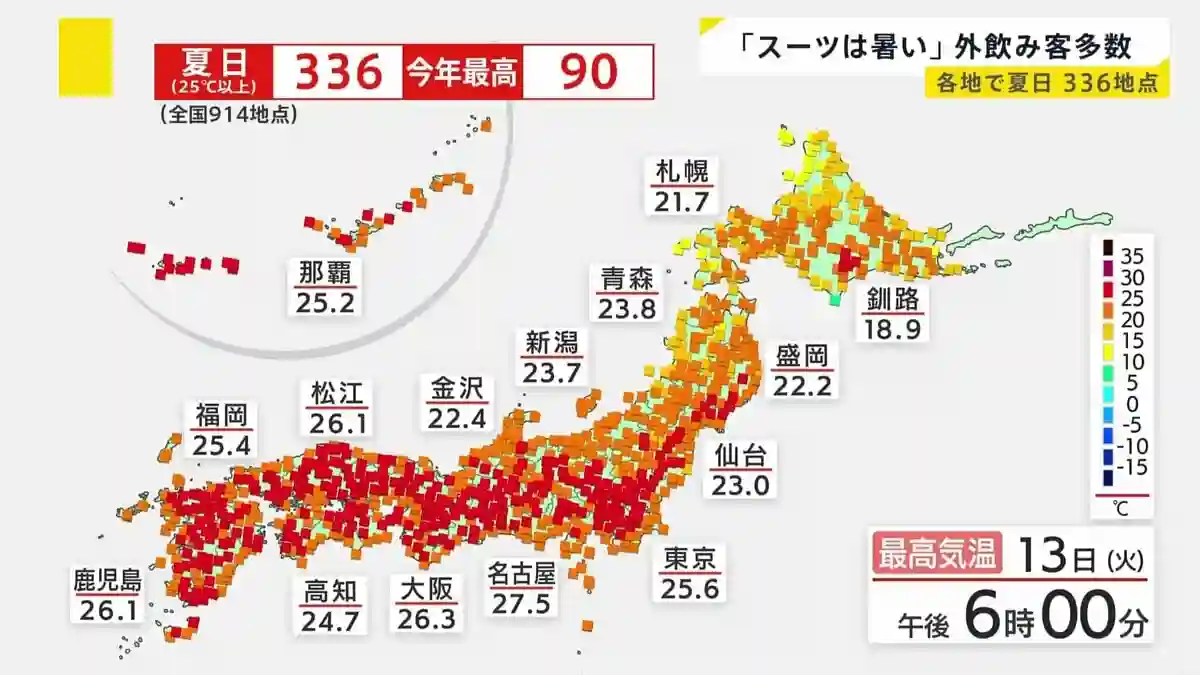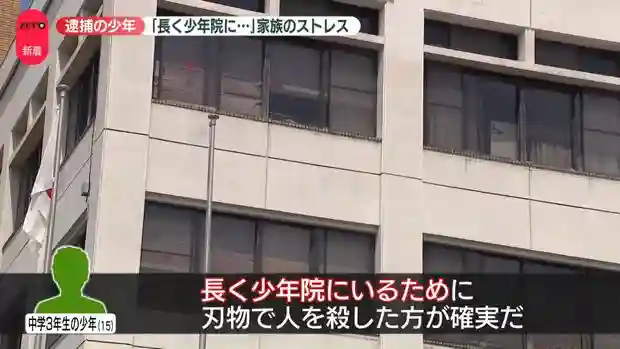一時よりは減ったとはいえ、唐揚げ専門店を街中で見かけることは珍しくなくなった。4月22日からはコンビニ最大手のセブン-イレブンも「若鶏のからあげ」を新発売することからも、まだまだ唐揚げの需要は根強そうだ。消費経済アナリストの渡辺広明氏が、唐揚げの「これまで」と「これから」に迫る。 *** 【写真】もはや日本の国民食…「セブン」と「吉野家」の唐揚げは生き残れるのか ゴールデンウィーク中、セブンの店頭には「ジューシーからあげ」の垂れ幕が掲げられ、テレビCMを見た人も多かったのではないだろうか。筆者も思わず買ってしまったが非常においしかった。ストレスのない状態で45日前後飼育された鶏を使ったこだわりの一品だそうで、もも・むねの2種類がラインナップされて280円(税抜き)。“巣ごもり”の休日を過ごした方にとっては、この唐揚げは連休のちょっとした楽しみになったのではないだろうか。 「唐揚げであれば売れる」時期は過ぎ…(写真はイメージ) 何度もブームを巻き起こしてきた唐揚げは、コンビニはもちろん、スーパーでも売上の主力商品となっている。たとえばイオンの「唐揚げ唐王」は、第16回からあげグランプリ東日本スーパー惣菜部門で2年連続の最高金賞を受賞。バナナや水、カツ丼といったライバル商品を抑えて2024年度には食品部門の単品売上でNo.1だというから驚きである。 唐揚げ専門店も増えているが、昨年12月には牛丼チェーンの吉野家が参戦。昨年12月に「から揚げ専門店 でいから」を神奈川県横浜市にオープンした。これも唐揚げ人気の高まりを象徴する出来事といえる。 和民の唐揚げ失速が意味すること 近年の唐揚げの盛り上がりは、2009年に「元祖中津からあげ もり山」と「とりあん」が、それぞれ大分県から東京に初進出したことに始まる。その後、同様の専門店が次々と首都圏に出店し、さらにコロナ禍で外食の機会が激減したことで、自炊疲れの人々が唐揚げ専門店を利用するようになった。結果、2012年に450店舗だった専門店は、2023年には約10倍の4,388店舗(日本唐揚協会調べ)にまで増加した。 すかいらーくグループは2014年に「から好し」を、かつやを展開するアークランドサービスは2017年に「からやま」に立ち上げており、コロナ禍は唐揚げ人気がさらに強固なものになったという時期といえる。 急激に店舗数を伸ばしたことで、その反動として閉店の動きも起こり「唐揚げブーム終焉」が報じられたこともあった。たとえば、和民とタレントのテリー伊藤が手がけた「から揚げの天才」。コロナ前の2018年に始動し、コロナ禍の波に乗りフランチャイズ展開を本格化させた同店は、2022年には120店舗以上にまで拡大した。だが競争の激化とテリー伊藤のメディア露出の減少も影響し、2025年2月現在では7店舗にまで縮小している。 外食ジャーナリストは、 「居酒屋業態をベースとする和民流の『タレの浅漬け』が外国産の肉臭さを解消できず、揚げてからスパイスやタレをかけて味を変化させるスタイルなので敏感な人には『肉が臭い』と受け入れられなかった」 との意見だ。つまり、唐揚げであればなんでも売れるという時期は過ぎ、美味しくなければ市場に残れない、消費者にとっては大変嬉しい状況になっているといえるだろう。 店長時代に数えきれないくらい「からあげクン」を揚げた 唐揚げを語るうえで避けて通れないのが、ローソンの「からあげクン」の存在だが、こちらは一般的な唐揚げとは一線を画す独自のジャンルを確立したといえるかもしれない。一口サイズに均一にカットしたむね肉を二段階で揚げるなど独自の製法を採用し、来年発売40周年を迎える。2024年12月時点で、累計44億食も食べられているという。これまでコラボを含め390種類以上のフレーバーが発売されていて、いつ店頭に行っても、常に新しい味が用意されているように思う。 筆者はかつてローソンで店長をしていたが、「からあげクン」は圧倒的な売れ筋で、何個揚げたかわからない。Uber Eatsをはじめとするクイックコマースにおいても、売上ベスト3はすべて「からあげクン」が占めていた時期もあったそうだ。今も昔も変わらぬ人気ぶりだ。 ついでながら、日本における鶏肉の消費をコンビニが支えていることに言及しておきたい。たとえば、骨なし、ジューシー、片手で食べられるといった特徴を持つファミリーマートの「ファミチキ」は、同店の看板商品だし、ローソンの「Lチキ」やセブンの「ななチキ」も若者を中心に人気を集め、鶏肉を日常的に食べる習慣を後押ししている。 「醤油味でもも肉」はひと段落 唐揚げの専門家は、今の人気ぶりをどう見ているのだろうか。 「唐揚げはおやつでもあり、おかずでもあり、つまみにもなる。外食・中食・内食のすべてに対応できる国民食だ」 とは、日本唐揚協会の八木宏一郎専務理事である。 「醤油味のもも肉をめぐる開発競争はひと段落し、今は“第二の定番”を模索する動きが活発化しています。最近は、『むね肉』を使ったジューシーな唐揚げを、醤油味や塩味で開発する企業が増えています。また、骨付きや希少部位にチャレンジした新商品も増え、部位のバリエーションが広がってきました」 実際、セブンでは「むね肉」を使った唐揚げも用意されているし、軟骨や手羽元といった部位を使った唐揚げも専門店で見られるようになってきた。味だけでなく、食感、希少性といった新たな価値軸が唐揚げには求められるようになっているのかもしれない。商品開発が極まり進化したことで、唐揚げは「何を選ぶか」が問われる時代へと進んでいる。 「唐揚げは日本食」 そしてもうひとつ、八木専務の「唐揚げは日本の国民食」という指摘は唐揚げの「これから」を考えるうえで興味深い。たしかに世界では、フライドチキンなど「揚げてから味付けする」または「衣に味をつける」スタイルの揚げ鶏は一般的だが、日本の唐揚げはそれらと異なる。鶏肉をタレに漬け込んでしっかり味を染み込ませてから揚げるという、日本らしいひと手間が加えられているのが特徴だ。 日本のたまごサンドがインバウンド客の間で人気を博したように、唐揚げが世界に“再発見”される日も遠くないだろう。日本式唐揚げを看板にした専門店の海外展開が進み、 “日本の国民食”が“世界の人気食”になるのは、案外近い未来かもしれない。 渡辺広明(わたなべ・ひろあき) 消費経済アナリスト、流通アナリスト、コンビニジャーナリスト。1967年静岡県浜松市生まれ。株式会社ローソンに22年間勤務し、店長、スーパーバイザー、バイヤーなどを経験。現在は商品開発・営業・マーケティング・顧問・コンサル業務などの活動の傍ら、全国で講演活動を行っている(依頼はやらまいかマーケティングまで)。フジテレビ「FNN Live News α」レギュラーコメンテーター、TOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」パーソナリティ。近著『ニッポン経済の問題を消費者目線で考えてみた』(フォレスト出版)。 デイリー新潮編集部