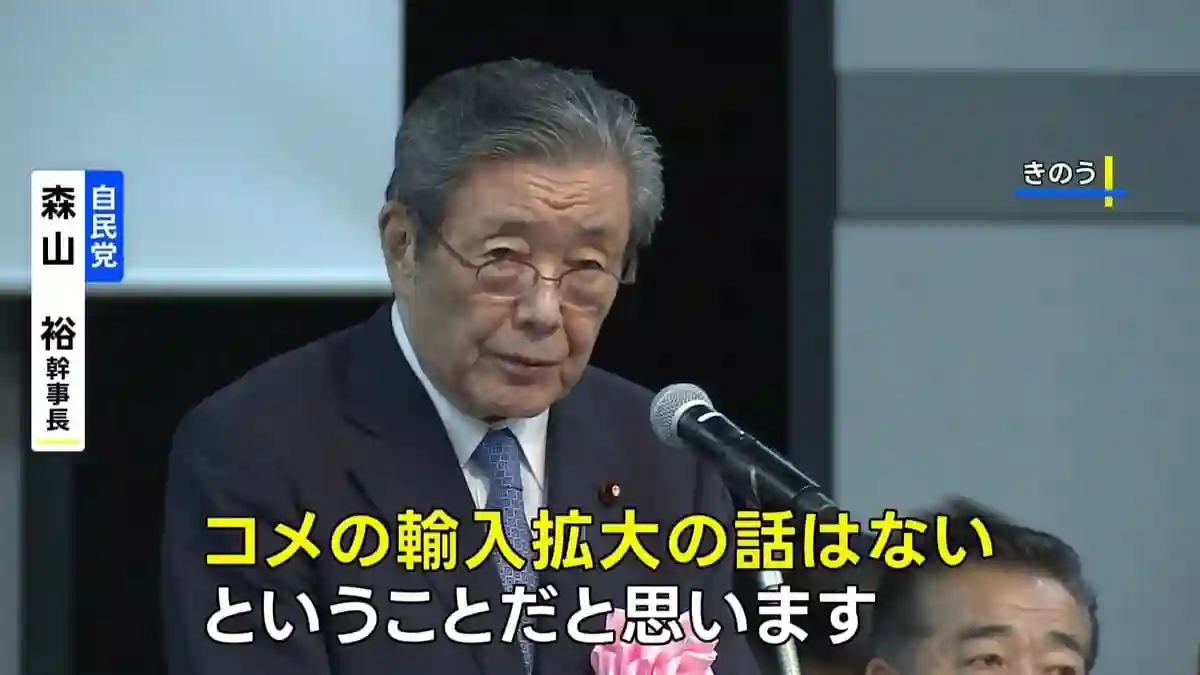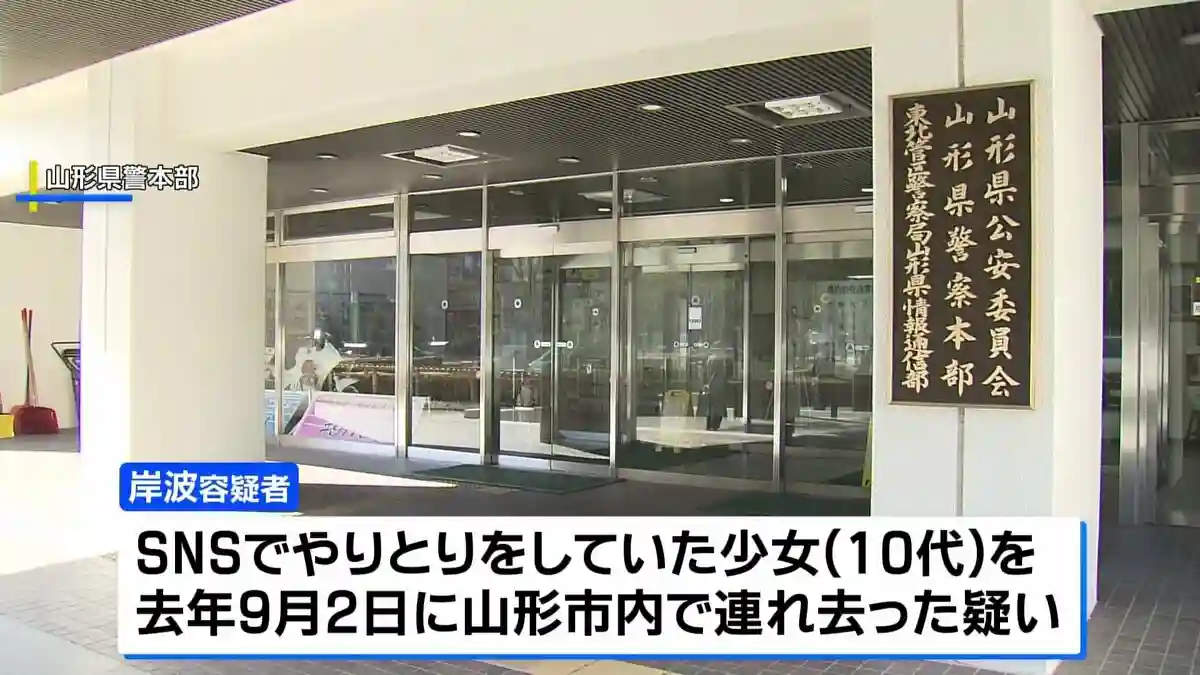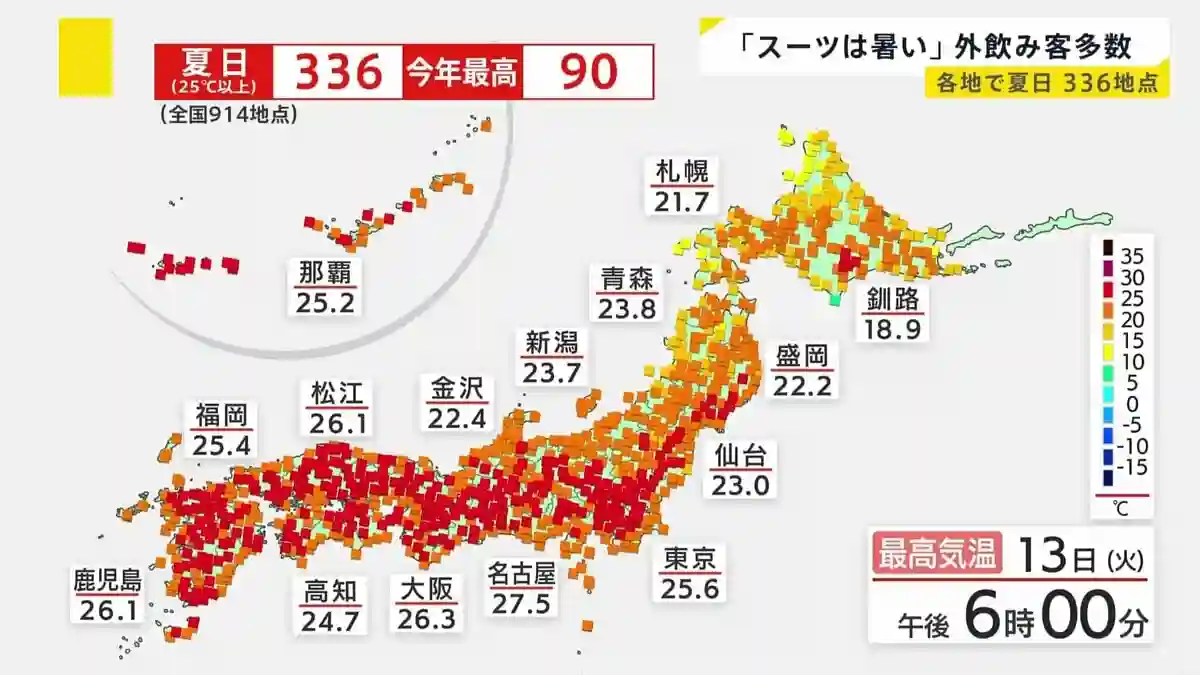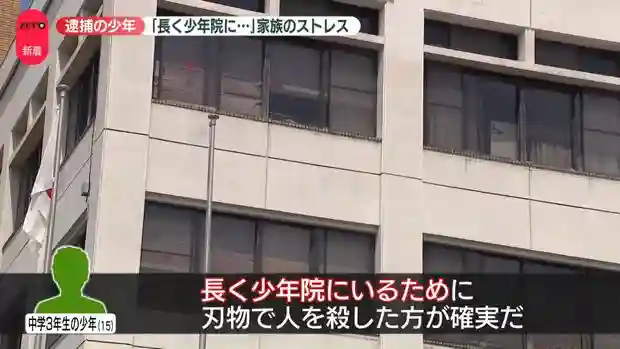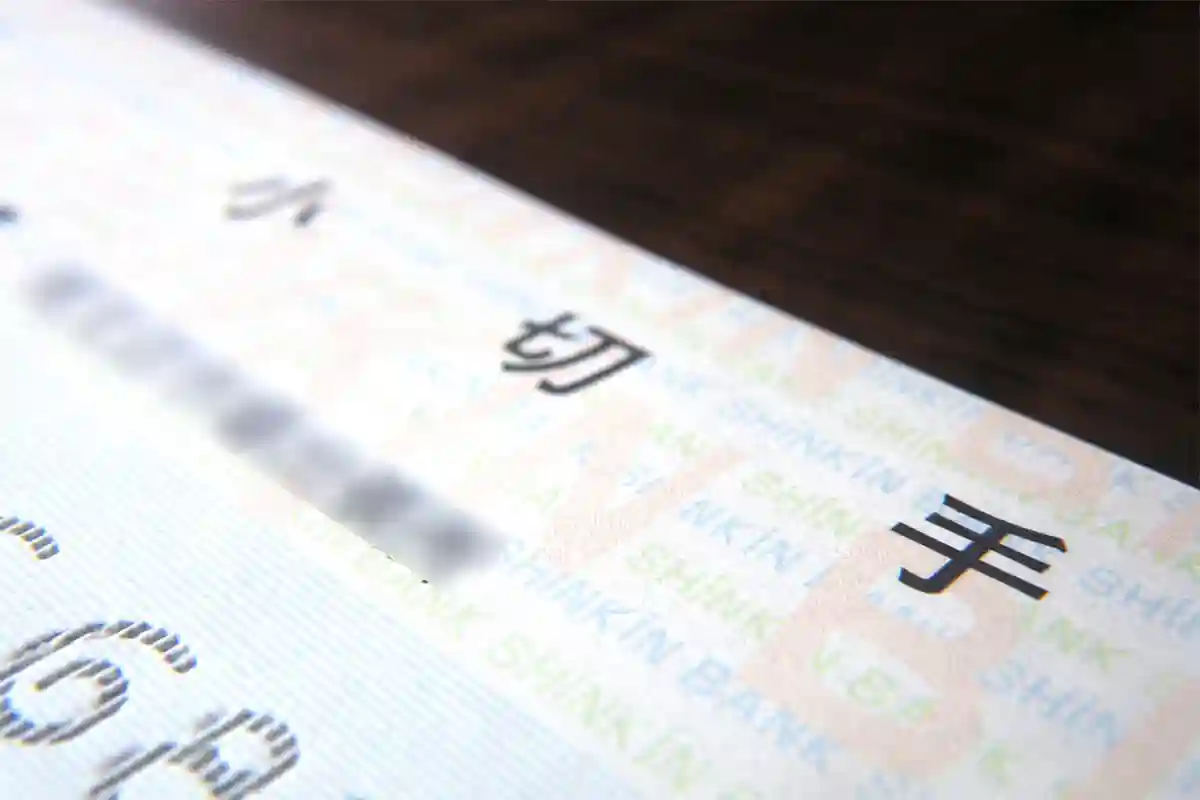
第1回【2026年度末で「手形」と「小切手」が廃止の衝撃…680億円の巨額“絵画取引”のウラで手形と小切手が飛び交った「イトマン事件」を振り返る】からの続き──。似た機能を持つ手形と小切手だが、詳細を見ると微妙に異なる。まず安心感が強いのは小切手のほうだろう。(全2回の第2回) *** 【写真】ともに住友銀行(現・(現・三井住友銀行)の頭取として、イトマン事件で闇勢力と対峙した、巽外夫氏(1923年〜2021年)と西川善文氏(1938年〜2020年) 銀行の当座預金に残高がなければ、小切手を振り出すことはできない建前だ。受け取る側も小切手なら即座に現金化することができる。 一方の手形は、支払い側の手元に資金がなくても振り出すことが可能。さらに支払いの期日が設定されており、受け取った側は現金化する場合は、期日を待つ必要がある。担当記者が言う。 姿を消す小切手(写真はイメージです) 「手形や小切手を使った決済で、最大のリスクは不渡りです。そして、よりリスクが高いのは、やはり資金が手元になくとも振り出せる手形でしょう。会社が6カ月以内に2回の不渡りを出すと実質上の倒産と見なされます。逆に手形を受け取った側が資金繰りに困っている場合もあります。期日を待つ余裕がない場合は手形を割り引きます。支払い期日の前でも金融機関などに手形を持ち込めば、金利や手数料などを引いた上で現金化してくれます。もちろん信用に不安があると、手形割引を拒否されるのは言うまでもありません」 前編で紹介した週刊新潮の特集記事「特集『住友銀行』『伊藤萬』心中未遂の後始末」を思い出していただきたいが、金融関係者がイトマンの異変に気づいたのは、名門商社が振り出した手形が怪しげな街金融で割り引かれたという事実が広まったからだ。 手形詐欺を描いた傑作小説 手形や小切手は極めてアナログな決済システムだ。しかし、だからこそ無数の人間ドラマを生んできたとも言える。 要するに「カネを巡って繰り広げられる関係者の右往左往、阿鼻叫喚」の象徴が手形と小切手というわけだ。そのため優れた作家の創作意欲を刺激することも多かった。 例えば、松本清張の長編推理小説『眼の壁』(新潮文庫)は手形詐欺の詳細を描いたことでも高い評価を受けている。城山三郎の短編小説『老人の眼』(新潮文庫『生命なき街』所収)も同じく手形詐欺がテーマだ。 傑作コミック『ナニワ金融道』(青木雄二)や『闇金ウシジマくん』(真鍋昌平)の愛読者なら、手形や小切手のことはよくご存知だろう。登場人物が手形や小切手に翻弄されたり、様々な駆け引きを繰り広げたりする姿がリアルに描かれた。 「今でも中小企業や商店を中心に手形と小切手のニーズはあります。しかし政府も金融機関も廃止を目指し、経済界に要請を重ねてきました。実際、手形や小切手を使った決済は減少の一途を辿っています。手形や小切手は振り出した側と受け取る側が別の金融機関を使っていることが珍しくありません。そのため各地に『手形交換所』が設置されました。周辺の金融機関が決済の必要な手形や小切手を持ち寄り、交換して精算したのです。この交換所における交換額の推移を調べると、手形や小切手が“過去の遺物”になっていった過程が浮かび上がります」(同・記者) 手形を禁止する法律も ちなみに手形交換所も18世紀にロンドンで設置されたのが世界初という長い歴史を持っている。 日本では1990(平成2)年に手形や小切手の交換額が約4797兆円でピークに達した。その後は電子決済の普及などで右肩下がりとなり、昨年には約75兆円まで落ちこんだ。 2022(令和4)年には紙の交換所が廃止され、電子交換所が設置された。それでも金融機関は事務手続きが煩瑣で負担が大きすぎると廃止を求めた。 さらに手形は仕事の発注者や元請けなど強い立場の者が振り出し、弱い立場の下請けが受け取ることが珍しくない。 長期の支払期日を押し付けられたり、銀行が手数料を取ることで契約金の全額を受け取ることができないなど、いわゆる“下請けいじめ”の温床となっていた。 政府は電子交換所が設置された2022年に「2026年までの手形廃止」を経済界に要求。今年3月には手形払いを禁止する下請法改正案を閣議決定した。全国銀行業界も手形や小切手に変わる新しい電子決済システムの「でんさい」の利用を呼びかけている。 こうした動きを経済ジャーナリストは、どのように受け止めているのだろうか。経済誌「財界」の主幹を務める村田博文氏は、これまで50年にわたって、延べにすると万単位の経営者を取材してきた。 利便追求で失われる伝統 村田氏は、手形と小切手の実質的な廃止は感慨深いものがあるという。 「これまで数多くの経営者にインタビューを依頼してきましたが、特に自分で会社を作った創業者に話を伺っている時は、必ずと言っていいほど資金繰りに困った時の思い出話となり、手形や小切手を巡るエピソードが飛び出しました。極端かもしれませんが、資金繰りで危機的な状況に直面した歴史がない企業は皆無なのではないかと思うほどです。丸の内に立派なオフィスを構えている有名企業や名門企業も同じではないでしょうか」 資金繰りで辛酸をなめた経験を持つからこそ、「手形を振り出せる立場になった時は嬉しかった」と村田氏に語る経営者も多いという。 「創業者の多くは手形や小切手に、ある種の“重み”を感じ取っていました。自分が作った会社の経営が軌道に乗り、金融機関が信用してくれた。その証が手形や小切手だというわけです。ただし、経営者が感じていた“重み”は、紙の有価証券だったからこそでしょう。2022年に電子化された際に重みは消え、あの時点で手形や小切手の社会的使命は終わったのだと思います」 手形や小切手が電子化された時点で、それは“重い”どころか“軽く”なってしまったと村田氏は言う。 古い価値観の継承も そして手形や小切手の実質的廃止を象徴として、経済界に悪い意味の“軽さ”が蔓延しないか、不安になる時があるそうだ。 例えば「創業」という言葉を考えてみよう。古くさい印象もあるだろうが、重みは充分だ。優れたサービスを提供して消費者から評価され、長年にわたって経営を続けることで従業員の生活を守る、といった企業倫理を反映させたニュアンスを持つ。 では「起業」はどうだろうか。もちろん高い志を持つ起業家も多い。その一方で、短期的な利益だけを追求し、急いで株式を新興市場に上場。他社に買収してもらうことがゴールという例も散見されるのは事実だ。会社を興す動機としては、あまりに軽い。 「昔は怪しげなM資金話に手形や小切手が登場することもありました。変な話ですが、手形や小切手を悪用した詐欺を企むのは、犯人側も大変でした。専門的な知識が要求されるからです。それが今では詐欺事件の大半を特殊詐欺が占めるようになりました。これは電子決済が発達したことも大きな影響を与えています。闇バイトの逮捕者が、あまりに軽い気持ちで参加していることにも驚かされます。企業がデジタル化で利便性を追求するのはやむを得ないでしょう。しかしアナログの時代に存在した“経営者の矜持”や“企業の社会的責任”といった重い価値観が、デジタル化に伴う“軽さ”で失われてしまわないか、私も注意しながら取材を続けていきたいと考えています」(同・村田氏) 第1回【2026年度末で「手形」と「小切手」が廃止の衝撃…680億円の巨額“絵画取引”のウラで手形と小切手が飛び交った「イトマン事件」を振り返る】では、戦後最大の経済事件と呼ばれる「イトマン事件」で手形と小切手が注目され、大阪地検特捜部が動いた理由について詳細に報じている──。 デイリー新潮編集部