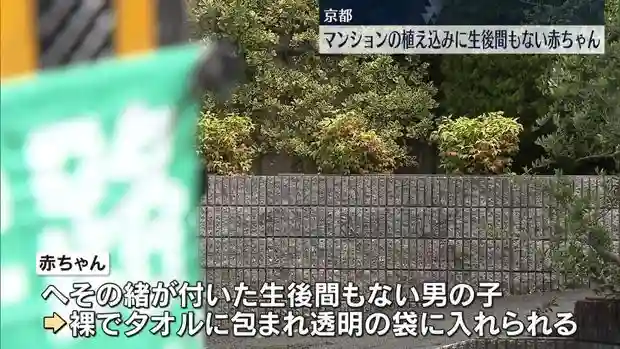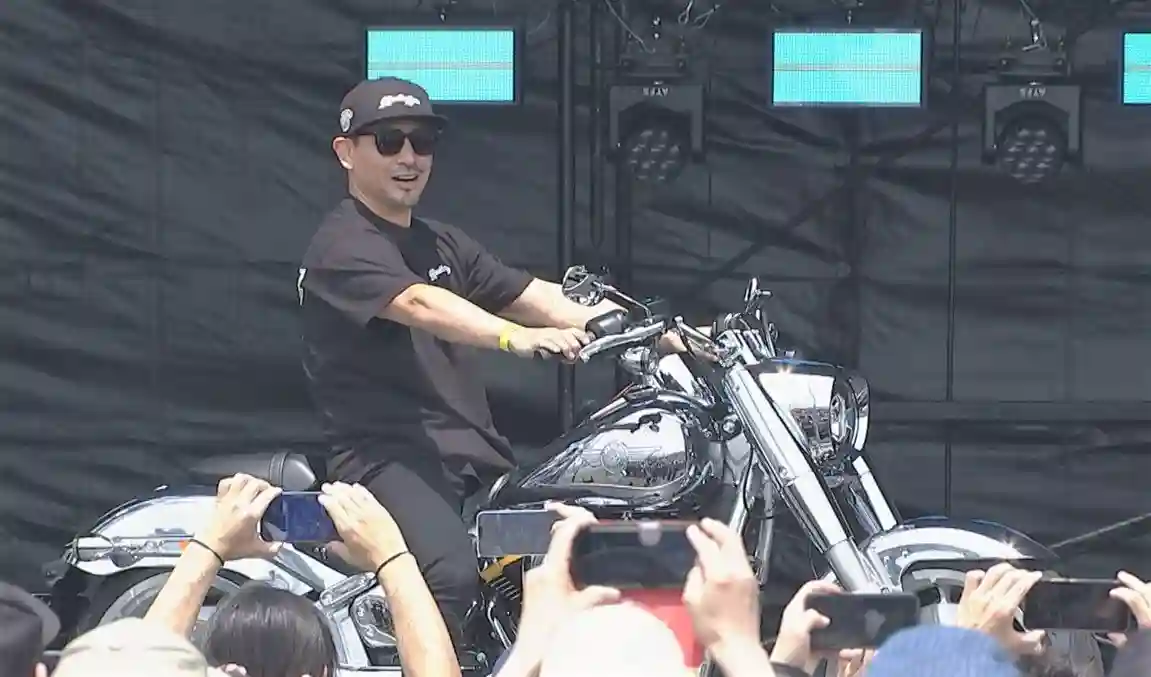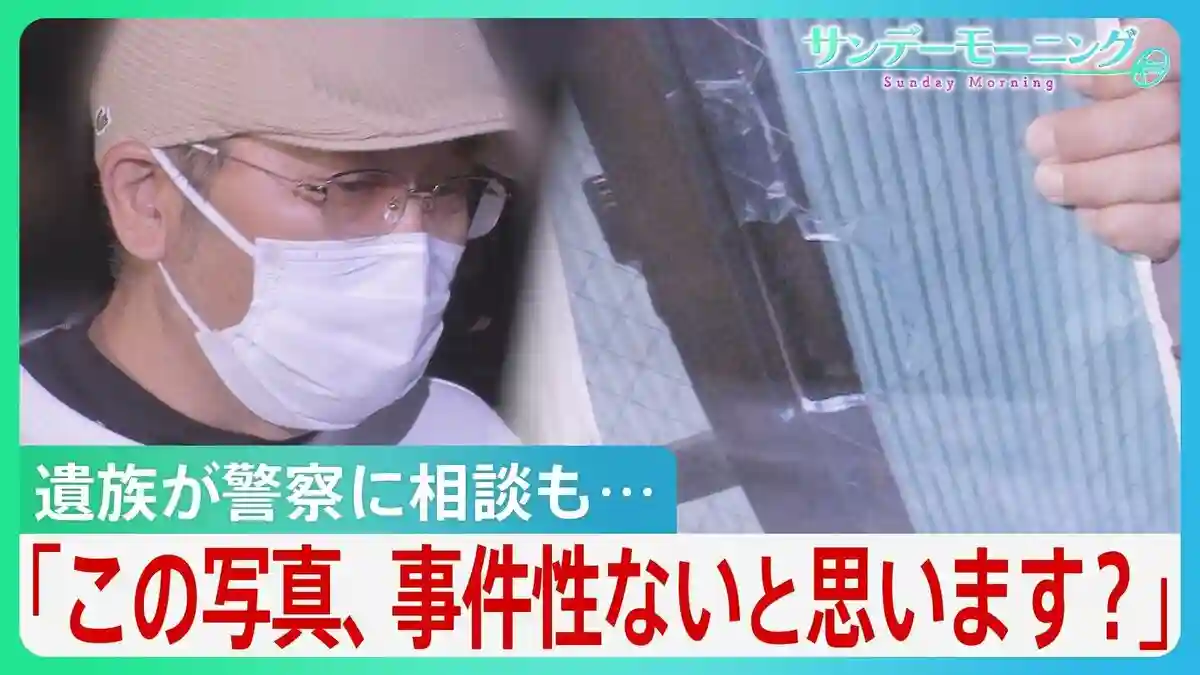連休明けの今、学校を休む子が増える時期です。そういった場合、親はどう対応したらよいのか? 奈良県にある畿央大学の大久保賢一教授(専門:特別支援教育、応用行動分析学、ポジティブ行動支援)に聞きました。 大久保賢一教授 連休明けのこの時期は、新年度のクラス替えや担任教員の変更などにより、緊張しながら頑張ってきた子どもたちにとって、ちょうど疲れが表面化してくる時期です。子どもが学校を休みたがったり、疲れた様子を見せたりする場合、「疲れたなどと言わずに学校に行きなさい」「甘えているだけじゃないの」などと頭ごなしに叱るのは避けた方がよいでしょう。 まずは「どうしたの?」と声をかけ、子どもの話にしっかり耳を傾けることが重要です。そして、たとえ学校に行けなくても、子ども自身の価値が損なわれるわけではなく、親としての愛情に変わりはないということが子どもに伝わっていることが大切です。 子どもが頭痛や腹痛といった体調不良を訴えることも少なくありません。単に休みたいから言うのではなく、実際に身体的な痛みとして現れていることもあります。スクールカウンセラーをしていると、「学校に行きたくない」という自分の気持ちをはっきり表現できる子どもにも多く出会います。 このような場合、親御さんは「どうして行きたくないのか」「学校のどんなところが嫌なのか」という子どもの話を、途中で怒ったりアドバイスしたりせず、聴くことが大切です。 親御さんの対応の中には「何がなんでも学校に行かせる」といった強制的なアプローチと、「本人が行きたくなるまで休ませる」といった消極的な対応という両極端が見られることがあります。 しかし、効果的なのは無理強いせずに、実現可能な小さな目標を子どもと一緒に設定し、その達成を支援していくというバランスの取れた方法であることが多いです。 ──子ども自身もなぜ学校に行けないのか、わからない場合も多いようですね。 そうですね。理由が複数あったり、本人も、うまく言葉にできなかったりすることはよくあります。私の経験では、主な理由として友人関係のトラブル、先生との関係、勉強の難しさ、そして感覚の敏感さなどがあげられるように思います。 例えば、厳しく叱るタイプの先生に対して、感覚が鋭敏な子どもは強い不安や苦痛を感じることがあります。また、授業の内容についていくのが難しい場合や、教室のザワザワした環境に耐えられない子どももいます。 原因に目星がついた場合は、改善に向けて学校と話し合うことが望ましいですが、そのような調整が難しい場合には、適応指導教室(今は教育支援ルームなどと呼ばれることが多いです)や民間のフリースクールなど、お子さんに合った場所を探してみるのも選択肢の一つとなるでしょう。 また、当面の休息が必要なケースもあります。友達関係に疲れ切ってしまったり、いじめを受けたりした場合などです。そんな時は、親御さんが子どもを責めるのではなく、まずはしっかり休ませてあげることが大切です。 私の経験では、回復してきたサインとして「暇だな」と子どもが言い始めることが一つの目安になるケースがあるように感じています。そういった回復の兆しが見えてきたら、私が親御さんにお伝えしているのは、学校に戻るにしても、他の選択をするにしても、「勉強を続けること」「人との関わりを練習する機会を持つこと」「日中の安全な居場所を確保すること」という3つの要素を大切にしてほしいということです。 これらのバランスを取りながら環境を整えることが、子どもの健やかな成長を支える土台になると考えています。 ■すべての行動には、それをする理由がある ──先生が取り組んでいるポジティブ行動支援について教えてください。 ポジティブ行動支援(英語ではPositive Behavior Support、PBSと略されることもあります)は、もともと重度の知的障害がある方々のために開発されたアプローチです。最近では、特にアメリカの学校教育で、よく活用されています。 この考え方の基本は「すべての行動には、それをする(あるいは、それをしない)理由がある」というシンプルな考え方です。 例えば、ある行動をすると人から注目してもらえたり、自分の要求が通ったり、嫌なことを避けられたりするなど、子どもにとって何らかの得るものがあるから、その行動を選んでいるのだと考えます。一見「問題行動」に見える行為も、実は子どもが自分のニーズを表現する手段なのだと理解することが大切です。 重要なのは、こうした行動を罰や強制で、やめさせようとするのではなく、「この子はこの行動で何を伝えようとしているのだろう」と考える視点を持つことです。 具体的な支援の方法には主に3つの柱があります。1つ目は環境を整えること。2つ目は問題行動の代わりになる適切な行動の仕方を教えること。3つ目は心理学では「強化」と呼ばれるもので、ある行動をした結果、子どもが良い経験をするよう設定することです。 例えば、適切な行動を褒めるといった方法です。褒め方にはコツがありますが、基本的には子どもと一緒に「できたね、良かったね」と成功を共に喜ぶ姿勢を示すことが効果的であることが多いです。子どもが「良かった」「うれしい」と感じることで、その行動は自然と繰り返されるようになります。 具体例:朝の支度が遅く、遅刻してしまうケース 朝の支度が遅れて遅刻が続く場合、その背景にはいくつかの要因が考えられます。単に睡眠不足で眠いという可能性もあれば、忙しい親御さんが普段、十分に関わる時間を持てないため、子どもが無意識のうちに親の注目を引こうとして、あえてゆっくりと支度している可能性もあります。 忙しい朝は大人もイライラしがちで、すぐに叱ってしまいがちですが、ポジティブ行動支援では、まず環境を整えることから始めます。例えば、就寝時間が遅く、十分な睡眠が取れていないことが原因なら、就寝時間を適切に設定し、早く眠る習慣を少しずつ作っていきましょう。 就寝前の流れを決めておくことも効果的です。お風呂の後にリラックスできる活動を取り入れたり、寝る前のスマホやゲームの使用に一定のルールを設けたりする工夫も考えられます。 また、気が散りやすい子どもの場合、朝の活動中に別のことに気を取られて、予定通りに進められないことがあります。そんな時は、朝やるべきことを時間とともに視覚的に示した表を作ると効果的です。「7:00〜7:10 布団から出て着替える」「7:10〜7:30 朝ごはんを食べる」といった具体的な時間配分を示し、終わったらチェックを入れる仕組みを取り入れてみましょう。 このプロセスで大切なのは、子どもが各ステップをクリアするたびに、親御さんが「できたね」と認め、一緒に成功を喜ぶことです。こうした小さな成功体験の積み重ねが、子どもの「自分にもできる」という感覚を育て、自分から行動する力につながります。 また、前の晩に翌朝の準備(服を選んでおく、カバンの用意をするなど)をしておくことで、朝の混乱を減らすことができます。このように、問題行動を単に、やめさせようとするのではなく、その背景にある理由を理解した上で、環境を整え、適切な行動を強化していくアプローチが、長続きする行動の変化をもたらす鍵となります。 ──先ほどの具体例の中で、就寝時間に関する話題がありました。例えば親子で「夜9時半には寝よう」と約束しても、実際には、なかなか守られないことが多いと思いますが、どのように対応すればよいでしょうか。 そうですね、この状況は多くのご家庭で見られる課題です。単に「夜9時半に寝る」と決めるだけでは、うまくいかないことが多いので、もう少し工夫が必要です。 まず、学校から帰った後の過ごし方全体を見直して、夜9時半に寝るためには何時までに何をすべきかを親子で一緒に考えてみましょう。 効果的な方法の一つは、夕方から夜にかけての活動とその時間配分を紙に書き出してみることです。また、目標達成には段階的なアプローチが有効です。例えば、最終的に夜9時半に寝ることを目指しつつも、まずは実際に何時に寝ているかを記録していきます。現在は夜11時に寝ている場合でも、叱らずに客観的に記録し、少しでも目標時間に近づいたら「昨日より早く寝られたね」と小さな進歩を一緒に喜びましょう。 この記録には副次的な効果もあります。就寝時間が遅くなりやすい日のパターンが見えてくるかもしれません。例えば、特定の活動をした日や、宿題が多かった日、あるいはスマホやゲームを長く使った日などに遅くなる傾向があるかもしれません。 こうした記録から、就寝時間に影響する良い要素と改善すべき要素を親子で話し合い、生活の中で良い要素を増やしていくことが効果的です。さらに、約束を守るやる気を高める方法として「トークンエコノミー」という仕組みも役立ちます。これは、決めた時間に寝られた日にシールや丸印などをカレンダーに貼り、一定数たまったら、子どもが楽しみにしている少し大きめのご褒美と交換できるという方法です。 こうした目に見える形の報酬システムは、抽象的な目標を小さな達成可能なステップに分け、子どもの自主性と達成感を育てる効果があります。 このように、良い生活習慣づくりには、具体的な計画、段階的な目標設定、継続的な記録と振り返り、そして適切な報酬の仕組みを組み合わせた総合的なアプローチが効果的です。親御さんの一貫した関わりとポジティブなフィードバックによって、子どもは少しずつ、より良い生活習慣を身につけていくことが期待できます。 ■親御さんへのメッセージ 親御さんには、何よりもお子さんの良き理解者であり、支援者であってほしいと思います。日々の小さな成功体験を子どもと一緒に喜ぶ。その積み重ねがお子さんの自信を育んでいきます。 この世界に完璧な人はいません。大人にとっても、時に誰かに助けを求めることは必要なことです。子育ての長い道のりの中で、親御さんご自身をケアすることも忘れないでください。ご自身の健康は、お子さんへのより良いサポートの土台となります。 そして、お子さんにも完璧を求めるのではなく、親子の小さな成長の瞬間を宝物として大切に集めていってください。子どもの成長は早く、子どもと日々、向き合うこの特別な時間は、いつか形を変えていきます。限られた時間の中で、どうか子育てを楽しんでいただければと思います。 ■子どもたちへのメッセージ 自分の感情を大切にしてほしいと思います。うれしい気持ちや楽しい気持ちはもちろん、つらい気持ちや面倒くさいと感じること、イヤだなと思う気持ちも、同じように大切なものです。 そんな気持ちに気づいたとき、「どうして今、こんな気持ちなんだろう?」と少し考えてみてください。そして、信頼できる大人に話してみることも良いことです。 世の中には「いつも元気で明るくいるのが良いことだ」という考え方もありますが、私はそうである必要はないと思います。いろいろな感情を素直に感じることが、自分自身を理解することにつながります。 また、ついつい周りの人と自分を比べて落ち込んでしまうことがあるかもしれませんが、そんなことをする必要はありません。自分だけが人生の中で立ち止まっているような気がしたり、時には逆戻りしているような気がするときもあるかもしれませんが、たまに立ち止まったり後ろ向きになったりしても全く問題ないのです。 大事なことは、自分のペースで、自分が行きたい方向に向かって、自分の足で歩いていくこと。それが一番、大切なことだと思います。