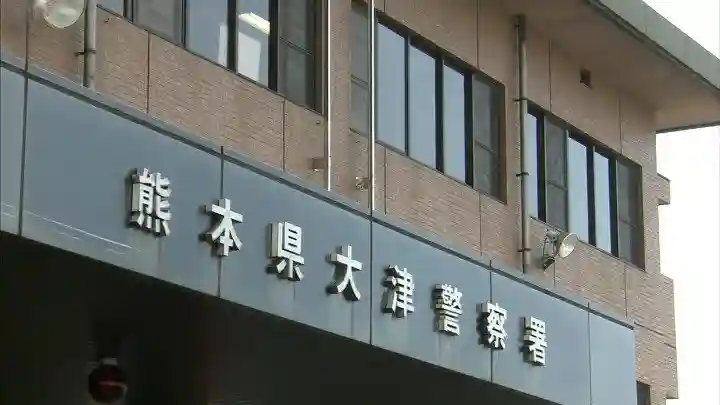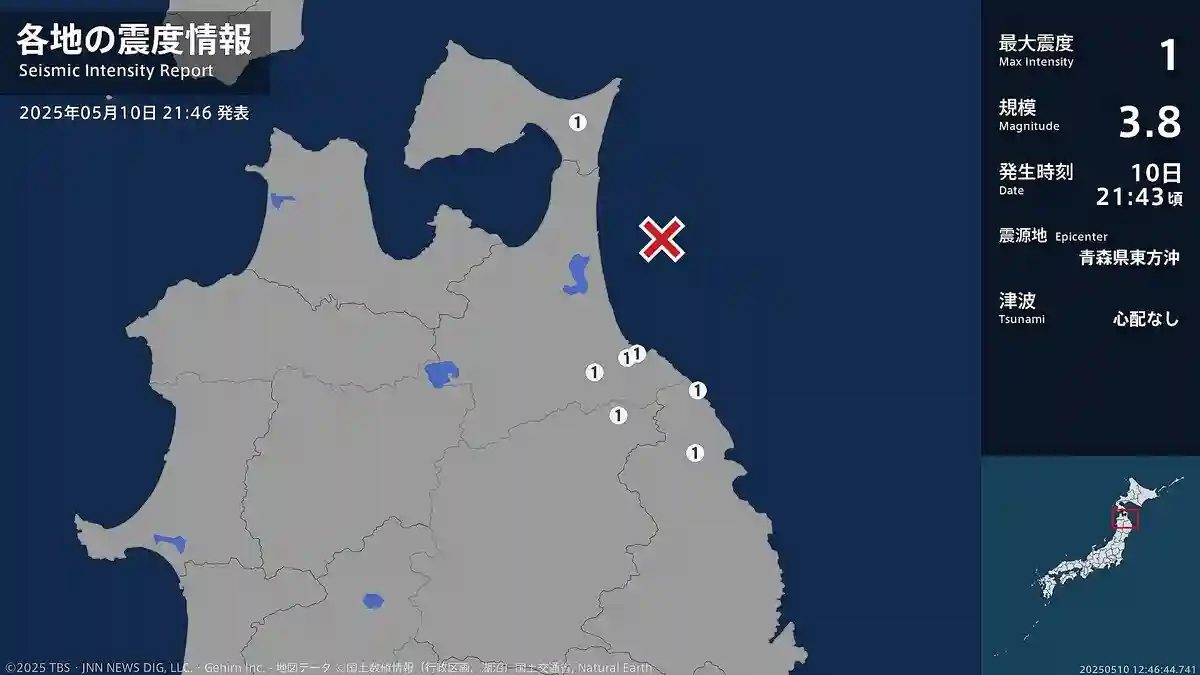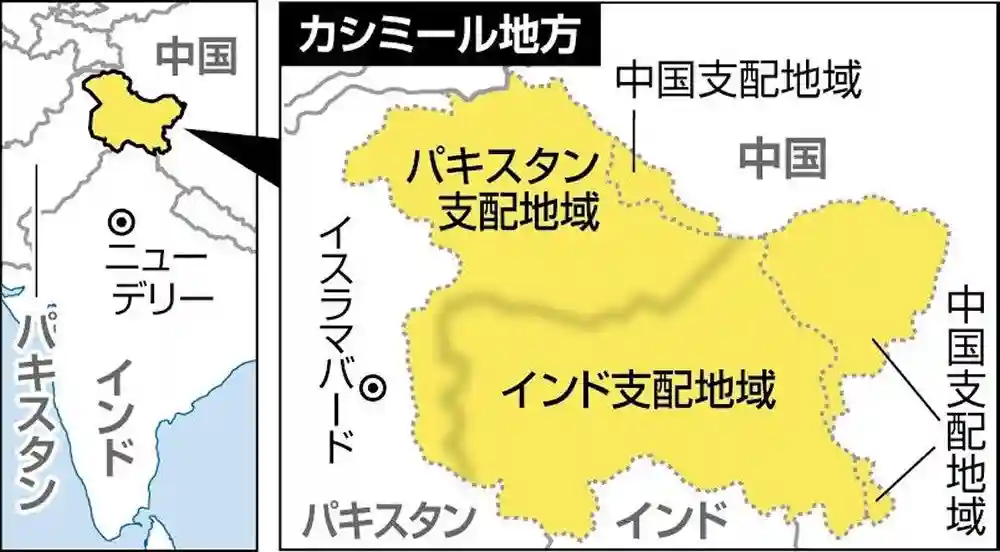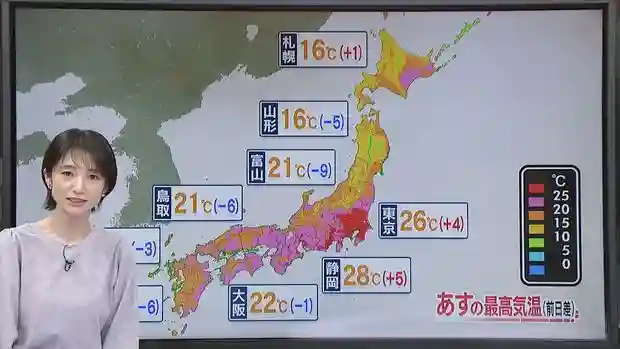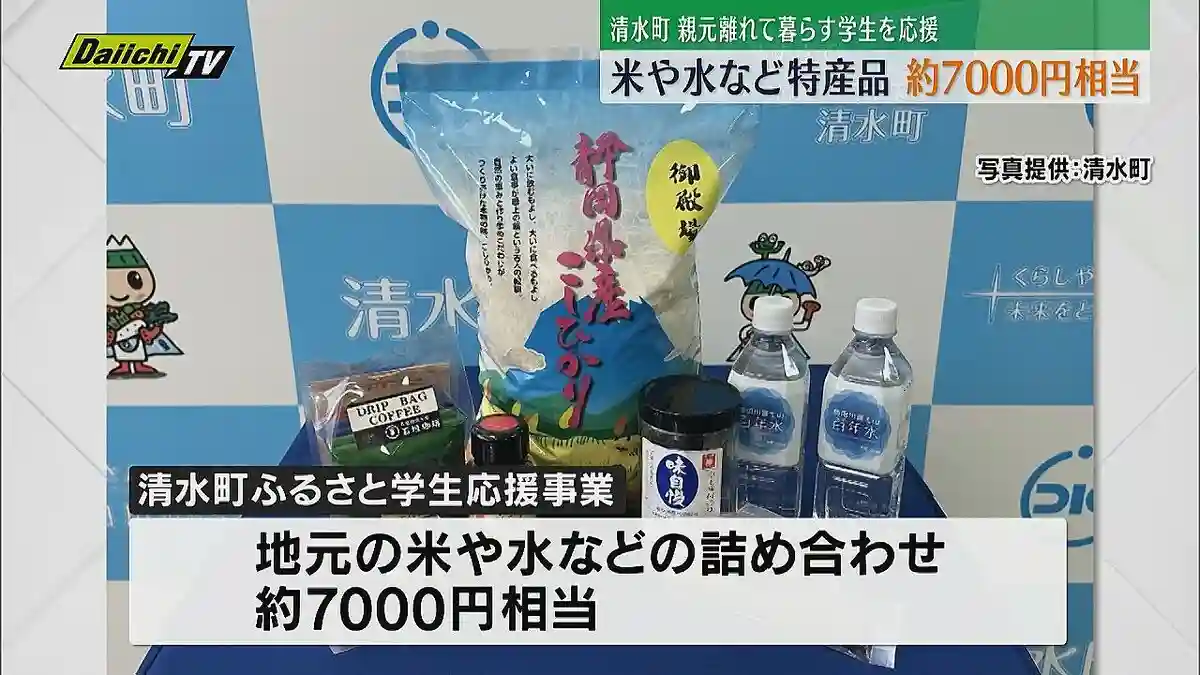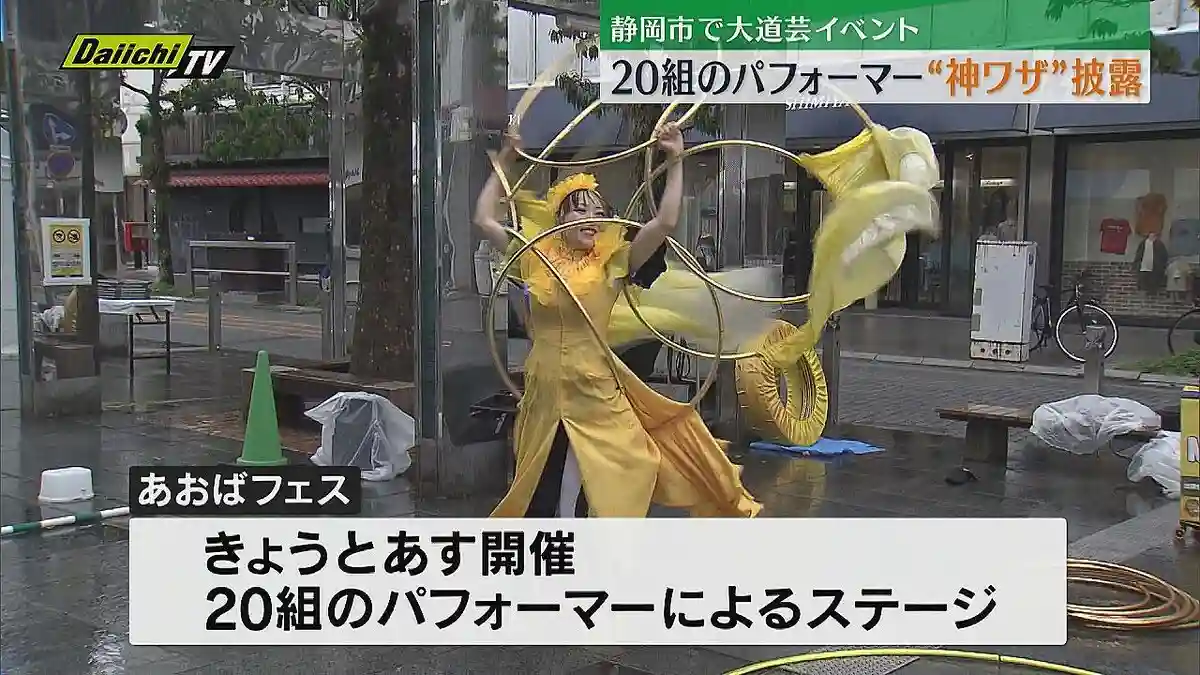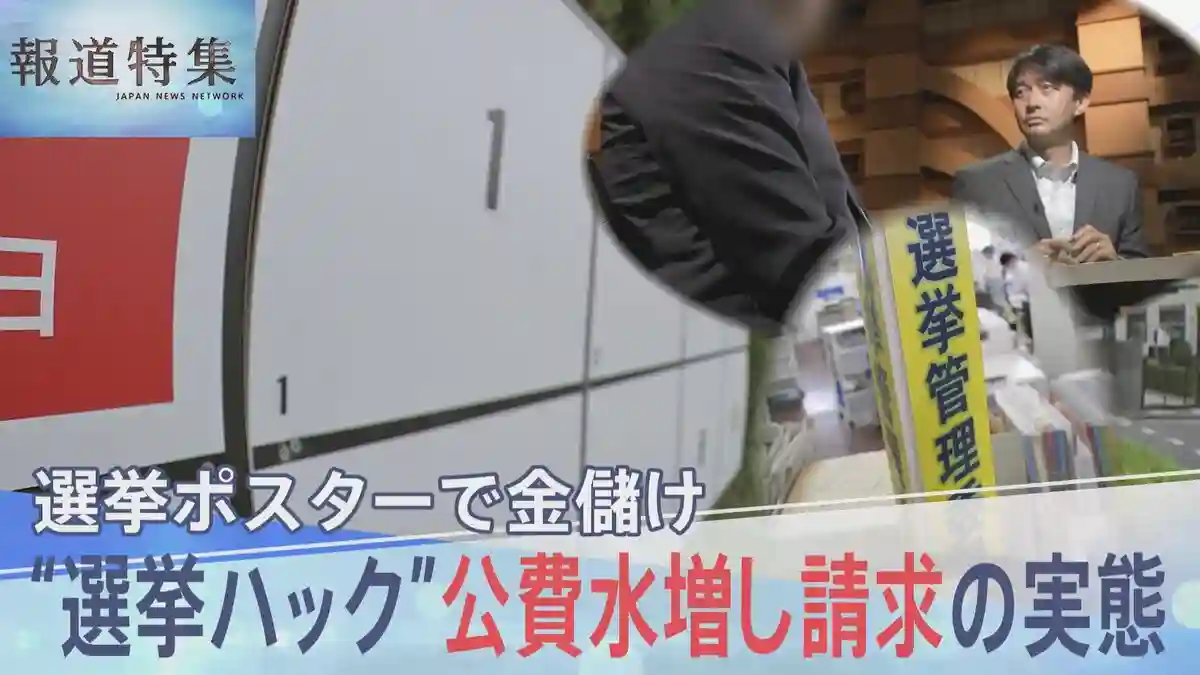東大を卒業して故郷の山形県に戻り、25歳で60年続く祖父の米農家を継いだ「米利休(こめのりきゅう)」氏(26)。「やればやるほど赤字」になる農業経営からの脱却を目指し、「稼げる」農業を実現するためのさまざまなチャレンジしている。その一つが販路拡大のためのSNS発信だ。 【画像】フォロワー65万人を抱える米利休氏のTikTok 東大時代、SNSを活用した通販ビジネスで培ったスキルを生かし、現在は複数のSNSで「廃業寸前農家の生き残りをかけたリアルストーリー」と題した米農家の実情を投稿。TikTokは6万フォロワーを超え、Instagramのフォロワー数は約18万人(2025年5月時点)を誇る。 そんな米利休氏の投稿でバズったものの1つが、〈農家1年目の年収が15万円〉と赤裸々な経営事情を公表した動画だ。〈月収ではなくて?〉と驚きをもって受け止められ、リール再生数は500万回超え。ただし、米利休氏いわく「年収15万円」を公開するまでには葛藤があったという──。 米利休氏の著書『東大卒、じいちゃんの田んぼを継ぐ 廃業寸前ギリギリ農家の人生を賭けた挑戦』(KADOKAWA)より、年収15万円投稿の舞台裏をお届けする。(同書より一部抜粋して再構成)【全4回の第2回。第1回を読む】 * * * 農業を継ぐにあたって、いくつかの前提条件がありました。 まず、1年目の年収は15万円であること。どうしてこの数字が出てきたのかというと、それまでは毎年じいちゃんが、近くに住んでいる知人に農繁期限定でアルバイトをお願いしていて、アルバイトの報酬がおよそ15万円でした。僕が農業に従事することで労働力が確保できれば、アルバイトは雇わずに済むため、アルバイト代に回していたお金を僕の収入として考えることにしたのです。 また、販路を広げて、これまでよりも売上を上げられれば、その分の売上は僕の報酬にしてもいいことになりました。そこで販路拡大には、これまでの経験を活かせるSNSを駆使することにしました。 近年、SNSで販路を拡大している農家さんは少しずつ増えてきています。例えば“まいひめおじさん”は、熊本県で高糖度のトマト「まいひめ物語」や、そのトマトで添加物、着色料、保存料などを一切使用しないトマトジュースを、SNSを中心に販売しています。果物くらい糖度の高いトマトを使用した季節限定・本数限定のトマトジュースは1本6000円で販売されるのですが、即完売するそうです。僕が農業を始めた当初は、まいひめおじさんのSNSを参考にさせていただきました。 農業収入が少ないことから生活費を自分で稼ぐ必要があり、当初は家庭教師の準備を進めていました。ところが、SNSを始めた1カ月後には、本当にありがたいことに、約10万人の方にフォローしていただきました。広告や案件などによる収入が見込めるようになったことで、家庭教師の計画はストップさせて農業ビジネスに振り切ることを決めました。 2024年に関しては、補助金がもらえるようになったことも大きかったです。新規の農業従事者を支援する県の補助金(年75万円)と、6次産業化(※)の町の補助金(20万円)、合計95万円をいただきました。補助金は種類が豊富にあるのですが、条件が厳しいことも多く、世帯年収でフィルタリングされるものもあります。 ※農業者が生産(第1次産業)だけでなく加工(第2次産業)や販売(第3次産業)にも取り組むことで、生産物の価値を高め、農業所得の向上を目指す取り組み。1次×2次×3次=6次の意味。 なかには補助金を嫌う方もいます。町・県・国のお金、つまり国民のお金を使って農業をするのか、という厳しいお言葉をいただくこともあります。頼らずに済むのなら、本当にかっこいいと思います。しかし、わが家の場合は、補助金や助成金、交付金がなければ成り立たず、使えるものは使いながら頑張っていこうと考えています。 SNSを活用して収入を得るためには、どんなことを発信するのかがとても重要になりますが、「年収15万円で米をつくっています」と投稿したときには、「それでどうやって生活するんだ」「もっとマシなウソをつけ」といった厳しいコメントもいただきました。僕も農業に無縁の人間だったら、そう思ったでしょう。多くの方は、一般的な会社に就職して働けば、毎月のお給料が15万円以下ということはあまりないと思います。しかも、僕の場合は月収ではなく年収が15万円。信じられないと思われるのもわからなくはありません。また、農家の方から「1年目なら年収15万円で妥当」「年収がプラスになっている時点で上出来」といったコメントもいただきました。でも、そうした農業の固定観念も個人的には嫌だなと思っていました。 実は、年収15万円という事実を公表するかどうかは、かなり迷いました。これは僕の個人的な印象ですが、おいしい農作物をつくる農家さんや農業法人は、農業が儲からないとはいいながらも、儲かっているはずだと思っていました。儲かっている=おいしい、という公式が成り立つ部分は少なからずあるだろうと考えていたのです。年収15万円ということは、この農家がつくっているものはおいしくないから売れないのではないか、という印象を与えかねず、それだけは避けたいと考えていました。 年収15万円というのはインパクトのある言葉なので、良くも悪くもバズることは予測できました。悪いほうにバズって炎上してしまうことだけは避けたいけれど、果たしてどちらに転ぶのかは本当にわかりませんでした。でも最後は、農家の不遇な状況を理解して、おいしい農作物をつくることができることと、農家が儲かることが必ずしもイコールではないとわかってくださる方もいるのではないか、というわずかな望みにかけました。蓋を開けてみたら、否定的なコメントは全体の1割もなく、9割以上は応援コメント。結果的にはSNSがいい方向に働き、とても安心しました。 僕と同じように農業に従事されている方の反応については2パターンあって、大半は「うちも同じような状況です」「米農家って大変ですよね」と同調するケースなのですが、一部の方からは「うちはそんなにひどい経営はしていない」「どんな経営をしたらそうなるんだ?」など、マウントをとるようなコメントもいただきました。 悲しくないわけではないし、「今に見ていろ」という気持ちにもなりましたが、僕はまだ農業を始めたばかり。何を言われたとしても「これから改善していきます」と言うしかなく、思ったほど精神的なダメージになることはありませんでした。 (第3回に続く)