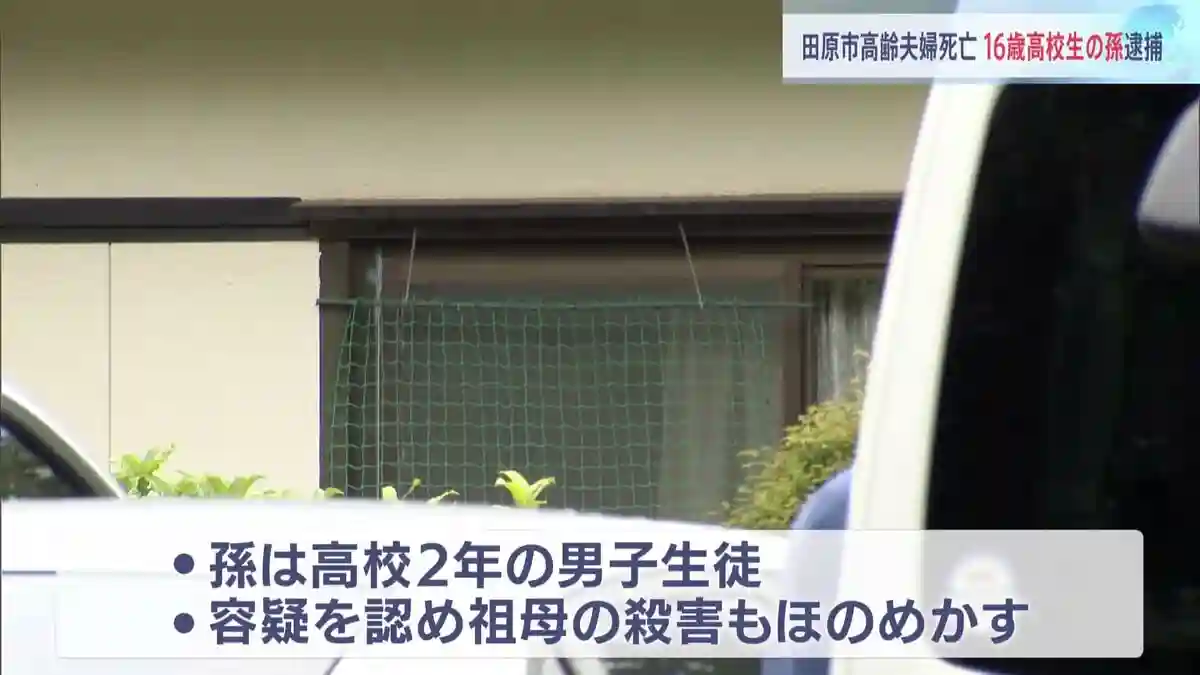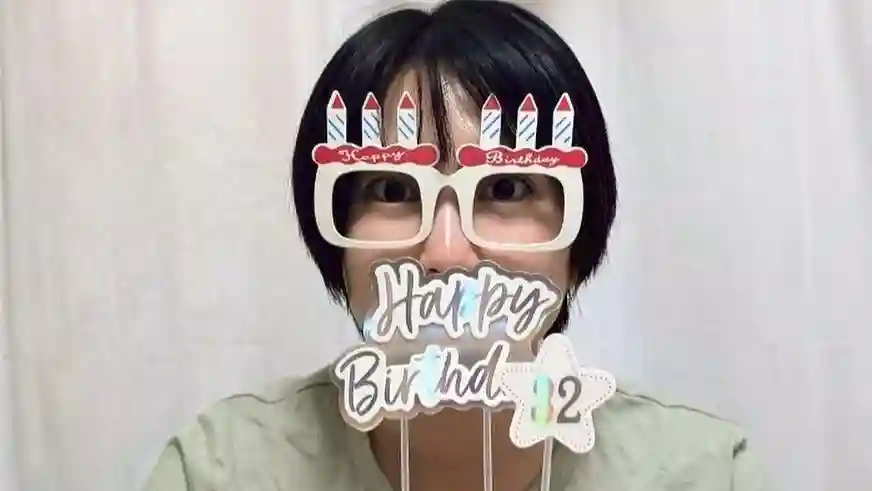世界の内燃機関のクルマで最も多いのは直列エンジンだ。他形式に比べ部品点数が少なく、コスト的には最も有利だ。直列は3気筒、4気筒、6気筒が一般的だが、6気筒になると全長が長くなるため、V型を採用することが多い。V型6気筒なので「V6」と呼ばれる。 エンジンによってクルマのデザインも変わる 直列エンジンのシリンダー(気筒)が文字通り直列に並ぶのに対して、V型はシリンダーをV字に折り曲げた形になるので全長が短くなる。直列6気筒に比べV6はボンネットが短くなり、キャビン(車室)を広くとれるメリットがある。 ただし、V型エンジンは上下方向に重心が高くなる傾向がある。直列に比べ、回転バランスや振動面で不利となるため、V型はバランサーを設けるなど、工夫が必要になる。V型には伊フェラーリのようにV型12気筒の大排気量エンジンを量産するメーカーもある。 V型エンジンのシリンダーをさらに下げ、水平に向き合うように配置したのが水平対向エンジンだ。水平対向は直列やV型に比べて重心が低く、互いに向き合ったピストンが左右の慣性力を打ち消すため、バランスがよく、振動も少ない。 向き合ったピストンの動きが、ボクシングのボクサーが互いに打ち合う動きに似ていることから、水平対向は「ボクサーエンジン」とも呼ばれる。重心の低さから「フラットエンジン」とも呼ばれる。 水平対向は理想のエンジンだがコストがかかる 水平対向は重心の低さと回転バランスの良さ、振動の少なさでは理想のエンジンだ。部品点数が多く、コストがかかるため、現在はSUBARU(スバル)と独ポルシェだけが量産している。 ただし、オートバイの世界ではホンダや独BMWも水平対向エンジンを量産している。趣味性の高いオートバイでは「走り」や「乗り味」が重視されるからだ。 ホンダは水平対向6気筒エンジンを大型バイクに搭載。「重厚感、パルス感を持つサウンドを伴った余裕あるトルク特性で、ゆったりとしたクルージング性能と、トルク感あふれるダイナミックな加速フィールを両立している」と説明している。 水平対向エンジンの排気音は独特で、「ボクサーサウンド」とも呼ばれ、熱烈なファンが多い。 スバルはエンジン横置きにして左右対称のバランスをデザイン 最近は中国の比亜迪(BYD)が高級車「仰望(ヤンワン)」のプラグインハイブリッドカー「U7」に水平対向エンジンを採用すると発表し、話題となった。BYDは全高と重心の低さから、コンパクトな水平対向を選んだようだ。 現在はハイブリッドカーが人気だが、これまでは直列かV型エンジンが主流だった。近年はスバルやポルシェも水平対向で本格的なハイブリッドカーを発売しており、ユーザーの選択肢が増えた。 ハイブリッドカーを含み、日本車のエンジンの大半は直列4気筒かV型6気筒だが、スバルは水平対向4気筒だ。スバルはこれを縦置きにして、エンジンからプロペラシャフト、リヤデフまでが左右対称となっている。 スバルはこのレイアウトを「シンメトリカルAWD」と呼び、重心の低さとともに左右対称のバランスの良さをアピールしている。 筆者はスバルインプレッサWRX-STIを所有し、富士スピードウェイのショートサーキットを走っているが、貴重な体験をしたことがある。あるクラブ主催の走行会だったが、あいにくの雨天だった。ショートサーキットではマツダRX-7、マツダロードスター、日産180SXなどのFR車や日産マーチ、ホンダCR-XなどのFF車が多く参加していたが、ウエット路面のコーナーで次々とスピンした。 エンジン回転音の魅力も車選びのポイント FR車やFF車に続き、4WDの三菱ランサーエボリューションもスピンした。筆者のインプレッサWRX-STIも限界を超えると最終的にスピンしたが、参加車の中で最もスピンしにくかった。これは水平対向エンジンを核とするシンメトリカルAWDの低重心・左右対称レイアウトの効果だったと思う。 もちろん、クルマなど走ればよく、燃費が第一だというユーザーもいるだろう。その点、スバルの水平対向エンジンはハイブリッドになっても、他メーカーに比べて燃費がよいとは言えない。燃費でスバルは明らかに優位性を欠く。 エンジンにはガソリンエンジンのほか、ディーゼルエンジンもあるが、こちらも基本的に直列かV型だ。このほかマツダは世界で唯一、ロータリーエンジンを量産したメーカーだが、現在は発電用に小型のロータリーエンジンを搭載しており、モーター駆動で走る。ロータリーエンジンの力を直接タイヤに伝えることはできない。 内燃機関がいつまで続くかわからないが、エンジン形式の違いは決して無視できないだろう。エンジンの回転フィールやサウンドは、走行安定性や燃費などと並び、クルマを選ぶ重要なポイントであるのは間違いない。 (ジャーナリスト 岩城諒 )