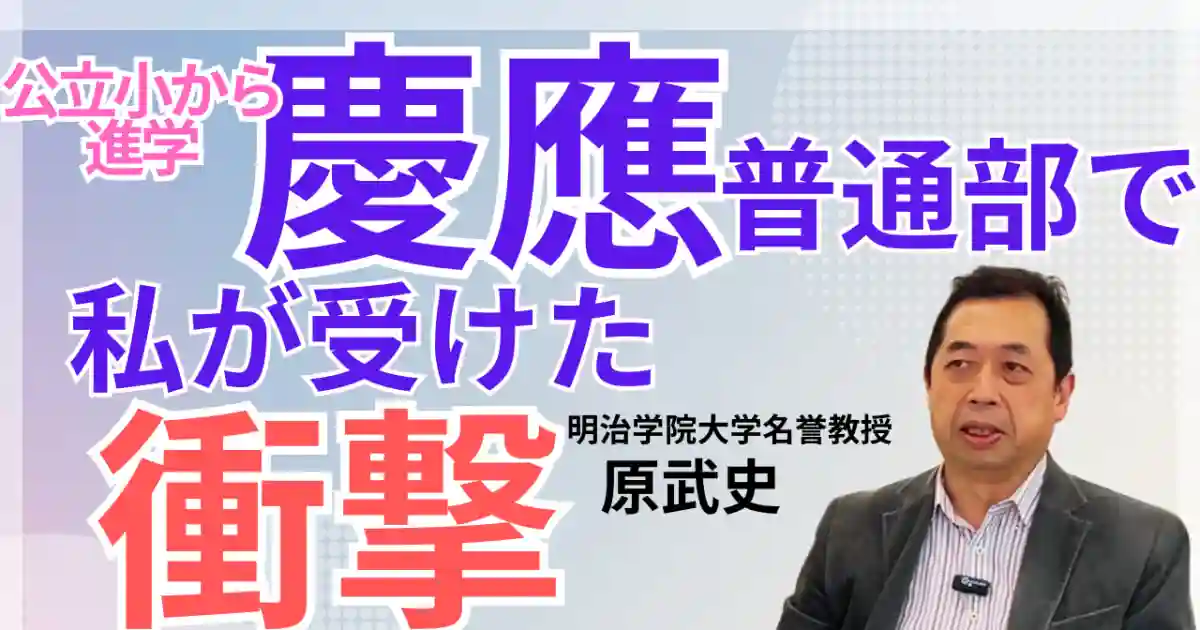
明治学院大学名誉教授の原武史さんが、「慶應義塾普通部」(=慶大義塾大の付属の中学校)に通っていたときのことを振り返った『日吉アカデミア一九七六』が、刊行後話題になっています。 1975年、東京都東久留米市の公立小学校から普通部に進学した原少年は、そこでなにを目にしたのか。そこで感じた「慶應らしさ」とはどのようなものだったのか。原さんにインタビューしました。 「慶應についての報道」への違和感 --なぜ今というタイミングで慶應時代のことを振り返ろうと思ったのでしょうか。 原: 2023年の夏の高校野球で慶應高校が優勝しましたが、あのときにスタンドの応援が批判を浴びました。 応援がちょっと怖いというか、甲子園球場を(大学野球の早慶戦がおこなわれる)神宮球場みたいに変えてしまって、一体になって応援をする。見事なまでに統制が効いていて、ものすごい迫力ものすごい大音響で敵を圧倒するようなもので、ああした応援はいかがなものかと言われた--そのように私は理解しました。 そうした状況を受けて、月刊誌「文藝春秋」も特集を組みました。「慶應義塾の三田人脈」といったイメージですね。「連合三田会」というすごい組織があって、一枚岩になっているような書き振りでした。そうした特集が出ると、ますます慶應というのは、一枚岩的な、鉄の結束を持っている、ちょっと恐ろしいような組織に映りますよね? それに対して、中高の6年間を慶應で過ごした人間としては、もちろん理解できる部分もあるんですけども、それだけで語られてしまうということには違和感を持ちました。 しかし、それに対して反論する人もあまりいなかった。だから、体験者がその当時の「内部の目線」に立ち戻って、そのときにどう感じていたのかをまとめておく必要があるのではないかという気持ちになったんです。 --ありがとうございます。ではまず、小学校を卒業して、慶應普通部に行かれたとき、最初に感じたことについておしえてください。 原:私は、じつは慶應は第一志望じゃなくて、開成中学に落ちて慶應に進学したんです。 当時は、四谷大塚と日本進学教室というのが「二大中学進学塾」でした。四谷大塚の「合不合判定テスト」というのがあって、当時のランキングで一番難しかったのは教育大駒場(現在の筑駒)。そのつぎがじつは慶應普通部だったんですね。 なぜそうなるかというと、慶應普通部は試験日がズレていて、麻布や開成などと違う日になっている。麻布や開成を受ける連中はみんな慶應普通部も併願しているから、慶應のほうが麻布、快晴よりもランキングが上だったんですね。 私の場合、開成は事前のテストで合格基準をクリアしていたので、合格するものだと思っていた。でも当日すごく緊張して落ちてしまったんです。 逆に慶応は受からないと思っていました。二次試験で図画や工作、体育があったんですが、あまりにもできなくて泣いてしまうほどでしたから。でも、受からないだろうと思っていたところ、蓋を開けたら受かっていた。余計に嬉しかったですね。 --原さんは2007年に、小学校時代を振り返った『滝山コミューン一九七四』という本をお書きになっています。西武池袋線沿線にできた巨大団地である「滝山団地」と、その団地から通う児童がほとんどを占める「七小」の当時の様子を活写したものです。 そこでは共産主義の影響を受けた教育方針が採用され、同調圧力が強く、集団主義的で、かなり息苦しい環境だったことが想像される内容となっています。小学校時代とのギャップなどはいかがでしたか? 原:七小を卒業すると、9割以上の児童がすぐ隣にある「西中学校」に通います。つまりメンツが変わらないわけです。そのまま西中学校に行くと、またあのような全体主義的な雰囲気のなかで過ごさなくてはいけない。そこからはとにかく逃れたいという気持ちが強かった。 慶應に行くというのは、そこから全然違う世界に行くということです。とにかくそれが一番嬉しかった。慶應がどういう学校かということよりは、西中に行かなくて済むということが一番重要でしたね。 --その後、実際に慶應普通部で生活を送るなかでは、集団主義的な「滝山コミューン」とは違うという感じはありましたか? 原:滝山コミューンのように「みんな同じ」という感じはまったくなかったですね。 ほかにも驚いたのは、みんな「体格が違う」ということですね。団地で育った子というのは、けっこうみんな「もやしっ子」なんですよ。私もそんなに背が高くなかったけど、でも背の順では真ん中ぐらいだった。 ところが慶應に行くと、驚くことにみんな体格がいいんです。全体的に「栄養十分」みたいなね。肥満体質もいるし、すでにスポーツ選手みたいにたくましいマッチョな感じのやつもいて。だから、背の順で並ぶと私もほとんど一番前になっちゃうんですよ。それにはやっぱりコンプレックスを抱きました。 それから、たとえば昼間の弁当。七小のときは給食ですから、もちろんみんな同じ食事です。一方、普通部は弁当ですから、モロにおのおの食事が違うことがわかるわけです。 それで、中学生なのに鰻の弁当を食べているやつなんかがいるんですよ。教室に鰻のいい匂いが漂ってね……。そうすると、自分の弁当が貧弱に見えてくるんですね。 --ある意味で「階層のジャンプ」を経験したところがあるんでしょうか? 原:それはすごくありましたね。 林間学校で奥日光に行ったときには「南間ホテル」という、今はなくなってしまったホテルに泊まりました。今の上皇がそこで玉音放送を聞いたという有名なホテルです。 ここに行ったら、スイス料理が出たんです。スイス料理ですよ、いきなり。私はもちろん食べたことないわけですが、みんな当たり前のような顔をして食べている。非常にびっくりしましたね。 それから、滝山団地にはファーストフードもなかったんですね。だから、たとえば「ケンタッキー」がわからないんです。最初は「洗濯機」と間違えてしまいました。あとは「ミスタードーナツ」を、「ドーナツ」という男性の名前だと思い込んだり(笑)。それで馬鹿にされましたね。 --そうしたお話を聞くと、慶應普通部のほうも、いっけん個性があるようで、ある意味では同質的に見えます。 原:やっぱり慶應幼稚舎からの文化だと思います。 当然私みたいに受験して入ってくるやつもいるにはいますよ。でも、最初は違いが目立っても、みんな徐々に同化されていくわけです。たとえば、外部から入ってきたやつはたしかに最初はダサいんだけど、だんだんみんな洗練されてくる。持ち物も全然違ってくる。 最初は膨れてパンパンになっているような学生カバンを使っていたやつが、そういうのをやめてちょっと洗練された紙袋なんかを使うようになったりとか。すっかり変わってくるんですね。 --ある特定の階層が、外の人を取り込んでいくというか、「環境が人をつくる」ところがあることを感じられそうな場所ですね。 原:まったくそうでした。 ただ、変わりようがないものもあるわけです。たとえば団地に住んでいるという事実ですよね。 普通部に入学して最初に名簿をもらったときに、やたら自分の住所だけが長かったのが恥ずかしかった。団地ですから、「◯棟◯号室」みたいな数字がついてとても長くなっているんですね。戸建てはだいたい数字が三つぐらいで終わりますよね。 それから、入学当初は東久留米に住んでいましたが、そのときは自分だけ郵便番号が5桁でした。当時は多くの場所では郵便番号が3桁で終わりだったんですが、私の済んでいた東久留米は5桁だった。それを見ただけで、うちは田舎だということがわかっってしまって、それもすごく嫌でした。 --中学一年生で階層を痛感するというのは、衝撃が強いですね。 * 【後編】「 慶應の「美しき伝統」と「知られざる裏側」…中高のOBが語る「私学の雄」の素顔 」につづきます。 【つづき】慶應の「美しき伝統」と「知られざる裏側」…中高のOBが語る「私学の雄」の素顔









