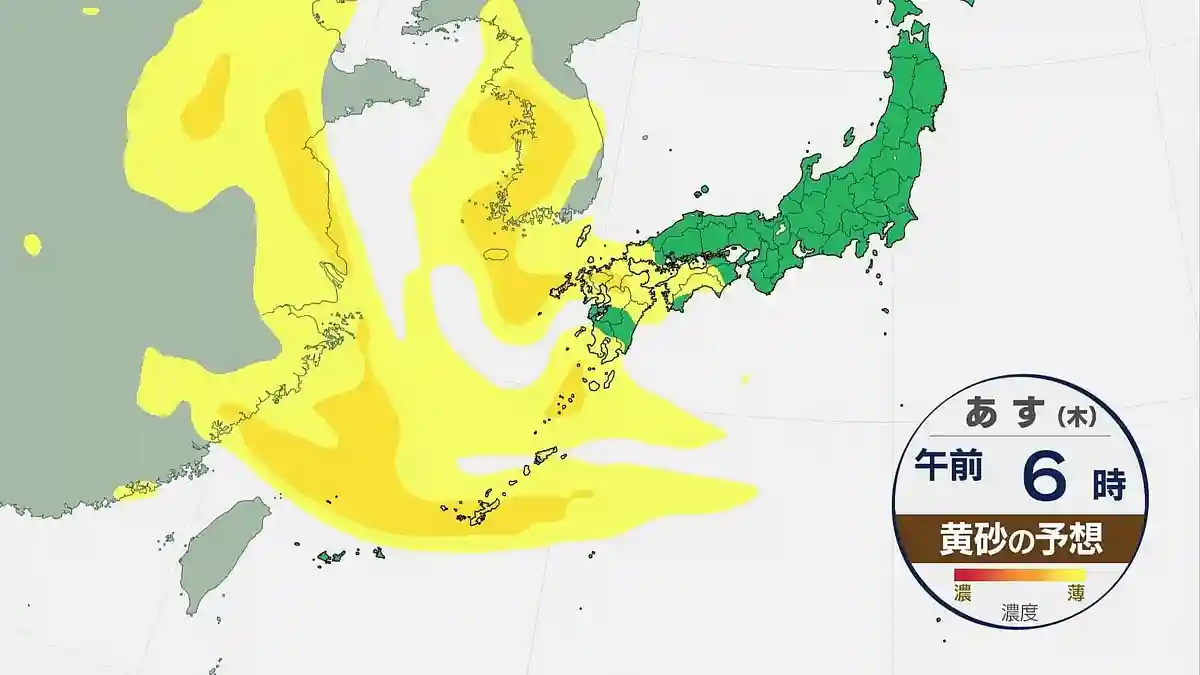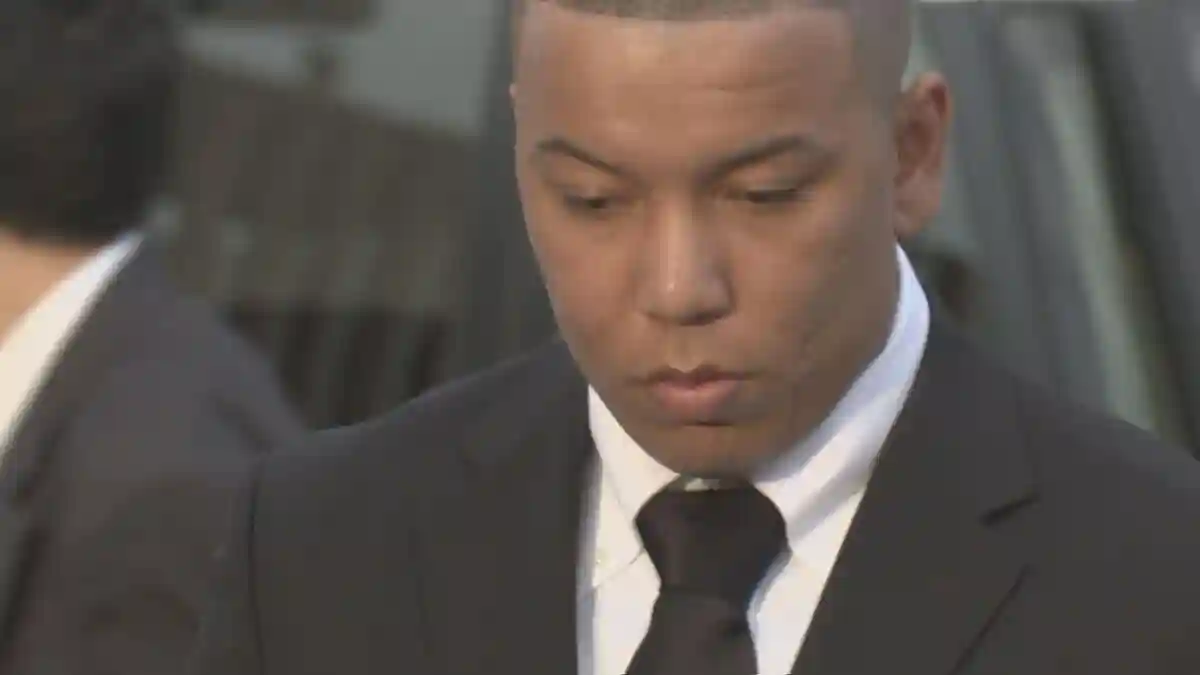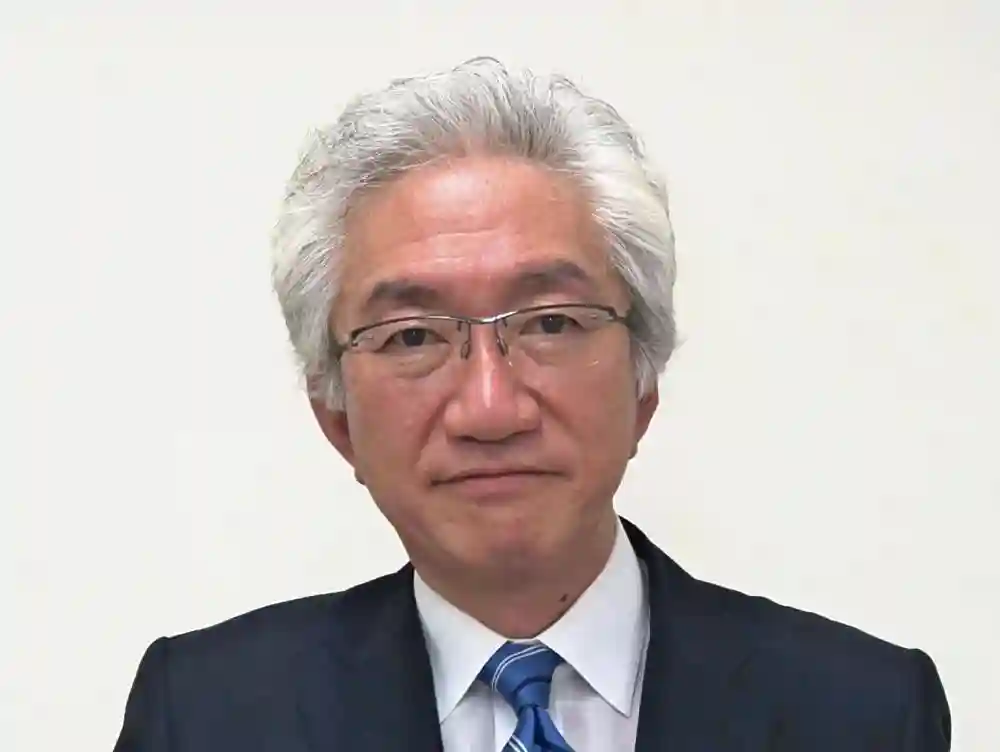今年1月28日、経済アナリストの森永卓郎氏が死去した。原発不明がんと闘いながらも、亡くなる直前までメディアに出演し続け、世界経済の行方に多くの警鐘を鳴らしてきた。 「AIバブルは崩壊する…」「日経平均はこれから大暴落する…」 彼がこう語った背景には一体何があるのか。そして残された私たちは、この先行き不透明な社会をどう乗り越えていくべきなのか。 「闘う経済評論家」として世の中の歪に注目する息子の康平が、父・卓郎の「最後の問題提起」を真っ向から受け止め、私たちのこれからの人生に必要な「解」を紡いでいくーー。 『この国でそれでも生きていく人たちへ』より一部抜粋・再編集してお届けする。 『この国でそれでも生きていく人たちへ』連載第70回 『企業が重視するのは結局「学歴」…森永卓郎さんの息子・康平さんが「能力の低い人ほど学歴を重視せよ」と語るワケ』より続く。 学歴選抜はむしろ公平? 学歴による選抜は、ほかの選抜方法に比べて比較的平等だという意見もある。 「試験の点数で決まる」というのは、「親の地位や財産は関係ない」ということでもある。先にも触れたように、ある程度教育にお金を使えるほうが有利だろうが、現代においては「教育は貴族しか受けられない」というわけではない。学力という「実力」で決まる割合が大きいと考えられる。 学歴を使わない選抜方法にすると、選ぶ側の主観が入るし、それこそコネがあるほうが有利になってしまう。 もちろん、「学歴だけ立派なポンコツ」もたくさんいる。だから学歴偏重社会が実力主義になっていない面も大きい。ただ、学歴による選抜をやめれば公平になって格差がなくなる、というわけではない。むしろ、より格差が広がる可能性もある。 そもそも大学卒業時の学生の実力にそれほど大きな差はない。東大卒だろうが無名大学卒だろうが、どのみち自分でできることは限られている。要は、学歴偏重社会だろうが、そうでなかろうが、その中でどう生きていくかが最も重要ということだ。 その意味で、父の言うように、プレゼン能力やクリエイティブ能力を伸ばすのは有効な方法だろう。面接で人材を見極めるのはとても難しいので、プレゼン力が高い人のほうが有能に見えて有利だ。 「上辺だけ」の人材にならないために ただ、上辺だけ誤魔化そうと考えてはならない。結局入社したところで通用しなければ本末転倒なので、仕事の能力もしっかり高めていく必要がある。ある意味、そうやってしたたかにキャリアを形成していく力が、本当に必要な能力なのかもしれない。 繰り返しになるが、マクロの話とミクロの話は分けなければならない。マクロの経済政策が正しくても、その中で個人の生き方が間違っていて不幸になることもある。逆に、マクロの経済政策が間違っていても、個人で幸せになることは可能だ。 ただ、個人の生き方がうまくいっていないことを、マクロのせいにしても意味はない。 国がダメでも、個人としてうまくいった人はたくさんいる。マクロに期待するよりも、自分にできることを最大限やったほうが人生はうまくいくだろう。 こういうと、自己責任論のように聞こえるかもしれない。そうではなく、あくまでマクロ政策では弱者を切り捨てるのではなく、国全体の幸福を考えるべきだ。 ミクロな思考で国に頼らない生き方を 一方で、ミクロ、すなわち個人の生き方としては、自分の人生に責任を持ちましょう、ということだ。先ほども述べたように、テクノロジーの進歩は、個人でやれることを増やしてくれた。昔よりも国に頼らなくて済むようになっているはずだ。 昔は受験に失敗した場合、その後の人生で大きなデメリットを抱えることになったが、今は人生を逆転する方法がたくさんある。学歴がなくても成功した人はたくさんいるし、YouTubeで稼ぐ人だっている。少し前ならブロガーとして一財を成した人もいる。 だから、国がダメ、政治がダメと人のせいにしていても仕方がない。自分のためにやれることをどんどんやっていくほうが、成功に近づけるだろう。 『「親ガチャ」のせいは「現実逃避」…森永卓郎さんの息子・康平さんが「家庭環境」に対する考え方を実体験を交えて語る』へ続く。 【つづきを読む】「親ガチャ」のせいは「現実逃避」…森永卓郎さんの息子・康平さんが「家庭環境」に対する考え方を実体験を交えて語る