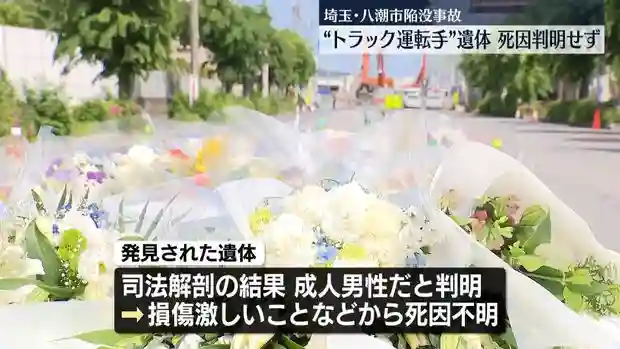再稼働に向けた安全審査は実に11年あまりに及びました。 原子力規制員会は、泊原発3号機について、事実上の合格を意味する「審査書案」を了承しました。 なぜ、審査は長期化したのでしょうか。 (原子力規制委員会 山中伸介委員長)「審査の結果の案を取りまとめることを決定してよろしいですか」 (規制委員)「決定してよいと考えます」 原子力規制委員会は泊原発3号機について、委員全員の一致で事実上の合格にあたる審査書案を了承しました。 北海道電力の原子炉の耐震設計や想定される津波への対応などが、新規制基準に適合していると判断しました。 北電が2013年7月に審査を申請してから、実に11年余りが経過していました。 なぜ審査が長期化? 原子力規制委の前委員も苦言 (原子力規制委員会 山中伸介委員長)「非常に困難なサイトというのは現在でもいくつか残っています。その代表的な例が泊の3号炉の審査だった。特に自然ハザードについて非常に慎重に審査を行った」 泊原発は再稼働に向け一歩前進した形ですが、全国的にみると関西電力の高浜原発や九州電力の川内原発は1年余りで「審査書案」が了承されています。 なぜ、泊原発の安全審査は長期に及んだのか。 2024年9月まで規制委員会の委員だった石渡明さんに話を聞きました。 (原子力規制委員会前委員 石渡明さん)「かなり時間がかかったなという印象ですね。北海道電力の場合は手戻りといいますか、たとえば火山灰の基準に使おうとしていた火山灰の地層そのものが実際にはありませんでしたということが途中で分かったりして」 (記者)「事業者側の問題が大きかった?」 (原子力規制委員会前委員 石渡明さん)「私はそう思いますね」 審査でポイントになったのは、泊原発の敷地内を走る断層です。 断層が活断層ではないと証明するため、大がかりな掘削調査が必要となるなど、審査に時間がかかりました。 (原子力規制委員会前委員 石渡明さん)「Fー1断層の場合、最初の時点ではしっかりした露頭がきちんと断層がよく見えるような状態になっていなかったんですよね。科学的にきちんとした形で確保されていなかったといいますか、しっかりした事実として我々の前に出されていなかったという面が大きいと思いますね」 また、北電は津波対策の防潮堤を一度建設しましたが、押し寄せる津波の高さなどを考慮し直し、新たな防潮堤を建設しています。 審査が長期化したことについて、北電の斎藤社長はー (北海道電力 斎藤晋社長)「非常に長い時間がかかったというのが正直なところです。その間、原子力の安全に対してしっかり議論するとともに、当社も技術力の向上であったり、いろんな体制をしてきました。今後運転に向けて世界最高水準の安全を維持するために絶えず努力していくことが重要だと思います」 今後、意見公募を経て、2025年夏にも正式合格となる見込みで、北電は2027年のできるだけ早い時期に再稼働したいとしています。 様々な審査ポイント 福島第一原発事故後に設けられた基準も こちらが審査の主なポイントです。 ▼泊原発の敷地内には11本の断層がありましたが、すべて「活断層ではない」と評価されました。 ▼津波では、高さ最大15.68メートルの津波の想定に対して、北電は海抜19メートルの防潮堤を建設中です。 ▼火山については、火山灰の影響が考慮されましたが、原子炉の安全機能は損なわれないと確認されました。 今回の安全審査は、福島第一原発事故の教訓から導かれた「新規制基準」に則っているかを判断しています。 地震や津波といった自然災害への備えは十分か、原発の設計基準はより強固になっているか。 そういった基準に適合しなければ、原発を稼働できないという大原則になっています。 30日に規制委が了承した審査書案が正式に決まると、第一段階の「原子炉設置変更許可」が下ります。 そのあと、原子炉の設計や工事などの妥当性を裏付ける「工事計画」や「保安規定」をクリアする必要があります。 そして、最終段階で「地元の同意」を得て再稼働に至るというのが一連のプロセスになります。 今後のハードルは「地元の同意」…どの範囲が“地元”?決まらぬ定義に周辺自治体は 泊原発3号機の再稼働については今後、地元の同意が必要になりますが、その地元とはどの範囲を指すのか、実は法的な定めはありません。 再稼働の是非について原発周辺のマチを取材しました。 泊村にある食堂です。 昼時になると次々と客が訪れます。 厨房で腕を振るうのは渋田真澄さん。 食堂と同じ建物で民宿も経営しています。 (記者)「一番出るメニューは?」 (渋田真澄さん)「やっぱり泊丼ですね。泊の海から来たりとか近郊の海のもの」 どんぶりから溢れんばかりのマグロやカレイ。 地元の海の幸をふんだんに使った「泊丼」です。 客の多くは泊原発で働く作業員だといいます。 渋田さんは、村の経済のためにも泊原発の再稼働には賛成の立場です。 (渋田真澄さん)「この右側の裏側になるんでしょうね」 (記者)「本当に近いですね」 (渋田真澄さん)「そうですね。300メートルあるかないかくらいですね」 (渋田真澄さん)「北電さんに助けられて、僕らも微力ですけど助けたいという気持ちがあって、共存共栄みたいな感じで僕はいます」 その一方で、原発の再稼働に反対する人も。 岩内町の町議会議員・佐藤英行さんです。 (佐藤英行さん)「泊原発の現地というのは4か町村なんですよね。4か町村を全部俯瞰できる場所なんです」 チョルノービリ原発や福島第一原発の事故などを教訓として、原発は廃炉にすべきと考えています。 (佐藤英行さん)「原発というのは1回事故が起きると取り返しがつかない歴史を生んでしまうということを皆さんに分かってもらって、そのために情報も公開していろいろなことを調べられるようにするべきだった」 今後必要になる「地元の同意」についてはー (佐藤英行さん)「本当は30キロ圏内あるいは80キロ圏内の人々も、放射能が出る原発に関しては発言権があるんだよということなんだと思います」 後志20市町村に独自アンケート 「地元の同意」各自治体の受け止めは? 「地元の同意」とはどこまでの範囲を指すのか? 実ははっきりとした規定はありません。 STVでは後志管内20の市町村を対象にアンケートを実施しました。 まず再稼働の賛否についてです。 賛成と答えたのは寿都町や黒松内町、島牧村など5つの自治体です。 泊村など原発立地の4町村は「申し上げる段階にない」などと答えました。 この4町村を含む10の自治体は「その他」と回答しました。 積丹町は議会で泊3号機の増設に反対する意見書を議決しているため、「特に慎重であるべき」としています また、「地元の同意」の範囲については、10の自治体が原発から半径30キロ圏内の市町村や後志全域などと回答しました。 再稼働の同意について鈴木知事はー (鈴木知事)「審査が継続中という状況なので、これまでも申し上げてきたが、予断をもって申し上げる状況にないことは変わりない。再稼働にかかわる地元同意の範囲についてはさまざまな意見があると承知しています。国としてはしっかり前面に立つということで方針を決めているわけですから、国で範囲確定することをやっていただく必要がある」 この夏にも審査に正式合格となる見込みの泊原発。 再稼働を最終的に判断する「地元の同意」が今後の焦点になります。