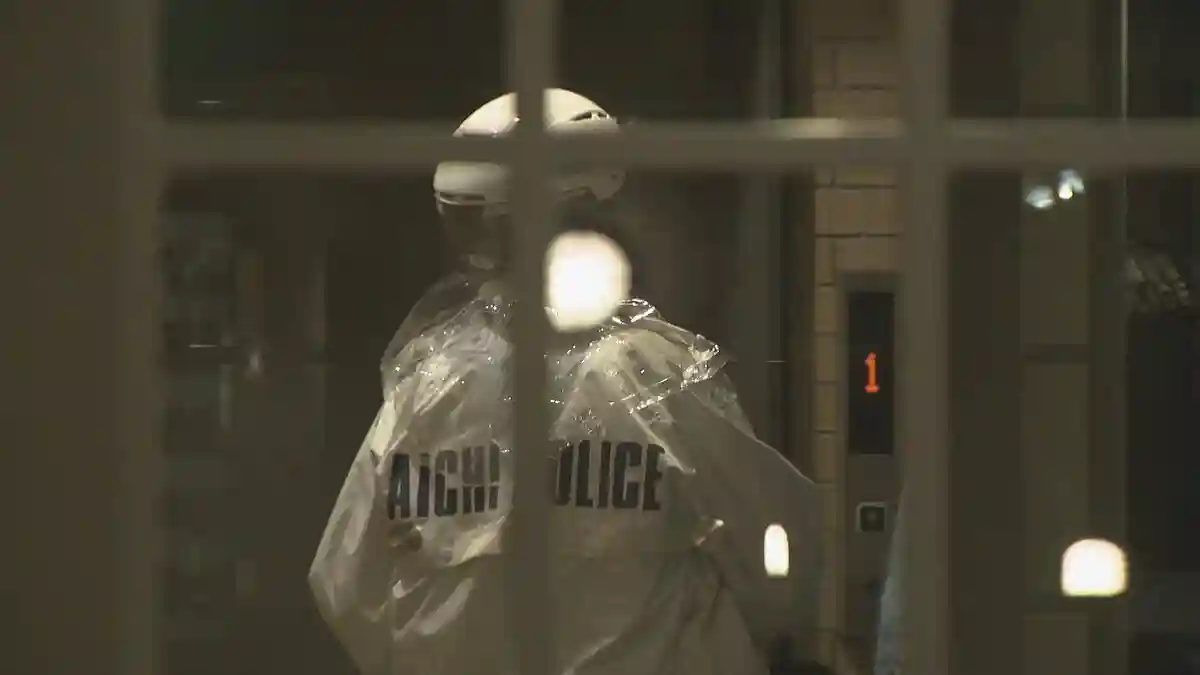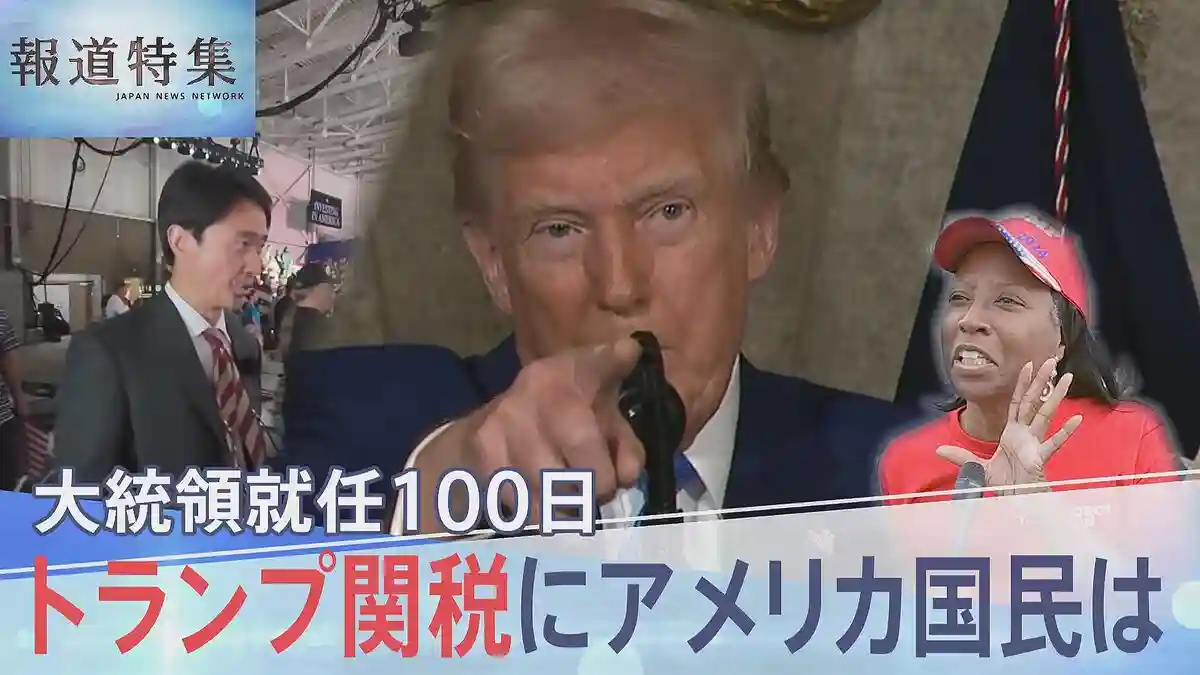明治時代におけるイギリス外交官の日本語勉強法 日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。 世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えた人も多いかもしれません。 日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『一外交官の見た明治維新』(講談社学術文庫)という本です。 著者は、イギリスの外交官であるアーネスト・メイスン・サトウ。1843年にイギリスに生まれたサトウは、1862年、幕末の日本を訪れ、在日イギリス公使館の通訳官や、駐日公使を務めました。 本書は、サトウが日本に滞在した期間に見聞きしたことをまとめたもの。そこからは、当時の日本が世界のなかでどのような立ち位置にあったのか、イギリスという「文明国」から日本がどう見えていたのか、あるいはそのころの国際情勢が伝わってきます。 たとえば、日本に来た外国人は、どのように日本人とコミュニケーションをとっていたのでしょうか。また、どうやって日本語を勉強していたのでしょうか。 本書より引用します(読みやすさのため、一部改行などを編集しています)。 *** 〈しばらく経って私は公使館の中に自分の部屋を持つことができ、ここで好きなだけ勉強をすることができた。ブラウン氏から受けた授業は非常に貴重であった。彼は、自身の著書『口語の日本語』を我々が音読するのを聞いてから文法の説明をしてくれただけでなく、『鳩翁道話』という本の序文を読み聞かせ、日本語の構成について理解を深めさせてくれた。 我々には二人教師がおり、一人は紀州和歌山の外科医である高岡要という人物で、もう一人の人物の名前は忘れてしまった。後者は頭が悪く、役に立たなかった。1863年の初頭にロバートソンが病気療養のため本国に帰ったので、私は高岡要を独占することができた。 当時日本政府とのやり取りは、彼らが唯一知っていたヨーロッパの言語であったオランダ語を介して行われた。そのため、日本の宮中言語はオランダ語であるという、あり得ないことを信じる人も当時はいたのである。それは真実からは程遠い。 オランダ語は、長崎のオランダ人居留地付きの通訳のみが勉強した言語であり、神奈川と箱館が外国との貿易のために開港したときに、この通訳たちの一部がこれらの港にあてがわれたのであった。 我々も、多少苦労はしたがオランダ語の通訳を集めることができた。それは、イングランド人が3人、ケープ出身のオランダ人が1人、スイス人が1人、オランダ本国からの純粋なオランダ人が1人で構成され、彼らは申し分ない額の給料を受け取っていた。私が日本語の読み書きや会話を覚え、これらの仲介人にとって代わろうという野心を抱いたのも当然だろう。 高岡はまず、読み書きを教えた。彼はまず短い文章を崩し字で書き、これを楷書に書き直して、その意味を教えてくれた。私はそれを翻訳し、それを記した紙をしばらくよけておいた。 そして、草書と楷書の両方の文章を再度読んだ。そのあと翻訳された文章を取り出して、記憶をたどってそれを日本語に書き直すというやり方で勉強したのである。このやり方は、ロジャー・アスカムや、私の学生時代の教科書の一つであった故ジョージ・ロング編集の『老年論』の序文において編者が推奨しているやり方である。 まもなく私は、いくつかの言いまわしを完全に会得した。当時の文語体は、他者を讃えるための定型的な語句を大量に用いることが作法だったので、これらを覚えたことによって書簡を書くことが極めて楽になった。 また、ある書道の老大家に毎日来るよう頼み、文字の書き方を教えてもらった。彼は眼病があり、涙が常に目にあふれていた。私の所作を訂正するために体を傾けるたびに、写本や紙、そしてテーブルに涙がこぼれ落ちた。強い学習意欲がなければ、このことを我慢できなかっただろう。〉 *** さらに「19世紀のイギリス外交官は、なぜ「日本という極東の国」に魅入られたのか? その意外な理由」では、サトウが日本に惹かれたきっかけについてくわしく紹介しています。 【つづきを読む】19世紀のイギリス外交官は、なぜ「日本という極東の国」に魅入られたのか? その意外な理由