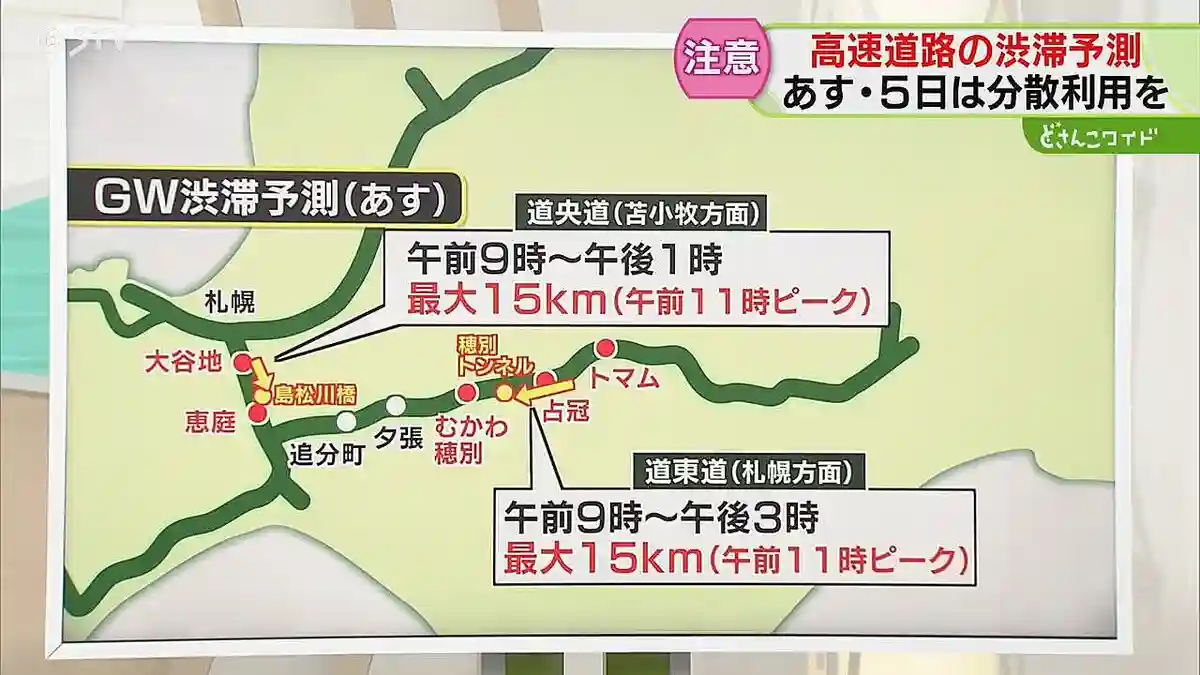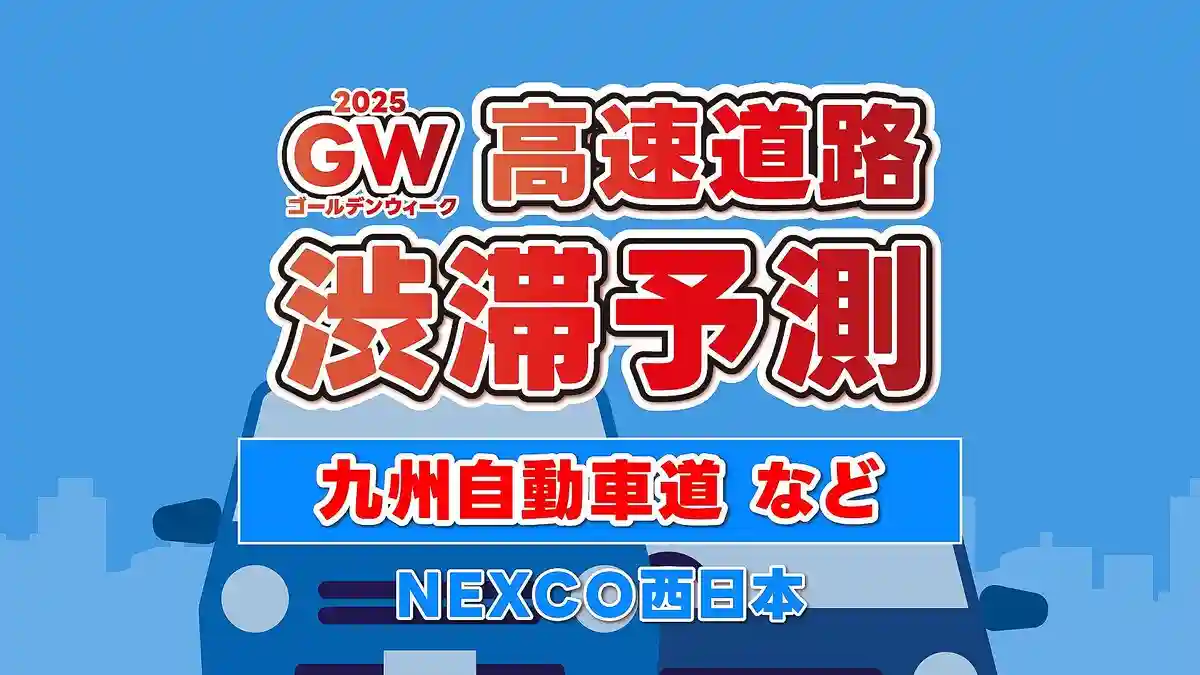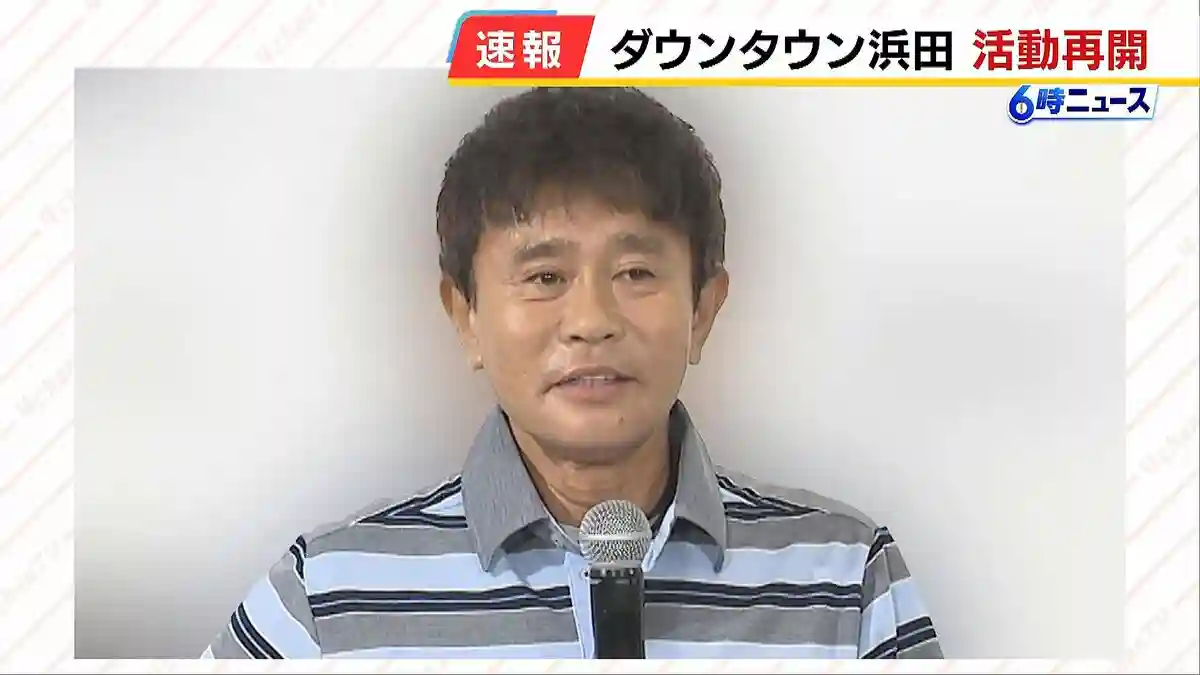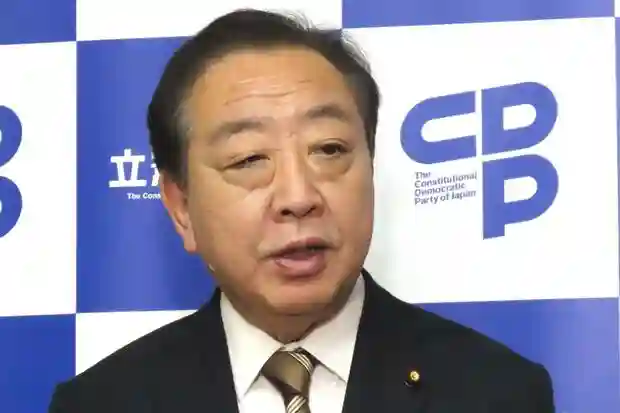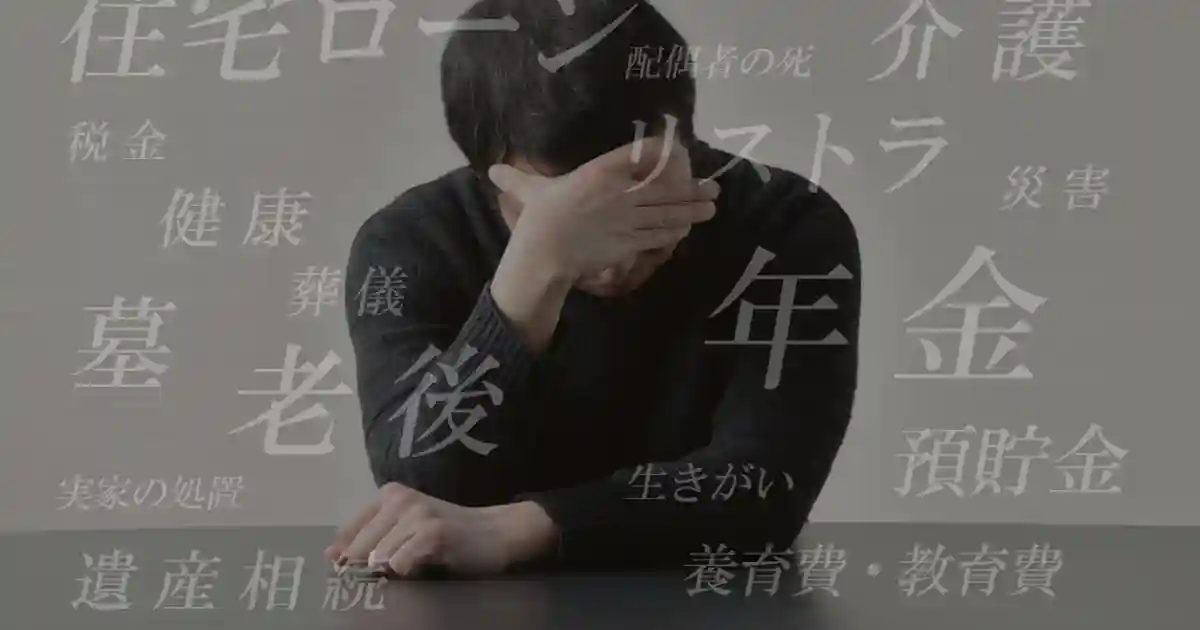
この国にはとにかく人が足りない!個人と企業はどう生きるか?人口減少経済は一体どこへ向かうのか? なぜ給料は上がり始めたのか、人手不足の最先端をゆく地方の実態、人件費高騰がインフレを引き起こす、「失われた30年」からの大転換、高齢者も女性もみんな働く時代に…… ベストセラー『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』では、豊富なデータと取材から激変する日本経済の「大変化」と「未来」を読み解く——。 (*本記事は坂本貴志『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』から抜粋・再編集したものです) 生産性が低いサービス業に人が集まる 付加価値額の増減と労働投入量の増減との関係を見てみるとどのような関係があるか。図表1-33は、内閣府「国民経済計算」から縦軸に労働生産性の変化を取り、横軸に労働投入量の変化を取って、その関係性を見たものである。 この散布図をみると、労働投入量変化と労働生産性変化には緩やかな負の相関があることがわかる。つまり、労働生産性が上昇している業界は労働投入量が減少している傾向がある。 逆に労働生産性が停滞している業界は、労働投入量が増大する傾向にある。このように生産性が上がらない産業に労働力が集中する現象は一般にボーモル効果と呼ばれるが、近年の日本の産業構造をみると、そうした効果が確かに顕在化している様子が見て取れる。 産業別にみたときにこうした現象が生じるのは、供給能力が向上しやすい業界と需要が増加しやすい業界が一対一に対応していないことが要因になっていると考えることができる。 製造業ではオートメーション(自動化)によって生産性が上昇した結果、より少ない労働力で付加価値を上げることができるようになっている。しかし、モノの需要は供給能力の上昇に比例して増加するわけではない。たとえば、工場における生産技術が向上し、自動車産業の生産能力が高まることでより安価で高機能な自動車の生産が可能になったとしても、それで国内の自動車需要が急増するわけではない。 逆に、保健衛生などの産業では高齢化に伴って需要が長期的に増加を続けている。しかし、たとえば介護業務の食事介助や入浴介助などのプロセスが数十年前と比べて変わっているかといえば、実態としてそのプロセスは大きくは変化していない。医療・介護の領域に関しては、機械化による効率化が進まないなかで、それと並行して需要だけが堅調に伸びてしまっているのである。 これは医療従事者や介護従事者のみではなく、ドライバーや建設現場の作業員、販売員、調理師、保育士などいわゆるエッセンシャルワーカーとして働く人で構成される産業に広くみられる現象である。 この現象をどう見るか。経済成長には需要の喚起が重要だと考えるのであれば、医療・介護産業は日本経済をけん引している産業だと捉えることができるだろう。しかし、経済成長には供給能力の強化が不可欠だという考え方に従えば、生産性が上昇しないまま膨張する医療・介護産業を評価することはできない。 こうした観点でみれば、過去のように人手がいくらでも余っていた時代であれば、膨張する医療・介護産業は労働市場のスラック(需給の緩み)を埋めてくれる貴重な産業であったといえる。 しかし、人口減少経済ではそうはいかない。希少な労働力を企業が奪い合う未来においては、各業界で限りある労働力を有効活用する取り組みが求められる。これからの時代においては、需要を喚起することよりも供給能力を強化することがより重要になるのである。 過去、需要が不足していた時代においては、企業が雇用を創出してくれることもまた望ましいことであった。しかし、そうした考え方も現代には徐々にそぐわなくなってきている。製造業に関して、過去には海外直接投資によって国内の雇用が失われることを懸念する声もあったが、日本経済はもうそのような局面にはないのである。 働き手が減少していくこれからの日本の人口動態を前提とすれば、日本におけるすべての産業がこれまで蓄積してきた資本や技術を活用しながら、少ない人手で生産する業態に変容していかなければならない。そのためにはボトルネックになっている産業の生産性を高め、より少ない人手で効率的に生産できる体制に変革させることが重要となる。 変化9 能力増強のための投資から省人化投資へ 経済の主な投入要素は労働と資本である。『ほんとうの日本経済』では主に労働に関する事柄を中心に経済環境の変化を記述しているが、労働市場と資本市場は密接に関係をしている。 ここでは、国内経済が人口減少局面へ移行していくにあたって、企業の投資構造にどのような変化が起きているかを概観する。 労働力を輸出する国から輸入する国に 図表1-34は日本の国際収支の動向をみたものである。 国際収支の長期推移をみると、貿易収支の黒字幅が縮小していることがわかる。近年では2011年から2015年に5ヵ年連続で貿易収支の赤字を記録したほか、2022年は15.7兆円の赤字を記録するなど、大幅な貿易赤字を計上する年も増えてきている。 2010年代前半の貿易収支の赤字は資源価格の高騰や東日本大震災に伴う火力発電のシェア拡大が大きな影響を及ぼした。また、足元ではウクライナ危機などに伴う原材料価格の高騰も貿易赤字の原因となっている。 このように貿易収支の赤字転換はその時々の短期的な要因によるところも大きいが、長期的にみれば日本の貿易収支が黒字であるというこれまで日本経済を支配してきた常識は、近年、明らかに通用しなくなってきている。 貿易収支が赤字基調に転じた背景には、製造企業の大規模な生産拠点の海外移転がある。海外直接投資の純資産残高は2023年末時点で257.2兆円に達している。同資産残高は2000年末時点で26.2兆円、2010年末時点で50.2兆円、2020年末時点で169.4兆円であったことから、近年も海外への投資が急速に伸びていることが確認できる。国内市場が相対的に縮小することが予想されるなか、企業は世界の旺盛な需要を取り込むために海外への投資を長期的に拡大させているのである。 貿易といえば、自国の技術の比較優位をもってして、海外へ財を輸出するといった側面がある。それと同時に輸出とは他国の代わりに製品を生産してあげる行為であり、逆に輸入は自国に代わって他国に財を生産してもらう行為にあたる。 こうした観点からみると、輸出は労働力が豊富な国からそうでない国に向かって行われるという側面もあり、時には二国間の貿易の不均衡をもってして失業の輸出をしているというような言われ方をすることもある。 『ほんとうの日本経済』では国内の労働市場を主に分析の対象としてきたが、労働市場は必ずしも国内で閉じるものではない。開放経済のもとでは、国内の労働市場は海外のそれとも緩やかにつながっているのである。 国内の企業が海外の労働力を利用しようと思ったときに選択肢になるのは、前述の海外直接投資があげられる。投資を行おうと考えたとき、企業はあらゆる選択肢の中で最も投資収益率が良い投資先に投資しようとする。投資対象国のマーケットが今後大きく成長し、高い収益を期待できるのであれば、国内への投資より当該国への投資を優先しようと考える。あるいは、投資対象国において安くて質の高い労働力が豊富に手に入るのであれば自国で生産するよりも容易に利益を確保することが可能であるため、企業は海外で生産しようと考える。 国内投資から海外投資へ 今後、日本の人口が減少するなかで、国内マーケットの世界におけるプレゼンスが相対的に縮小していくことは明らかである。企業の合理的な行動を前提とすれば、今後の日本で国内への投資が急速に拡大に向かうことは考えづらい。多額の資金やグローバルに通用する技術を有する国内企業は、今後も国内外問わず、最も収益を期待できる市場にその資本を投下していくことになるだろう。 これから先の長期の視点で見ると、日本の国際収支はどのように推移していくだろうか。国際収支については、発展段階説が広く知られている。 経済が未成熟の段階では自国の生産能力が低く、物資を輸入に頼らざるを得ないことから貿易収支が赤字となり債務が拡大する。その後、経済が発展していけば、次第に安い労働力を活用して輸出産業が成長し、貿易収支が黒字に転じる。そこからしばらくは貿易収支や所得収支の黒字幅拡大が続き、債権国に移行していくことになる。そして、やがて高齢化や賃金上昇などに伴って生産拠点としての国際競争力が低下し、債権を取り崩す段階へと移行していく。 国の経済発展と国際収支構造の変化をたどると、このように未成熟の債務国から成熟した債務国、未成熟の債権国、成熟した債権国へと移行していくことになる。このような理論に従えば、現在の日本は成熟した債権国の段階にあると考えることができる。 成熟した債権国の要諦は、海外の成長力をいかにして取り込み、それを国民所得の向上につなげていくかという点にある。これまで形成してきた資本や技術を活用して、効率的に高い収益を生み出すための仕組みを構築する必要があるのである。海外直接投資や海外証券投資の拡大によって所得収支が増加している現在の日本の状況は、このようにして理解することができる。 一方で、近年は現代ならではの注目を要する動きも見受けられている。インバウンドによる旅行収支の増加に反してサービス収支の赤字幅が拡大する傾向が生じているのである。 これにはGoogleやApple、Amazon、Microsoftなど米国のビッグテックへの支払いが急増していることが背景にあると考えられる。これらの企業が提供しているサービスは一見すると無料で提供されているように見えるが、消費者が直接支払うサービス購入料金やサブスクリプションはもちろんのこと、企業による広告掲載料金やクラウドサービスの利用料などを含めて、直接・間接を問わず、多大なサービス利用料が日本から米国に支払われている。 いわゆるデジタル赤字と言われる米国へのサービス料の支払い増加が日本の国民所得漏出を招いており、このような動きが強まっていけば、想像よりも早く債権の取り崩しの段階に入っていく可能性も否定できない。 国際収支はあくまで多国間でその収支がバランスすることが大切であって、黒字だから良いとか赤字だから悪いとかそういう考え方をすることは必ずしも適切ではない。 しかし、非資源国でありかつ世界に先駆けて人口減少と高齢化が進むであろう日本においては、国民所得向上のためにも、また日本円の信認を維持するためにも、これまで日本が築き上げてきた資産を最大限活かしながら、国際収支の黒字基調を極力維持することが重要になる。 省人化のためのソフトウェア投資は緩やかに増加 日本においては、国内投資は過去のような勢いでは伸びていかない状態が続いている。それは、国内のマーケットがこれ以上拡大していかないことに企業が気づいているからである。人口減少が約束されている日本の市場において、生産能力を増強するような設備投資はこれからも趨勢として伸びていくことはないだろう。しかし、だからといってすべての投資が日本国内から失われていくわけではない。 財務省「法人企業統計」から設備投資の動向を確認していくと、その中身が少しずつ変わってきている様子が確認できる。省力化のための投資が伸びているのである。 図表1-35は同統計から設備投資(ソフトウェア投資を除く)とソフトウェア投資の推移を表したものであるが、有形の固定資産投資が抑制されている一方で、ソフトウェア投資は長期的に拡大している様子が確認できる。 ソフトウェアを除く設備投資については、2023年で50.1兆円となっており、リーマンショック前の水準(44.3兆円)と比べて大きくは成長をしていない。一方で、ソフトウェア投資については7.9兆円から13.8兆円へと堅調に伸びている。 従来型の設備投資が能力増強のための投資であって、ソフトウェア投資はそうではないといった明確な区分けは難しいものの、後者の投資が効率化や省人化のための投資の色合いが強いということは確かだろう。 ソフトウェア投資が伸びている業態を見てみると、たとえば建設業や小売業があげられる(図表1-36)。 建設ではBIM(Building Information Modeling)による建設設計が普及し、建設機械の自動化施工も広がりを見せている。また、小売業ではセミセルフレジやセルフレジの導入が本格化してきており、多くの事業者が少ない人手で効率よく生産できる体制を整え始めている。 多くの人にとってなじみが深い事務の領域でみても、ビジネスチャットやweb会議ツールをはじめ、会計ソフトや勤怠管理ソフト、経営に関するさまざまな情報を統合的に管理するクラウドサービスなど効率化のためのさまざまなシステムが近年浸透してきている。 このように設備投資というと、工場などで生産能力拡大のために産業機械を導入するといった従来型の投資を思い浮かべる人が多いだろうが、情報技術の革新によってソフトウェアに比重が移りつつある。人手不足業種を中心に省人化のための投資はこれからも広がっていくだろう。 近年の日本の資本市場においては、国内マーケットの縮小懸念から投資需要が抑制され、金利も長く低い水準に抑えつけられてきた。そして、財・サービス市場でもデフレーションが進行する中で、実質政策金利を自然利子率以下の水準まで引き下げることができない、いわゆるゼロ金利制約に長く悩まされてきた。このような構造も労働市場がひっ迫していくこれからの経済環境の中では、変わっていく可能性が高い。 サービス関連業種の投資に関しては額自体がそこまで多くないことから、設備投資全体の基調をけん引していくかまではわからない。また、中小企業も含めてあまねく企業に先進資本の導入が進んでいくためには、新しい技術に安価にアクセスできる環境が不可欠であり、そのためにはさらなる技術革新を待たなければならない。 しかし、労働力が希少なものとなり、賃金水準がますます高騰する未来において、資本への代替の動きはさらに活発化していくだろう。人手不足による労働市場からの圧力が、日本経済のデジタル化を推し進めるのである。 【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ここへきて日本経済に起きていた「大変化」の正体