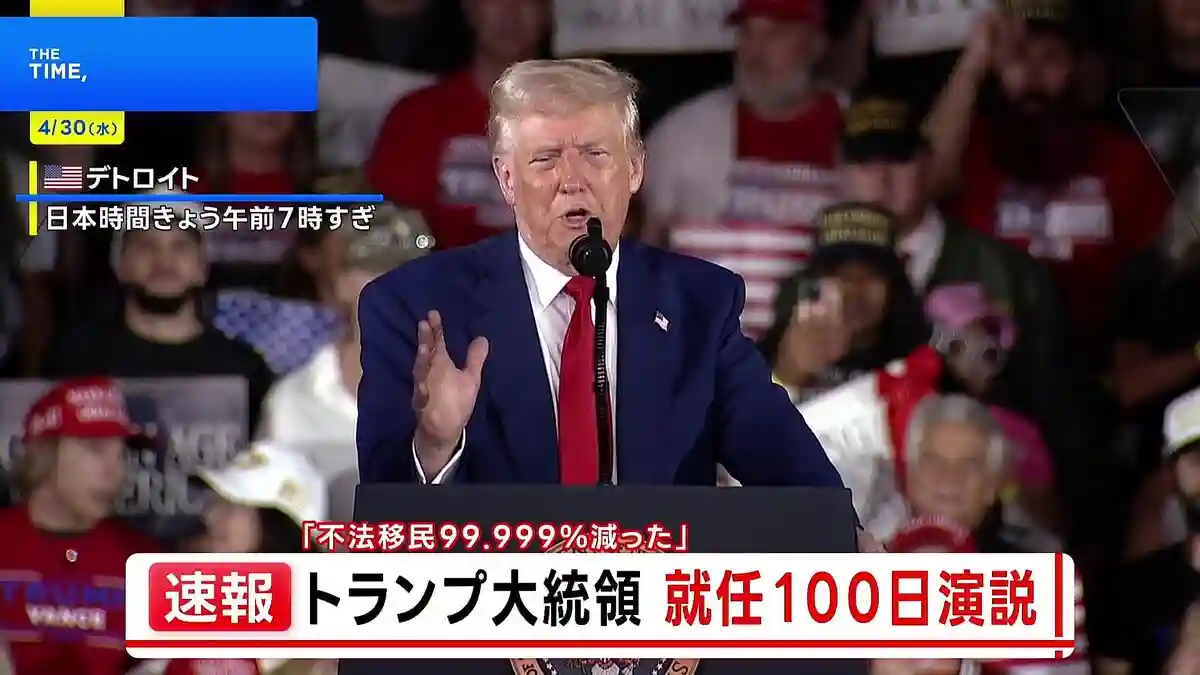グローバル化、格差拡大、揺らぐデモクラシー、近現代日本の戦争と平和——、現代日本の課題は、すでに戦前昭和にあった! 1980年代後半、冷戦が終結に向かう一方で、世界経済は大きく激動していく。日本も例外ではなかった。日経平均株価と土地価格指数はうなぎ上りに上がる。バブル消費社会の到来だった。 日本全国が好景気に沸き、人びとから戦争の記憶が消し去られたかのようだった。しかし、昭和天皇は戦争を忘れなかった。特に中国に対しての加害責任を気にし続けていた。他方で昭和の時代の終わりが近づいていた。 「戦後80年」であり「昭和100年」に当たる2025年に、『新書 昭和史』では、グローバリゼーション・格差・デモクラシーが織りなす日本の100年間の戦争と平和の歴史を追跡する。 (*本記事は井上寿一『新書 昭和史』から抜粋・再編集したものです) バブル消費社会──スーツのボタンだけで100万円 冷戦が終結に向かう一方で、世界経済は大きく激動していく。1985(昭和60)年9月22日、アメリカ・ニューヨークのプラザホテルでのG5(先進五ヵ国財務大臣・中央銀行総裁会議)会合後、共同声明(プラザ合意)が発表される。マクロ経済政策の協調だけでなく、ドル高是正を目的とする協調介入が決まったことは、ただちに日本経済にも影響を及ぼす。1ドル240円前後が翌年には150円にまで急上昇する。超金融緩和政策はバブル経済をもたらす。日経平均株価と土地価格指数はうなぎ上りに上がる。バブル消費社会が到来する。 あまたあるバブル消費社会の具体的な事例のなかで、一つだけ記しておく。1988年4月に三越日本橋本店に高級紳士服のオーダーサロンがオープンする。サロンの入り口は「ビクトリア王朝風の重厚でゴージャスなつくり」である。三越側が説明する。「アルマーニのプレタポルテを愛用しておられた方も、一度ここでオーダーメードされてからはお得意様になられました」。1着100万円のスーツも売れた。選べるボタンはボタンだけでワンセット100万円のものすらあった。スーツだけでなく、小物類も「一品仕立て」として、ワニ1匹をまるごと使ってそこからワニ革で小物類をすべてオーダーすることもできた(荻野目知子「『リッチ&おしゃれ』が泣いて喜ぶファーストサロン」)。 雇用の好調と物の安定が支えた楽観論 この類のエピソードが連綿と続くバブル消費社会が突然、冷却化する。天皇の病状が悪化していた。1988年の9月には新聞各紙が病名とともに報道するようになった。自粛ムードが一挙に広がる。歌舞音曲は控えなければならなくなった。ネオン街からは明かりが消えたかのようだった。100日あまりの自粛ののち、1989年1月7日、崩御の日を迎える。 崩御の前後でもバブル消費社会に変わりはなかった。『チベットのモーツアルト』などの作品でよく知られる文化人類学者の中沢新一は、同時代において、「何も起こらなかった/世がわり」と表現している。中沢は言う。「昭和から平成への世がわりで、なんといっても印象的だったのが、あの2日間。国民はほとんど昭和史の復習をさせられ、二日目にはすっかりあきてしまった」(中沢新一「何も起こらなかった/世がわり」)。「昭和史の復習」にあきた国民は、再びバブル消費社会に戻る。 東京の六本木ではゴールドのブレスレットをダブルでつけて、ブラックウィンドウのAMGメルセデス・ベンツのハンドルを握る「地上屋風にわか成金」が闊歩していた。高級車ブームだった。自動車評論家の徳大寺有恒は、当時、日本製の高級車をつぎのように批判していた。「クラスレス社会から生まれた高級車、拝金主義の国から生まれた高級車である」(徳大寺有恒「『高級車』」)。バブル経済は「拝金主義」を生む一方で、格差社会を逆転させるような「クラスレス社会」を可能にしたといえなくもなかった。 バブル景気に沸く日本で若い女性の贅沢は「大東亜レジャー圏」での長期休暇だった。彼女たちは東南アジアの「日本租界」化した島でゆったりと遊ぶ(「世紀末ニッポンの贅沢の行方」)。「大東亜共栄圏」構想がこのようなかたちで実現するとは、誰も予想しなかったにちがいない。 三菱総合研究所の佐藤公久は、当時、バブル消費社会の底流に「今の生活が一番大切、しかし10年後も結構ハッピー」という楽観論があるとみていた。この楽観論は好調な雇用状況と物の面の安定が支えていた。これらが失われれば、バブル消費社会は崩壊する。しかしともかくも「当分」はこのまま「いけそう」だった(佐藤公久「アウトドア型レジャー消費が/全開する」)。 未解決の問題 戦争責任は如何に バブル消費社会は人びとから戦争の記憶を消し去ったかのようだった。しかしあの戦争を忘れない人びとがいた。 昭和天皇もそのひとりだった。天皇にとって戦争を終わらせる大きな区切りになるはずだったのは、退位である。敗戦直後、あるいは独立回復後、退位すれば、戦争責任を果たすことができた。しかし退位の機会は政治によって奪われた。 退位しなければ、天皇の戦争責任の問題は続く。1971(昭和46)年の秋のことである。天皇の2度目の訪欧先は、デンマーク、ベルギー、フランス、イギリス、オランダ、スイス、西ドイツだった。ベルギーとオランダでは移動中の自動車が妨害を受けたり、西ドイツでは訪独反対デモがおこなわれたりした。天皇のもっとも信頼する模範国=イギリスでの晩餐会においても、エリザベス女王が戦争の過去にふれる発言をした。日本との戦争が終わって四半世紀を経ても、天皇に投げかけられる視線はきびしかった。 沖縄県民への最後のメッセージ それでも天皇が気にしたのは、欧州諸国に対してよりももっと大きな加害責任を負うべき中国に対してだった。中国との戦争は、日中国交正常化と日中平和友好条約の締結によって終わった。 この条約の締結の2ヵ月後(1978年10月)、�小平副首相が来日する。�小平との会談の冒頭、天皇は独断でつぎのように謝罪したといわれる。「わが国はお国に対して、数々の不都合なことをして迷惑をかけ、心から遺憾に思います。ひとえに私の責任です」。自身の戦争責任を認める率直で大胆な発言だった(古川隆久『昭和天皇』)。 天皇はさらに中国訪問を希望し続ける。天皇訪中が実現すれば、その時、中国との戦争は終わる。しかし結果的にその機会が訪れることはなかった。 天皇にとって戦争を終わらせるには訪中のほかにも沖縄訪問があった。天皇は1987年4月21日の記者会見において、つぎのように発言している。「念願の沖縄訪問が実現することになりましたならば、戦没者の霊を慰め、長年県民が味わってきた苦労をねぎらいたいと思っています」(久能靖『昭和天皇かく語りき』)。 沖縄訪問の準備が進行する。この年の7月28日、沖縄を訪れていた卜部亮吾侍従は、現地の関係者から「沖縄県民99%は歓迎」との情報を得ている(『昭和天皇最後の側近 卜部亮吾侍従日記 第3巻』)。 ところが翌月頃から暗雲が垂れ込めるようになる。天皇の健康問題が浮上したからである。9月14日には「手術にふみ切る線で沖縄もムリ」となった。 他方で沖縄国体が始まる。沖縄平和祈念堂における県民代表への天皇の「おことば」は、皇太子が代読する。そこには「一般住民を含む数多の尊い犠牲者を出した」ことだけでなく、「戦後も永らく多大の苦労を余儀なくされてきた」ことへの「深い悲しみと痛み」が記されていた。中国訪問だけでなく、沖縄訪問も実現することはなく、結果的にこの「おことば」が沖縄県民への最後のメッセージとなった。 それでも天皇は翌年4月25日の記者会見において、沖縄訪問の意思を語る。ところが記者との間で戦争をめぐる質疑応答がくりかえされる。天皇は率直に述べる。「なんといっても大戦、大戦のことが一番いやな思い出であります。戦後、国民が相協力して平和のために努めてくれたことを、うれしく思っています。どうか今後とも、そのことを国民が忘れずに、平和を守ってくれることを期待しています」(古川『昭和天皇』)。 昭和の時代が終わりに近づいていた。このメッセージが昭和天皇の国民に対する最後のメッセージとなった。翌年1月7日、昭和は終わる。中国訪問と沖縄訪問によって戦争を最終的に終わらせることはできなかった。つぎの天皇が戦争を最終的に終わらせなければならなかった。 【前回記事を読む】反ベトナム戦争運動で盛り上がる革命軍兵士たち--連合赤軍事件とあさま山荘事件という末路