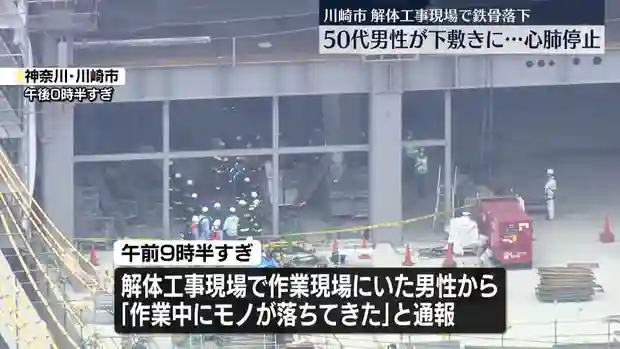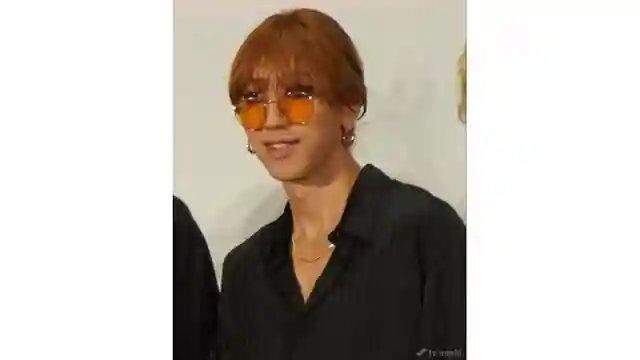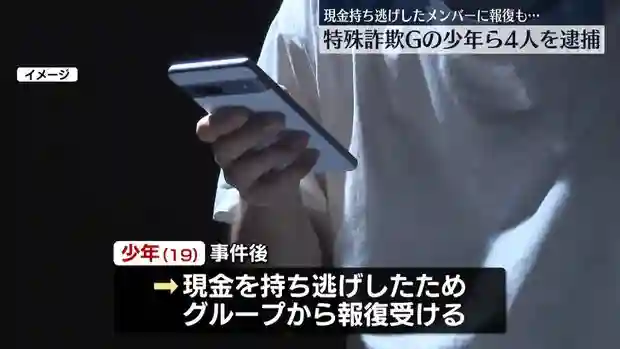ジャーナリストのなかのかおりさんは、「中学受験のバトン」という連載で、多くの中学受験に挑んだ家族の取材をしてきた。そこから見えてくるのは「いい学校」というのが必ずしも「受験難関校」ではないということだ。 子どもたちひとりひとりがその能力を伸ばし、生き生きと生活をするための「いい学校」とは何か。それを考えるためにも、なかのさんが多様な”学校”を取材していく。 今回は難関中高一貫校から通信制のN高に転校し、塾には行かずに自学で東京大学に合格しAさんになかのさんが話を聞いている。 前編では人気の最難関中高一貫校から通信制のN高に転校を決めた理由、そしてそこからどうして東京大学に行きたいと思い、達成したのかということを聞いた。 後編では中高一貫校、カナダの学校、そして通信制のN高を経験し、現在東大で学ぶAさんの考える「いい学校」と、現在の学び方を聞く。 カナダの影響は大きかった 通信制のN高から、東大理科二類に合格したAさん。N高で個別のサポートがあったのが、良かった。 「小さい頃は、割とおとなしくてテンションが低い感じの子でした。でも、親が共働きで家にいない時間、自分が弟の面倒を見なきゃいけない。しっかりしなきゃと思うようになったかもしれません。 積極的になったのは、カナダに留学した時かな。学校は部活動の形式が日本と違って、シーズンごとに違う部活をしました。秋はバスケ、冬はバレーボール、春夏はアーチェリーとボート。 他に吹奏楽のクラリネットや、ロボットを作るクラブにもチャレンジしました。1年しかなかったから、できるだけ全部やろうと思って、いろんな経験ができたのが良かったです」 あとは、授業内で発表する機会を経て、発言するようになった。 「目立つのは好きじゃないんですけど、以前よりは、コミュニケーションを取る面白さがわかりました。やっぱり伝えなきゃいけないんだ、と思い、人前で発言することができるようになった。留学を体験して、アクティブになった感じはあります」 「いい学校」とは Aさんの受験ヒストリーを伺うと、留学をきっかけにアクティブになったことで、自分の目標に向かって、N高と上手に付き合えたのではないかと思う。 通信制というと、不登校の生徒が多いと紹介されることもある。だが近年は、やりたいことがある生徒や、スポーツ選手も在籍している。いろいろな人がいて、それぞれの主体性を感じる。 Aさんが思う、「いい学校」は、どんな学校なのだろうか。 「 私にとっては、N高の授業は、受身の授業ではなかった。自分が興味があることに取り組む時間があり、自分の好きな方向で勉強する、その自由度が高いというのが魅力的でした。何より、N高の職員さんに、個別に適切なサポートをしていただいたのが、大きかったと思います」 東大ではラクロスに打ち込む さらに、進学した東大の良さを聞いたら、なんとAさんは、入学してまず、スポーツを選んだという。 「ラクロスに打ち込みました。一時期は休学して、部活を優先しました。東大の運動部の女子部の中では最大規模で、50人ぐらいいます。元々、東大でスポーツはやりたいなって思っていました。中高一貫校時代のバスケ部の先輩が、東大のラクロス部で活躍していて、誘われて新歓に行ったら楽しそうで、入りました。 東大に入るために、ずっとインドアで勉強をしてきたけれど、ラクロスをやってみたい。そういう環境や、チャレンジする気持ちが、仲間と共通しています。東大はグラウンドに恵まれていて、農学部のキャンパスにもあります。体を動かしたり、先輩や友達ができたり、すごく楽しかった。昨年の11月に、引退しました」 東大ブランドや、偏差値で選ぶ人も多い中、Aさんにとって東大のどういうところが「いい大学」なのか。 「東大に入ってから、部活漬けの生活をしました。朝練をやって授業に行って、また放課後練。朝練は基本、全員で練習する。あとは自主練とか、自主トレーニングっていう形ではあったんですけど、朝の練習が授業とかぶったら、練習を優先するみたいな感じでした。単位を取れるように、テスト前は勉強します。 私の代で初めて、1部リーグに上がって。ずっと2部や3部リーグのチームだったんですけど、1部に上がるのが目標で、達成できたので、部活に打ち込んで良かったと思っています。 部活は自分にとって、居心地もいいし、みんな勉強もラクロスも他のことも、すごく頑張っています。東大のラクロス部は、エネルギッシュな人が多くて、そういうチームに入れて、すごく楽しかったです」 そうした同じ価値観の仲間に出会い、恵まれた環境でスポーツや学問に打ち込める大学。それがAさんにとって、東大だったのだと思う。 やりたい研究を見つける これからAさんは、大学の研究室を選び、研究中心の生活に入る。 「いろんな研究室を回って、体験してみて最終的に決めます。研究に本腰を入れるところです。 農学部を選んだのは、間違っていなかったと実感しています。もちろん志望を変える人もいると思うんですけど、元々入りたいと思っていた学科に一番興味があります。 自分がやりたいと思ったことの方向性は、合っています。大学院まで行く予定で、修士課程、その先の博士課程に行くか、将来は研究者になるか、これから考えます」 N高に恩返しもしたい 現在、Aさんは、N高に恩返しをしている。Aさんが相談に乗ってもらったのと同じような枠組みで、チューターを務める。 「N高で、2種類の仕事をしています。一つは、私も受けていたコーチング。オンラインで希望者と、お話します。担当の生徒さんと週1回、面談をして、学習計画を立てたり、相談に乗ったりします。 もう一つは、N高にコミュニティがあり、サポートしています。それはN高、S高の中で、東大や京大を目指したり、勉強を頑張りたい生徒がつながるためのコミュニティです。東大生のメンバーが問題を作って、生徒が解きます。 自分がお世話になった先生経由で、声をかけていただいて、N高の子たちに還元したいと思ったんです」 自分で勉強したほうが効率が良かった コロナ禍以降、不登校が過去最多を更新し、個別最適な教育が求められている。スポーツややりたいこと、多様性を実現できるN高のような学校は人気だ。 文部科学省がまとめた2024年度学校基本調査(速報値)によると、通信制高校の生徒数が9年連続増加し、過去最多の29万118人に。私立通信制課程は29年連続増加し、3年連続で10%以上伸びた。公立の通信制課程の生徒も3年連続増加し、6万333人となっている。 目指す大学に行くために、「大多数の人が通る道」を行けば安心だからか、人気の塾や、予備校に早くから通う人は少なくない。そこから外れるのが怖い、という感情もあるだろう。 だから、自分のやり方を貫くAさんのような強さは、なかなか持てないかもしれない。 自分をしっかり持って、他の人と違う道を行き、やりたいことを実現するのは、簡単ではない。 「できなかったらどうしようとか、後ろ向きなことは考えてこなかったです。中高一貫校に残ったとしても、東大受験の難易度は変わらない。それだったら、自分で勉強した方が、効率がいいんじゃないかって考えたんです。 変わってるねと、しょっちゅう言われますよ。中学でも高校でも大学でも。実際に行動するところが、いい意味で変わっているのかな。やりたいと思ったことをやらないと、気が済まないっていう面はありますね」(Aさん) これからも、個々に合った、多様な方法で、行きたい大学に進学する生徒が増えるのではないだろうか。 【前編】最難関中高一貫校からN高に転校して「塾なし自学だけ」で東大合格するまで