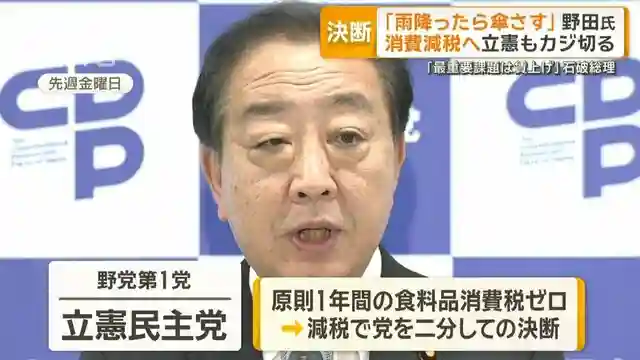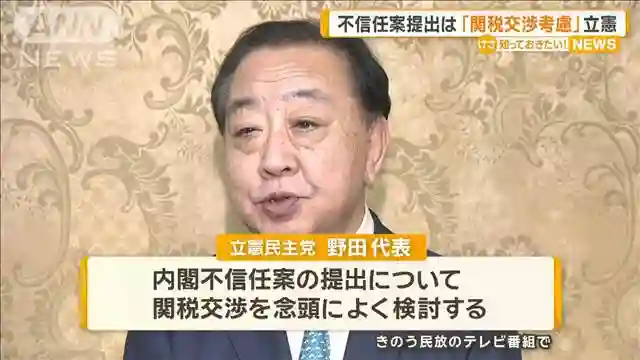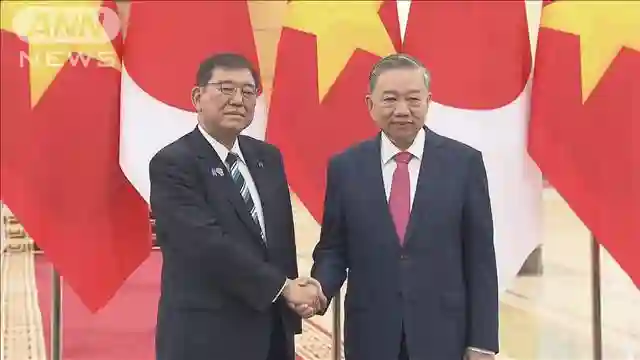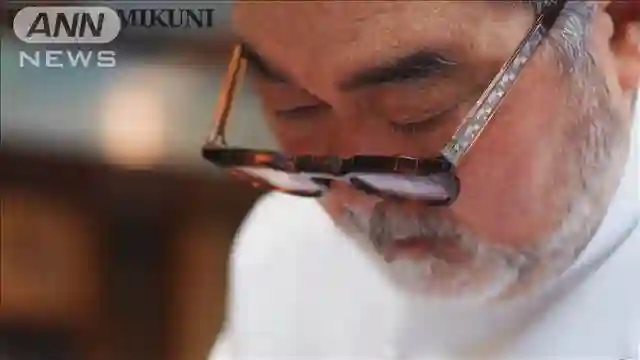[SNSと選挙]時代遅れの制度<2> 「暑くて困っちゃうわ」。 昨年7月の東京都知事選に立候補した内野愛里氏(32)は政見放送中に突然、服を脱ぎだし、胸元もあらわなチューブトップ姿になった。5分30秒の放送時間中、自分の名前を連呼するばかりで政策は一切語らず、「LINEのお友だち登録をしてね」と何度も呼びかけた。 普段は都内でバーを経営し、ユーチューバーとしても活動する。過去の政見放送で悪ふざけのような行動をする候補者がいたこともあり、「私も脱げば注目を集められるかも」と思いついた。都知事選の直前、政治団体「カワイイ私の政見放送を見てね」を設立し、出馬した。 政見放送を自身のユーチューブチャンネルに投稿すると、SNSを通じて瞬く間に拡散された。LINEの友だち申請が相次ぎ、約300人だった友だち登録はすぐに上限の5000人に。メッセージが来れば、「お店で待っていますね」と返信した。海外でも大きな話題となり、バーにはアジアや欧米からの訪日客が多く訪れた。 一方、街頭演説で訴えていた労働者の環境改善や子育て支援などの主張は、騒動にかき消されてしまった。「知名度がないと見向きもされないので、奇抜な行動をとった。でもかえって自分の問題意識を伝えることができなかった」。冷静になった今、そう振り返る。 ◇ 政見放送は、候補者が自身の政策や経歴をテレビやラジオを通して有権者に訴える場だ。公職選挙法は、政見放送について「そのまま放送しなければならない」と定める一方、候補者に対し、内容に一定の品位を保つよう求める。 具体例として、自治省(当時)はテレビで政見放送が始まった1969年、派手なメイクや過度な身ぶりをしないよう求めたが、品位規定に罰則はなく、派手な仮装をしたり、選挙と無関係な言動をしたりする候補者はその後も現れた。 インターネットを利用した選挙運動が2013年に解禁され、SNSに政見放送を投稿できるようになると、この傾向が加速。過激なパフォーマンスに走る候補者が続出するようになった。 21年の千葉県知事選の政見放送では、ピエロのような白塗りメイクをしたり、公開プロポーズをしたりする候補者が現れた。県選挙管理委員会には「税金の無駄」「県民をばかにしているのか」と苦情が殺到。政見放送のあり方を巡る議論は国会で度々、俎上(そじょう)に上るが、見直しの機運は高まっていない。 政見放送を収録するNHKは事前に、全候補者に対し品位規定の内容を説明している。身体障害者への差別発言を削除して放送した例はあるが、原則として内容に介入したり、編集を加えたりすることはない。NHKは「政見放送の内容は候補者が自らの責任で決めるもの。今後のあり方は国会で議論されるべきだ」とする。 ◇ 昨年の都知事選の政見放送では、政治団体「NHKから国民を守る党」の候補者たちが、「掲示板のスペースを開放する」「お近くに掲示板がある方はチャンス」と訴え、「詳しくはNHK党のホームページへ」と呼びかけていた。 同団体はホームページ上で、擁立候補の選挙ポスター掲示板の枠を事実上販売していた。政見放送中の特定の商品広告や営業宣伝は公選法で禁止されているが、政見放送外のSNSに誘導した視聴者に営業活動をしても、処罰する規定はない。 選挙制度に詳しい高千穂大の五野井郁夫教授は、「候補者が広告塔となり、政見放送を売名やビジネスに悪用する動きが広がれば、選挙制度への有権者の信頼がゆらぎ、政治離れにつながりかねない」と警鐘を鳴らす。