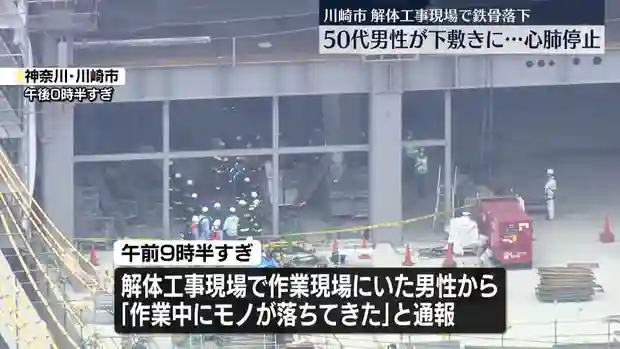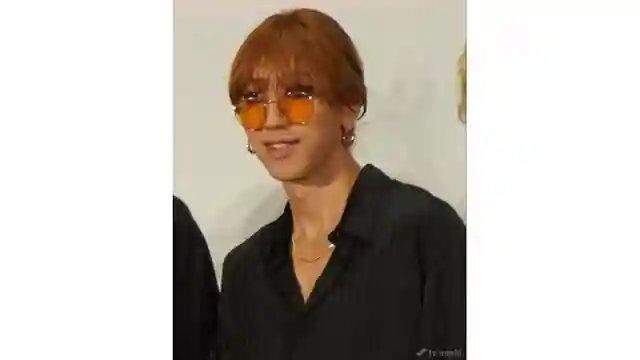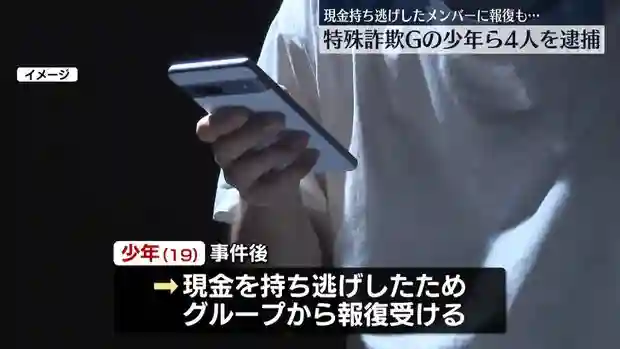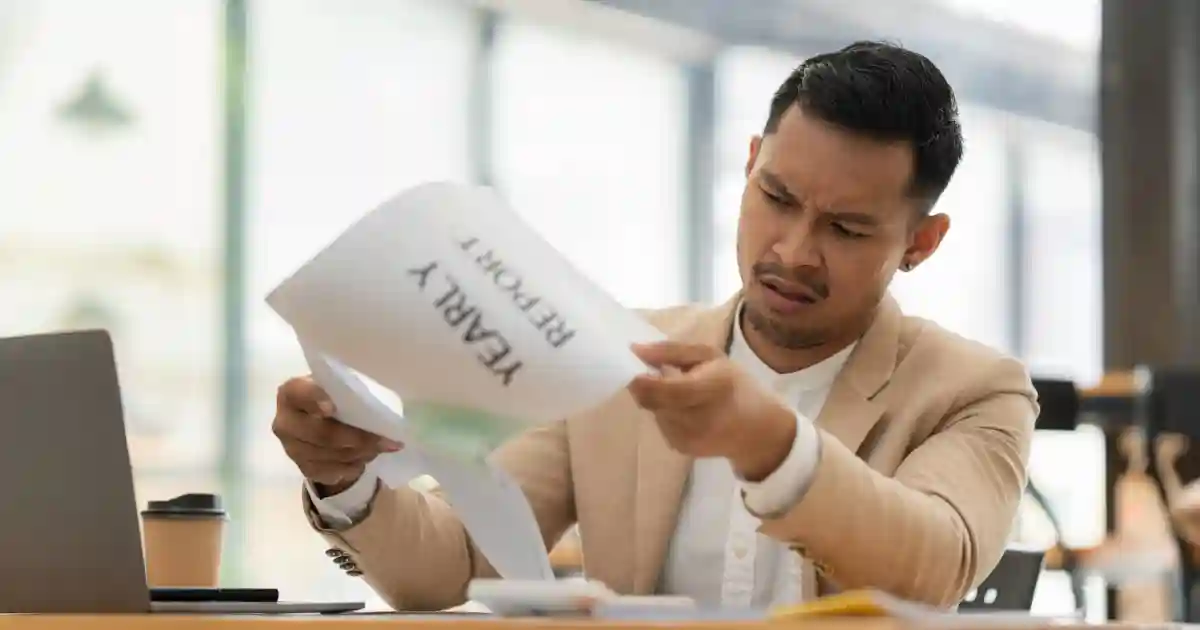
メールやSNSをはじめとして、仕事でもプライベートでも文章を書く機会は多くあります。ところが他人に分かりやすい文章を書くのが苦手、という人は意外に多いようです。 こうした「文章の技術」に焦点をあてた大ベストセラー『「分かりやすい文章」の技術 』 が新装版になって発売となりました! 新装版では時代に合わせて内容をブラッシュアップして、更に「分かりやすく」進化しています。 本記事では20年以上読みつがれる本書から、読みどころを厳選してお届けします。 ※本記事は、「分かりやすい文章」の技術 新装版 読み手を説得する18のテクニック 』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。 文章術の最重要テクニック 小説では、しばしば冒頭で謎の事件を紹介し、読者の興味を呼び起こします。 映画でもよく、冒頭で、互いに関係のなさそうな断片的映像をいくつも見せて、観客に「何だろう?」と思わせ、物語の世界に惹き入れてしまいます。 芸術文ならそれでも合格ですが実務文では失格です。実務文はまず「何が言いたいのか?」がはっきりしなくては読んでもらえません。 たとえば、あなたがお客様向けに書いたダイレクト・メールの文章が、一読しただけで趣旨が伝わらなければどうなるでしょう。たとえそれがお客様にとって本当に有利なお知らせだとしても、お客様は「文章」を理解しようとしないまま、ゴミ箱に放り込んでしまうでしょう。 裁判の判決で裁判長は、まず「被告人を懲役五年に処す」などと主文を読み上げ、それから判決理由を述べるのが普通です。先に判決理由を長々と述べて、「無罪だろうか?有罪だろうか?」と気をもませるようなことはしません。 分かりにくい文章は、こうした判決文とは逆に、読み手に「いったい何が言いたいんだろう?」と気をもませます。 実務文は感動ではなく情報を伝えるのが仕事です。読み手を待たせない構成が良い構成なのです。 それでは、どうしたら一読で趣旨が伝わる構成にできるのでしょうか。良い構成のための最重要テクニックが皆さんも聞き飽きているはずの「要点を先に、詳細は後に書く」なのです。 早く脳内辞書を選ばせる では、なぜ要点を先に伝えると分かりやすいのでしょうか? その理由は、脳内関所の作業負担を軽減できるからです。 脳内関所の最初の仕事は「いろいろある辞書の中から適切な一冊を選ぶ」という作業でした(第二回記事参照)。脳内関所が辞書を選び終えるまでは、詳細情報を送っても、読み手は理解することができません。 脳内関所の辞書選びを助けるには、最初に概要情報を与えてやればよいのです。そうすれば早々と辞書が決まり、その後に送られてくる詳細情報も処理しやすくなります。 どの「かたまり」にも適用できるテクニック「要点を先に書く」のは、文章のあらゆるレベルに適用できるテクニックです。ここで言う「レベル」とは、文章内にある「かたまりの大きさ」を意味します。 本を例にとれば、まず本一冊全体の文章がいちばん大きな「かたまり」です。 次に「章」というかたまりがあります。もちろん、その一つの「章」の中でも、このテクニック「要点を先に書く」は生きています。章の冒頭で「この章では○○○を紹介します」と概要を書くという単純な対策で、分かりやすさは一段と向上します。 「章」の次に小さいかたまりに「節」があります。「節」は、さらに小さい複数個のかたまり「段落」の集合体です。段落を構成しているのは、より小さな「文」というかたまりです。 本書では、「文章」や「文書」という言葉との混同を避ける目的で、句点で終わる一個の「文」のことを「センテンス」と呼ぶことにします。 本に限らず、企画書でも論文でも報告書でも、どんな文書でも、いちばん大きな「かたまり」から、小さな「センテンス」という「かたまり」まであります。どんな大きさの「かたまり」でも常に、その「かたまり」の中で「要点を先に、詳細は後に書く」テクニックを使いましょう。 「要点」と「詳細」を他の言葉に置き換えても同じです。 「結論を先に、理由は後で」、「主張を先に、根拠は後で」、「結果を先に、原因は後で」などです。 「趣旨」を冒頭に置く たとえば、ある老人が自分のパソコン体験を短い文章に表現する場合を想定してみましょう。 この人がその文章でいちばん訴えたいのは「ホームページ作りは本当に楽しい。みなさんもぜひ挑戦しましょう!」だとします。 次に示す例では、分かりやすくするために、各段落の趣旨をそれぞれ一つのセンテンスで表現しています。その文章が、次のような趣旨の五段落で構成されていると考えてください。 段落1 孫にパソコンを勧められた。 段落2 買ったパソコンは思い通りに使いこなせなかった。 段落3 パソコン・スクールに通って苦労した。 段落4 インターネット接続にも苦労した。 段落5 その結果のホームページ作りは本当に楽しい。みなさんも挑戦しましょう! この構成は、芸術文なら問題ありません。時間順に書かれていて読みやすく、そうした体験の結果としての感想が最後に置かれるのも自然です。 しかし、たとえばインターネット・プロバイダーが、顧客にホームページ作りを勧める宣伝文の中で、この老人の体験談を利用する場合を考えてみましょう。 そうなるとこの文章は、ホームページ作りの楽しさを広く知ってもらい、そのプロバイダーへの加入者を増やそうという明確な目的を持つことになります。 その目的のためにいちばん言いたいことは「ホームページ作りは本当に楽しい。みなさんも挑戦しましょう!」のはずです。 ところが、そのことを述べた段落は、最後に置かれています。これでは実務文としては落第です。「斜め読み耐性」がないのです。 そこで次のように改善すべきでしょう。 斜め読み耐性を強化した文章 段落1 ホームページ作りは本当に楽しい。みなさんも挑戦しましょう! 段落2 孫にパソコンを勧められた。 段落3 買ったパソコンは思い通りに使いこなせなかった。 段落4 パソコン・スクールに通って苦労した。 段落5 インターネット接続にも苦労した。 段落6 ホームページ作りは本当に楽しい。みなさんも挑戦しましょう! 文章全体として伝えたい趣旨を含む段落を最初に置くことで「斜め読み耐性」を強化しました。 また、最後に段落1と同じ内容の段落6があることに注意してください。この点については後ほどお話しします。 このように、概要を伝える段落が冒頭にあれば、読み始めてすぐにその文章の目的を知ることができます。そのテーマに関心のある人は読み進みたくなります。 このテーマに関心がない、または読む必要のない人は、そこで読むのを止めることができ、時間の浪費を最少にできます。しかも読むのを止めても、「ホームページ作りは楽しい」という文章の趣旨は、りっぱに伝わっているのです。 これなら情報を素早く効率的に伝える実務文として合格です。「要点を先に書く」だけで「斜め読み耐性」を強化した文章にできるのです。 * * * 今回の記事では「要点を先に、詳細は後に書く」というテクニックを紹介しました。次回記事でも引き続き、このテクニックのポイントを解説します。 初回から読む>>>「日本の文章は誤解されやすい」という「衝撃の事実」! 日本特有の文化が生む「分かりにくさ」の「正体」! 【はじめから読む】「日本の文章は誤解されやすい」という「衝撃の事実」! 日本特有の文化が生む「分かりにくさ」の「正体」!