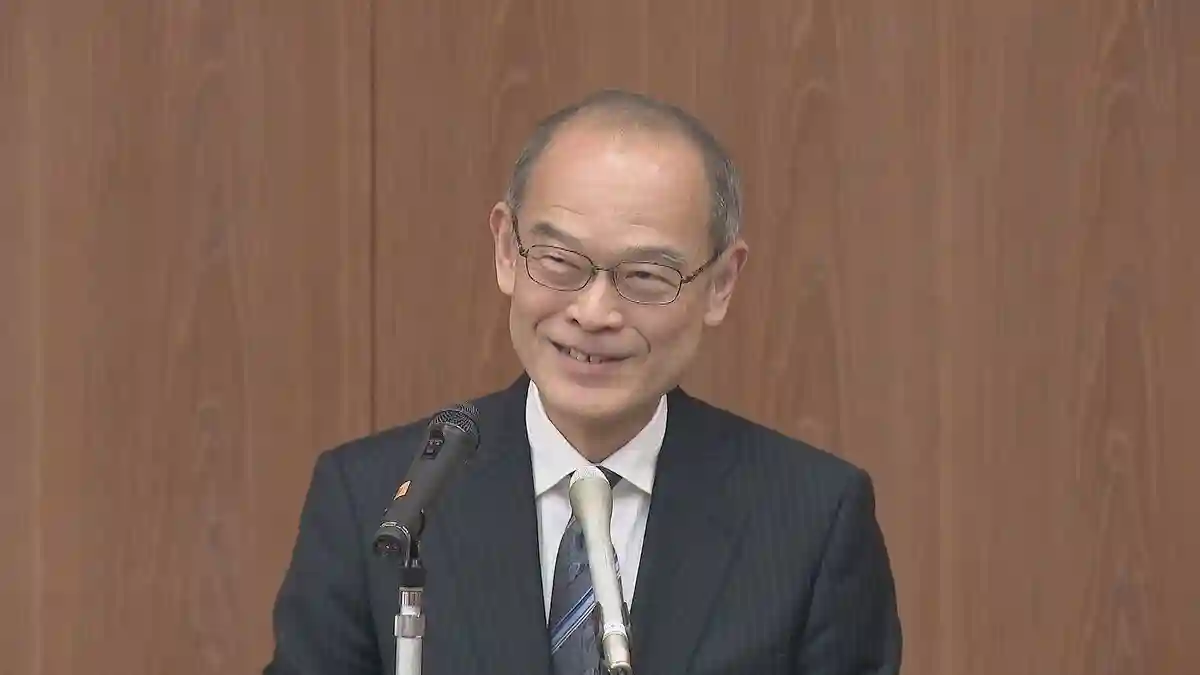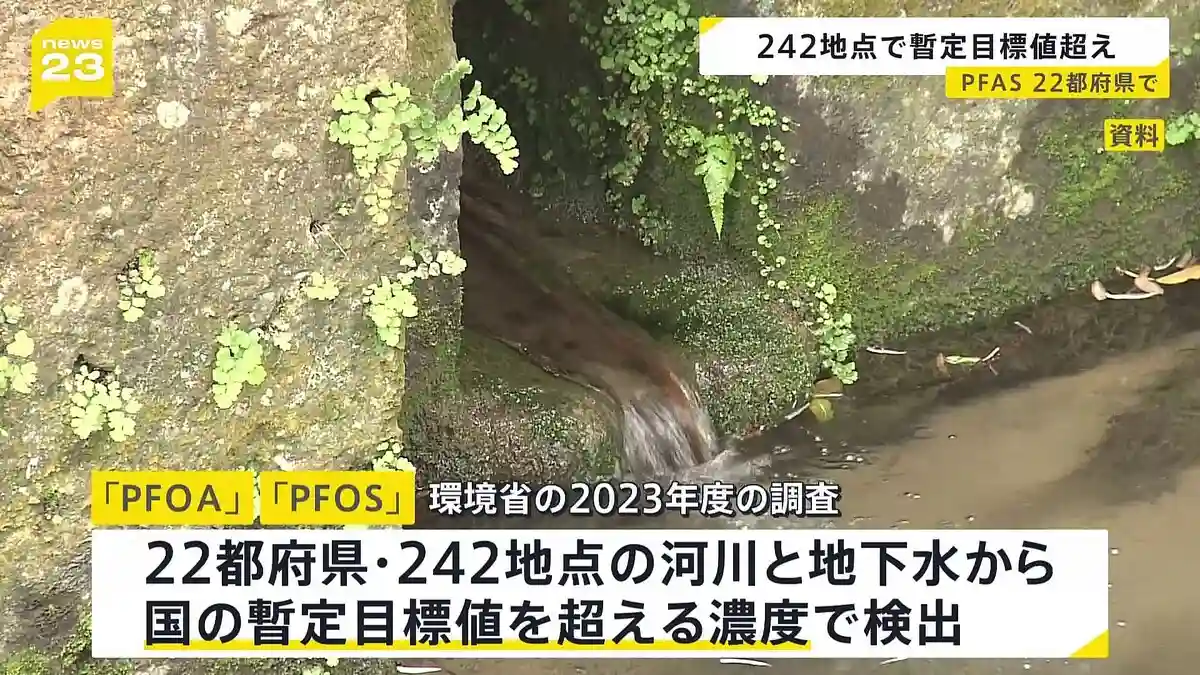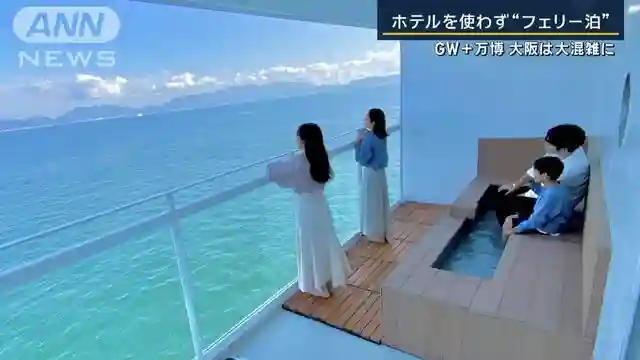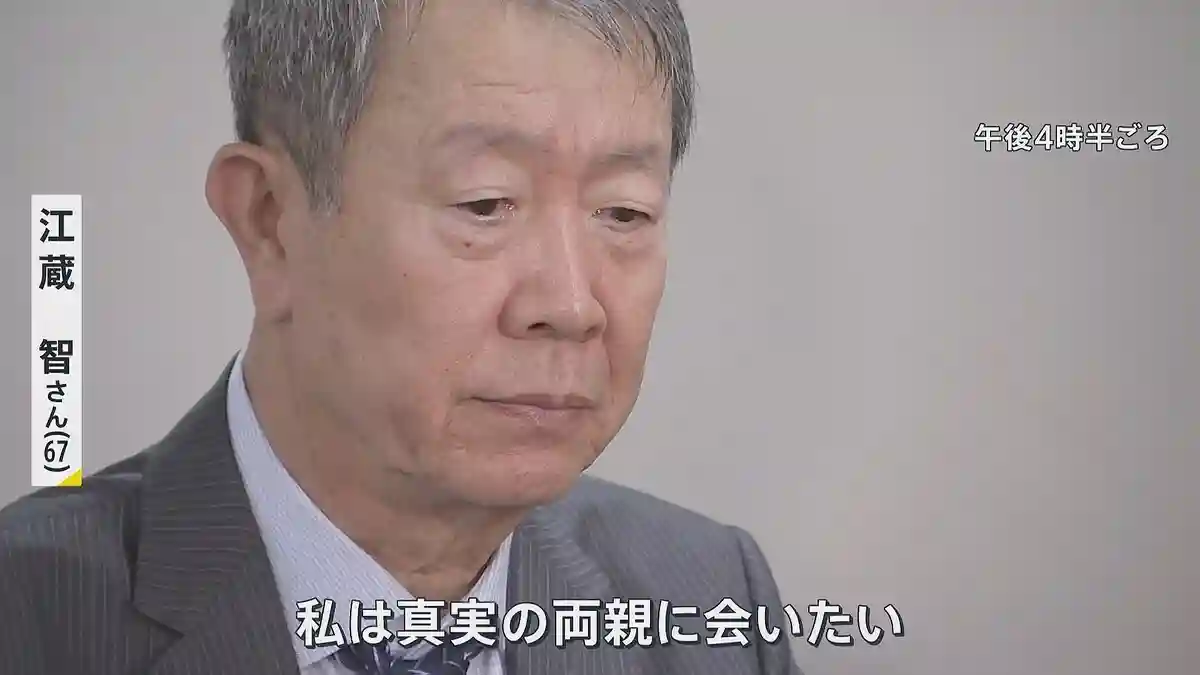近ごろ、テレビやネット上で「米不足」や「価格高騰」に関する報道を目にする機会が増えた。しかし、それらの情報の多くは一部の現象だけを切り取ったもので、全体像が見えにくい。「なぜこんなことになっているのか?」という本質的な部分に触れた内容は、実はあまり多くない。筆者は米屋として、日々、農家・集荷業者・JA(農協)などと関わる中で、現場からの“生の情報”に触れている。この経験を通じて得られた知見を、多くの人にできるだけわかりやすく伝えようと、情報発信を続けている。 米の業界は「ブラックボックス」、外からは実態が見えにくい世界だ。だからこそ、内部の動きを読み解き、可視化することは、農家の生産意欲を支え、消費者の理解を深めることにもつながっていく。 値上がりし続け、令和の米騒動へ 今回の“米パニック”とも呼ばれる騒動のきっかけは、ひと言で言えば、メディアの報道と、それに反応した消費者の買いだめである。特に8月は「端境期(はざかいき)」と呼ばれる、新米の出回り前でお米の在庫が少なくなる時期。もともと流通量が減るこの時期に、需要が急増したことが引き金となり、令和6(2024)年産のお米の価格は大きく上昇した。 この値動きは、業界内でも「想定外」と言われるほど急激なものだった。 では、どのような流れで価格が高騰していったのか? 以下では、そのプロセスを3つの段階に分けて説明する。 【第1段階】スーパー・量販店の先手買い 最初に動いたのは、スーパーや量販店といった小売業界だった。 品薄を感じた店舗は、「とにかく商品棚にお米を並べなければ」というプレッシャーから、卸売業者に対して強く仕入れの要請をかけたと考えられる。それに応じて、卸業者は7〜8月に収穫される“早場米”の産地(鹿児島、宮崎、佐賀、千葉など)に直接足を運び、農家と直接契約を始めた。問題はそのときの価格設定である。例年、高値をつける魚沼産コシヒカリの価格を上回るほどの買い取り価格で交渉が成立し、それが市場全体の価格を一気に押し上げることとなった。 コンビニも外食産業も米獲得に必死 【第2段階】農協への集荷が減少 この早期の直接買い付けは、全国に波及。本来なら農協(JA)に集まるはずだった米が、民間流通に流れてしまい、農協の集荷量が大幅に減少した。結果として、全国の卸売業者に対する供給が2〜3割減となり、足りない分を補うために、卸業者同士のやり取りや民間市場からの追加仕入れが活発化した。この動きもまた、価格の上昇を後押しする要因となった。 【第3段階】コンビニ・外食チェーンの“確保合戦” 次に動いたのは、コンビニチェーンや大手外食チェーンである。安定した店舗運営を守るため、これらの企業は商社などを通じて、産地での在庫確保を進めた。こうした動きが重なる中で、農協が提示する「通常価格」の1.3〜1.4倍といった高値での取引が定着していった。 この一連の流れを経てもなお、お米の需給バランスは不安定なままだ。令和7(2025)年4月時点での民間取引価格は、農協が卸売に提示する価格(相対価格)と比べて約2倍にまで上昇している。 これは単なる一時的な品薄ではなく、制度(生産調整)・流通(早期買い付け・直接契約)・心理(買いだめ・供給不安)が絡み合って生じた構造的な価格高騰と見るべきだろう。 なぜ今、日本のお米が足りないのか? 今年春、日本各地のスーパーや飲食店で「お米が手に入りにくい」「値段が想像以上に高い」といった声が相次いでいる。一体なぜ、米どころの日本で“米不足”が起きてしまったのか? 要因1:生産調整が引き起こした“供給不足” まず押さえておきたいのは、国(農林水産省)が続けてきた生産調整の影響である。 時は令和2(2020)年、コロナ禍の最中。飲食店の休業が相次ぎ、業務用需要が急落したことにより、国内の米流通には大きなギャップが生じた。実際、令和2年は12万トン、令和3(2021)年は19万トンの米が余剰となり、わずか2年間で約31万トンの在庫が発生した。 従来より統計を重視する農水省は、翌年以降も「消費は年間10万トンずつ減っていく」と予測し、各産地に対して作付面積を抑える“生産調整”を継続してしまった。だが、令和4(2022)年〜6年の年間消費量は、飲食業、家庭な消費も堅調となり、700万トン前後で需要が安定しており、想定より大きくは減っていなかった。結果として、国の予測と現実のギャップが拡大。需要があるのに作らせなかった政策判断が、令和6年産の米不足を招いたと考えられる。 国のデータにズレがある可能性 要因2:農水省の統計に“見えないズレ” 次に注目したいのは、国が発表する米の生産量データに誤差がある可能性だ。以下の3点がその根拠とされている。 � 作況指数と現場の感覚がずれている 毎年、農水省は「作況指数(米の生育状況を数値化したもの)」を公表しているが、実際の収穫量との差を感じるという声は、農家から多く聞く話だ。特に民間の集荷業者が多い県では、「農協ルートよりも実態が把握しづらく、数字にブレがある」とされる。これは、現場の情報が行政に正確に届いていない構造的な課題とも言える。 � ふるいのサイズの違いが“見えない減少”を生む 農水省が収穫量を推定する際には、「1.70mmのふるいを通った粒」(ふるいの上に残った粒)を基準にしている。 しかし、現場で実際に使用されているふるいは、西日本で1.85mm、東北などで1.90mmといった、より粗い網が主流だ。これにより、実際の製品として出荷される量は、農水省の推計より20〜40万トン少ないと見られている。参考までに、令和6年産の公表収穫量は679.2万トンだが:1.85mmのふるい基準で見た場合 → 657.2万トン1.90mm基準 → 639.6万トン。 この数字の開きが、“実感としての米不足”をより強く感じさせる一因となっている。 � 作付面積にも誤差の可能性 農水省は毎年、全国の稲作面積を公表しているが、これにもズレがある可能性が指摘されている。ある県では、公式データ上は「前年より300ヘクタール増加」となっていたが、実際に地元農協関係者に取材すると「実感としては2〜3%減っている」との回答があった。 仮に全国的にも作付面積が2%減少していたと仮定すると、125.9万ヘクタール → 123.4万ヘクタールとなり、その影響で生産量はさらに下がり、仮に1.85mm基準で見れば644.1万トン前後となる。消費量(約700万トン)との差は約56万トン。備蓄米を21万トン放出しても、単年度だけで見ても不足分は埋まらない計算だ。 米を巡る「ブラックボックス」 米不足の報道には、しばしば「消費者の買い占め」や「メディアの過剰報道」が原因とされることがある。しかし、今回見てきた通り、本質的には政策判断のミスや統計のズレが根底にあることは否定できない。問題なのは、これらの数字や制度の問題が、農家や消費者には十分に見えてこない“ブラックボックス”であることだ。 今後、日本の食を支える米の安定供給を守るには、「現場の実態と統計のすり合わせ」、「農業従事者が安心して生産できる環境づくり」が求められている。 「マイナ保険証」が義務化…でも、あせって「マイナ保険証」を作ってはいけないこれだけの理由