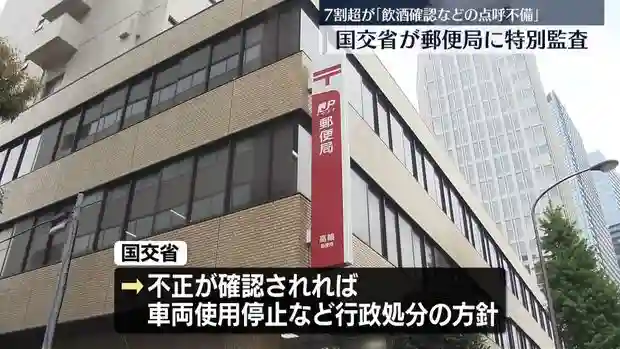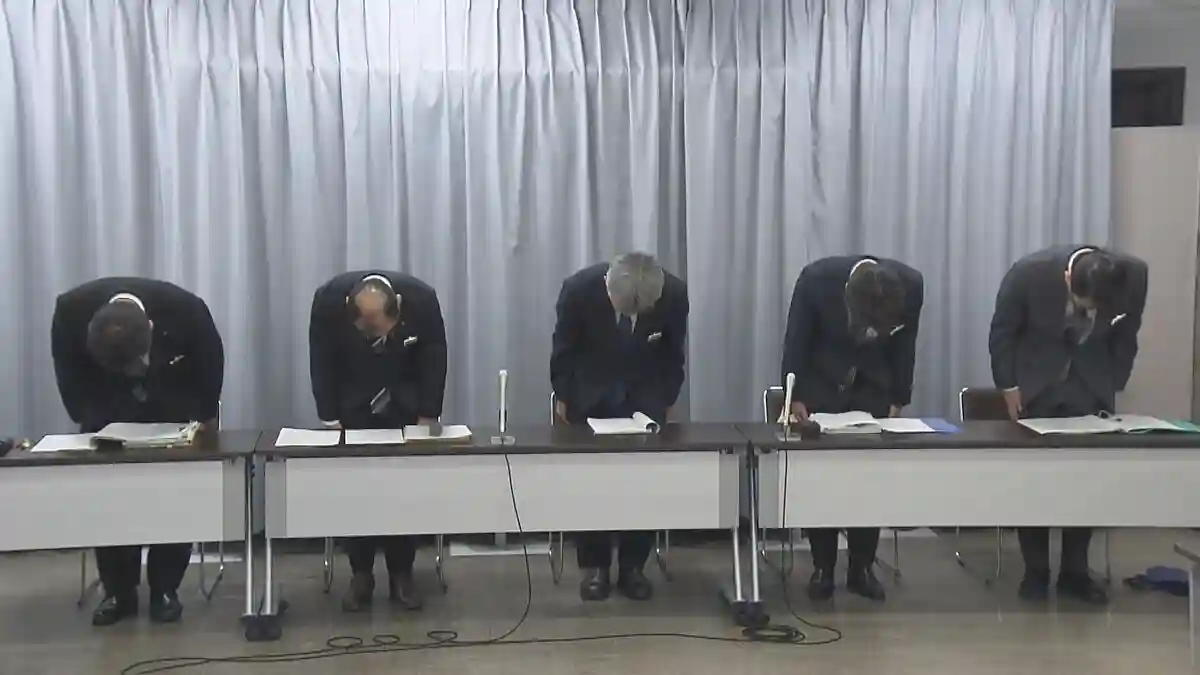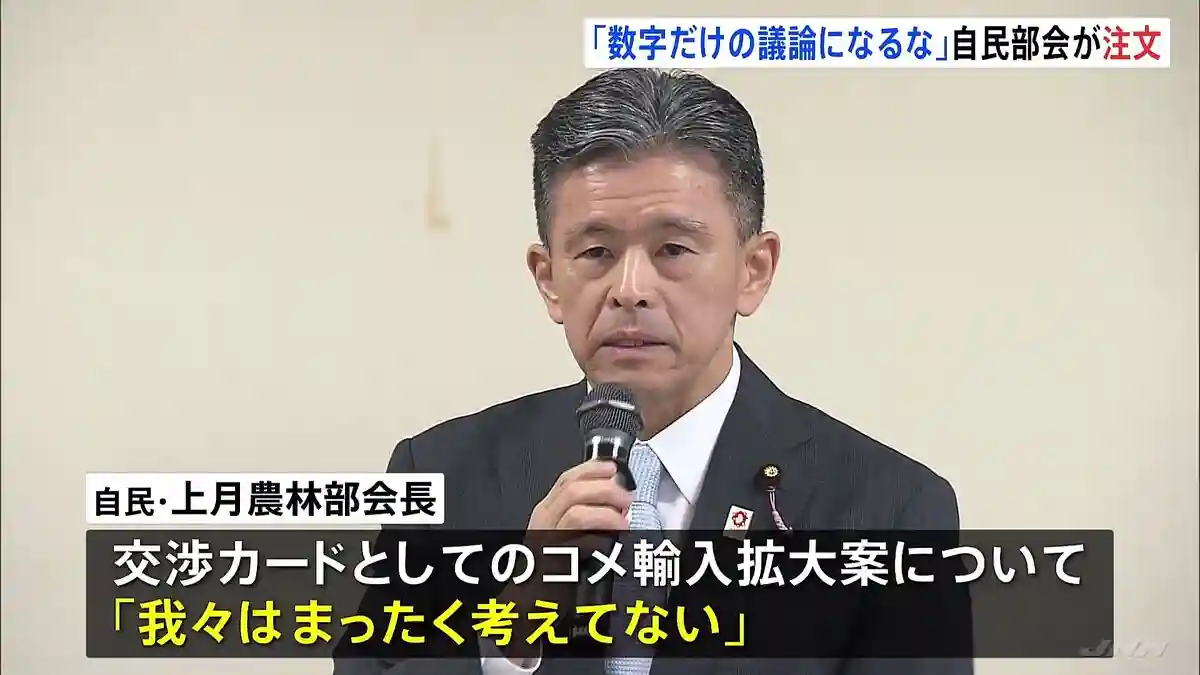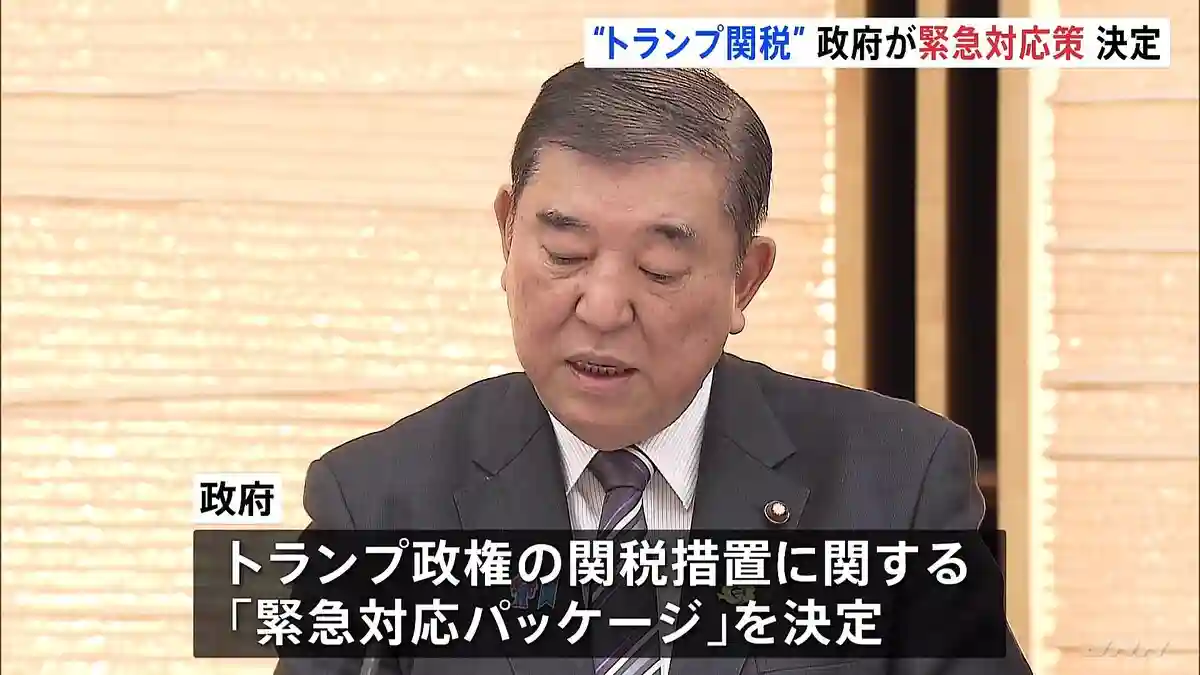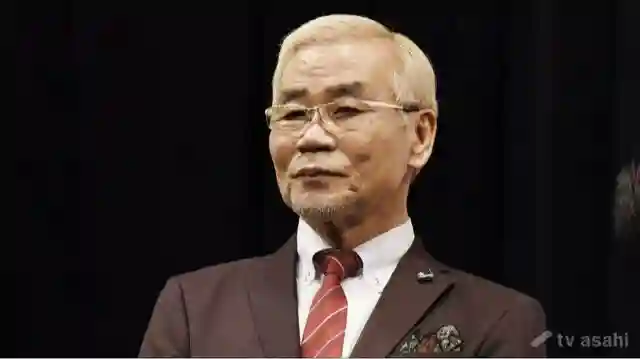日本製鉄のUSスチール買収で押さえるべき「事実」 日本製鉄のUSスチール買収案件は、4月7日にトランプ大統領がCFIUS(対米外国投資委員会)に再審査の指示を出したことで、新しい局面を迎えている。バイデン前大統領の禁止令が無効化された訳ではないが、45日以内に安全保障上の問題などを、まさに日米関税交渉の相手でもあるベッセント財務長官などトランプ政権の顔ぶれに一新された委員会が審査を進め報告書をあげ、その報告をもとにトランプ氏が15日以内に意思決定を行う、それが押さえておくべき「事実」になる。 もちろん、その決定がなされ一筋の光明が差した、と日本のメディアが書き立てた後で、13日には大統領専用機で当事者のトランプ大統領が、外国企業がUSスチールを支配すべきではない、という相変わらずの発言を行い、糠喜びが再び冷や水を浴びせられた格好になっているのは多くの読者も知るところだろう。 しかし、対トランプにおいて重要なのは、彼の発言を追うことよりも、「事実」として何が進んでいるのか、を冷静に見極めることだろうから、日本製鉄の案件については、まずはCFIUSの報告がどのようなものになるのか、そしてそれを受け(おそらくは日米関税交渉全体の行方も鑑みながら)トランプ氏がどのような判断をくだすのか、6月上旬の彼の決定を待つことになるだろう。 図1は、日本製鉄が2月6日に開催した2024年度第3Q決算説明会で、クロージングに向けた取り組みとして示した資料になるが、そこでは行政訴訟によって果たそうとしていたCFIUSの再審査を、粘り強い交渉やロビー活動、そしてまた広報の力で彼らは勝ち得たと言える。広報については、HPに掲載されているので、是非関心ある方はご覧になることをお勧めするが、例えばディールを歓迎する従業員の声なども採り上げた動画など見ると、おそらくは広報会社もかなり深くこの案件にかかわっているのが分かる。広報は日本企業が考えている以上に、重要な活動なのだ。 図1 出所:日本製鉄2024年度3Q決算説明会2025年2月6日資料より また、図2は同じ資料からの抜粋になるが、そこにはいかにこのディールがトランプ政権の政策に合致しているか、が書かれている。「新規雇用を創出」し、「米国経済を活性化」させ、「米国の産業とサプライチェーンを強化」させるこのディールが、「貿易不均衡を是正」する、おそらく彼らは粘り強く、こうした点を関係者に説明していったのだろう。 トランプ政権で起きた「対立軸の揺り戻し」 さて、筆者は、本件が一企業の意思決定の帰趨という範囲を越えて、時代そのものの認識に深くかかわる象徴性の高いディールと感じていたので、日付が新しい順に、2025年1月にはホワイトハウスを去ろうとしていたバイデン前大統領の禁止令発令のタイミングや、2024年7月にまさに安全保障上の問題に対し、日本製鉄がけじめを付けるかの如き意思決定をみせた中国、宝山鋼鉄との合弁解消のタイミング、そしてまた、本件が「日米同盟の強度」を占う案件であると認識した2024年4月、岸田前首相の訪米、議会演説のタイミングで記事を書いてきた。 ・「日本は1945年から何も学んでない」USスチール買収をめぐり「希望なき白人の物語」が日本人に鳴らす警鐘 ・日本製鉄、中国宝山鋼鉄との合弁解消は単なる「脱中国」ではない…その先にある「新冷戦」のリアル ・日本製鉄のUSスチール買収には大きな意味がある…「日米同盟」と「新冷戦相場」の強度を占う試金石 随分昔の話のように感じるが、2024年4月、丁度一年前には岸田前首相が、米国で議会演説に立ち「米国民が、たった独りで戦後国際秩序を守ってきて孤独感や疲弊を感じている事」に触れ、これからは日本が「自由や民主主義、法の支配」を守るために、トモダチとして、控えめな同盟国から、強くそのような価値観にコミットした同盟国として、その隣に立ち、この先もずっとグローバルパートナーであり続けるでしょう、と語っていたのだ。 そこから1年、4月2日に「たった独りで戦後国際秩序を守ってきたことで孤独感や疲弊を感じていた」米国民や、そのような国際秩序のなかで、割を食ってきた、と怨恨を貯め込んできたラストベルトの白人労働者層が権力の座に再び押し上げたトランプ氏が、まさに米国が戦後守ってきた国際秩序そのものから、相互関税措置を振りかざし「独立の日」を高らかに宣言したのは、歴史の皮肉以外のなにものでもないだろう。 そこで明らかになったのは「自由や民主主義、法の支配」といったイデオロギーが対立軸となる新冷戦ではなく、すでに世界は歴史を遡り1930年代や19世紀後半の「剥き出しの国家と国家の相克」こそが新しい対立軸となった世界に揺り戻されてしまったという事実だろう。 今後の「日米関係」の在り方を左右するディール 筆者は昨年の段階では、日本製鉄のUSスチール買収が占うものは、新しい冷戦という時代認識のなかで、本当に米国は防衛の要となる鉄を、同盟国とは言え日本企業にその再生を委ねる決断ができるか、どうか、このディールは新冷戦相場そのものの強度を占う、と書いた。 しかし、既にこのディールは冷戦を越えた次の新しい世界秩序のなかでの日米関係の在り方にかかるディールにとその性格を変えつつある。そして、鉄はやはり渡せない、という感覚がトランプ政権において揺るがないのであれば、大袈裟ではなく我々は安全保障についても自力で立つ覚悟がいるという話になるだろう。そして外交の根本的な戦略も、変わらざるをえないだろう。 1930年代の比喩で言えば、自由貿易圏としてのアジアに中国と韓国と共に軸足を移す選択も、ありうるだろうし、それは大日本帝国ではなく中国を盟主とする大東亜共栄圏という笑い話でもある(少なくともそうした選択もありうる、というカードの見せ方はある)。 しかし、逆にこのディールが成功するならば(本音が垣間見えた以上、いずれは、という覚悟は持ちながらも)まずは「自由で開かれたインド太平洋」を前提に、国家としても、企業としても、その活動を行えばいいことになる。そしてこうした案件を積み重ねることが米国をそれでも西側陣営に繋ぎ止めるフックになるのであれば、米国を極端な孤立主義に走らせることなく、緩やかに戦後国際秩序の修正を英国などと連携し、図っていくという行き方が見出せるだろう。 それはもしかすると同じ国際秩序の再構成を意図はしていても、米国第一主義を貫くナバロ氏とは異なり、耐用年数を過ぎたブレトンウッズ体制の再編成を願いはしても、自由主義陣営の連携という礎は意識している節のある穏健派のベッセント氏には支持される方向性かも知れない。 投資家が注目するポイント そう考えた場合、最大の焦点は、トランプ氏に、それでもこの枠組みが、最大の株主は日本製鉄であってもUSスチールがなお米国企業である、と納得させえるかどうか、になる。水面下での交渉で何かを譲歩している可能性は否定できないが、ガバナンスについての日本製鉄の提案は、2024年9月4日に公表されている図3のようなものなる。 ここにあるように、USスチールはまずはペンシルバニア州ピッツバーグに移転する日本製鉄の米国完全子会社NSNAを通じて存続され、更にa)取締役の過半数は米国籍、b)3名以上の米国籍の独立取締役、c)経営の中枢メンバーは米国籍、とされている。また、通商において米国籍の委員からなる「通商委員会」が置かれ、通商問題で取締役会に助言を行うほか、通商に関する決定は独立取締役の過半数の承認が必要、とされている。 こうして内容を読むと、ポイントは、独立取締役の人選、また通商委員会メンバーの人選にある、と感じる。つまりその人選がトランプ氏の意向に沿う人選であるかどうか、にある気がするが、そこを含め、USスチールがなお米国企業なのだ、と強弁できる細部の詰めが行われているのではないか、と思う。 そして、そうした交渉の内容・条件の修正を伺い知るチャンスは、これまでの流れを考えれば、5月9日に予定されている日本製鉄の2024年3月期の決算発表と決算説明会になる。6月上旬を待たず、手がかりを得る機会がそこにある。注目すべきだろう。 ただ、そうした歴史的な文脈を離れ、純粋に投資家としての立場で考えれば、3月28日には、ディールに向けて日本製鉄とトランプ政権が水面下の交渉を続けるなかで、投資額についても現状の27億ドルから最大70億ドルまでの増額が提案されているのではないか、というような観測記事が流れ、それを受けてか株価も(当日は全体が下げているが)下げている。 投資家は冷静に、逆にそこまで足枷を嵌められたディールが、本当に価値を生むのか、を眺めてもいる。 これは「日本国民への裏切り」だ…!財務省・中国・米国を優先する石破総理が「トランプ関税」に対して切る、まさかの「交渉カード」