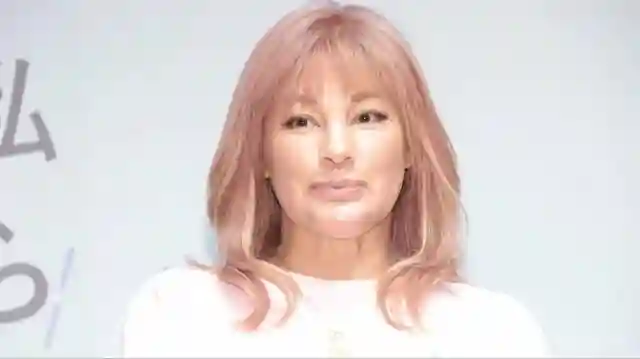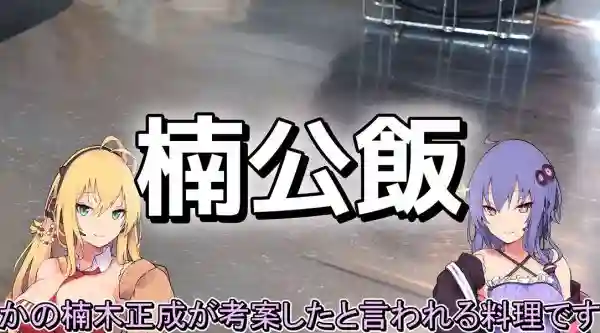大切な人を亡くしたとき、私たちはどうやってそのことを受け止めたらよいのでしょうか。「死に向き合う」という普遍的な事柄を、父の死という個人的な体験から書き綴ったエッセイ『星になっても』が発売されました。刊行を記念して、第1回「十円玉と骨」をお届けします。 十円玉と骨 父の死をライトモチーフにして何かを書き始めようとしている私を見たら、父はどんな顔をするだろう。おそらく、こんな感じのやり取りになる。 「父さんが死んだことを書いてもいいかな」 「書くってお前、どこに書くのよ」 「群像」 「群像? 何か書くことになったのか」 「うん、連載になると思う」 「……まぁ、いいんじゃないのか」 そう言って、父はちょっと誇らしげに、鼻を膨らませて笑う気がする。読書家の父は、文学贔屓で、息子贔屓。私の活躍を誰よりも喜んでくれる。自慢の息子が『群像』に書くのなら、とやかく言うまい。「いや、あんた、それでいいのかい」と、母の声までしてきそうである。 しかし、すでにこの世界にいない父の顔を見ることはできないし、父の声を聴くこともできない。こうして頭の中で話すことができるのは、私の中で父が生きているからなのか。それとも、決して現実化することのない可能性が永遠に宙吊りのままとどまるという、このどうにもならない事態こそが、父の死の動かしがたさを示しているのか。私にはどうにもまだ分からない。 それでも、数ヵ月前に死んでしまった父のことを書いてみることで、少しずついまの状況を受け入れられるようになるかもしれない。もしかしたら、死の意味についても、ちょっとは理解が深まるかもしれない。そもそも私が哲学の道に入ったのは、人はみないつか必ず死ぬという当たり前の事実が嫌だったからなのである。 「そんな甘いものではないんじゃないか」と、今度は父の声がする。そんな甘いものではないんじゃないか、と、私も思う。 いずれにせよ、これは私自身の哲学の始まりに戻る筆になりそうである。 ビーフ重を二つ 火葬場で食べる弁当を決めなければならない。何人くらい来そうなのかもよく分からないし、すでにみんな疲弊していて、考えるのも確かめるのも億劫だった。そんな時、葬儀屋から出された冊子をパラパラ見ながら、弟が「俺はビーフ重にするわ」と言った。 こうやって、弟はいつも我が道を突き進んでいくが、そういう堂々とした自己主張は、むやみに周囲に気を遣う私よりも、かえって場を和ますものである。そういえば、その日の昼食も、弟は一人、鰻重を食べていた。私はそんな弟に助けられたことが何度もある。 しかし、老人が集まる一族の葬儀で、ビーフ重を食べる気力があるのは、多くても数人。しかも、そのビーフ重は紐を引くと湯気が出て温まるタイプのもので、階下で父が焼かれながら食べるものとして相応しいのかも微妙。だが、それぞれが絶妙にうまくないおかずが詰まった弁当より、じつは私もビーフ重が食べたかった。よく言ってくれた、と、心の中で思った。 「俺もビーフ重にする」。母は呆れた顔で私たち兄弟を見た。同じ部屋の少し離れた場所で屍となっていた父も、この期に及んでの私たちのやりとりを聞いて、きっと呆れていたにちがいない。死体に口なし。いや、死体を見るたびいつも感じるのだが、何となく耳はあるような気がする。 結局、弟と私はビーフ重、他の親族は幕の内弁当。故人に近い兄弟がちょっと高いビーフ重を食べるなんて、と、批判的に見る老人もいるかもしれない。でも、大丈夫。弟がついている。何か言われても、弟が無言で睨みつけて事なきを得るだろう。弟の身長は185センチ、体重は90キロ近くあるのだ。私はその陰に隠れていればいい(私も同じ体格なのだが)。もちろん、父を失った兄弟に、そんなことを言える親族はいないのだけれど。 火葬場に移動するためバスに乗り込んだとき、葬儀屋の担当者が、バスに積んだお弁当の数を伝えてきた。お弁当の数と火葬場に行く人数を合わせなければならないからだ。お弁当が足りなければ、火葬場で蕎麦などを食べることもできるらしい。「もちろん、ビーフ重も二つ積みました」と担当者は言った。柩の蓋が閉められた後のかなしみと兄弟の食欲のシンボルであるビーフ重という、何とも言えないちぐはぐがおかしく、私は取り返しのつかない喪失を抱えながら不謹慎にも笑ってしまったのである。 十円玉を焼く 北海道には妙な風習がある。湯灌の儀式の際、柩に十円玉を入れるのである。そうして、火葬後の収骨のときに、焼け残った十円玉を拾い、以後、財布などに入れてお守り代わりに身につける。おそらく三途の川の渡し賃である六文銭と関係があるのだろうが、詳しいことは分からない。それに、これが北海道だけのものなのか、それとも、他の地域でも同じようなことをするのかも知らない。が、横浜出身の妻は、十円玉を入れたりはしない、と言っていた。 私は父方の祖母の葬儀でも同じことを経験していたから、そういえばそんなこともしたな、と、当時のことを思い出し、財布を開けてみたが十円玉がなかった。しかし、その場にいた親族が十円玉を持ち寄ってわらわらと集まってきたので、私の分も任せることにした。焼け残らないこともあるので、多めに入れたほうがいい、と、誰かが言った。これだけあれば、私の分もありそうである。 いまになって考えると、この風習は大丈夫なのか、という疑問もある。というのも、日本では「貨幣損傷等取締法」という法律があり、そこでこう規定されているからである。 (一)貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 (二)貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 (三)第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 十円玉を故意に鋳つぶして、何かを作ろうとしているわけではないものの、柩の十円玉が焼け残らないこともあるわけで、これは父の身体を焼くついでに、十円玉を高温で鋳つぶしているのと変わらない。どちらにしても、十円玉の損傷は免れえまい。 実際、私が持っている二枚の十円玉には、かなりの変色や変形が見られる。とはいえ、これが違法だったとしても、葬儀の後の懲役はきついだろう。葬儀の費用は莫大だから、罰金はもっときつい。 私は法律家ではないので、この法律がどのように運用されているのかは知る由もないし、もしかしたらこの法律はすでに形骸化しているのかもしれない。だとしても、葬儀屋や納棺師がこの法律を知らないことは考えにくいわけで、とにかく故人との関係を守ってあげるために北海道の妙な風習を優先している、とも感じられる。火葬場で収骨を手伝ってくれる人も当たり前に十円玉を探すのだから、いわばみんなグルである。 身も蓋もない話にはなるが、科学性や合理性の観点から考えるなら、死をめぐる一連の儀式はほとんど無意味である。どうせ燃えてなくなるのだから、死装束に着替えさせる必要はない。坊主の経もローカルな物語にすぎず、時間の無駄である。戒名もお墓も不要。大体、戒名によって値段が異なるということ自体、死後の身分を金で買っているようなもので、おかしいではないか。死んでしまった人間はなるはやで焼いて、その後で、どこかに散骨してしまえばいい。それが一番効率的だし、きちんと焼けば保健衛生上も問題ないはずである。たぶん。小さな寺は潰れてしまうだろうが、仕方ない。 だが、ふつう、そうはいかない。晴れやかな早朝に、近所のおばあさんが先立った夫の骨を庭に撒いていたら、私たちは絶句してしまう。死は一連の禁止線に囲われていて、だからこそ、それは私たちの日常に簡単に侵入してこないようになっている。聖と俗、ハレとケ、どんな区分でも構わないが、どうやら私たちは科学的であることや合理的であること以外の秩序を必要としているらしい。だから、この文明化された日本で、ほとんどの人間は、不合理な合理主義者として振る舞わざるをえないのだろう。とりわけ、死にかんしては。 貨幣損傷等取締法を遵守しつつ、それなりの仕方で北海道の風習を残す道はある。たとえば、十円玉に模した金属製の品を作って入れることもできる(あまり精巧にやりすぎると今度は別の法律に引っかかりそうではあるが)。あるいは、火葬場を離れる際に、お土産代わりに十円玉を袋に入れて持たせることもできそうである。 ところが、正真正銘の最期、父の遺体と一緒に焼かれた本物の十円玉であること──この事実がないとしたら、私は半年も経てばそれをどこにやったのかを忘れてしまう気がする。もしかしたら、それと分かっていても、小銭が足りないときに出してしまうかもしれない。たとえば、大好きなハンバーガーを買うときなどに。天国の父さんも喜んでいるわ、と、訳の分からないことを言いながら。 幼い父と散歩する 本当に焼かれた本物の十円玉だからこそ、祖母のも父のも大切にしまってある。いま、二つの十円玉は机の引き出しの中にある。もちろん、鍵付きである。そういえば、祖父は、父がまだ幼いころに亡くなっていて、父はよく「片親」や「ひとり親」という言葉を口にした。いつもテレビに向かって文句ばかり言っているくせに、シングルマザーの貧困のニュースにだけは妙な共感を示していたことを覚えている。父と祖母の間には、私には分からない母子の紐帯があったはずだ。 父には兄と姉がいて、末っ子である。だから、特に可愛がられていたのだと思う。祖母が死んだとき、父は柩の横に布団を敷き、「ばあちゃんと寝る」と言って、祖母の屍と一緒に眠った。母はその光景を見て、ちょっとぎょっとしたと言っていたが、私には気持ちが何となく分かった。口には出さなかったが、人一倍苦労して自分を育ててくれた母(祖母)と過ごす時間が、最後に欲しかったのだろう。 父の通夜の晩、酔った伯父がこんな話をしてくれた。祖父が死んですぐに、それまで住んでいた社宅を出なければならなくなり、親戚の伝手を頼りにして移り住んだ家は札幌の宮の沢の外れにあった。バス停のある札樽道からは1キロ弱離れていて、バラックに毛の生えたような家だったらしい。住み始めた当初は電気すらも通っておらず、ランプで生活していたという。当時は北電に頼んでも電柱を立てるのにはお金がかかり、結局、祖母がしばらくかけて自費で負担して電気を通してもらったのである。要は、『北の国から』の世界だ。 北海道の冬は厳しい。冬が深まってくると、ほとんど毎日、雪が降り積もることもある。夜にしんしんと雪が降ると、朝には辺り一面真っ白の雪景色である。そういうときでも、祖母は仕事に出てしまう。3人はバスに乗って手稲中央小学校に行かなければならない。しかし、見渡す限り雪だらけ。すると、まずは、長男の伯父が雪の原に足跡をつける。その後、伯母が踏み固めて道をつくる。そうして、最後に小学校に入ったばかりの父がついていく。こうやって、自分たちで通学路をつくりながら、冬は3人で一列になって登校していたんだよ、と、伯父は笑いながら話した。 こういう誰にも語られていないであろう父の人生の記憶が、どこかにたくさん埋まっているにちがいなかったが、それをすべて見て回ることはもうできそうにない。父はその秘密と一緒に消えてしまった。父との思い出は私が記憶しておけばいい。が、記憶の中の父の記憶にアクセスすることは、私には許されていない。父のことを語る人びとも、やがていなくなるだろう。そういう私も同じ運命にある。 こんな喪失の予感をかかえながら、ときどき私は、父の幼少期の姿を自分の息子に重ねてしまう。息子を抱っこしていると、まだ小さな父を抱っこしているような気分になるのだ。夕方、息子の手を握って散歩に出かける。しかし私にとってその出来事は、幼い父の手を握りながらの散歩でもある。ちょっとどうかしているのかもしれない。でも、生きて死んでいくことの不思議、その全体に対する直観みたいなものが、そこに働いているのは確かである。 いまの私を見たら、父は何を言うだろう。私が経験している不思議な錯覚を、いつかの父が私に感じたことはあるのだろうか。私と手をつなぎながら、幼い祖父と散歩したことはあるのだろうか。それとも、これはやっぱり私だけの個人的な体験にすぎないのか。 「お前、ちょっと頭が変になったんじゃないのか」と口では言いながらも、父の表情の中に、私に対するある種の共感を見出せそうな感じもする。それは変人同士のシンパシー。訊いてみたい。それができない。十円玉は何も応えない。 弟、骨を砕く 骨壺に収めるために、骨を砕かなければならない。粉骨である。あれは、いい気持のしない作業だ。納棺師が父の身体を触りながら、「骨太ですね」と、冗談交じりに言っていたが、人によって骨量は異なる。たとえば、焼き終わった後で、火葬場の担当者が骨を目分量で確認して、もし入らなそうだったら、骨壺の大きさを臨機応変に変えてしまえばいいのに。現代の技術を用いれば、事前に確認することだってできそうである。 とはいえ、たしかに大腿骨などは多少砕く必要があるだろう。そのまま入れようとしたら、人によってはかなり大きな骨壺になる。私は185センチ。しかも、ラグビーをやっていたから、おそらくそれなりの大腿骨である。頭も大きいから頭蓋骨もでかい。 その大腿骨や頭蓋骨を入れるための、あまりにも大きい骨壺を、私の息子が二人がかりで持って運んでいく光景は、想像しただけで滑稽である。妻がそこにいたら、思わず笑ってしまうにちがいない。死別のかなしみにフィットする大きさというものがあるのかもしれない。 話を戻そう。父の骨を収めなければならない。骨を砕くための棒が用意されていて、それを使って骨を粉砕していくのである。ふつう、故人に近い親族が担当するらしいので、やはり私がやらないといけない。私は、骨になった父を前にして、父が祖母の骨を砕いていたことを思い出していた。これも供養なんだ、と、自分に言い聞かせる。 寝ずの番も供養だし、酒を飲むのも供養になる。しかし、いまでは火を使わないLED式の線香があるし、若い人は何を言われても酒を飲まない。まさか葬儀の席でアルハラを申し立てられることはないだろうが、意味不明な儀礼よりも、個人の意志が尊重される時代である。何とか粉骨の役回りをかわすことはできないだろうか。しかし、故人の遺志というものもあるだろう。他の人間にやられるよりは、私にやってほしいはずである。 とにかくやってみよう。私が恐る恐るやり始めたまさにそのときである。「そんなんじゃ全然入らんぞ」と、横から弟が出てきた。私の手の棒を取ると、弟はまるで親の仇のように骨を潰していく。あまりにも力いっぱいやるものだから、骨の粉が宙に舞い、私はそれを吸い込んでしまわないか不安になったくらいである。迷わずガシガシ嫌な労働を進めてくれる。 私はその光景を見て、流石だと思った。親の骨をあんな力とスピードで、しかも悲しみの中で砕ける人は、日本中を探しても見つかるまい。いわば全国屈指の粉骨師。これがビーフ重を一息で平らげてしまう弟の凄味である。私は、心の中で、頼む、もうお前しかいない、と呟いた。どうにもならない状況に置かれた一般人が、スーパーマンに託す願いである。 弟の奮闘(粉闘?)で無事に収骨が終わり、私は骨壺を持って帰りのバスに乗り込んだ。それはまだ温かくて、冷たくなった父の身体に命が吹き込まれたのではないか、と思った。父が死んでから、初めて父の体温に触れられた気がした。それで、とてもかなしくなった。 父が死んで、焼け残った十円玉と骨。十円玉は変色し、骨は粉々になってしまった。いま、父はどこにいるんだろう。父がいないこの世界で、私は後、どのくらい生きていくのだろう。とにかく一生懸命やってみれ、と、いつかの父の声を聴く。 少しでも長く生きてほしいのに「その日」を待ち望んでいる自分がいる…入院した父の死を待つ「1年間」の日々